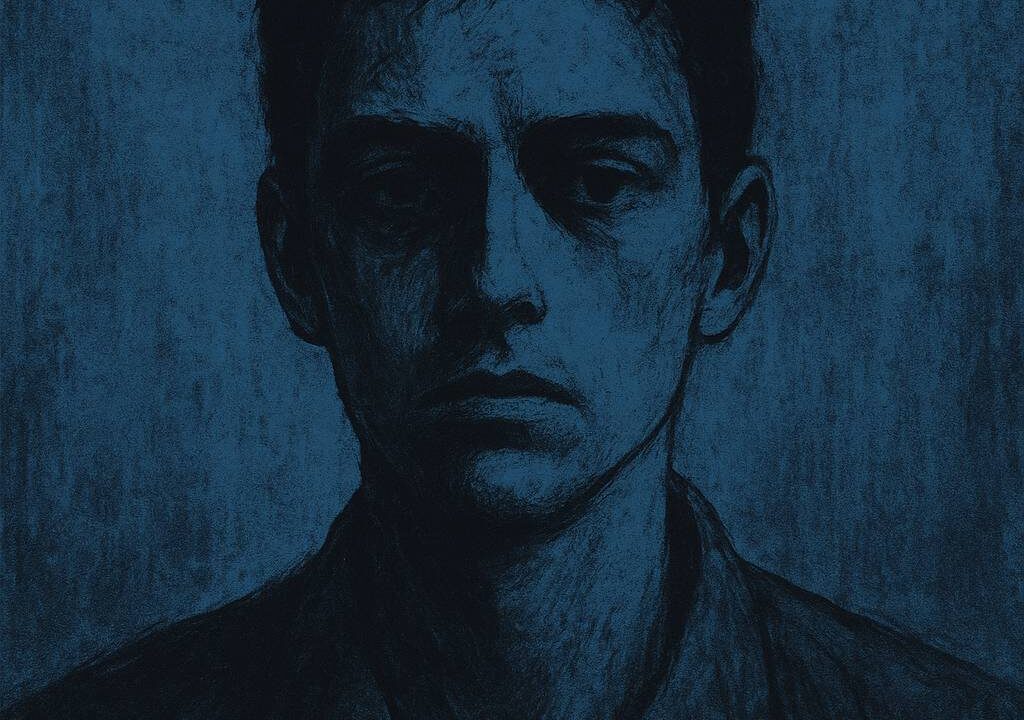【ベトナム出張辞令から飛行機離陸まで】
【告知】半隠遁者の新刊発売中
【1】
蘇我部長から出張の辞令が出たのは、残暑がようやく衰え、街がうっすらと秋の気配を纏い始めた頃だった。行き先はベトナム。ハノイという都市名を口にされたとき、私は特に驚きもしなかった。ただ、ああベトナムに行くのだな。という感想だけだった。目的は、ベトナム人技能実習生の採用面接。名目はそれだけだが、どうせ他にもあるのだろうと察した。察したところで、どうということもない。
私の勤める防人水産は、従業員十名ほどの地方の小さな水産加工会社で、魚介類を調味し、パック詰めして出荷するだけの工場だ。創業者の名前がそのまま社名になっている。全国に名が知れたわけでもないが、それでも海沿いの町では「防人の味」とやらでそこそこの認知度がある。
だが、人は来ない。求人を出しても、面接にすら来ない。来たとしても、三日もすれば海を呪い出す。魚臭い、と言って去っていく。まあ、魚工場に来て魚臭いと言う者もいるのだから、そもそも労働とは何か、という問いの出発点が異なるのだろう。そう考えれば、外国人技能実習生の採用は、ある意味で会社にとっても一つの幻想維持装置のようなものかもしれない。
「蒲生君、来月の頭にベトナムに行ってもらうから。」
その言葉は、昼食中の弁当をガツガツとやっていた時に落ちてきた。箸を止めるほどの衝撃ではない。私はただ「ベトナムですか?唐突ですね。」とだけ言った。別に嫌とも好奇心ともつかぬ声音で。言われれば行く。それだけのことだった。
蘇我部長は、テーブルに肘をつきながら、湯気の向こうにあるような声で話を続けた。
「最近はさ、日本人の雇用が難しくてね。面接して採用しても、三ヶ月もすれば辞めていく。魚が臭いとか、冷蔵室が寒いとか。知っていたはずのことを、まるで初耳のように。」
「それは困りましたね」と私は言った。困ったとは思っていない。
「それで社長から、外国人採用の話が出たんだよ。社長の友人が、技能実習生の管理団体に出資しててね。この間の飲み会で、その話で盛り上がったらしくて。」
「ああ、例の夜会ですか?」
「そう。蒲生君も行ったことある?」
「ええ、何度か社長に連行されました。」
「連行とはまた、物騒な言葉を使うね。」部長は苦笑を漏らす。だが、それ以上の感情の動きはなかった。こちらも同じだ。
「まあ、ああいう場は社長のおごりですから、社会勉強だと思って。もっとも、もうそういう歳でもありませんが。」
私はそう言って、残りの味噌汁をすすった。会話はまだ続いていたが、心のどこかではもうハノイの街の喧騒を想像していた。おそらく、あちらの昼食はもっと香辛料の効いた味がするのだろう。
私が防人水産に勤めて、かれこれ7年が過ぎた。もともとは高校の社会科教員を目指していた。大学で教職課程を取り、真面目に勉強していたほうだと思う。だが教員採用試験には落ちた。一次で落ちたのか、筆記か面接か、今となっては覚えていない。とにかく落ちた。それから一年、就職浪人という名の空白を過ごし、当然のようにそれも失敗した。
都会の下宿を引き払い、荷物をまとめて地元へ戻った。地元の空気は懐かしいというより、ただ湿っぽかった。とりあえず飯を食わねばと思い、仕事を探した。そのとき見つけたのが防人水産だった。
面接の記憶は薄い。気がついたら髪をネットにしまい、魚を洗っていた。あれから7年。いまだに私は社内で最年少だ。ということは、7年間、新しく誰も入ってきていないということになる。若手がいない会社というのは、時間が止まっているかのようだ。あるいは、ただ時計を見ていないだけかもしれない。
気がつけば三十の山を越えていた。結婚もせず、子もなく、静かな生活を送っている。週末は一人で近所を散歩し、読書か語学の勉強でもして過ごす。特に不満もない。だが特筆すべきこともない。専門性があるかと問われると、否と答えるしかない。専門性のない半隠遁者。
海外出張には体力がいる。ベトナムともなれば、湿気も時差も言葉も相手にしなければならない。そうなると、社内で中堅どころに差しかかった私のような人間が選ばれるのも自然の成り行きだった。いや、自然というより、消去法だ。所帯持ちの先輩方には無理、社長は動かない、若手はいない。となれば私だ。
選ばれたからといって、誇らしくもなく、落胆するでもない。ただ「はい」と答え、社用スマホのスケジュールを一つ埋めた。人生とは、そんな連続のような気がしてきた。なんとなくの選択の連続。時には自発的な行動。少々の受け身行動。輪廻が続く。
「蒲生君はベトナム旅行の経験は?」
昼食後のコーヒーを啜りながら、部長が訊いた。
「ありませんね。海外はヨーロッパだけです。最近は独学で世界史の勉強をしているので、そこから少しベトナムについて知っている程度です。ただ、大学時代にベトナム語を専攻していたので、日常会話レベルならなんとかなりそうです。」
私はカップを置き、わざとらしくない程度の自信を見せながら答えた。部長は少しだけ目を見開き、関心があるのか、あるふりをしただけなのか、判別がつかなかった。
「でも、どうして僕なんですか?管理団体と知り合いなら、社長が現地に行きそうなものですが。観光も兼ねて。」
私は尋ねた。好奇心というより、確認のようなものだった。
「そうなんだよな。私も初めはそう思ったんだが、社長的には蒲生君に経験を積ませる意図もあるらしいよ。」
その言葉には、意図以上の意味はなかった。少なくとも、私にはそう聞こえた。
「はあ。部長は志願しなかったのですか?」
と聞いてみた。冗談のつもりだった。
「私?お生憎。暑いのは嫌いなんだよ。会社の経費でもごめんだね。やはり日本が一番さ。」
部長は鼻で笑いながらそう言った。私は笑わなかった。ただ「なるほど」と一言、口の中で転がした。
軽口と皮肉を交えながら、部長は答えた。
その言葉だけを聞けば、どこか時代錯誤な国内第一主義にも見えるが、実際にはそうでもない。
部長の海外経験は豊富だ。商社時代に中南米に駐在していたらしく、通訳としても現地の駐在員たちと渡り合っていたという。現地調査、工場視察、文化的交流――そうした話を本人から聞くことはほとんどなかったが、飲み会の三次会あたりで誰かが酔って漏らしていた。
「ということだから、君が抜擢されたのさ。」
部長は一息ついて、湯呑を軽く置いた。
「まあ、いいじゃないか。旅費は全部会社持ちだし、観光日もついてくるらしいよ。初の東南アジアなんだから、せいぜい楽しんできたまえ。お土産はいらないから、面白話を聞かせてくれ。」
その言い回しは、どこか他人事のようだった。
たしかに土産はいらないかもしれない。だが「面白話」というのは、思ったよりもハードルが高い。冗談に見せかけた社命のようなものだ。
そうして私は、観光付きの“採用任務”を仰せつかることになった。飛行機のチケットより先に、責任の重さが配られた気がした。
【2】
9月の中旬、企画は突然決まった。そして、出発は11月の中旬。
2ヶ月もあれば、書類の準備も予防接種も間に合う。だが、精神の準備というものは、期限が切られても自然に進まない。
急な話だった。私にとっては。しかし、社長たちにとってはずいぶん前から仕組まれた筋書きらしく、「段取りは現地にも伝えてある」と、部長は電話機越しに言っていた。まるで料理の下拵えを語るような軽さだった。
話を整理しておこう。
防人水産の菅原社長。そして、その友人であり、管理団体に出資している検非違使建設の藤原社長。さらに、管理団体の実質的な統括を担う、ベトナム人のトン理事長。この三名が“技能実習生受け入れ”という名の舞台の演出家たちである。三位一体。信仰ではなく、利益の共犯関係において。
現地訪問の際は、このベトナム人のトンさんが同行してくれるという。現地事情にも精通し、送り出し機関とも太いパイプがあるらしい。噂では政府関係者との縁もあるそうだ。誰もがそう言ったが、私がそれを実感するのはまだ先の話だ。
ここで、技能実習制度について簡単に触れておこう。
制度の正式名称は「外国人技能実習制度」。建前は、「開発途上国への技能移転による国際貢献」である。だが、現場ではその理想は形骸化し、日本国内の人手不足に応じた“低賃金労働力”として実習生を扱う例も少なくない。
実習生は、送り出し国の機関を通して選抜され、日本の監理団体と受け入れ企業に配置される。彼らは最初の1ヶ月を研修に費やし、その後は実際の就労に移る。契約期間はおおむね3年、延長すれば5年に及ぶ。
制度の根幹には、「教育」という名の労働があり、「貢献」という名の補填がある。そして、送り出し機関、管理団体、受け入れ企業――そのどこにも利権が生まれる。
透明な制度とは言い難いが、少なくとも今のところ、多くの中小企業にとっては“命綱”である。
制度の是非は、ここでは問わない。ただ、制度の中に送り込まれる「人間」のことを、私たちはときどき忘れてしまう。現地に赴き、名前のある個人たちと向き合うことで、その“制度”がどんな顔をしているのかを、私は知ることになる。
技能実習制度とは、表向きには「国際貢献」という仰々しい名目のもと、開発途上国の若者に日本の高度な技術や規律を伝授し、母国の発展に寄与してもらおうという、なんとも徳の高そうな仕組みである。日本らしいと言えば日本らしい。だが、その実態はどうかと言えば、単刀直入に言って「人手不足対策」であり、「労働力輸入制度」と言ったほうがしっくりくるという声も少なくない。
特にベトナムは、この制度の最大の供給源として頭角を現している。2020年代以降、日本に来る技能実習生のおよそ半数がベトナム出身である。送り出しには政府公認の機関が関与し、若者たちは日本語を片言だけ詰め込み、希望と不安を詰めたスーツケースを携えて来日する。一方の日本では、「監理団体」と呼ばれる謎めいた非営利法人が、企業と実習生の間に入り、実習の名のもとに働く彼らの生活と労働を見守る――はずなのである。
この制度、利点がないわけではない。地方の工場、農場、建設現場など、いわゆる3K職場(きつい、汚い、危険)において、若くて真面目な外国人労働力が安定的に供給されるというのは、日本企業にとって大きな魅力である。また、実習生本人にとっても、母国では到底得られぬ水準の収入が可能であり、うまくいけば帰国後の起業資金や家族の生活改善につながる。
さらに、実習を通じて日本の製造技術や職場の習慣、品質管理に対する厳格な姿勢を学ぶことで、帰国後の就業やキャリアアップに直結する成功例も少なくない。日本企業と交流を持った経験が、将来のビジネスにもつながるケースもある。こうした制度の理念が、現場で忠実に実行された場合、技能実習は確かに「学びと成長の場」として機能する。
ただし、制度が理想通りに機能すればの話である。現実には、日本語能力が不十分なまま現場に放り込まれ、言葉が通じぬまま機械の音と怒声の中で仕事を覚える羽目になる者も少なくない。待遇面も一筋縄ではいかず、法定最低賃金すれすれ、あるいはそれ以下というケースも散見される。彼らは「実習生」であって「労働者」ではないという建前のもと、労働法の網の目をすり抜ける現場もある。
さらに、母国側の問題も無視できない。送り出し機関の中には、若者に高額な渡航費や保証金を課すところもあり、借金を背負って来日するという本末転倒な話も耳にする。技能どころか、返済のために必死で働かねばならず、「国際貢献」とやらは遠い理想となる。
このように、技能実習制度は、日本の人手不足とベトナムの経済格差という二つの現実に橋を架ける制度ではあるが、その橋の材質は、けっして強靭とは言えない。理念と現実の乖離、その狭間で、実習生たちは今日も工場のラインに立つ。制度を真に「貢献的」なものとするためには、透明性と公正さ、そして何より「人間」を扱うという根本の自覚が必要であろう。労働力の前に、彼らは一人の人間なのだ。
【3】
出張の流れは、事前の国内打ち合わせに始まり、管理団体の職員との同行出発、現地での面接、軽い観光、そして帰国。よくある出張のフォーマットである。
私はまず、自室に積まれていた『地球の歩き方・ベトナム編』を手に取った。どんな国であれ、一冊のガイドブックと多少の知識があれば、小遣い稼ぎの旅くらいにはなるものだ。もっとも今回は、旅ではない。出張である。だが、私の中ではこの二つをあえて厳密に区別する理由もない。なぜなら、どちらも「よそ者の視点」で世界を見るという点では変わりがないからだ。
初めての海外ではない。フランス、ドイツ、イギリス――あの辺りには一度だけ長期で滞在したことがある。だからベトナムが初の異文化体験、というわけでもなかった。むしろ私の関心は、「この国の裏側にある制度と人々の顔」だった。
面接相手が履歴書にどんな夢を書いていようと、私たちはその裏にある“見えざる契約書”を読む必要がある。その契約書とは、制度のことだ。技能実習制度という巨大な歯車の中で、彼らがどう位置づけられ、どう送り出され、どう帰ってくるのか。そこには、たぶん、旅行者には見えない匂いがある。
今回は、私一人ではない。ベトナム人の通訳が同行する。ありがたい話だ。いくら第二外国語でベトナム語をかじっていたとはいえ、それは学生時代の話で、今ではもっぱらビールの銘柄を覚える方が得意である。
日常会話くらいなら何とかなる気もするが、「実習制度下での面接」では、万が一があってはならない。通訳には万全を期してお願いした。そうすれば、余計な責任も避けられる。
私は準備を始めた。必要なのは、次の4点だった。
- ベトナムの現地情報(特に気候と交通)
- 簡単な歴史(戦争と革命とフランス)
- ベトナム語(日常会話の再確認)
- 技能実習制度の構造と矛盾(これは皮肉と共に)
それくらい頭に叩き込んでおけば、向こうでぼうっとしていても最低限の体裁は保てるだろう。現地人と“心を通わせたい”などというロマンチックな幻想は持っていない。ただ、言葉の断片を口にすれば、少しは場の空気が和らぐ。
通訳と管理団体の職員がいれば、大きな誤解も避けられる。ベトナム語をひけらかす機会など、あってもせいぜい屋台での注文くらいだろう。おそらく、私はこの出張で、「なにかを変える」のではなく、「なにかを見つける」ことになる。
ただし、それが何かは、まだわからない。私は観察者として旅に出る。
そしてそれは、半隠遁者にとって、なにより誠実な旅のあり方なのかもしれない。
出張も仕事と割り切ってしまえばそれまでだが、他にも吸収しようとする気構えがあれば一味違ってくる。今回の出張も仕事で終わらせない。自分なりの発見をしてみたい。異国の旅はこれがあるから面白い。昔から旅は大きな知見を生み出す。本人の意欲も比例してくる。一心不乱に準備に取り掛かった。
【4】
打ち合わせの当日、防人水産の菅原社長、私、検非違使建設の藤原社長、そして出島協同組合のベトナム人のトン理事長が一堂に会した。
場所は市内のビジネスホテルのロビー横にある会議室。無難で、落ち着きがあり、特筆すべき点のない空間。こういう空間では、かえって人間そのものの「輪郭」が際立つように思える。
それぞれが名刺を交換し、儀礼的な笑顔を交わす。形式上の“礼”というものは、たとえ一回限りでも、繰り返されてきたものに属している。誰もが、同じような名刺を同じような動きで差し出し、同じような言葉で受け取る。それでも、初対面の滑り出しとしては悪くない。「儀式」があるおかげで、無言の不安が場を支配することはない。
「蒲生は、検非違使さんはお初だったか?」
そう切り出したのは、うちの社長――菅原だった。
「はい。お名前は以前より伺っておりましたが、お会いするのは初めてでございます。」
私は抑え気味に微笑み、少しだけ頭を下げた。過剰にならぬ程度に礼を添えるのは、地方企業の人間として身についた「癖」のようなものだ。
「よろしくね、蒲生君。話は聞いてるよ。防人水産のホープだってね。」
藤原社長が大きな声で、まるで野外で話しているかのような調子で私に言った。豪快というより、音量が人格に勝っている印象だ。私は「光栄です。」とだけ言って、改めて向かいの二人を観察する。言葉よりも、視線のほうが多くを物語ることがある。
藤原社長――検非違使建設の長は、やはり見た目からしても「現場主義」的な人物であった。大柄で、皮膚は日焼けにより赤褐色を帯びており、腕も太い。典型的な「強い男」の輪郭をなぞっていた。
肉付きがよく、背も高い。おそらくジムには通っていないが、週末はゴルフや釣りに精を出している――そんな予感を抱かせる身体だった。話を聞くと、実際にアウトドアの趣味が豊富らしく、釣りとゴルフと焼き肉を好むという、昭和と令和の中間に立つような趣味嗜好を持っているらしい。
そして何より、彼はよく喋る。場の主導権を握るのが自然であるかのように、間を埋め、話を展開し、笑いを起こそうとする。言葉が多い人間には二通りある。沈黙に不安を覚える人間と、議場を支配しようとする人間。藤原社長は明らかに後者だった。
防人水産の社長――つまり私の長と、波長が合うのも納得できた。どちらも、自分の言葉が空気の色を決めることに何の疑問も持っていないようだった。
私? 私はというと、ただそこに座り、出されたお茶を手にし、時折頷き、話題が私の方向に来たときだけ、言葉を返した。観察者は多くを語らない。だが、語らぬことは、考えていないことを意味しない。
隣のベトナム人理事長はトンさんという名だった。小柄で、髪はきっちりと刈り上げられている。ベトナム男性に多く見られるスタイルで、ガイドブックやSNSの屋台紹介動画にもよく登場する髪型だ。どこか既視感のある輪郭。それでも、実物のトンさんは画面上のそれとは違っていた。
彼は寡黙というわけではないが、言葉を選ぶ節があり、むやみに話を膨らませない。聞く人の理解力を前提にしたような話しぶりは、ある種の実務者――特に、数字と段取りを重んじる者たちの特徴に似ていた。見た目こそ中肉中背だが、話すと、その中に仕込まれた「切れ味」がうっすらとにじむ。
トンさんはベトナムの高校を卒業後、しばらく現地で働き、貯金をして日本へ留学したという。学生時代はビジネス系の専門学校に通いながら、通訳のバイトをいくつも掛け持っていたそうだ。いかにも目的意識の強い生き方だ。
その中で身につけた流暢な日本語と、まじめさ、機転の良さを買われて、藤原社長に見初められたらしい。そして立ち上がったのが、彼が理事長を務めるベトナム人技能実習生の監理団体――出島協同組合というわけだ。
今では、検非違使建設をはじめとする、藤原氏の“信頼ネットワーク”の中で実習生の送り出しを一手に引き受けており、顔の利く先は多いと聞く。話を聞く限り、なかなかの切れ者だ。
この人物が今回の出張に同行してくれるのは、控えめに言っても百人力だった。言葉の壁を軽々と越え、文化の摩擦も和らげてくれる。何より、両国の事情に通じており、ベトナムを詳しく知らぬ私にとっては、まるでガイドと外交官を兼ねた存在だった。
「初めまして、蒲生さん。今回の採用面接に同行するトンです。」
そう言って握手を求めた彼は、控えめだが、誠実さがにじむような微笑みを浮かべていた。口元の筋肉の動きすら計算に入れているような微笑みだった。
「蒲生さんは、ベトナムは初めてですか?」
「ええ。初めてなんです。ガイドブックを読んだり、動画を見たりして準備はしていますが、実際は……暗中模索というやつです。」
「ははは、それは素晴らしいですね。今まで、そこまで熱心な方はいませんでしたよ。ご安心ください、面接では私が同席しますし、渡航中も常に同行します。」
それを聞いて私は、ほんの少しだけ肩の力を抜いた。
とはいえ、この種の“安心”というのは、たいてい「信頼できる者がいる」という意味ではなく、「想定外のことが起きても、責任を共有できる相手がいる」という程度のものである。
気が楽になる反面、それは同時に、「自分一人の旅ではない」という制約でもあった。
それでも、初めての土地に踏み込むには、これ以上ない同行者だろう。そう思いながら、私は無言でうなずいた。主張に対して何も期待せず、ただ、次に進むために。
「ありがとうございます。日常会話程度ならベトナム語を話せます。困ったときは、トンさんに頼らせていただきます。」
私がそう答えると、トンさんの目がわずかに見開かれた。
驚きと好奇心が、そのまま顔に浮かんでいる。
「ほお……日本人でベトナム語を話す方にお会いするのは初めてですよ。」
その言葉には、少しの敬意と、少しの珍しさを楽しむ気配があった。
その横で、菅原社長が目を丸くしてこちらを見ている。
「君がベトナム語を話せるとはねぇ……これは想定外だったな。それならば、今回の出張にはうってつけじゃないか。現地での交渉も安心だし、実習生の指導も君なら事を欠かないだろう。」
そう言って、にやにやと笑う社長。
私はうなずきながら、心のどこかで「ああ、また仕事が増えたな」と思っていた。
そして、待ってましたとばかりに、藤原社長が前傾姿勢になって口を開いた。
「うむ、蒲生君なら、きっといい人材を発掘してくれるだろう。ベトナム語ができるというのは、実習生にとっても非常に心強い。言葉の壁があるだけで、彼らの不安は大きいからね。」
「ええ、あれは大変でしたね。でも、時間をかければ馴染んでくれるものです。」
と、横からトンさんが静かに口を挟んだ。
どうやら、検非違使建設に配属された実習生たちは、ある程度うまくやっているらしい。
私は頷いた。社交辞令としてでも、それが正しい態度だった。が、心の中では冷めた笑みを一つ浮かべていた。語学ができるからといって、全てがうまくいくわけではない。だが、彼らにとってはそれだけで“物語”になるのだ。
日本語を話すベトナム人は、成功者として扱われる。ベトナム語を話す日本人は、救世主のように見られる。その構図が、私は少し可笑しかった。
配属までは、まだしばらく時間がある。今はただ、笑って頷いていればいい。防人水産の準備がどれほど整うか、そちらのほうがよほど気がかりだった。
【5】
この日の打ち合わせで、渡航予定のスケジュール表を受け取った。
日曜日から水曜日までの短い滞在。前日の土曜日には空港近くのビジネスホテルに泊まり、日曜午後にはハノイに降り立つ。月曜に面接、火曜に観光、水曜の午後には帰路につくという段取りだ。簡潔で、隙のない工程。つまり、逃げ場もないということだ。
観光が入っているのは、気遣いだろうか、それとも社交辞令のような慰めだろうか。どちらにせよ、面接と観光を同じ文脈で語るこの国の企業風土は、時に滑稽で、時に人間的だ。
ハノイがどんな街かは知らない。知っているつもりになっていた知識も、現地の空気を吸えば一変するだろう。どのような旅になるのか。どのような自分と出会うのか。それは行ってみなければ分からない。
打ち合わせを終えて部署に戻ると、蘇我部長が声をかけてきた。
「どうだい蒲生君、うまくいきそうかい?」
「ええ。藤原社長、トンさんともお会いしました。一方は豪腕、もう一方は頭脳。典型的な力と智の役割分担ですね。」
部長は軽く笑いながら言った。
「そうかい。特にトンさんは、あの界隈ではなかなかの顔役らしいよ。ベトナム人相手にも、日本の役所相手にも、話が通るんだってさ。聞いた話じゃ、日本政府とベトナム政府、両方にパイプがあるとか。」
「なるほど。監理団体の理事長にしては、少しスケールが大きすぎますね。大使館のほうが似合うんじゃないですか?」
「いやいや、君、それじゃ仕事にならないんだよ。」
と、蘇我部長は笑いながら、しかし少しだけ目を細めて続けた。
「“理事長だから”いいんだよ。目立たないけど、動かせる。そういうポジションさ。」
なるほど。世の中には、名刺の肩書き以上に重たい人間がいる。理事長という軽やかな肩書きの裏には、たぶん、ずっしりとした何かがあるのだろう。
ベトナムの面接出張。これは単なる人材採用の任務などではなく、“見えない構造”の中に足を踏み入れる通過儀礼なのかもしれない――ふと、そんな予感が頭をよぎった。
意味深長な言葉を残して、蘇我部長は去っていった。
まるで、重要な伏線を会話の中に紛れ込ませる脚本家のように。
「いち監理団体理事長だからいいんだよ。」
気にしすぎだろうか。しかし、引っかかった。いや、引っかけられたのかもしれない。
光は祝福を与えるが、暴くこともある。
スポットライトを浴びる者は、同時に影を長く引きずる。
表舞台に立つ者の背後には、いかなる正義も、時に脆い。
技能実習制度について調べるほど、その構造の複雑さに気づかされる。制度とは往々にして、理念と現実の折衷だ。表向きは国際協力、人材育成、友好の架け橋。だがその内実は、労働力不足の穴を埋めるための、都合のいい“人間資源”の輸入でもある。
「光と闇がある」と言うのは、どの制度にも適用可能な常套句だ。しかし、この制度における“闇”は、個人の生活や尊厳に直結している。成功例もある。だがそれは、語られるべき“例外”として扱われがちだ。
交通事故や殺人事件がニュースに取り上げられるのは、それが稀だからである。日常に埋もれた普通の暮らしは、ニュースにはならない。制度の成功も同様だ。正しく機能した事例ほど、誰にも語られない。
失敗の多くは、関係者が自社の利益を優先した結果だ。労働者ではなく“商品”として彼らを見る時、関係性は摩耗する。短期的な成果を追うほど、長期的な信頼は損なわれる。制度は制度であっても、人間関係は“等価交換”ではない。
気がつけば、出発日が目前に迫っていた。書類、パスポート、現地通貨、辞書……必要なものは一通り揃ったが、肝心なのは「覚悟」か「鈍感力」か。この旅が「採用面接」以上の意味を持つような予感が、どこかでずっとしていた。