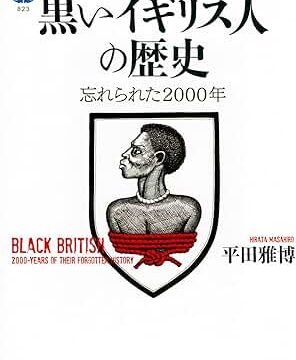第一節 四面楚歌の口入屋
阿波の城下は、
冬になると空気が固くなる。
新町川の風が、
町人の言い訳まで
乾かしてしまうからだ。
口入屋「伊予屋」の主人、
謀次郎は、朝から帳面を睨んでいた。
睨んでも米の値は下がらない。
下がらないものを睨むのが、
町人の冬仕事である。
店先には、火鉢が一つ。
炭は節約され、灰だけが豪華だ。
謀次郎の暮らしも似ている。
見栄は燃やさず、寒さだけは確かだ。
そこへ、最初の客が来た。
紺の羽織が
“武家っぽいが武家ではない”
種類の男で、
腰の物は立派だが目は落ち着きがない。
「ご主人、口入を一つ頼みたい」
「口入は“頼む”ものではなく、
“困る”ものです」
男は笑った。
笑い方が、
借金の利子のように細く長い。
「困っている。
だから頼む。これで道理は立つ」
謀次郎は、
道理が立つ話ほど
胡散臭いと知っている。
道理は立たせるものではなく、
たいてい勝手に立ってしまう。
立ってしまった道理を倒すのが、
こちらの仕事だ。
「どんな困り事で」
男は小声になった。
「奉公人の口を、塞ぎたい」
謀次郎は、茶を注いだ。
注いだ茶の音が、
店の静けさを一瞬だけ殺した。
「口入屋は口を開く仕事です。
人の命を塞ぐのは別口でしょう」
「いや、塞ぐのではない。
……移すのだ。遠くへ。阿波の外へ」
言い換えの手際が良い。
手際の良い言い換えは、
たいてい罪の香りがする。
謀次郎は相槌を打たず、
帳面に墨を落とした。
墨は正直で、落ちたら戻らない。
「条件は」
男は懐から紙を出した。
金額が書いてある。
金額は、
どんな悪事も一瞬で善行に見せる。
「……これは」
「口入屋にしては、
景気のよい話だろう」
「景気のよい話は、
あとで必ず帳尻が合います。命で」
男の笑いが少しだけ固くなった。
「命は勘定に入れていない。
奉公人の将来のためだ」
将来。
この世でいちばん便利な言葉だ。
明日を言えば、
今日の汚れが見えなくなる。
謀次郎が紙を返そうとした、
そのとき。
次の客が、戸を開けた。
女だった。
町家の女房風だが、
身なりが妙に整いすぎている。
整いすぎた身なりは、
だいたい“人に見せる用”である。
「伊予屋さん?
うちの手代のことで……」
謀次郎は、
胸の奥で小さくため息をついた。
冬は客が増える。
奉公替え、奉公争い、奉公逃げ。
人は寒くなると、
よく働くか、よく揉める。
女は言った。
「手代が“口入屋さんに話を通した”って申しますの。でも、うちはそんな話、聞いておりません」
先ほどの男が、茶碗に目を落とした。
目を落とすのが早い。
早い男は信用できない。
落とす前に拾うからだ。
謀次郎は二人を見比べた。
そして、妙な匂いを嗅いだ。
同じ話だ。
奉公人を“移す”。
奉公人の“口”。
奉公人の“話が通った”。
しかも女は、こう続けた。
「奉公人の“将来”のために、よそへ出してやるのが慈悲だと……そう言うのです」
将来。また出た。
便利な言葉が二度出るとき、
それは偶然ではない。
誰かが“使っている”。
謀次郎は笑わなかった。
笑うと、相手が安心する。
口入屋が相手を安心させるのは、
手付金をもらった後でいい。
「旦那様は、手代をよそへ?」
女房は首を振った。
「よそへ出すなら、うちの都合で出します。勝手に話を通されるのは困ります」
「困るのは結構。
困りごとが飯になります」
女房は、一瞬だけ目を細めた。
町人の女房は、
たいてい武家より恐ろしい。
家計簿という刀を
常に抜いているからだ。
そこへ、三人目の客が来た。
寺の小僧である。
真面目そうな顔をしているが、
真面目そうな顔の者ほど話が早い。
「伊予屋のご主人、至急です。お寺の庫裏で揉め事がございまして……奉公口の件で」
謀次郎は、
さすがに湯呑みを置いた。
奉公口。
また同じ言葉。
謀次郎の背中に、
冷たいものが這った。
戸口は一つなのに、
話が四方から入ってくる。
――四面楚歌。
むろん、楚の歌などこの城下にはない。
あるのは阿波節と、町人の噂話だけだ。
だが噂話は歌より厄介だ。
耳に残り、口に移る。
謀次郎は、三人の客に向けて、
穏やかに言った。
「本日は、口入の相談が多い。
どうやらこの店、今夜は合唱会らしい」
誰も笑わない。
笑わないということは、
皆、歌う側ではなく、
聞かせる側に回りたいのだ。
謀次郎は、帳面を閉じた。
「順番に伺います。ただし一つ。同じ奉公人の話なら、先に言ってください」
三人とも、
微妙に視線をずらした。
答えの代わりに、沈黙が増えた。
その沈黙の形が、
謀次郎には見えた。
四方から、じわじわと。
包囲されるのは戦だけではない。
口入屋も、噂と義理と金で囲まれる。
謀次郎は、火鉢の灰を箸でならした。
灰は何度ならしても、すぐ乱れる。
人の話も同じだ。
「……なるほど」
誰にともなく呟いた。
「これは“口入”じゃない。
“口封じ”の品評会だ」
第二節 四方からの声
- 謀次郎の口入屋「伊予屋」に、奇妙な依頼が三つ同時に舞い込む
- 「四面楚歌」という言葉が、城下の現実として立ち上がってくる
- 人情と算段の間で、謀次郎は“誰の味方でもない”顔を保つ
伊予屋の戸を開けると、
冬の空気がひょろりと入り、
帳場の蝋燭が一瞬だけ震えた。
謀次郎は、
その震えを「世の中の都合」と
呼ぶ癖がある。
風でもないのに揺れるものは、
たいてい人情か金勘定だ。
「旦那、今朝は景気がいいですよ」
幸吉が、景気のよさそうな声で言った。
声だけは相場が上がりやすい。
「何が来た」
「四方から来ました」
「四方?」
幸吉は指を折った。
「まず町奉行所の手先が、口入の名簿を見せろと。次に組頭が、うちの口入が“よその組”に流れてるって。三つ目に、蔵元の番頭が、奉公人の入替えを“今すぐ”って。四つ目に——」
「四つもあるのか」
「四つ目が肝でして。伊予屋に雇われたいって浪人が、入口に座り込んでます」
謀次郎は、入口の方を見た。
そこにいる浪人は、
座り込んでいるというより、
地面に根を張っていた。
肩が濡れている。
昨夜から降った霙を、
きちんと受け止めている。
「名は」
「名は言いません。
言うと弱くなるから、と」
「弱くなるのは、名ではなく腕だ」
謀次郎は茶をすすった。味が薄い。
誰かが水を足したのだろう。
こういうときの水増しは、
たいてい人情である。
「旦那様」
幸吉が声を落とした。
「手先が来たの、
例の“噂”のせいですぜ」
噂——。
城下では、噂は魚より早く腐る。
腐ると臭いが強くなる。
臭いが強いと、皆が嗅ぎに来る。
嗅ぎに来ると、ますます腐る。
「『伊予屋は人の口を入れるが、
うしろで口も封じる』って」
幸吉は、
まるで名文を朗読するように言った。
名文ほど人を殺す。
短いほど致命傷になる。
謀次郎は、
帳場脇にいる小僧・佐一を見た。
「佐一、今朝の客は誰から入れた」
「皆さま、勝手に……」
「勝手に来るのが客だ。
勝手に帰るのが金だ」
謀次郎は、外の霙を見た。
霙は降るでもなく止むでもなく、
ただ“決めきれない顔”で落ちている。
室町でも戦国でもなく——
いや、これは江戸だ。
江戸の空もまた、決めきれない。
店先に座る浪人が、こちらを見た。
目が乾いている。
乾きすぎて、
泣く余地がない目だった。
「入れ」
謀次郎が言うと、浪人は立ち上がり、
草履の泥を落とすでもなく
上がってきた。
礼はする。だが腰は折れない。
腰を折るのは、
奉公口が決まってからだと
言わんばかりだった。
「口入を願う」
浪人が言った。
「口を入れるのは、
こちらの仕事だ。そちらは口を閉じろ」
謀次郎は平然と言った。
相手の気骨を試すときほど、
言葉は粗くする。
粗い言葉に耐えられる相手は、
だいたい世間の荒波にも耐える。
浪人は、顔色ひとつ変えずに言った。
「閉じている。今は腹の方が鳴る」
「どこの者だ」
「四方から来た」
幸吉が笑いそうになり、
咳でごまかした。
「四方から来た、とは」
「行く先が四方とも閉じた。どこへ行っても、同じ顔をされる。――四面楚歌だ」
謀次郎は、
心の中で“楚歌”という音を転がした。
故事成語は便利だ。
言い訳を知的にしてくれる。
知的な言い訳は、
貧乏より肩身が狭い。
「楚の歌を聞いたことはあるか」
「ない」
「なら、四面楚歌ではない。
ただの四面空腹だ」
浪人は、初めて笑った。
笑い方が下手だった。
だが下手な笑いは信用できる。
上手い笑いは、商いの匂いがする。
そこへ、戸が叩かれた。
「伊予屋どの。奉行所よりである」
手先だ。
声だけが立派で、腹は軽い声だ。
謀次郎は、幸吉に目で合図した。
幸吉は、
笑顔という武器を携えて
戸へ向かった。
「へぇ、どちらさまで」
「名乗る必要はない。名簿を見せよ」
「名乗らない方に限って、
名簿を見たがるもんで」
幸吉は軽口を叩きながらも、
帳場の奥の箱をちらりと見た。
あの箱には、口入の名簿だけでなく、
名簿には書けぬもの——
借金、素行、親の病、
縁談の破れ、夜逃げの匂い——
が、紙片の形で詰まっている。
謀次郎は箱に手を置いた。
「名簿は見せる。
だが“名簿の外”は見せぬ」
「外とは何だ」
「人間だ」
手先は一瞬、黙った。
黙ると弱くなるのは、
名ではなく権威である。
そこへ今度は、
裏口から組頭が入ってきた。
こちらは名乗る。
名乗らないと損をする種類の人間だ。
「伊予屋。最近、うちの組の奉公人が、よその組へ流れておるぞ」
「流れるのは水で、
流れないのは米だ。人は歩く」
「口が立つな」
「口入屋ですから」
組頭は鼻を鳴らした。
鼻で笑う人間は、口で泣く。
さらに番頭が来た。
蔵元の番頭は、
笑顔が硬貨のように硬い。
「謀次郎さん。今すぐ人が要る。年末の勘定が回らん。いい人間を“外さず”に頼む」
「外すのは、網か約束だ」
「外さないでくれ」
店の中に、声が四方から重なった。
名簿を見せろ。
うちの人間を返せ。
今すぐ寄越せ。
口入を頼む。
謀次郎は、茶を置いた。
帳場の蝋燭が、また震えた。
今度は風ではない。声だ。
幸吉が小声で言った。
「旦那。
……これ、ほんとに四面楚歌ですよ」
謀次郎は静かに答えた。
「違う。四面楚歌は、
逃げ場がないという話だ」
「じゃあ、うちは」
「うちは、逃げ場が“多すぎる”」
「多すぎる?」
「どこへ逃げても、
誰かが怒る。――それが商いだ」
浪人が、ぽつりと言った。
「怒られない場所は?」
謀次郎は、浪人の目を見た。
乾いた目が、今は少しだけ湿っている。
腹が鳴る音が、
店の奥でひっそり鳴った。
誰の腹か分からない。
腹の音は、階級を越える。
「怒られない場所などない」
謀次郎は言った。
「ただし、怒られ方を選べる場所はある。――それが奉公口だ」
手先が言う。
「答弁になっておらん」
組頭が言う。
「煙に巻く気か」
番頭が言う。
「時間がない」
謀次郎は立ち上がった。
そして、箱を抱えた。
「名簿を見せる。だが条件がある」
三人が身を乗り出した。
人間は、条件が付くと急に真剣になる。
「今この場で、
四方の者が同じ歌を歌え」
「歌?」
「楚でも阿波でもいい。内容は何でもいい。ただし——」
謀次郎は、笑わずに言った。
「同じ歌を、同じ調子で歌え。できないなら、四面楚歌ではない。――ただの“身勝手の合唱”だ」
一瞬、沈黙が落ちた。
蝋燭が、今度は落ち着いた。
声が止むと、炎は人間より賢い。
幸吉が、耐えきれずに噴き出した。
「旦那、それ、いま一番怖い歌ですね」
謀次郎は、箱を机に戻した。
「怖い歌ほど、よく売れる」
浪人は、なぜか深くうなずいた。
彼には分かるのだろう。
四方からの声が、
どれも同じに
聞こえ始めたときの恐ろしさが。
謀次郎は、箱の蓋に指を置いた。
「さて——誰から、開けてやろうか」
その指先は、霙より冷たかった。
だが冷たい指先で扱うからこそ、
人の運命は紙のまま破れずに済む。
店の中に、
また四方から視線が集まった。
視線は歌より刺さる。
しかも無音である。
謀次郎は思った。
四面楚歌とは、包囲ではない。
“正しさ”が四方から来ることだ。
そして正しさは、
いつも腹を満たさない。
第三節 楚歌は外からではなく内から聞こえる
謀次郎は、その晩、
伊予屋の戸を早めに閉めた。
早く閉めると、客は増える。
遅くまで開けると、面倒が増える。
商いというのは、だいたい逆だ。
帳場には、幸吉と浪人が残った。
浪人は名を名乗らないまま、
火鉢の前に座っている。
名を名乗らない者は、
だいたい自分の名に食われている。
「お前さん、歌は歌えるか」
謀次郎が不意に言った。
浪人は目を瞬いた。
「歌?」
「楚の歌でも、阿波節でもいい」
「……歌えますが」
「腹は?」
「鳴ります」
「よし。条件は揃った」
幸吉が首を傾げる。
「旦那、何の条件です」
「四面楚歌を裏返す条件だ」
翌朝、
伊予屋の前には人だかりができた。
昨夜のうちに噂が走ったらしい。
伊予屋が、
“口入の席”を設ける。
口入屋が“席”を設けるときは、
だいたい禄でも縁でもなく、
言い訳が配られる。
武家筋、町人、組頭、番頭、寺の小僧。
前日に顔を揃えた面々が、
互いに目を合わせぬように座った。
誰もが思っている。
――自分は正しい。
――他が無茶を言っている。
四方から正しさが集まると、
部屋は途端に息苦しくなる。
これが、楚歌の正体だ。
謀次郎は、
あえて最初に浪人を座らせた。
「この者を、どこへ口入するか」
番頭が即座に言う。
「うちだ。人手が足りん」
組頭が被せる。
「いや、うちの組だ。腕がありそうだ」
手先が咳払いする。
「奉行所としては、
素性が分からぬ者は困る」
寺の小僧が小声で言う。
「庫裏にも……」
四方から、声。
浪人は黙っている。
黙っている者が、
いちばん賢く見える瞬間だ。
謀次郎は、
火鉢の炭を一つ動かした。
「なるほど。
皆が欲しい」
全員が頷く。
欲しい理由は違うが、結論は同じだ。
「では、皆で歌いましょう」
沈黙。
「歌?」
「ええ。昨日言いました。
四面楚歌なら、同じ歌を、同じ調子で」
幸吉が、堪えきれずに吹き出した。
「旦那、それ本気ですか」
「本気ほど、冗談に見えるものはない」
謀次郎は、浪人を見た。
「歌え」
浪人は一瞬迷い、
そして腹を括った顔になった。
阿波節だった。
節回しは下手だが、声がまっすぐだ。
♪風吹けば
吉野の川も
よう揺れる――
途中で止めた。
「次」
番頭に視線を向ける。
番頭は顔をしかめながらも、
同じ節をなぞった。
声は硬い。
金勘定の声だ。
組頭、手先、寺の小僧。
全員が同じ節を、同じ歌詞で、
それぞれ違う腹で歌う。
部屋は、奇妙な合唱になった。
音は揃っている。
だが意味が揃っていない。
謀次郎は、そこで言った。
「これが四面楚歌です」
全員が黙った。
「敵に囲まれる話ではない。
正しさに囲まれる話だ」
謀次郎は帳面を開いた。
「浪人は、奉公に出す」
番頭が身を乗り出す。
「どこへ」
「四方のどこにも」
ざわり、と空気が動いた。
「どういう意味だ」
「意味は単純です。誰か一人に出せば、他の三方が“敵”になる」
「それが商いだろう」
「いいえ。それは戦です」
謀次郎は、にこりともせずに言った。
「口入屋は、戦を請け負わない」
「では、どうする」
謀次郎は、浪人に向き直った。
「お前、歌で食え」
浪人は口を開けた。
「……歌?」
「阿波節は、冬に売れる。
祭りがなくとも、座敷はある」
番頭が言う。
「そんな馬鹿な」
「馬鹿だから、売れる」
謀次郎は続けた。
「この者を“誰のものでもない者”として売る。皆は、金を出す。だが、誰も所有しない」
「そんな口入があるか」
「あります。“芸”です」
沈黙が落ちた。
四方からの正しさが、
行き場を失っている。
謀次郎は畳みかけた。
「武家は体面を失わず、町人は人手を直接抱えず、奉行所は素性を問わず、寺は慈悲を果たした顔ができる」
「浪人は?」
「腹が満ちる」
浪人は、火鉢を見つめたまま、
小さく頷いた。
幸吉が呟いた。
「……四面楚歌、
じゃなくなりましたね」
謀次郎は首を振る。
「いいや。楚歌は消えていない」
「ただ、歌い手が増えただけだ」
外で、
誰かが阿波節を口ずさんでいた。
噂はもう、
次の町角へ向かっている。
謀次郎は思う。
四面楚歌とは、
逃げ場のない包囲ではない。
逃げたくなる正しさが、
四方から来る状態だ。
そしてそれを、
一段低い音程に落とすのが、
口入屋の仕事である。
第四節 算盤は鳴り、人情は転ぶ
口入の席が終わったあと、
伊予屋には奇妙な静けさが残った。
誰も勝っていない。
だが、誰も完全には負けていない。
この状態が、いちばん不満を生む。
最初に口を開いたのは、
蔵元の番頭だった。
「……つまり、
うちは人手を直接得られんと」
「ええ」
謀次郎は、湯呑みに湯を足した。
湯を足す音は、決断を薄める。
「だが、座敷で歌うなら、うちの旦那衆が金を落とす可能性はある」
「可能性はあります。
“必ず”は売りません」
「商売人が“必ず”を嫌うとは、珍しい」
「口入屋は、
必ずを売ったら終わりです」
番頭は鼻を鳴らした。
鼻で鳴らす音は、
算盤の外れた音に似ている。
次に組頭が腕を組んだ。
「うちの組としては、素性の怪しい浪人が、うろつくのは困る」
「うろつきません」
「歌って歩くなら、なおさら目立つ」
「目立つ者は、裏で悪さができません」
謀次郎の言葉に、
組頭は一瞬、言葉を詰まらせた。
裏で悪さができない、というのは、
取り締まる側にとっては
“扱いやすい不審者”
という意味でもある。
「……ふん」
組頭は、
負けを認めたわけではない。
ただ、
勝ち筋が見えなくなっただけだ。
奉行所の手先は、
ずっと黙っていた。
黙る者ほど、
最後に厄介なことを言う。
「奉行所としては、前例がない」
「前例があることだけで、
町は回りません」
「だが、前例がないことは、
責任の所在が曖昧だ」
謀次郎は、少しだけ笑った。
「責任は、いつも曖昧です。ただ、誰が引き受けるかが、決まっているだけで」
手先は、
その“誰”が謀次郎であることを
理解したらしかった。
「……伊予屋が、すべて請け負うと?」
「ええ。噂も、苦情も、
失敗したときの悪口も」
「そこまでして、何を得る」
「帳面の余白です」
寺の小僧は、
最後まで落ち着かなかった。
「浪人を、寺で預かるという話は……」
「しません」
「慈悲として……」
「慈悲は、
腹が満ちてから考えるものです」
小僧は、顔を赤らめた。
慈悲を否定された者ほど、
自分が善人だと信じている。
謀次郎は、
あえて声を和らげた。
「寺は、歌を聴けばいい。
それで十分、顔が立ちます」
一通りの不満が出尽くすと、
人は急に現実的になる。
番頭が言った。
「で、取り分は」
謀次郎は、
待っていましたと
言わんばかりに帳面を開いた。
「座敷ごとに折半。伊予屋は口銭のみ」
「安すぎる」
「安いから、長く続く」
組頭が笑った。
「欲のない口入屋だ」
「欲がないのではない。
欲を一つにしないだけです」
浪人は、
そのやり取りを黙って聞いていた。
自分の人生が、
算盤の上を転がっているのを、
不思議そうに見ている。
「……あの」
浪人が、
初めて口を挟んだ。
「俺は、商品ですか」
謀次郎は、
即座に答えた。
「違う。“場”だ」
「場?」
「お前がいることで、皆が少しずつ引く。それで均(なら)しが起きる」
浪人は、
よく分からないまま頷いた。
分からないまま頷ける者は、
意外と長生きする。
話がまとまると、
人は急に帰りたがる。
番頭は袖を整え、
組頭は咳払いし、
手先は“記録に残さぬ”顔をした。
寺の小僧だけが、
名残惜しそうに浪人を見た。
「……お達者で」
「腹いっぱい、歌います」
浪人は、
ぎこちなく笑った。
全員が去ったあと、
伊予屋には
幸吉と謀次郎だけが残った。
「旦那」
幸吉が言った。
「誰も得してませんね」
謀次郎は、
帳面を閉じた。
「誰も損もしとらん」
「それが、一番文句が出るやつです」
「文句が出るうちは、町は生きている」
幸吉は火鉢に炭を足した。
「四面楚歌って、
こういうことですかね」
謀次郎は、
少し考えてから答えた。
「いいや。これはまだ前奏だ」
外から、
浪人の歌声が聞こえた。
調子は外れている。
だが、声はまっすぐだ。
♪風吹けば
川も町も
よう揺れる――
謀次郎は、
その歌を聞きながら思った。
楚歌は、
敵が歌うものではない。
自分たちが、
納得できない気分を
紛らわすために歌うものだ。
そしてそれを、
一番よく知っているのが、
口入屋なのである。
第五節 楚歌を歌うのは誰か
浪人の歌は、
三日で城下に馴染んだ。
馴染むというのは、
褒め言葉ではない。
人々が「気にしなくなった」
という意味だ。
朝は河岸で、
昼は蔵元の裏座敷で、
夜は料理屋の二階で。
下手な阿波節が、
下手なまま町に溶けていった。
四日目の朝、
伊予屋の戸口に貼り紙が出た。
「口入一時休業」
字は丁寧だが、
理由は書いていない。
理由を書かぬ貼り紙ほど、
人の想像を刺激する。
「夜逃げか」
「奉行所沙汰か」
「金を持って逃げたらしい」
噂は、
貼り紙より早く増えた。
幸吉が、
昼前に戻ってきた。
「旦那、えらいことになってます」
「噂か」
「ええ。しかも、四方から」
謀次郎は、
静かに湯を注いだ。
四方から噂が来る。
それはつまり、
誰も責任を取らないということだ。
「番頭筋が言ってます。
『伊予屋が人を使って儲けてる』って」
「事実だ」
「組頭は、
『怪しい浪人を放し飼いにしてる』と」
「放し飼いではない。座敷飼いだ」
「奉行所は、『前例がない』と」
「前例がある方が、よほど危ない」
幸吉は、
口を尖らせた。
「……寺まで言ってますよ。
『慈悲が足りぬ』って」
謀次郎は、
小さく笑った。
「慈悲が足りるときは、
だいたい腹が足りている」
昼過ぎ、
番頭が一人、
伊予屋を訪ねてきた。
今度は、
強気ではない。
「謀次郎さん。あの浪人だが……」
「歌が下手でしょう」
「いや、妙に客が笑う」
謀次郎は、
その“妙に”を聞き逃さなかった。
「笑う、とは」
「……安心する、と言った方が近い」
番頭は言った。
「世の中、皆がうまい歌を求めてるわけじゃない。下手な歌を聞くと、自分の暮らしも少し許せる」
謀次郎は、
茶を差し出した。
「それは結構な効能です」
「だがな……」
番頭は声を落とす。
「それで、
伊予屋が儲かるとなると、話は別だ」
その晩、
組頭が来た。
「浪人を、うちで引き取らせろ」
「歌を取り上げるのか」
「歌わせる。だが、管理する」
謀次郎は、
首を振った。
「管理した歌は、すぐ飽きられます」
組頭は、
苦い顔をした。
翌日、
奉行所の手先が来た。
「浪人の素性が、曖昧だ」
「歌は、確かです」
「歌で、身分は保証できぬ」
「身分で、心は保証できぬ」
三日で、
三方向から、
同じ話が来た。
取り込め。
管理しろ。
都合よく使え。
それぞれ、
自分が正しい顔で。
謀次郎は、
その夜、
浪人を呼んだ。
「町を出ろ」
浪人は、
驚かなかった。
「……四面楚歌ですか」
「違う」
謀次郎は言った。
「四面“合唱”だ」
「皆が、同じ歌を欲しがっている」
「それは、悪いことですか」
「歌が、誰のものか。
決まった瞬間に、悪くなる」
謀次郎は、
銭を一包み渡した。
「次の町で、また下手に歌え」
浪人は、
深く頭を下げた。
名は、
最後まで名乗らなかった。
翌朝、
浪人はいなかった。
歌声も、
消えた。
城下は、
少しだけ静かになった。
貼り紙は、
剥がされた。
伊予屋は、
何事もなかったように
再び戸を開けた。
客は減らない。
だが、
増えもしない。
ちょうどいい。
幸吉が言った。
「旦那、あれで良かったんですか」
謀次郎は、
帳面を閉じながら答えた。
「四面楚歌というのはな」
「はい」
「敵に囲まれる話じゃない」
謀次郎は、
火鉢の灰をならした。
「正しさが四方から来て、
逃げ場がなくなる話だ」
「……」
「だから、歌わせるしかない」
外で、
誰かが別の歌を口ずさんでいる。
下手だが、
気楽な調子だ。
謀次郎は、
その声を聞きながら思った。
楚歌は、
滅びの合図ではない。
人が、
自分の正しさに
疲れたときに歌うものだ。
そしてその疲れを、
少しだけ軽くするのが、
口入屋の仕事である。
伊予屋の帳場に、
今日も新しい相談が置かれる。
四方から。
だが、
謀次郎は知っている。
歌が聞こえるうちは、
この城下は、
まだ持ちこたえる。
最後までお読みいただきありがとうございました。
良ければKindleで小説を販売しているのでご覧ください。
【Kindleで半隠遁者の小説を販売中】
① オチ解説
「四面楚歌」は“包囲”ではなく“正しさの過剰”である
通常の意味
故事成語 四面楚歌 は、
四方から敵に囲まれ、
もはや逃げ場がなくなった絶望的状況
を意味します。
中国史においては、
項羽が垓下で敗れ、
敵陣から楚の歌(故郷の歌)が聞こえ、
「味方すら失った」と
悟る場面が原型です。
つまり本来は
軍事的敗北・孤立・滅亡の象徴でした。
本作での再解釈
しかし本作では、
四面楚歌は
一度も「敵に囲まれる状況」として
描かれません。
むしろ謀次郎は、
次のように定義し直します。
四面楚歌とは、
正しさが四方から来て、
逃げ場がなくなる状態である
ここが最大の転換点です。
- 奉行所の「治安としての正しさ」
- 組頭の「秩序としての正しさ」
- 番頭の「経済としての正しさ」
- 寺の「慈悲としての正しさ」
これらはすべて
個別には正論であり、
善意であり、合理的です。
しかし
それが同時に襲いかかるとき、
人はこうなります。
- どこへ行っても怒られる
- どの選択も誰かを敵にする
- 誰の言うことも「間違ってはいない」
つまり、
正しさの包囲網が完成する。
なぜ「歌わせる」必要があったのか
謀次郎は、この四面楚歌を
- 戦わず
- 誰かを切り捨てず
- 正論で押し返さず
「歌」に変換します。
歌とは、
- 論理ではない
- 命令でもない
- 責任の所在が曖昧
- だが、感情を緩める力がある
ものです。
浪人が下手な歌を歌うことで、
- 皆の「正しさ」は一段階下がる
- 主張は笑いに変わる
- 管理したくなる衝動が露呈する
そして最終的に、
四方の者たちは同じ歌を欲しがる。
ここで物語は反転します。
囲まれていたのは浪人ではなく、
「正しさに取り憑かれた側」だった
最終オチの核心
浪人が去ったあと、城下は静かになる。
しかしこれは救済ではありません。
- 正しさは消えていない
- ただ、疲れて一時的に黙っただけ
謀次郎が最後に示すのは、
四面楚歌からの脱出ではなく、
対処法です。
正しさに囲まれたとき、
人は歌うしかない
このオチは、
- 解決を与えない
- 勝利も敗北も示さない
- だが、世界の動かし方だけは示す
という、
非常に江戸的・商人的・現代的な
結末になっています。
② 🧠 時代背景解説 阿波藩・口入屋・奉公制度の現実
阿波藩(徳島藩)の城下町
阿波藩(蜂須賀家)は、
- 外様大名
- 石高は大きいが、政治的発言力は限定的
- 城下町の統治は極めて実務的
という特徴を持ちます。
そのため、
- 治安
- 労働力
- 流民(浪人・無宿人)
の管理が、
幕府以上にシビアでした。
浪人は「危険人物」ではなく、
管理されない労働力
として恐れられます。
口入屋とは何者か
口入屋は、現代で言えば
- 人材紹介業
- 派遣会社
- 身元保証人
- トラブル調整役
をすべて兼ねた存在です。
重要なのは、
口入屋は「人を売る商人」ではない
「人と社会の摩擦を調整する商人」
だという点
謀次郎が常に
- 誰の味方にもならず
- しかし誰からも完全に嫌われない
立ち位置を取るのは、
職能として極めて正しい。
奉公制度のリアル
江戸の奉公は、
- 終身雇用ではない
- 契約は曖昧
- 人情と噂が支配する世界
です。
奉公人は「家の一部」ですが、
同時に 交換可能な存在でもある。
だからこそ、
- 素性
- 性格
- 癖
- 不満
を把握する口入屋が不可欠でした。
なぜ「芸」で逃がしたのか
浪人を
- 武家に入れれば、政治問題
- 町に入れれば、治安問題
- 寺に入れれば、慈善の競争
になる。
そこで謀次郎は、
労働力でも、管理対象でもない存在
――「芸」として町に放ちます。
これは江戸的には極めて合理的です。
- 芸は管理しづらい
- だからこそ、誰の所有物にもならない
- そして、責任が拡散する
つまり、
四面楚歌を
“四面合唱”に変換する技術です。
総括
この短編が描いたのは、
- 善悪の物語ではなく
- 勝敗の物語でもなく
社会が壊れないための、
ぎりぎりの知恵
です。
四面楚歌とは、
滅びの合図ではない。
正しさが多すぎるとき、
人は歌い始める
――それを知っている者だけが、
江戸の城下で、
そして現代社会でも、生き残る。
現代社会との対応解説 評価社会・管理社会における「四面楚歌」
1. 現代の「四面楚歌」は敵から来ない
現代社会において、
私たちは
敵に囲まれることは
ほとんどありません。
代わりに囲まれているのは、
- 上司の評価
- 同僚の視線
- 顧客の満足度
- SNSの反応
- 数値化された成果
- 空気としての「常識」
です。
つまり現代の四面楚歌とは、
悪意ではなく、
善意と合理性に囲まれる状態
なのです。
2. 評価社会=正しさの合唱
評価社会の特徴は単純です。
- すべてが可視化される
- 数値で比較される
- 説明責任が求められる
- 沈黙は「同意」とみなされる
このとき、
誰も「間違ったこと」を
言っていません。
- 上司は合理的
- 組織は効率的
- ルールは公平
- 数値は客観的
それでも人は疲弊します。
なぜか。
正しさが、
同時に、
四方から来るからです
これはまさに、
本作で描かれた四面楚歌と同型です。
3. 管理社会は「歌わせない」
江戸の城下では、
謀次郎は浪人に
「歌わせる」ことで逃がしました。
しかし現代社会は違います。
- 歌う前にKPIが設定される
- 歌い方にマニュアルができる
- 音程が評価される
- 客の反応が集計される
つまり、
歌すら管理される
結果として、
- 自由はあるが裁量はない
- 表現は許されるが評価される
- 逃げ道はあるが、記録が残る
この状態が、
現代的ディストピアの核心です。
4. 「誰のものでもない存在」は許されない
本作で最も重要なのは、
浪人が最後に
「誰のものでもない存在」 として
城下を去る点です。
現代では、この立場が極端に難しい。
- フリーランス → 評価サイト
- クリエイター → アルゴリズム
- 無職 → 社会的ラベル
- 沈黙 → 同意扱い
つまり現代社会は、
必ず「どこかに所属させる」社会
であり、
所属しない者は
「不安定」「危険」「非合理」
とされる。
これは江戸以上に厳しい。
5. 四面楚歌が「静か」になった理由
江戸の四面楚歌は、
- 噂
- 面子
- 直接の視線
によって成立していました。
現代の四面楚歌は違います。
- 通知
- スコア
- ダッシュボード
- ログ
- レコメンド
つまり、
楚歌が聞こえない
にもかかわらず、
常に包囲されている。
これが、
「笑えないが、はっきり怖い」
理由です。
6. 現代における「歌」とは何か
では現代において、
謀次郎的な「歌」は何か。
それはおそらく、
- 無意味な雑談
- 役に立たない趣味
- 収益化しない創作
- 評価されない善意
- あえて下手な振る舞い
です。
つまり、
最適化されない行為
評価社会では、これらは
「非効率」「無駄」「改善対象」
とされます。
しかしそれこそが、
四面楚歌から抜ける
唯一の“呼吸”
でもあります。
7. 本作が現代に突きつける問い
この短編は、
現代の読者にこう問い返します。
- あなたを囲んでいる「正しさ」は誰のものか
- その評価は、本当にあなたを救っているか
- 歌っているつもりで、管理されていないか
- そして――
歌うことを、怖れていないか
謀次郎は解決を示しません。
ただ一つの知恵だけを示します。
正しさが四方から来たとき、
それを正面から受け止めるな
一段、音程を下げろ
総括
江戸の城下町と現代社会は、
制度も技術も違います。
しかし共通しているのは、
人は「正しい世界」では生きられない
という事実です。
四面楚歌とは、
滅びの前兆ではありません。
管理と評価が完成しすぎた世界で、
人が息苦しさを感じ始めた合図
本作はそれを、説教ではなく、
人情と滑稽という古い技法で
描いた物語です。
だからこそ、
現代にもそのまま響くのです。