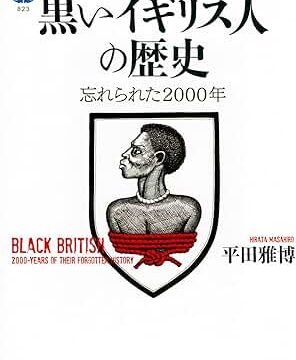【1】臨洮への道
出立の日の朝は、晴れていた。上邽の夏は、晴れると徹底して晴れる。雲がひとつもないというより、雲が出ることを忘れたような空で、東からの陽が城壁と屋根を斜めに照らしていた。
まだ暑くはないが、日が昇りきれば、黄土の道はたちまち光を跳ね返してまぶしくなる。旅立つにはちょうどいい時刻だった。
白起は荷を少なくした。凛にも最低限の荷を準備させた。残りは臨洮にあるものを使うつもりである。彼は本来、装備を整えてから出たい性分だが、今回の任務は「臨時」であり「補完」である。そこに余裕も、威厳も求められていない。
必要最低限の筆記具、墨、暦の控え、そして咸陽式の記録帳。衣は夏用で二組。あとは皮袋に入れた水、乾穀物と干し肉。軍の遠征に比べれば、まるで散歩のような量である。
上邽の北門を出ると、景色がいきなり開ける。城内の家屋と木々が視野から消え、黄土の台地が遠くまで続く。
春先なら野草が揺れているが、今は収穫に近づいた畑が多く、ところどころで雑穀と麻が育っている。背の低い作物ばかりなので、風が地面をすべるように走る。その風に土の匂いが混じる。乾いた、しかし不快ではない夏の匂いだ。
白起は一騎だけで北へ向かった。臨時の出張に加え、監察官の思惑もあったのだろう、県府からの援助は無かった。全て自前で用意し、道中の費用も自費だ。規定通りの天文官の出張であれば、馬車を雇い護衛を付けてもらえる。
しかし、白起の扱いはそれに及ばない。嫌われ者はどこの国でも冷遇される。だが、白起は歯牙にもかけなかった。むしろひとりのほうが気が楽だった。余計な世間話をせずに風と雲だけを見ていられる。
季節の変わり目の風景。夏から秋に差し掛かっていた。同行者はおらずとも、自然を共にし道中を楽しむ。
風は北からだった。乾いていて、しかし冷えの芯を持っている。夏の風でありながら、どこかもう秋を含んでいる。
(歩きやすい風だ。)
白起はそれだけ心の中で言った。声にはしない。声にすると、誰かと語ろうとする癖がつく。ひとりの旅は、ひとりのままがよい。
午前のうちは畑が続いた。畦には麻と、ところどころに染料のような草が植えられている。稲が背を伸ばし、色を黄金色にしていく。収穫の時期が近づいている。この時期を民は待ち続けている。北へ行くほど畑はまばらになり、代わって放牧の地が増えた。羊と、小さな在地の馬が、風のなかで草を食んでいる。
(このあたりから田はなくなるな。)
頭の中で記す。この川筋は、谷がすぐにふくれて増水する。田を作っても、ひとたび川が「怒る」と、流されてしまう。民はそれを知っているから、背の高い作物を避け、畜を増やす。生活が天候に押し戻されている土地だ。誰も天災には逆らえない。人間の営みとはそれほどか弱いものなのだ。
昼前、黄土を切って作った小さな窪地の集落に着いた。葺き屋根の家が十ほど、すり鉢の底のようにまとまっている。女たちが牛を世話し、子どもが羊を追っている。男たちは半分が畑、半分が川へ出ているのか、姿が少ない。白起が馬を引いて入っていくと、家から初老の男がひとり出てきた。顔が赤く、鼻筋が広い。胡の血が混じっているのかもしれない。
「お役人さんかね。」
「はい、上邽から臨洮への出張です。天文官の職を任されています。」白起は答えた。
「天を――」
男は白起を見上げて、少し背を伸ばした。
「このあたりの自然は、よく怒る。あんた、宥めてくれるのか。」
白起は首を振った。
「私は見るだけ。そして、暦を作る。宥めの力はない。自然がどう怒るかを見に行くだけです。」
「どう怒るか、か。偉い人は、怒りの筋を見に行くのか。」
その言い回しに白起の口元が、ほんのわずかだけ動いた。
「神さんでも、人でも、怒るには道理がある。川だってそうだ。何もないのに増水はせん。あんたらは、その“何か”を見るんだろう。」
「予兆を見逃さないようにするのが天文官です。」
「ふむ。」
男は空を見た。雲はほとんどない。
「では、今は準備期間だな。山に雲がかかりはじめたら、気をつけることだ。いまごろ、臨洮のほうは雨期に入る。」
「羌のほうから風が下りるのですか。」
「そうそう、羌のほうからだ。」
男は当たり前のように言った。白起は、その「羌のほうから。」という言い方を、いかにも現地の言い回しだと思った。天文官が「北西からの湿った気」が下ると書くところを、民は「羌のほうから」と言う。どちらも実態は同じだが、後者のほうが少し暖かい。
水をもらい、馬に馬草をやり、短く休んでから再び北へ向かった。午後になると風が強くなってきた。さきほどの男が言ったとおり、遠くの山の上にうっすらと薄い雲がかかりはじめる。黄土の地面を風が削り、ところどころで細かな砂が舞う。空はまだ青いが、青の底に鈍い灰が差してきた。
(今夜は鳴るな。)
白起は馬上で空を見上げた。
(昼は乾き、夜に雷と雨。)
今回の記録に、気象の型として残しておく。臨洮周辺の農耕暦を調整するには、夜間の降水も無視できない。少し北に上るだけで気象がこうも違ってくる。天文官が各地に配置されている理由がここにある。民は暦のズレに敏感になる。暦は農耕の生命線だからだ。
この辺から先は、話しかける者もいない。馬の歩む音と、風の音だけが続く。ときおり対向してくる荷馬車が「調子はどうだ。」と声をかけてくるが、白起は「悪くない。」とだけ答えて通りすぎる。長くは話さない。話をすればするほど、観測が曖昧になる。風の匂い、地面の柔らかさ、遠雷の間隔、不意にくる気象、徐々に変わりゆく天候――そういったものを逃したくなかった。
夕刻、丘を背にした小さな官舎に着いた。旅人と役人が使う簡素な宿で、壁は厚く、窓は狭い。番をしている若い兵が一人いたが、礼をしてから奥へ引っ込んだ。白起が話したのは、宿代と馬の餌の量だけだった。
夜になると、昼に見たとおり北のほうで雷が鳴り出した。直接の雨は来ないが、風だけが冷えて吹き下ろしてくる。白起は寝台に横になりながら、その雷鳴を数え、間隔を測った。遠雷が一晩で何度鳴るかで、向こうの雨量の大きさがだいたいわかる。
民が「神の咆哮」と呼ぶものを、白起は「風と雨の等時性」として記す。同じ音を聞きながら、違う言葉で残す。彼はそういう生き方を、もう十年もしていた。
第二日目の朝は、空が低かった。夜に遠くで鳴いていた雷のせいで、上層の風が湿っている。東の端が白む頃にはもう雲が薄く張っていて、陽は出ているのに光はやわらいでいた。白起は早めに起き、馬の具を直し、昨夜まとめた竹簡を巻き直した。ひとりで旅をしていると、こうした細かな手入れがそのまま心の整えになる。
宿の外へ出ると、風は北からだが、昨日よりも冷たかった。
――羌のほうで、水を落としている。
そう頭の中で言っておき、馬の手綱をとった。干し肉を口に放り込みながら道を進んだ。
この日の道は、しだいに下っていった。丘がゆるく溶け、黄土の段が低くなり、土はやや湿りを帯びる。川に近づく土地の変化である。畑は少なくなり、代わりに空き地で羊を洗う女たちの姿が目についた。羊の毛には黄土の粉がかぶっており、それを川の水で落としているのだ。
やがて、水音が聞こえはじめた。まだ川面は見えないが、風に混じってくる。乾いた土地で聞く水音は、耳にやさしい。川べりに出ると、予想どおり、流れは広くはないが速かった。
黄土色の水が、狭い谷をすべるように走っている。仮の桟橋があり、その脇に渡し船が一艘、杭につながれている。船は丸木をくり抜いたもので、旅人が立って乗るには心もとないが、馬と荷を渡すには十分だ。
渡し守は老いた男だった。髪も髭も白く、肌は黒く焼けている。ここで長く風に当たってきた者の色だった。白起が馬を連れて近づくと、男は竿を立てかけたまま、品定めをするように目を細めた。
「おひとりか」
「ええ。」
「見たところ役の方だな。」
「天文官の職で天を見に行くのです。」
「臨洮か。ちょうど風の出るころだ。」
男はそう言って、にやりと笑った。
「今日は水がやさしい。午の刻を過ぎると、上流がふくれる。渡るなら今がよい。」
言葉は短いが、どれも川の機嫌を知っている者の口ぶりだった。
白起は頷き、まず馬を船に乗せた。馬が警戒して前脚を踏みしめると、男は手早く鼻綱をとって、頭を低くさせる。動作に無駄がない。白起も板の上に立った。
「臨洮に赴任するのかい。」
男が竿を押しながら言った。
「いえ、咸陽からの命令で、しばらく滞在するのです。」
「ほお、それは大変な役目だ。向こうは夏も終わりかけている。気温の変化で体をやられないように気をつけたほうがいい。」
「肝に銘じておきます。向こうに言ったことが。」
「ああ、数年間、鍛冶場で働いていた。この近くは俺の生地でね。両親の世話をするために戻ってきたのよ。」
男は笑った。
「とても親孝行なお方だ。」
「まあ、親の相続がもらえるということも理由の一つだがな。」
男が高笑した。笑い声が谷に響く。随分と良く通る声だった。
「あなたの両親はどうしている。」
「私は孤児です。両親の記憶はありません。成人すると軍に入り生きてきました。」
「その軍人さんが天文官とは。なかなかに数奇な人生を歩んできたんだな。」
「ええ、これからも数奇は続くかも知れません。」
「ふむ、まあ飯と寝床があれば案外、幸せに暮らせる。人間は単純だからな。」
「まさに。高尚な考えなどすぐに欲求に負けてしまう。」
男がまた大声で笑う。
「よく悟られた方だ。久しぶりにあんたのような人間にあった。これだから船頭はやめられない。」
男は楽しそうに歯を見せた。男は白気を気に入ったらしく、一人で何度も頷いていた。
川の中ほどは流れが強く、竿がしなった。白起は無言で対岸を見ていた。水の色は昨日の夕方より濃い。音もやや太い。向こうでまとまって降っているときの水だ。
――今夜も鳴る。
白起は心に記す。
――夜に雨、昼に乾き、風は北。
臨洮の気候の型が、だんだんはっきりしてきた。
「いつから天文官をやっているんだ。」
男がまた話しかけてきた。
「春から赴任しました。」
男は苦笑した。
「まだまだ新人の天文官さんじゃありませんか。それにしては貫禄があるな。」
「一応、軍人をしていましたからね。その名残や習慣が残っているのでしょう。」
「官吏といえば、たくさんの人間を連れて出張するはずなんだがな。」
その言葉は、いまの自分に向けられたもののように聞こえた。実際、今回の出張をひとりにしたのは自分である。誰かを連れてくれば楽になるが、言葉が増えれば観測が散る。ひとりであれば、見るものが明確になってくる。
対岸に着くと、男は馬を静かに降ろした。
「さあ、天文官さんや、着きましたよ。」
「うむ、良い舵でした。」
「道中はお気をつけて。時々、山賊まがいのものが現れるのでな。」
男は笑い、少しだけ真顔になって付け加えた。
「臨洮は、夜が少しうるさい。風が吹き抜ける。眠るときは、窓を閉めて寝るこった。
「覚えておきます。」
白起は馬を引きながらそう言い、腰の袋から小さな銅貨を出して渡した。男は受け取って、軽く頭を下げた。
川を離れると、地形が変わった。丘が多くなり、乾いた土に灰が混じったような色になる。谷筋には細い水が走っているが、すぐに地にしみてしまう。そういうところには小さな木が生え、そこに羊や馬が身を寄せている。
道は、荷を運ぶ者が通るせいで、堅く踏み固められていた。前からは毛皮を背負った羌の男と見られる二人が、荷馬を引いてきた。白起をちらと見ただけで、何も言わずにすれ違った。互いに、ここは通るところであって、とどまるところではないと知っている。
少し行くと、煙のにおいがした。川水を使った作業場があるのだろうと思って近づくと、やはり、大きな釜で何かを煮ていた。羊の皮がいくつも積まれている。皮を柔らかくし、毛を落としているところだった。湯には草の汁か、灰汁が混じっている。匂いは強いが、風があるのでこもらない。
作業をしていた若い男が、白起の荷の形を見て声をかけた。
「役の方ですか。」
「ええ、臨洮の方へ。」
「なら、あの先の丘を越えたら休むといいですよ。風がまっすぐ当たるので、雲の形がよく見えます。そこで昼食などを取られると良いです。」
白起は軽く頷いた。
(この土地の者は、雲を見る場所を知っている。)
彼の専門と、まるで別のようでいて、根は同じところを向いている。
さらに進むと、小さな集落の脇に塩の煮詰め場があった。山のほうから出る塩泉を桶にため、土器に移し、火で炊いて白くする。女と老人が交代でかき混ぜている。薪は高いので、風の強い日を選んで火を燃やす。風があれば火力が上がるからだ。
風があるから乾く。
風があるから家は冷える。
風があるから塩ができる。
同じ風が、暮らしを助け、暮らしを痛めつける。これを「地の苦」と名づけるのがふさわしいと白起は思った。
昼どき、白起は丘の陰に馬をつなぎ、簡単な飯をとった。干した肉を小さくちぎり、水でふやかした麦餅と一緒に食べる。風が冷たいので、体の芯はいくらか楽だった。
食べていると、さきほどの塩場の老人が、壺をひとつ持って近づいてきた。白起が官の人間だと見たのだろう。
「お役人さん、飲むかね。」
「これは。」
「ちと塩を溶かした水だ。暑いときには楽になる。汗をかくときはこれに限る。」
白起は受け取り、口をつけた。しょっぱいが、不快ではない。乾いた土地で飲むと、かえって体が落ち着く。
「臨洮へかい。」
「ええ、天文官の仕事を任されています。」
「なら、夜に降ると言ってやるといい。あす、あさっては、きっと雨だ。」
「分かるのですか。」
「雲が低い。山の向こうで、昼に溜めて、夜に落とす。ここらはそういう時節だ。あんたらの書にも、そう書いといてくれ。」
老人は冗談めかして言ったが、目はまじめだった。
(民にも、書かれたい気候がある。)
そう白起は気づいた。自分たちが一行で済ませてしまう「夜雨」のうしろには、塩を炊く者、皮をなめす者、馬を育てる者、それぞれの日々がある。書くという行為が、彼らの生活を中央へ「通す」ことになる。
「書いても、雨は降り続けますがね。」
白起が言うと、老人は歯を見せた。
「やまんでもかまわん。忘れられるほうが困る。」
その言葉は、白起の胸にすとんと落ちた。
(忘れられるほうが困る。)
天文の報文も、まさにそれだった。星の位置がずれ、暦が遅れ、季節の掟がずれたとき、一行でよいから「ここでずれた」と残しておく。それがのちの者の手がかりになる。地上の塩も、川の怒りも、同じように「ここでそうなった」と記されるべきなのだ。
午後、空はさらに低くなった。遠くの山の稜線に、灰色の帯がかかる。音はまだしない。だが、空気が冷える。山を登りと寒さが強くなる。当たり前のことだが平地に住んでいると気づかない。現実の体験が経験の蓄積に生かされる。軍にいた時も同じだった。都で学んだ軍学が現場で役に立たない時が何度もあった。
白起は馬の歩をやや速めた。あまり遅くなると、川から上がってくる冷気が丘の上まで満ちて、夜の観測がしづらくなる。今日も宿に着いたら、雷の間隔を数えたい。北で鳴る音と、ここで感じる風との差が、臨洮の雨量の実態を教えてくれる。
この日の宿は、前日よりも粗末だった。土を積んだだけの小屋で、壁と屋根のすきまから風が通る。馬をつなぐ杭と、藁のかたまりがあるだけだ。番をしている若者が一人いたが、白起が手形を見せると礼をして下がった。話はそれで終わりだ。
ひとりでいると、沈黙が沈黙のままで済む。白起は荷をほどき、竹簡と筆を出して、今日見聞きしたものを順に記していった。川幅、渡しの数、川守の言葉、塩の煮詰め、風の冷え、雲の高さ。どれも大きくはないが、積み重ねるとその土地の「顔」になる。
書き終えるころ、北のほうでまた雷が鳴りはじめた。昨日よりも近い。
(今夜は、向こうで強く降る。)
そう確信し、白起は寝台に横になった。壁を打つ風の音が、臨洮へ近づいていることを告げていた。
三日目の朝は、乾いていた。夜半に北のほうで長く雷が鳴っていたが、こちらには一滴も落ちなかった。風だけが冷えて、宿の壁の隙間から通り抜け、寝台の上の薄布を揺らした。白起は夜のうちに雷の間隔を数え、竹簡に“北雷、五十余。間、おおむね均し。降水、向彼丘後面”と記しておいた。書き終えて寝たときには、空はまだうす暗かった。
夜明けには、雲がほどけていた。高いところに白い筋が流れ、東からの陽が黄土の丘を鈍く照らす。地面はやや冷えているが乾き切っている。前日の風で露が飛ばされたのだ。白起は馬具を締めを確認してから、北の道に戻った。
このあたりから、景色は「上邽の匂い」ではなくなった。土の色が少し灰を含み、丘が幾重にもかさなり、風に乗ってくる匂いに畜産の営みがまじる。畑はさらに減り、あるとしても谷筋に細く刻まれたものばかりだ。そこに黍や豆、短い麻が植えてある。丘の肩の部分には、羊の群れが点々と見える。羊の白が、黄土の色の上に浮いていた。
道は、ところどころで小さな市にぶつかった。とはいっても、城の市のように整っているわけではない。旅人が集まる場所に、だれかが布を張って湯を沸かし、だれかが干し肉や焼いた粉餅を並べる。荷を積んだ馬が並び、北から来た羌の男が腰をおろし、南に帰る秦の商人が水を飲む。そういう「通過の場」だ。白起は足を止めるつもりはなかったが、風がだんだん冷えてきたので、ひとつめの茶屋で馬を休めることにした。
布を張っただけの小さな茶屋だった。柱は三本、布は厚手で、風をいくらかはらっている。中に、大きな土器がふたつ、湯をたぎらせていた。そばに女がひとりいた。頬の骨が張り、目が涼しい。北の女に多い顔立ちで、手はよく働く者の手をしている。白起が馬をつなぎ、自分の水筒を持ったのを見て、女は器を出した。
「お役の方ですか。」
「上邽から参りました。」
「臨洮まで?」
「はい、臨時の出張で向かっています。臨洮はどのような気候ですか。」
「この時期は雨季に当たりますね。時々、大雨で作物が流されたり、村人が亡くなったりしています。」
女はまるで住んでいたかのように語る。
「夏でも風が冷たい。冬はもっと冷たい。雨は夜に来て、朝には顔を見せない。そういう町です。」
「夜に降るのですか。」
「ええ。山の向こうで昼に溜めて、こっちに落ちるのは夜。ここらではそう言います。もちろん昼に降ることもありますが。」
女がくすりと笑う。
「雨の多い町は初めてです。衣服が乾きにくそうです。」
白起がすぐに言うと、女は目を丸くした。
「お役人さん自ら家事をなさるので。」
「まあ、今回は臨時の職なので。そういえば、二夜つづけて北で雷が鳴理ました。風が冷えている。雲も低い。羌のほうで水を落としているかもしれません。」
「さすがは天文官様。」
女は感心したように湯を注いだ。湯には炒った麦の粉が入っていて、香ばしい匂いが立った。
「わたしらも空は見るんですよ。けど“降りそう”とか“今夜は鳴るぞ”とか、それくらいしか言えない。書にはできない。書くことができる人はえらいです。」
「しかし、書くことが災をもたらすこともありますから。」
白起が意味深長なことを言った。
「そうでしょうねえ。でも、書いといてもらえると安心しますよ。忘れないでいてくれるってことですから。三年前の大水も、五年前の洪水も、あっというまに忘れるんです、人は。忘れると、また同じところに家を立てる。そして、自然がそれを洗い流す。」
女は少し肩をすくめた。風が布を叩き、湯気が横に流れた。白起は器を持ったまま、その言葉を心の中にとどめた。
(忘れると、また同じところに家を立てる。同じ失敗を繰り返す。)
これは天文の報文においても同じだった。暦を一日ずらしたことも、閏月を足したことも、十年もすれば「なぜそうしたか」を忘れる。だから前と後をつなぐ一行が要る。ここでの「夜雨続」も、そこへ載せてやればいい。
「臨洮は、商いが多いです。羌の産物が流れてきたり、南からの商人が往来するので。」
女は土器の蓋をしめながら言った。
「畑でも食べますけどね。あそこは“通す”ところですよ。北から毛皮、南から塩や鉄、あとは秦の馬。羌の人も来るし、胡も来る。風があるから、旅人の匂いが残らない。まあ、そのぶん冬はつらいですけど。」
「風があるから炉が回る。塩も乾く。人がいなければ商いも生まれない。」
「そうです。風がないと、塩が死ぬんです。塩は貴重な品物ですから。」
女は、風で布がばたばたするのを押さえながら笑った。
「だから臨洮の人は、風に文句は言いますけど、風を嫌いにはなりません。風がなければ暮らせない。風があるから寒い。どっちもです。」
「地の苦ですね。」
「え?」
「地が与える苦しみです。」
「ああ、そう言うんですか。お役人さんは良い言い方を知ってますね。」
女は愉快そうだった。白起は器を返し、銅片をおいて茶屋を出た。
丘をひとつ越えると、空気がまた変わった。風がまっすぐ当たる。熱ではなく、山から下りてくる冷えを含んだ風で、馬の耳がぴくりと動いた。地面は締まっていて、砂は舞いにくい。遠くのほうで、馬の嘶きがよく響く。
(馬の町でもあるのか。)
白起はそう見当をつけた。風が強く、病が広がりにくい土地は、軍馬の育成にも向く。北や羌の馬をいったん臨洮で受け、南へ送る。そうなれば、そこには必ず「中央の目」が置かれる。今回の自分の派遣も、その延長線上にある。天文と軍馬は、一見離れているようで、実際は同じところで監視される。
さらに進むと、道が緩やかに右へ折れ、丘のあいだから盆地のような平地がのぞいた。そこに、黄土を固めた外郭が見えた高い城ではない。土を層にして積み上げ、ところどころ木の柵で補強してある。
外側には荷を積んだ馬が並び、番所の前で順番を待っている。皮を巻いた羌の男、塩を積んだ秦の馬車、鉄の農具を積んだ小商人。いずれも長居をする風ではない。ここで税を払い、またどこかへ向かう。女が言ったとおり「通す町」だった。
白起は馬をゆるめ、列の最後についた。風が、外郭の壁にあたって渦を巻き、砂を少し上げる。壁の上には弓を持った兵がいて、北から来る者を静かに見ている。順番になると、番士が近づいてきた。革の鎧に、黄土の色がしみている。
「どこから来た。名前と場所を。」
「上邽、天文台。白起。」
白起が手形を差し出すと、番士は受け取り、目を見開いた。
「白起様でございますか。」
「県令の田陵殿に面会をお願いしたい。」
「はい。県令より“白起殿来らば、直ちに迎えよ”と仰せを預かっております。さあ、中へ。」
番士は急に丁寧になり、門の脇に控えていた若い兵に合図した。若い兵が走って内側へ消える。すぐに門がわずかに広く開けられた。列を待っていた商人たちが、好奇の目でこちらを見たが、誰も何も言わなかった。ここでは、中央から来た客に対してそういう目が向けられるらしい。
門をくぐると、風の音が一段おさまった。外郭の土が、外の冷たい風をわずかに遮った。だが、完全には止まない。城内の通りにも、細く長く、北からの風が走っている。中は思ったよりも整っていた。中央に県府の建物があり、そのまわりに倉と兵舎、さらに外側に民家と作業場。塩を煮る小さな竈、皮を干す架、馬に水をやるおり。外から来た品をそのまま処理できるように、城の中に「手」が並んでいる。城というより、ひとつの大きな作業場のようでもあった。
すぐに、文吏らしい若い者が走ってきた。衣は粗いが、帯はきちんと締め、息を整えて礼をした。
「白起様でいらっしゃいますね。県令・田陵が待っています。お疲れのところ恐れ入りますが、まず府へお越しください。」
「お願いします。」
「こちらへ。」
若い文吏は先に立って歩き出した。白起は馬を兵に預け、荷をひとつだけ持ってあとを追った。
通りを歩くあいだにも、風は吹いていた。建物の角にあたって音を立てる。塩を煮ていた女たちが手を止め、白起を見た。外から来た者を測るような視線だった。
(この町は、外気が抜けない。)
白起はそう感じた。風は城壁で一度はね返されるが、また別のところから入り込む。外の気配を完全には遮断できない土地なのだ。
天文を記すには、こういう土地のほうがやりやすい。風や雲が「そのまま」届くからだ。だが同時に、中央の目もそのまま届くだろう。臨洮が辺境でありながら辺境ではないゆえんだった。
県府の前に着いたとき、風がふたたび強くなった。庇の下で、数人の役が並んでいた。その先頭に、五十前後の男が立っている。頬に少し陽に焼けた跡があり、眼差しは柔らかい。衣は飾り気がなく、ただ清潔だった。
「よくぞおいでくださいました。臨洮県令の田陵です。」
男は深く礼をした。
「遠路を。北の風は、慣れませんでしょう。」
「はい、なかなかに険路でした。風も強く、慣れるまでに時間がかかりそうです。」
白起は答えた。
「夜も風が止まらないのは一つの特徴ですね。」
「まさにそのとおり。ここは、昼は乾き、夜は騒ぐ土地です。だからこそ、白起殿にお越しいただきたかった。」
田陵の声には、歓迎だけでなく、どこか安堵が混じっていた。
「観測の器具は、上邽からのものと同じにはそろいませぬ。圭表も少し傾き、漏刻も管が傷んでおります。どうかお目こぼしを。」
「承知いたしました。よその者がとやかくいう事ではないので。」
白起はそう言って、広間へ入った。外で鳴っていた風の音が、家の壁にさえぎられて細くなる。だが、それでも完全には消えない。城の外から吹きつけていた冷たい風が、この家のどこかからもしのび込み、床の上をすべっていた。
(外の風は、止まらない。)
白起はそのことを、まず最初にこの町の成り立ちとして心に刻んだ。これからいく月か、この風の下で天を見、雨の型を記し、そしておそらくは中央の目とも向き合う。道中の孤独はここでいったん終わる。だが、孤独そのものが消えるわけではない。むしろ、ここからの孤独は、まわりに人がいるぶんだけ、静かで、深くなるのだろうと白起は考えていた。
【2】臨洮の匂い
臨洮の県府の広間は、思ったよりも簡素だった。咸陽の官舎にあるような塗りや彫りはなく、黄土を固めた壁に木の柱を渡し、床には厚い敷き蓆を重ねてあるだけだ。だが掃除が行き届いており、砂が溜まっていない。風の強い土地でこれを保つのは、それだけで仕事である。
「遠いところを、よく来られました。白起殿に来ていただけると、天文の仕事も捗りますし、何より臨洮の天文部の士気が上がります。」
「いえ、私のような人間にそのような力は。」
と謙遜する白起に田陵は笑顔で手をふる。
改めて見ると、県令・田陵は年は五十に届いたか届かぬか、整った額に白いものが少し混じっている。目つきは柔らかいが、辺境の官らしい、よく見ている目でもあった。
「上邽よりの簡を拝見いたしました。北天宿の観測補完、ならびに暦の微調整。加えて、風候の定点観察。どれもこちらとしては願ってもないことでございます。臨洮の暦は、どうしても一月ほどずれが生じることがあるのです。山からの風がそうさせるのか、民の気性がそうさせるのか。」
「原因を突き止めなければ官民ともに影響が出ますね。」
白起は簡潔に言った。
「夜に水が落ちると、民は朝を一日分長く見積もります。昼だけを見て耕すと、季節が遅れることがございます。」
「やはり、そうでございますか。」
田陵は嬉しそうに言った。
「こちらでもそう思ってはおったのですが、形にして咸陽へ上げるとなると、“そう思う”では済まぬ。白様に見ていただけるなら、こちらも胸が張れまする。」
「見て、書く。それだけですが尽力いたします。」
「それが一番ありがたい仕事でございます。」
田陵は笑った。笑ったあと、すぐに表情を戻し、白起の衣の砂に目をやった。
「三日程で来られましたか。」
「ええ、三日程。川で少しとどまったので遅れました。」
「この時節なら上出来でございます。羌のほうで降ると、こちらの川もすぐ機嫌を変えます。途中で足止めされたらどうしようかと思っておりました。……お疲れでしょう。すでに宿舎を整えさせております。臨洮の官舎は狭くて申し訳ないが、白様には一室を空けてあります。お連れは?」
「今回の職務は一人で行けとの咸陽の命です。」
「ではなおのこと、ゆっくりお休みいただけますな。――耆(き)よ。」
田陵が声をかけると、奥から中年の書吏が出てきた。体は細く、足取りが軽い。
「白起殿を官宿へ案内せよ。湯を沸かしておけ。食も、今日のうちに温かいものを。北の風で冷えておられる。」
「承知しました。」
書吏の耆は、すぐに白起に向き直って頭を下げた。
「こちらでございます。」
県府を出ると、また風が顔をなでた。城内でも風は弱まらない。白起は歩きながら、壁の陰と陽向きで温度が違うのを確かめた。夜に冷える町は、昼の温度差も大きい。
官宿舎は、県府からそう遠くなかった。府の北側、外郭のすぐ内側に、横一列に長く建てられている。兵と書吏、出張してきた官が寝泊まりできるようにしたものらしい。外観は粗く見えたが、基礎の土はよく叩いてあり、扉は新しい。戸口の脇に、臨洮でよく使うらしい乾いた木が積まれている。
「こちらは、ふだんは三人か四人で一室を使っております。が、白起様はお一人でお使いください。天文台の官吏もここで寝起きしておりますので、顔を合わせることがあるかと思います。」
耆が先に中へ入った。中は思ったよりもひろびろしていた。まず共用の土間があり、そこから右に食堂、左に長い廊下が伸びている。土間には旅人が靴を洗えるように水桶が置かれ、壁には衣を掛けるための木が並んでいた。
床は踏み固めた土に薄く漆喰を塗ってあり、砂が溜まっても掃き出しやすいようになっている。風の通り道には布が下げてあり、砂が直接入らない工夫がしてある。辺境の宿にしては、よく考えてあった。
食堂と呼ばれた部屋は、四角い空間に長机が二つ置かれただけのものだった。机は太い木を削って作られており、ところどころに傷がある。壁際に大きな竈があり、今日の分だろうか、干した肉と根菜とを煮た鍋が煙を上げている。竈の上には鉄の鉤が吊ってあり、冬にはここにさらに大きな鍋をかけるのだろう。風が吹いても火が消えないよう、竈のまわりには半月形の土塀が築いてある。
「日の出の際の朝食、昼休憩時の軽食、陽が傾くころに一度。徹夜の見回りがある日はもう一度、薄い粥を。白起様には、別にお持ちできるようにも申しておきます。自室でも食堂でも召し上がることができますので、いつでも申し付けください。」
「ご配慮に感謝いたします。基本的には食堂で食事しようと思います。」
「かしこまりました。」
廊下は、土と木を組んだだけの簡素なものだったが、ところどころに小さな明かり取りの穴があり、昼間は灯を入れずとも歩ける。窓は狭く、外に向けると砂が入るので、内側の中庭に向けて開けてある。中庭には井戸がひとつ、ささやかな畑がひとつ。葱と薬草が植わっていた。
「こちらです。」
耆が止まったのは、廊下のいちばん奥の部屋だった。扉を開けると、ひんやりした空気が出てきた。外よりも冷たい。壁が厚く作ってあるからだろう。中は一人で使うには十分すぎるほどの広さで、右手に寝台、左手に書き物ができる低い卓、それに木の箱がふたつ。床にも薄い敷き蓆が敷いてある。窓は一つだけで、北に向いている。上部に細い隙間が設けてあり、風だけが通る。
「この部屋は、もとより客用でございます。長く空いておりましたので、すぐにでもお使いいただけます。湯を持って来させますゆえ、荷物の整理をされておくとよろしゅうございます。」
「ご厚意に感謝いたします。」
白起が言うと、耆は一礼して下がっていった。足音が遠ざかると、宿舎の中は急に静かになった。外では風が鳴っている。だが厚い壁と戸が、音を丸くしている。人の声も聞こえない。食堂から鍋をかき混ぜる音が、時おりこすれるように伝わるだけだ。
白起は寝台に荷を置き、まず外衣を払った。三日分の砂が衣の襞からぽろぽろと落ちた。黄土の粉が薄く積もっている。これをここで落としておかないと、夜に書をひろげるときに汚れる。馬に使った紐、観測用の小さな器具、筆と墨。順番に卓の上に並べていく。
卓は低いが、面は平らで、墨をすっても揺れない。こういうところに、ここの官の性質が出る。見かけは粗いが、必要なところはきちんと作ってある。
荷をおおかたほどいたところで、戸口に気配がした。耆が湯を持ってきたのである。細長い土器に熱い湯を入れ、桶をひとつ持っている。
「こちらに。風が冷たいので、すぐ使われたほうがよろしゅうございます。」
「頂戴します。」
湯は、山のほうの井戸水を温めたものらしく、少し鉄の匂いがした。白起は袖をまくり、顔と手を洗った。砂と汗の筋が落ち、指先に血が通う。三日間、川でらしく洗うことができなかったので、これだけでもだいぶ軽くなった。
耆が下がると、また静かになった。白起は卓に向かい、巻いてきた竹簡をひろげた。
――上邽出立の日、風北。黄土乾。
――日目、村あり。民、川を人格で語るも、実は時節を知る。
――二日目、川幅中等。渡し守、三年前の出水を語る。
――塩煮詰め場あり。風を利用。
――三日目、風さらに冷ゆ。臨洮に入る荷多し。
簡潔に書いてはいるが、あの川の老人の顔も、茶屋の女の言い方も、地面の冷たさも、字には残っていない。文字にすると、土地の匂いが削がれる。だが、だからといって書かねば、たちまち忘れる。三日目に聞いた「忘れられるほうが困る」という言葉が、耳の奥に残っていた。
白起は筆を置き、窓のほうを見た。窓の外には、中庭の葱の葉が揺れている。揺れ方で、風の強さと向きがだいたいわかる。今は北西、強さは中くらい。日が傾きかけており、空はうすく白い。
――この風の下で、夜に観る。
そう決めると、旅のあいだ張っていた筋がゆるんだ。
白起はこれまでの三日間を内省していた。ひとりで歩いた。話した相手は、村の男と渡し守と、塩場の老人と、茶屋の女だけだ。どれも短い時間で終わる話ばかりだった。これがよかった。
長々と話せば、民は天を「信仰」で語りはじめる。それはそれで興味深いが、今の自分には要らぬ厚みだった。必要なのは、風がどこから来て、雨がいつ落ちるかだけである。
それでも、あの男が言った「怒りの筋」という言い方は、覚えておいてもよいと思った。川も山も、怒る前に印を出す。風を変え、雲を低くし、鳥を静かにする。人がそれを見逃すから、怒りだけが突然に見える。怒りの前と後をつなぐのが、天文官の仕事だ。
――臨洮でも、それをやる。白起は静かにうなずいた。
廊下のほうから、鍋のふたを開ける音がした。香りが流れ込んでくる。干した羊肉を柔らかく煮た匂い、根菜の甘い匂い、北の葱の強い香り。旅の途中で食べた干し肉や麦餅にくらべると、はるかに落ち着いた匂いだった。
昼餉の時間になっている共用の食堂では、兵や書吏たちがもう椀を手にしているだろう。彼らは互いに今日の見張りのことや、北から来た羌が何を売っていたかを話す。だがこの部屋には、その声は届いてこない。
――ひとりで食べることもできるな。
白起は卓の上の墨をふたたび整え、明日からの観測の段取りを頭に並べた。まず臨洮の圭表を見る。傾きがあれば、地面の沈みか、風で動いたかを確認する。漏刻は、おそらく管が傷んでいるので、上邽式の目盛りに合わせ直す。
夜の観測は、風があるので衣を増やす。報文の書式は、上邽で使っているものを渡す。田陵は喜ぶだろう。そうやって仕事の筋を立てていくうちに、旅の疲れは自然と仕事のほうへ吸い込まれていった。
窓の外で、風がまた強くなった。壁がうすく鳴る。白起は耳を澄ませた。
――昼は乾き、夜は騒ぐ。
この町の気候をあらわす最初の一行が、心の中で形になった。彼は筆をとりあげ、そのまま竹簡に記した。「臨洮 風冷く 昼乾き 夜騒ぐ」それを書いておいてから、立ち上がった。食堂へ行くには、もうよい時刻だった。
食堂は、昼餉の匂いで満たされていた。
干した羊肉を煮た匂い、根菜を崩れるまで煮込んだ甘い匂い、北の葱のつんとした香り。竈の火は土塀で囲まれているので炎は見えないが、湯気だけが細く立って、昼の光に照らされた室内をゆらがせていた。窓は小さく、外の砂が入らないように布が垂らしてある。外はまだ風が鳴っているが、この部屋ではそれが遠い。
白起は人の少ないほうの長机に腰をおろした。湯気の立つ椀をひとつ、あとは麦の餅を三枚。旅のあとの胃には、これで十分だった。椀の中身は、羊と大根に似た根と葱、それを骨でとった出汁で煮たものだ。脂はほとんど浮いていない。辺境の煮物は、油より塩で味を作る。
一口、白起は静かに食べた。塩が少し強い。だが冷えた体には収まりがいい。向こうの机では、兵と書吏が三、四人で騒がしく話している。北から来た羌の荷がどうとか、明日、塩を運ぶ番がどうとか、そういう話である。
白起の机までは全て届かない。誰も彼に話しかけようとはしなかった。新しく来た官が無口で食べているときは、放っておくのがこの土地の礼儀なのだろう。そう思っていたが、
「……白起殿であられるな。」
背のほうから、年配の、しかしよく通る声がした。白起が顔を上げると、目の前に痩せた男が立っていた。見たところ官吏の制服を着ており、食堂にいるということは役人だろう。衣は簡素にまとめており、腰に帯を締めている。顔は長く、目は細い。だが目の奥は疲れていない。
「私は公孫庭と申します。明日から貴殿と天文台を取り仕切る者です。お会いできて光栄です。席をともにしてもよろしいか。」
「どうぞ。」
白起が椀を少し脇に寄せると、公孫庭は正面ではなく、やや斜めに腰をおろした。向かい合いすぎると話しづらい、という土地流の配慮かもしれない。すぐあとから、三十そこそこの男が一人、若く几帳面そうな男が一人、そして肩幅の広いがっしりとした男が一人、順に入ってきた。
「白起様、お邪魔いたします。」
梁宛が一番丁寧に頭を下げた。眉が濃く、目つきはまじめで、あまりむだなことを言わなさそうな男だった。つづいて荀潁が、慌てているような、しかし興味が勝っているような顔で会釈した。最後に入ってきた馬渓だけが、椀を二つ持っていて、にやりと笑った。
「今日の食堂はちゃんとしたものが出てますな。」
馬渓はまるで自分の家であるかのように机の端に腰を下ろした。公孫庭も咎めない。どうやら、これがいつもの並びなのだろう。
「白起殿。」
公孫庭があらためて言った。
「臨洮の天文を預かっている者たちです。さきほどは粗略な挨拶になりましたでな。食の席で失礼いたします。」
「いや。こちらこそきちんとした挨拶もまだでした。他の皆様も。」
白起が答えると、公孫庭は満足そうにうなずいた。
「三日で来られたとか。風が味方しましたな。あの川で一晩でも寝ると、もう体が冷えてしまう。都暮らしの人間には厳しい環境ですよ。」
「渡し守がよく働いたのです。川の調子も良かったのです。」
「おお、まだおりましたか。あの老人は川のほうが家より長い。まさしく守神といったところだ。」
公孫庭は愉快そうに笑った。この男は、古いが、地の話題をよく覚えている。白起はそう思った。
「では、あらためてご紹介を。」
公孫庭が手で示した。
「こちらが、ふだん夜の観測をまとめている梁宛。若いが、星をじっと見ていられる目を持っております。」
「梁宛です。白起様のお名前は文で拝見しておりました。記録が、ええ……無駄がないという感想です。」
梁宛は言葉を選びながら言った。褒めているのに、指先に緊張が残っている。白起が寡黙だと聞いて、言いすぎないようにしているのかもしれない。
「こちらが記録を担当する荀潁。記載を乱さないので助かっております。」
「荀潁でございます。白起様の報文を実物で見られるのは光栄です。勉強になります。」
若いのに官の言い回しが板についている。白起はうっすらと、こういう若い目がひとりいると、部は長く持つな、と感じた。
「で、この者が」
「馬渓です。白起様がおいでになったら、飯が増えるって聞いております。」
馬渓が先に言った。公孫庭も梁宛も苦笑した。白起は馬渓を史狗と重ねていた。馬渓は自分で竈のほうへ行き、鍋から肉を少し多めによそって戻ってきた。竈の女も注意しない。いつものことなのだろう。
「四人。これがいまの臨洮の天文でございます。」
公孫庭がまとめた。
「本来なら、書く者がもう一人おってもよいのですが、ここは兵との兼帯もありますのでな。羌賊が出ると、見張りのほうも人手がいる。だから、白起様がお越しくださったのは、実を言うと天文だけのためではなく……」
「人を割く余裕がない。」
「お察しが早い。」
公孫庭は笑って、椀に口をつけた。白起も食べながら、彼らの顔をひとりずつ見た。梁宛は椀を持つ手がまっすぐで、食べ方も静かだ。荀潁は緊張しているのか、肉よりも汁ばかり飲んでいる。馬渓だけは、もう二度目の肉に箸を伸ばしていた。
「臨洮の産は、見てこられたか。」
公孫庭が問うた。
「河川での皮と、塩の煮詰めと、馬を見ました。」
「それなら、おおかたは掴んでおられますな。」
公孫庭はうなずき、少しだけ説明を足した。
「臨洮は、畑だけで食えぬ土地です。昼は乾きますし、雨は夜に落ちます。だから、日中に働く農は、どうしても水のない時間ができる。その時間をみな、手の仕事に回すのです。皮をなめす、塩を煮る、鉄を打つ、縄を綯う。風があるから火が回る。風があるから乾く。風があるから家が冷える。そういう土地です。」
「“通す”と言っていました。」
白起が言うと、公孫庭は目を細めた。
「茶屋の女が申しましたか。」
「そうです。」
「あの女はよく見ております。ここは通す土地です。北から来る毛皮も、南から来る鉄も、一度ここで数え、税をとり、また通す。関の役割もある。そして、羌族への防衛戦にもなります。だからこそ、ここに天文の目を置けと、咸陽が言ったのです。通す土地は、季節が少しでもずれると、すぐに商いの息が止まる。」
そこまで言ったところで、横から声が入った。梁宛だった。
「白起様。ここは夜に観ることが多いので、圭表がすぐ狂います。風で傾くのか、土が沈むのか、はっきりとは申し上げられませんが、ひと月に一度は直してやらぬと、昼の影が合わないのです。上邽でもそういうことはありますか。」
「ない。あそこは風が弱い。土も深い。」
「やはり……」
梁宛は小さく息をついた。
「ですから、こちらでは“昼の影で決めてはならぬ”と言い伝えがあるのです。夜の星で見て、昼は合わせるだけにせよ、と。」
「それが臨洮のやり方か。」
「はい。」
白起は少し考えた。雨が多い土地で夜の星をもとに暦を引くのは、いくぶん無茶にも見える。だが、そうでもしなければ日中の乾いた時間にばかり引っ張られて、作業の暦がずれていくのだろう。
――夜を主にし、昼を従にする。
この土地の気候に沿っている。それを、公孫庭はきれいな官文にしづらくて困っているに違いない。
「公孫殿。」
「はい。」
「臨洮のやり方を、そのまま咸陽に上げたことはありますか。」
「あります。ありますが……」
公孫庭は、少し肩をすくめた。
「“夜に雨が多いゆえ、夜の星を主にす”と書きましてな。それでも、咸陽の役は“昼に測り夜に補え”から動こうとしない。あちらはあちらで理が立っておるのでしょう。ですが、ここでそのやり方をすると狂う。だから、いったん咸陽の形にしてから、臨洮の中だけで“ほんとうの暦”を回しております。」
「二重にしているのか。」
「そうなります。理想と現実は違う。そううまくはいかぬのが天文、白起殿もよく承知のはず。」
公孫庭の声に、どこか批判めいたところがあった。規格に従いつつ、実務で別のものを回す。官としてはあまり褒められたことではない。
そこで、これまで黙って食べていた馬渓が、箸を止めて口を挟んだ。
「白起様。あの咸陽の書き方のままなら、ここの奴らは、いつまでも畑に水を引くのが遅れるんです。へたしたら水が行く前に夜が鳴って、また流される。それで、また“神が怒った”と言う。馬も動かせんです。だから俺らが“今夜降るぞ、明日は遅く起きろ”って言うと、やっと合うんです。」
言ってから、少し気まずそうに白起を見た。白起は眉を寄せもせず、ただうなずいた。
「理に合うなら、それでいい。」
「え?」
「理は、守るためにある。書くためではない。理想ばかり追って何物も得られないのなら、何のために官があるのか。」
馬渓の顔に、ぱっと明るいものが出た。公孫庭も、どこか安心したようだった。
「そうおっしゃっていただけると、こちらも気が軽くなります。……咸陽の書式を守ることと、民を季節に合わせることと、どちらかを一日だけずらせと言われたら、わたしは後者をとります。」
「正しいことです。」
白起は短く言った。そこへ、荀潁が、ためらいがちに手を上げた。
「あの、白起様。ひとつお伺いしてもよろしいでしょうか。」
「うむ。」
「上邽の天文台の報文で、“風候を三日に一度くわしく書く”というのがありました。あれは、ここと同じく、夜に変化が多いからでしょうか。それとも、咸陽がそう求めたのですか。」
若いだけに、質問がまっすぐだ。白起は椀を置いて、荀潁を見た。
「三日に一度詳しくしたのは、私の考えだ。川上の天気が三日周期で変わるときがある。三日で一巡するものは、日々では拾いきれん。」
「では、こちらも三日に一度で。」
「いや」
白起は切った。
「ここは、夜が多い。三日では足りぬ。二日に一度にする。夜に雨があったら、そのぶんは翌朝に書け。昼の乾きも添えろ。夜雨と昼乾きがつづくと、土が割れる。割れた土に、次の雨が深く入る。」
荀潁は一気に顔を明るくして、懐から小さな札を出して書きつけはじめた。梁宛も聞き漏らすまいとして身を乗り出した。こういう瞬間だけ、部屋の空気が若くなる。白起はその変化を、どこか外から見るような気分で眺めていた。
食堂の外で風がまた強く鳴った。布がはためき、竈の火が小さく揺れた。臨洮の夜が近づいている。まだ星は出ていないが、天を語る者たちの顔にはすでに「今夜は観る」という色があった。
談義のあとは、しばらく五人とも黙って椀を進めた。黙っていても気まずくならないあたり、この四人はふだんから一緒に飯を食っているのだろう。白起は、彼らの食べ方の違いを見ていた。
梁宛は静かに、汁をこぼさず、箸を机に打ちつけることもない。荀潁は書きつけた札を膝に置いたままで、上の空で飲んでいる。馬渓は音を立てる寸前で止める、ぎりぎりのところで食う。公孫庭だけが、年寄りらしくゆっくり噛んでいた。
やがて、公孫庭が思い出したように白起を見た。
「白起様。……ひとつ、今年のことでご相談がございます。」
「何事でしょうか。」
「この春先、川が一度だけ“妙な増え方”をいたしました。夜に鳴っていなかったのに、昼過ぎにいきなり水が出たのです。風も北ではなく西寄りで。わたしどもの記録棚を見ましたが、似たようなことは十数年前に一度あるきり。あれはどう書くべきか、ずっと迷っておったのです。」
「十数年前のは、残っているのですか。」
「残しております。墨が薄くなっていますが、“一日のうちに水かさ増す。山より来る音なし”とだけ。」
「では今年のも、そのまま書きましょう。無理に理をつけずに。理がつかぬときは“つかぬ”と書く。」
白起がそう言うと、梁宛が顔を上げた。
「“理がつかぬ”と、咸陽に出してよろしいのでしょうか。」
「よい。事実をねじって理に合わせるよりはましだ。あとから見る者が、“この年は何かあった”とわかればいい」
荀潁が、また札を出して書きはじめた。その様子を見て、馬渓がにやりとした。
「荀さん。書きすぎるとまた棚が重くなりますぞ。」
「重い棚のほうが、後で見る人が嬉しいんだ。公孫様だってそうおっしゃっていた。」
「わしは“不要なものは捨てろ”とも言ったぞ。」
公孫庭が笑いを含ませて言った。部屋の空気が少し和んだところで、白起が口を開いた。
「その春先の増水だが、山のほうで伐りはなかったのですか。」
「伐り……?」
「木を切ることです。薪か、開墾かで。」
「ありましたな。」
先に答えたのは馬渓だった。手を止めずに話す。
「羌のやつらが山の肩を荒らした。あそこに木を残しておくと、獣が潜むからって。」
「木を切ると、水が直接降りる。土に含ませる前に、谷に落ちる。音がなく水だけ来るのは、そのせいだ。そうも書いておけ。」
「なるほど……。」
公孫庭が素直に感嘆した。
「“羌、山を伐る。翌月、音なくして水出づ”――これなら、咸陽にも通るかもしれませぬ。木を切ると水が荒ぶる、というのは、ほうぼうで言われてはおりますが、こうして官の文に立てたことはあまりない。」
「木と水はつなげておくと良いです。臨洮は、風と水が動く土地です。」
「はい。……いやあ、助かりますな。」
そのとき、梁宛が、少し遠慮がちに白起を見た。
「白起様。ついでに、もうひとつお尋ねしてもよろしいでしょうか。」
「うむ。」
「このところ、北天が……いや、北ではなく、北西の空が、夜になると白むのです。雲でもない、砂でもない。ごくうすい、白い煙のようなものが、空の高いところに出る。星は見えますが、線が引きにくい。あれは、何と書けばよろしいでしょう。」
「……北西が白む?」
白起は箸を止めた。臨洮は咸陽よりも北西に近い。大陸の乾いた風が、そのまま高空を流れる。砂が高く舞えば、夜でも白んで見えることがある。だが、梁宛の言い方は、もう少し違う気配を含んでいた。
「夜のどの刻だ。」
「子の半ばから丑にかけて。風が急におさまると、うっすらと。」
「地面は冷えるか。」
「冷えます。」
「なら、上の冷えと、地の冷えがかぶっておる。上が乾きすぎて、光をよく返すのだ。書き方は“夜、上乾きて白む。星なお見ゆ”でいい。」
「“なお見ゆ”……。」
荀潁がまた書きとめた。
「“星を失うほどにはあらず”でもいいが、長いな。」
「長いですね。」
「短くしておくことだ。」
白起はまた椀に手を伸ばした。すると今度は、馬渓が、椀を持ったまま身を乗り出した。
「白起様。産のことですけどな。塩がこの夏は薄いんです。山の泉がちょろちょろいうだけで、冬の残りが足りない。あれも書いといたほうがええですか。」
「塩が薄いのは、山の水が増えているからだろう。春のうちに多く雨が落ちたか。」
「落ちました。」
「なら、塩の薄さも書け。塩が薄いと、皮も傷みやすくなる。皮が傷むと、北の商いが止まる。北の商いが止まると、ここを通る馬が減る。馬が減ると、兵にすぐに響く。……産も天文に連ねておけ。通す町は、天気が止まるとすぐに商いが止まる。」
馬渓は「ああ、やっぱり」といった顔をした。
「県令殿が“塩のこともあげておけ”ってうるさく言うんです。天の書に、塩も入れろって。」
「田陵殿は間違っていない。」
白起が言うと、四人とも少し驚いたように彼を見た。白起は構わず続ける。
「臨洮の天文は、この土地を動かす理をまとめる役だ。塩が薄くなるのは、山の水が多いからだ。山の水が多いのは、風と雲がそうしたからだ。なら、天文の帳に書いてよい。書けば、あとの者が“この年は塩が弱い”とわかる。」
「なるほど……。」
公孫庭が目を閉じてうなずいた。
「では、わたしたちのこれまでの“ついで書き”も、あながち間違いではなかったわけだ。」
「間違いではない。むしろ皆は、この土地をきちんと見ている。」
静かな言葉だったが、梁宛と荀潁は顔をほころばせた。馬渓は照れ隠しに、わざと大きく汁をすすった。
そのとき、廊下を誰かが歩いてくる音がした。足音は二つ。食堂の戸が音を立てて開き、ひとりの男が中をのぞいた。四十前後、細身で、目が冷たい。衣は他の者よりも新しく、腰の帯は濃い色をしている。監察吏の韓慎だった。
「おや、そろっておられる。」
声は穏やかだが、観察する目だった。
「新しいお客人も。」
公孫庭がすぐに立ち上がった。
「韓慎殿。上邽から白起殿がお越しですので、ささやかながら歓迎を。」
「それはそれは。……白起殿、咸陽よりお名前はうかがっております。」
韓慎は礼をした。その礼は、深くもなく、浅くもなく、ちょうど官に対するぶんだけのものだった。
「韓慎と申します。臨洮への出張監察の任で来ております。」
「白起です。私も臨時の出張で。」
白起も短く名乗った。
「お加減はいかがです。北の風は、内地の方には堪えましょう。」
「はい、何とか体を慣らしております。」
「それは何より。」
慎はすぐには腰をおろさず、室内を一巡するように見た。竈、机、壁、窓。視線が最後に白起の卓の上に止まり、すぐに離れた。
「こちらの天文部は、こうして食をともにされるのですな。仲がよろしい。」
「人手が少のうございますのでな。」
公孫庭が答えた。
「では、咸陽からのお目付け役にも混ざっていただきとう存じますが。」
「いえ、わたしは見ておるだけで。どうぞ続けて。」
そうは言いながら、韓慎も椀をとり、卓の端に腰を下ろした。距離はあえて一つ分あけた。白起の真正面ではなく、斜めの位置だ。話すときも、こちらが正面を向かねばならない角度ではない。
馬渓が、いつもの調子で話を続けようとしたが、梁宛がわずかに首を振った。韓慎がいるときは、あまり軽口を利くな、という合図だった。だが韓慎はそれを見て、逆に言った。
「構いませんよ。仕事の話なら、むしろ聞かせていただきたい。わたしはこの土地の気象は素人ですので。臨洮は、夜に降るのでしたな?」
「はい。夜に騒ぎ、昼に乾きます。もちろん昼の雨もありますが。」
梁宛が答えた。
「それで、上邽の書式だと少し合わないと。先ほど白起様にお教えいただいたところでございます。」
「ほう。」
韓慎は白起に目を向けた。
「さすがに、お見えになってすぐに“二日に一度にせよ”とは。咸陽でもそういう柔らかさを見せていただけるとよいのですが。」
「土地に合わせるだけです。」
「ええ。土地に合わせる、ですか。」
韓慎は、笑っているのかどうか判別しにくい表情をした。
「わたしはいつも思うのですが、書というものは、汚れているほうが後々まで残るものです。きれいに整えた文は、読むと気持ちはいいが、どこにも引っかからずに流れていく。白起殿のように、短く整った書きぶりは、わたしのような者には少し眩しすぎる。」
「汚れは、後の者が困りますので。」
「困っても、残るのですよ。」
韓慎は椀に口をつけた。公孫庭も、これはあまり深入りさせないほうがいいと見たのか、話題を横へずらした。
「韓慎殿、白起殿に、ここの産のことも少しお話しておりました。塩が薄い年は、やはり監察のほうでも気になりますか。」
「なりますね。税の数字が変わりますので。」
「天文の帳に添えても良いので。」
「書けるなら、書いていただけると助かります。天文の帳は“手を入れにくい”ので、そこに産の数字がちらと残っていると、後から“この年は山が出なかった”とわかる。記録を汚すことになりますが。」
また「汚す」を使った。白起は箸を置き、韓慎を見た。
「汚れていても読めるものと、汚れたら読めなくなるものがあります。」
「ええ。だから白起殿に来ていただいたのでしょう。」
韓慎は、抑揚のない声で言った。
「臨洮の帳は、臨洮の風でだんだん汚れていく。そこへ一度、上邽の風を入れて、どこまで澄むかを見てみよう――咸陽はそう考えたのだと、わたしは理解しています。」
それは、ほとんど本音だった。部屋の空気が少しだけ引き締まった。馬渓が椀を置き、荀潁が姿勢を正し、梁宛が公孫庭を見た。公孫庭は何も言わない。白起も何も言わない。
沈黙が、短く一巡した。その沈黙の質が、昼に白起が部屋で感じたものと同じだと、彼は思った。外から入ってきた風が、厚い壁で丸くされたあとの、残りの静けさ。完全には消えないが、直接は当たらない静けさ。
最初にそれを破ったのは、公孫庭だった。
「……まあ、風が変わるのはよいことです。わたしたちも、ずっと四人でやっていると、どうしても同じところを同じことばで書いてしまう。そこに、中央のやり方と、上邽のやり方と、おまけに白起殿の目とが入れば、帳も色を増やすことができます。」
白起もそこでうなずいた。
「同じ土地を同じ者が見続けると、目も土地の色になる。外から来た目が、年に一度でもそこを見ておくと、ずれがわかります。」
「やはり、来ていただいてよかった。」
公孫庭の声には、心底の安堵があった。梁宛も続けた。
「わたしたちはここで生まれましたから、この風が“普通だ”と思ってしまうのです。ですが白起様は三日歩いただけで、“夜に騒ぐ土地だ”とおっしゃる。そうだ、これは騒いでいるのだ、と気づきました。」
「騒ぐ土地に、静かな帳は似合いませんから。」
白起が言うと、馬渓が面白そうに笑った。
「臨洮が騒ぐと前からいっておったでしょう。」
「おまえの言い方は乱暴なんだ」
梁宛が苦笑した。荀潁も、少しほっとしたように笑った。韓慎は、そのやりとりを静かに眺めていた。やがて立ち上がった。
「邪魔をしました。白起殿、今夜の観測にもお出ましになりますか。」
「いえ、観測は明日の夜からとなっております。」
「では、明日は私も見させていただきます。……臨洮の夜は冷えます。上邽の衣のままでは、少し足りないかもしれませんよ。」
「お気遣い感謝します。」
「では。」
韓慎は礼をして、静かに出て行った。廊下の足音も乱れない。彼が去ると、部屋の空気がまた一段やわらいだ。馬渓が、大きく息を吐いた。
「ふう。あの人がいると、汁まで冷える。」
「失礼なことを言うな。」
公孫庭が言ったが、怒ってはいない。
「しかしまあ、よいものを見られた。咸陽の目の前で、白起殿に“それでいい”と言っていただけたのだからな。」
「わたしも、よくないことはよくないと言う。」
白起は椀を置いた。
「ですが、皆さんはこの土地を見て書いている。なら、理に立つ。理に立つなら、上へも出せる。」
「はい。」
梁宛が、はっきりとうなずいた。荀潁も、札を大事そうに胸にしまった。馬渓は、残っていた肉をすばやくさらった。
「白起殿。」
公孫庭が、最後にもう一度だけ呼びかけた。
「明日の観測は、まず圭表をご覧になりますか。それとも、丘に上がって北天を見ますか。」
「まず器です。器が狂っていれば、星を見ても意味がない。」
「承知です。梁宛、馬渓、あの傾いたものを据え直しておけ。荀、おまえは今日の分の帳をまとめて、白起様のところへ持っていけ。」
「はい。」
四人はすぐに立ちあがった。食堂は一気にがらんとした。竈の火だけがぼっと明るく、外の風の音がまた戻ってくる。白起は少し遅れて立ち、器を重ね、竈の女に返した。
「口に合いましたか。」
「臨洮を知ることができました。」」
「それはよかった。北の風が出ると、あたたかいものがいちばんです。」
女はそう言って、また鍋をかき回した。白起は食堂を出て、廊下に立った。外はまだ昼時で、風は穏やかになっている。廊下の突き当たりには、自分の部屋の戸が見える。
これからこの町で夜に騒ぐ天を相手にする。ほんの少しだけ、人の声を聞いておいたのは、悪くないことだった。
【3】臨洮の町
食を終えると、白起は椀を返し、食堂の女に一礼して廊下へ出た。風はさきほどより冷えている。部屋に戻り、帯を締め直し、靴の紐を改め、袖口を二重に折る。観測の道具は置いていく。散歩が目的で、荷は軽いほうがよい。竹簡と細い筆だけを筒に入れ、腰へ結んだ。戸を閉めると、厚い壁の内側の静けさが背中に残った。
官宿の廊下を抜けて外へ出る。日が傾き、城内の影が長い。風は北西から通り抜け、建物の角で音が変わる。門番に手形を見せると、番は軽く礼をして道をあけた。
県府の前の通りは、城の骨である。中央に馬の通り道、左右に人の道、道の間には排水の浅い溝が掘ってある。土は踏み固められていて、砂が舞いにくい。通りの奥に、塩を煮る小さな竈が幾つも見えた。風を拾うように半円の土塀を置き、その内側で火を守っている。女たちが木の棒で鍋をかき混ぜ、上に薄い膜が張ると、網で取り上げ、土器の皿に広げて乾かす。風があるので、乾くのは早い。
少し進むと、皮を扱う場があった。羊の皮が横木に張られ、しみ出した水が溝へ落ちていく。桶には草の汁と灰汁が混ざっている。男が棒で皮をなで、毛を落とす。匂いは強いが、風が拡げる。白起は足を止めず、数を数えた。皮の数、鍋の数、火の数。こういうものは季節の指標になる。
通りの角では小さな鍛冶の音がした。鉄の農具を打つ場で、少年がふいごを押し、老人が槌を振る。扉は風下に向けて少しだけ開いている。余計な砂を避け、火にだけ風を当てるように作ってある。刃を水に落とす音が短く鋭い。白起はひとつだけ質問した。
「今季の鉄は、割れやすいですか。」
老人が顔を上げて答えた。
「春は少し。今は落ち着きました。水が多いと割れます。」
「左様ですか。」
白起は歩いた。城の西側へ回ると、馬の囲いがある。木の杭を結い、馬が頭を突っ込んで餌を食べられるようになっている。南へ送る馬、北から来た馬、入れ替えの馬が列になっている。水桶に薄い氷のような膜はない。今はまだ秋の手前だ。若い者が馬の脚を見ていた。白起が近づくと、若者は立ち上がり、帽を取った。
「県府の方でございますか。」
「上邽の天文官、白起だ。」
「そうでしたか。遠路お疲れ様でございました。今夜は風が少し強くなりそうです。」
「そうだろうな。」
白起は囲いの端まで歩き、糞の山と藁の湿りを見た。湿りが浅い。昼間に乾いている証拠だ。夜に雨が来れば、朝にはまた顔を変える。竹簡に短く記した。
城の北側は、外郭の土塁が高い。風がぶつかり、音が重くなる。ここから城外へ出る小門があり、見張りが二人立っている。遠くの丘の上に、薄い雲が出た。白起は立ち止まり、雲の高さを見て、風の硬さを確かめた。北西、高さは低い。夜には音が来る。今はまだ静かだ。
南側へ戻る道の途中、白起は県府にあるという竹簡部屋へ向かった。昼に公孫庭が「古い棚がある」と言っていた場所だ。見張りに名を告げると、書吏が現れた。細い体つきだが、手は墨で黒い。
「白起様。竹簡をご覧になりますか。砂を払ってからお入りください。」
白起は袖で砂を払ってから中へ入った。部屋は狭いが、棚が多い。竹簡の束が横に寝かされ、束ごとに木札が付いている。札には年と事柄が記されている。「風候」「水利」「税」「軍馬」。白起は「風候」を手に取り、束の端をほどいた。古い墨の匂い。字は細いが、よく残っている。
書吏が灯を持って来て、隣に控えた。
「臨洮の記は、昔から夜に多いのです。夜に変化が多いということでしょう。」
「ふむ、貴重な資料だ。」
束の中ほどに、目当てのものがあった。「夜雨多」。年は幾つか。短い記述が続く。「夜、三に一度」「夜、連続、昼乾」「雷、子に鳴り、丑に収む」。白起は、自分が道中で書いた言葉と、ここにある言葉が重なるのを確認した。土地の癖は、長く変わらない。
別の束を開く。「水」。そこには川の怒りが記されていた。「羌のほうから災あり、翌日に増」「音なくして水出づ」。十数年前の記録もある。昼間に水が出た年の短い記。これは今日、食堂で公孫庭が話したものに違いない。墨は薄いが、字は読める。白起はその横に竹簡を差し入れ、今日の言葉を付け加えた。「羌、山を伐る。翌月、音なくして水出づ」。書吏が灯を傾けて覗いた。
「それを、そのまま残してよろしいでしょうか。」
「その方が良いな。」
「はっ。」
白起は別の棚へ移った。「産」。塩の束があり、年ごとに収量の短い数字と、簡単な注釈がある。「泉薄し」「薪価高し」「風弱し」。今年の束はまだ薄い。白起は一つだけ空いた竹簡を取り、短く書いた。「夏、泉薄し。塩弱し。北商、滞り気味」。書吏が驚いたように顔を上げた。
「天文の帳に入れられるのですか。」
「産も理に連なる。覚えておくといい。」
「心得ました。」
書吏は頭を下げ、棚の紐を整えた。白起は最後に「軍馬」の束を開いた。入れ替えの記録が並んでいる。季節ごとに数の上下があり、冬に落ち、春に戻る。ここ数年、夏の数が緩く落ちる年がある。夏に塩が弱い年と一致している。白起は紐を戻し、棚を閉じた。
「古い地誌はあるか。」
「ございます。『隴西記』の写しが少し。臨洮の項は短いですが――」
書吏が奥から小さな束を持ってきた。古い地名が並び、川の名、丘の名、羌の道、塩の泉の場所が記されている。「風、北より。冬長し」「夜雨あり」「通す所」。言葉は少なく、必要なことだけ。白起はそこに指を置き、いくつかの地名を半ば声に出さず確かめた。
「これを借りる。」
「写しをお作りします。今夜は灯を延ばしますので、明日の朝には。」
「すまぬな、頼まれてくれ。」
白起は部屋を出た。外気が冷たい。書物の匂いが衣に残っている。役所の角を曲がると、夕方の市にぶつかった。市と言っても、布を張っただけの小さな列だ。干し肉、粉餅、細工の粗い鉄の釘、塩の袋。北から来た羌が毛皮を広げ、秦の商が布を見ている。税の小屋の前に、短い列ができている。書吏が小さな札に数を書き、銅片を受け取り、印を打つ。風が吹くと、札が少し揺れた。
茶を沸かす場があり、湯気がまっすぐ立つ。白起は足を止め、湯の具合で風の筋を見た。まっすぐだが、時折、横へ折れる。上の風と下の風が重なり始めている。今夜の音は、昨日より近い。竹簡に短く記す。
城の南側には、井戸の小さな広場がある。桶の列、縄の擦れる音、水面の薄い波。女が持ち上げ、子が見て、老人が手を洗う。
広場の端に、小さな石柱が立っている。洪水の高さを刻む柱だ。過去の年の印が刻んであり、上のほうに二、三の深い線がある。白起はそれを目の高さで見、近い年の印を竹簡に移した。
外郭の見張り台に灯がともる。交代の笛が一度鳴り、城の内の音が少し変わる。羊が囲いに戻され、塩の竈の火が落ち始める。風は冷え、空気が軽くなる。白起は城の東側へ回った。丘への道があり、夜の観測に使う小さな台がある。そこへ向かう馬の足跡が新しい。梁宛と馬渓だろう。圭表を据え直しに行くと言っていた。彼らの足取りはまっすぐで、迷いがない。
白起は台まで上がらず、手前の段で立ち止まった。臨洮の町が一望できる。外郭の線、県府の屋根、宿舎の列、竈の煙。川は見えないが、谷の暗さで場所はわかる。北の稜線に薄い雲が張り、まだ星は出ない。足元の土は乾いている。爪先で軽く押すと、崩れずに返る。乾きの強さはこの一週間、続くだろう。
下へ降り、再び城の中へ戻る。西の門の近くで、「旅の掲」と書かれた札が目に入った。掲示の場所で、移動する者が互いの情報を短く残す。誰が北へ、誰が南へ。川の渡しの状態、道の通り。今日の札には、「羌の道、夜は静か」「南の谷、橋一本落つ」「塩、今週は弱し」。白起は「臨洮、夜騒ぎ、昼乾く。二日に一度詳記」とだけ書いて札を掛けた。字は小さく、誰でも読める言い方にした。
県府の裏手へ出ると、物見の小さな塔がある。登りはしない。風が強い時は、ここで見張りが交代する。塔の基礎は太く、土台に石が埋めてある。風の土地は足を広く取る。臨洮の建て方は合理的だ。家の開口は中庭に向け、外には小さな穴だけ。火は半分土に沈め、煙は風へ流す。庭の畝は低く、葱と薬草。こういう形で、長く残る。
小門から少し外へ出た。守が同行しようとしたが、白起は首を振った。城のすぐ外、土の傾き、風の重さ、草の背丈、砂の粒。外の空気が、城内にどう入るかを見るには、小門の外が一番よい。丘の肩に上がると、風が一枚増える。耳の音が変わる。そこから城を振り返ると、外郭の土が風に当たり、砂がわずかに流れる。土は保つが、表面は常に動いている。こういう場所では、柱を深く埋め、脚を太くする。圭表が傾きやすい理由も、ここにある。
城内へ戻ると、灯がひとつ増えていた。県府の二階の窓だ。公孫庭か田陵が仕事をしているのだろう。白起は宿舎へ向かった。竈の女が鍋を片付けていた。
「お帰りなさいませ、白起様。」
「うむ。」
「今夜は冷えます。湯をもう一つ、部屋へ持たせましょうか。」
「頼む。」
女は頷き、土器を洗い始めた。白起は廊下を進み、奥の自室へ入った。戸を閉めると、外の風が一段遠くなる。卓の上に竹簡を広げ、散歩の記録を短くまとめた。
臨洮は、通す所。
昼乾き、夜に雨あり。
塩、泉薄し。皮、数多し。
鉄、春割れ、今は安。
馬、数は安定。
羌の道、夜静か。
圭表の地、風の脚。脚を深く。
夜、上乾きて白む。星、なお見ゆ。
川、音なくして水出づ年あり。木の伐りと併記。
文字は短い。だが、頭の中には城の姿が残っている。外郭の角で変わる風の音。塩の膜の薄さ。皮の張りの強さ。鍛冶の刃の音の鋭さ。井戸の水と広場。旅の掲の札の字の軽さ。どれも今夜の観測に向けて、土地の調子を示すものだ。
戸口に足音がした。耆が湯を持ってきたのだ。
「湯をお持ちしました。」
「ああ。」
桶を受け取り、袖をまくって手と顔を洗う。指先が温かくなり、筆が持ちやすくなる。耆は桶を置いて下がった。白起は帯を締め直し、外衣にもう一枚を重ねた。夜の丘は冷える。衣は多いほうがよい。
戸を開けると、廊下の先に荀潁の影が見えた。手に帳の束を抱えている。白起に気づくと、荀潁は駆け寄り、深く礼をした。
「白起様。本日の帳をまとめました。ご指示のとおり、夜雨の項を立て、昼乾きを添記しております。」
「助かる。仕事の合間に申し訳ないな。」
「とんでもない。仕事の一部ですよ。圭表は梁が据え直しました。馬渓が漏刻を洗いました。明日の夜の観測、丘でお待ちしております。」
「ああ、ご苦労だった。」
白起は帳を受け取り、竹簡を棚に戻す。昼に見たもの、書籍部屋で確かめたもの、今、風が運ぶ音。すべてを一つの帳にまとめるために、静かに自室を整えた。
(明日から本格的に観測が始まる。ここでは何を得られるのか。)
白起は内省しながら記録をまとめていく。すっかり暗くなった臨洮の町は民に灯された明かりで照らされていた。
【4】観測開始
夜の初め、白起は宿舎を出て城の東辺にある天文台へ向かった。丘へ上がる手前の台地を切り整え、上邽の天文小屋に似せて作った施設である。ただし臨洮の風に合わせ、北と東は土塀を高く、南と西は風抜けを確保して低くしてある。床は固く叩き、砂払いの箒と布を所定の場所に掛ける規定がある。
入口脇に漏刻の甕が二つ。大きい甕を上刻、小さい甕を細刻に用い、吐水の管は焼きの強い土管。口を麻糸で締めて流量を合わせる。甕の前に目盛り板と竹針。替え管、麻糸、油、拭い布は棚にまとめ、夜ごと点検表に朱を入れる決まりだ。
中央に圭表。方形石台に孔を穿ち、榫で脚を差し、周囲を締め土で固める。脚の根に小石を抱かせて湿りを逃がす。影盤は二重刻線。夜に影は使わないが、翌日の照合の要である。圭表の北側に仮柱を立て、北極高の照準紐を張る。東縁に星位見取り用の簡易架台が三基。視筒は用いず、二点竹尺で挟む旧法で通す。
梁宛と馬渓が先着し、最後の据えをしていた。梁宛は圭表の脚を叩き直し、馬渓は風よけの布を斜に落として灯の炎の揺れを抑える。
「白起様。圭表の脚、据え直し済みにございます。根は締まっております。」
「漏刻は洗い、目盛りを合わせました。初更のうちは落ちをわずかに重く、二更へ入る前に定へ寄せます。」
白起は甕口を覗き、水の落ちの滑らかさと針の揺れの小ささを確かめた。風は弱い。今夜は乱れが少ない。
荀潁が帳板を抱えて上がる。
「白起様。今夜の板を取り付けました。星列は『室・壁・奎・婁』から起こしてあります。」
「うむ、ご苦労だ。今夜も冷える。暖を忘れぬように。」
台の東縁に立って空を見る。西の地際に薄明が残り、上空は乾いて澄んでいる。露は薄い。初夜の観測は落ち着いて進められそうだった。
この地の勤務割は簡潔だ。立ち上がりは五人。初更で器と方位を固め、二更に向けて落ちを整え、三更から本格的に拾う。公孫庭は目が続かぬため、夜半前に記録へ回る。梁宛と馬渓が器、荀潁が筆、白起が時刻と方位の総覧。監察の韓慎は時折現れて、遠巻きに見るという手筈で、外の暗がりに小灯がひとつ動いた。
――初更のはじめ
東が先に暗く、北は一呼吸遅れて落ちる。稜線の上、四星が正方に整い始める。室宿・壁宿である。白起は竹片で角度をとり、荀潁へ合図した。
「室・壁、が見えている。時間は初更半。梁宛。」
「記しました。」
梁宛が北紐に目をやる。
「白起様、北紐、ずれ無しです。」
「うむ。」
白起は視線を東へ滑らせる。室・壁の北に連なる奎宿の列が細く立ち、ほどなく婁が続く。臨洮の空は今夜、透明が勝ち、奎の筋が早い。南低く、北落師門が単独で明るい。秋の南の目印で、今夜は低層の靄がかかっている。
「南、北落師門、明るし」
荀潁が運筆する。梁宛は方位盤の南線を指先でなぞり、馬渓は風よけ布の角度を一段下げ、灯の高さを合わせた。
北天は澄んでいる。北辰の周りが輪を崩さない。臨洮は高層の揺れが少ない夜は、星像が小さく鋭い。白起は荀潁に初日の骨子を指示した。
「今夜は“秋の入口”の型で書け。基点は室・壁。奎・婁・胃の順。南は北落師門。天漢は薄。北紐、正。」
「承りました。」
足元の土を指先で押し、締まりを確かめる。乾いている。
奎の先、淡い光の広がりが肉眼に触れる。余事は記さない。官の帳は意味の筋だけを明確にする。
「初更の尽き際、婁、出そろう。胃、低し。」
「記しました。北落師門、色、一定。」
「それで良い。」
公孫庭が影に寄り、灯を低く掲げて言う。
「白起殿。落ち着いた初夜、幸いにございます。器がすぐ馴染みまする。」
「風がよい。今夜、書は任せる。目は若い三人で足りる。」
「承知。」
――二更のはじめ。
西の高みで夏の川(天漢)が細り、線を減らす。秋の星は形が少なく、基準点が明確だ。室・壁の四角が崩れぬかを注視し、奎・婁の角度を追う。北の紐は揺れず、風も弱い。白起は口少なく必要な句だけを告げる。
「東、奎・婁、角、揃い。南、変化なし。」
「板に反映しました。」
荀潁の返事は短い。字は乱れない。馬渓が甕を覗き、報ずる。
「落ち、二更半で定に寄りました。針の震え、僅かです。」
「よし。三更に入る前に管の締めを一度行うように。油は十分あるな。」
「承知いたしました。」
白起は台の周囲を半周し、土塀の風抜き、布の張り、灯の高さを確認し戻る。徐々に夜が更けていく。ここからが天文官の本領発揮である。
――二更の尽き際。
東低く、胃の散りが整い、奎・婁の流れが落ち着く。南の北落師門は明度を保つ。西の夏の名残は地際に沈んでいる。北は鋭い。初夜の骨が組み上がった。白起は“詳記”欄の立項を命じた。
「荀潁。詳記に次の順。
一、天の型――室・壁正。奎・婁・胃、順。
二、風候――風、弱。露、薄。灯、揺れず。
三、器――北紐、ずれ無し。落ち、二更尽で定。
四、特記――北落師門、色、一定。天漢、細」
「承りました。」
梁宛が圭表脚の根を足で軽く押し、乾き過ぎを白起に目で伝える。白起はうなずき、明日の照合で石を一枚噛ませる判断だけ口にした。
「明朝、照合の上で石を一つ追加しておくように。今は動かすな。」
「承知。」
東の地際がさらに賑やかになる時刻。白起は声を抑えて連絡した。
「三更のはじめ、昴の気。肉眼で星は拾うな。まとまりを先に記せ。」
「はい。——昴、兆し、記しました。」
北は依然として澄んでいる。紐は揺れない。灯の炎も立つ。白起は台の縁に一歩下がり、夜の進みを短句で心中に並べた。
――初更半、室・壁正。二更初、奎・婁起。二更尽、胃整。三更初、昴兆。
観測の骨子が揃えば、見落としは減る。公孫庭が古い棚の抄をめくり、短く言う。
「白起殿。『秋初良夜』の束に今夜を併せます。十七年前の記と語が合います。」
「語はそのままでよい。」
「承知。」
白起は衣の襟を直し、指先の感覚を確かめた。夜の観測は目と手の微細な緊張で持つ。過ぎれば見落とし、緩めれば粗くなる。今夜は穏やかな夜になりそうな気がした。
――三更の半ば。
昴のまとまりが濃くなり、群の縁がはっきりする。白起は竹片で位置を取り、荀潁に短く渡す。
「昴、明瞭。三更半。」
「記しました。」
「畢、兆し。」
「はい。赤、目立つ。」
「『色、赤』でよい。」
梁宛が北紐を再点検。
「白起様、紐、たるみわずか。結び替えます。」
「露の重みだ。結び位置を上げるように。」
「承知。」
馬渓が漏刻の管口を指で締め直し、針の落ちを見て頷く。
「落ち、安定。報の刻で合図いたします。」
「頼む。」
白起は南へ目をやり、北落師門の色と高さを確認。変化なし。西は夏の川がほぼ消え、線が減る。秋の空らしく、暗部が増してくる。帳には「星、鋭」とだけ記す。
――三更の尽き際。
昴が一段高く、畢が出端を見せる。白起は初夜の“核”をここに置く判断を固めた。室・壁は初更半、奎・婁・胃は二更尽、昴・畢は三更尽――三点で夜の枠が定まる。以後は刻追いで補う。
公孫庭が低い声で言う。
「白起殿。今夜はここまでで“良夜”の印を打てましょう。」
「うむ、それで打とう。三点基準で清書するように。」
「了解した。」
白起は台の周りをもう一度回り、布の張りと灯の油、甕の縁の砂を指で拭って戻った。ここまでで初夜の前半の務めは果たした。以後は拾い漏らしを抑え、器に癖を覚えさせないように配分するだけだ。
空は静かだ。風はなお弱い。灯は揺れない。臨洮の秋の夜が、そのまま帳に落ちていく。白起は短く息を吐き、次の更へ意識を移した。
三更の尽き際を核と定め、白起はひとつ息を整えて四更に備えた。台の上では灯の油が安定し、布の覆いは低く張られ、甕の針はぶれがない。周囲の土は乾き、足の裏に冷えだけが残る。
四更のはじめ、東の地際がさらに賑やかになる。昴のまとまりは濃く、畢の群れが明瞭に広がる。赤い星が際立つ。荀潁が板の余白に手を置いて待っている。
「昴、四更初、明瞭。畢、出端。色、赤、一」
「記しました。」
梁宛は北の照準紐をもう一度確かめ、たるみをわずかに上へ逃がす。露の重さが出はじめる刻だ。紐はまっすぐに戻った。
「白起様、北紐、正。」
「うむ。参の兆しに備えてくれ。觜は薄く乗るはずだ。」
「承知しました。」
臨洮のこの夜は、風が終始弱い。灯の炎はほとんど揺れず、甕の水は静かに落ち続ける。馬渓が短く報告する。
「落ち、四更初、安定。油は半壺。覆いの紐、結び直し一度に留めます。」
「それでよい。刻頭だけ合図せよ。」
白起は南に視線を移した。北落師門は明るさを保ち、色は一定。高さをわずかに増し、低層の湿りにも鈍らない。西では夏の川が地際に沈み、線がほとんど見えなくなっている。北は澄んでおり、星のにじみがない。
四更の半ば、参の三つが横に並ぶ。上下の揺れはなく、並びは端正だ。その上に觜の小さな集まりがうすく乗る。白起は竹片で角度をとり、声を落として指示した。
「参、四更半、低し。觜、薄く。昴、尚高く。畢、広し。」
「記しました。」
「参・觜の位置で方位にずれがないか照合。梁宛。」
「はい。……揃い、良好。」
荀潁が筆を止め、小声で問う。
「白起様、『畢、広し』の語、昨年は『畢、疎』で統一しておりましたが、今夜はどちらに。」
「『広し』でよい。空が乾く夜は縁が広がって見える。『疎』は群の中の星の間を言う。今夜は縁のほうだ。」
「承りました。」
公孫庭が台の縁で古い束を繰り、短く添える。
「白起殿。『四更半、参見ゆ。冬の徴』という書き付けが三、四点。今夜と符合いたします。」
「その語を末尾に置いてくれ。冬の準備に用いることができる。」
「御意。」
台の外で足音が一つ止まり、暗がりに灯が動いた。監察の韓慎の宿直が交代したのだろう。距離は保たれ、観測の邪魔にはならない。白起は目を星と器から離さない。
四更の尽き際、参はわずかに高さを増し、觜の乗りもはっきりする。昴は高く、畢の赤はなお目に立つ。北は澄み、紐は張りを保つ。白起は詳記欄の追記を命じた。
「荀。追記。四更、参・觜、明瞭。冬の徴、早し。北、澄。」
「記しました。」
「梁宛、圭表の脚は触れるな。明朝の照合で石を噛ませる。」
「承知。」
馬渓が甕の口を拭う。
「白起様、砂、付きなし。油は五更初で一度足します。」
「頼む。」
空は良い。騒ぎはない。秋の星が順に通り、台は静かに応じている。白起は内心で短句を並べ直し、見落としのないように骨を固めた。初更半、室・壁正。二更尽、奎・婁・胃、順。三更尽、昴・畢、本。四更半、参・觜、明瞭。これで夜の流れは整った。
五更のはじめ、東の地際がわずかに白む。夜の終わりの徴である。星の数が急には減らず、ゆっくりと薄れる。乾いた夜だ。白起は口にせず、荀潁の筆の運びを見て、必要な語だけ与える。
「五更初、東、淡白。星、なお見ゆ。昴、形を保つ。」
「承りました。」
梁宛が北の照準紐から目を離し、東の淡白を確かめる。
「白起様、東の白み、薄し。乱れは出ません。」
「よい。参・觜の形が崩れたら記せ。今はまだ要らぬ。」
馬渓が灯の油を足し、覆いの角度を一寸上げた。炎は揺れない。甕の針は落ちを守る。公孫庭が古い束を閉じ、板に視線を落とした。
「白起殿。今夜の語は端正で、読みやすくなりましょう。」
「端正でよい。後の者が拾える語にせよ。」
「承知。」
五更の半ば、参の三つはなお整い、觜はそこに乗ったまま。昴は高く、畢は広い。北落師門は色を保つ。西の暗さが増し、夏の名残は消えた。白起は短く確認した。
「荀。『北落師門、色、一定』を夜末にも重ねて記せ。」
「重記いたしました。」
「梁宛、北紐、終夜ずれ無し。記に添えてくれ。」
「承知しました。」
夜の終わりが近づくと、台の清掃に向けた手順をあらかじめ分担する。漏刻の針を上に上げ、油を落とし、甕の縁を拭き、布を畳む。圭表は覆いを掛けず、足元の石に布を当てる。土の湿りを避けるためだ。白起はそれを口に出さず、短い合図で流れを作る。
五更の尽き際、東の白みが増し、参の三つが薄くなる。昴はまだ形を保つが、群の縁は弱くなる。畢の赤は沈む。白起は観測の締めに入った。
「荀。今夜の核になる三点を復唱。初更半、室・壁正。三更尽、昴・畢。四更半、参・觜。——これを上に置き、詳記を下へ。」
「復唱、書き込み済みです。」
「よし。語に『良夜』を冠せ。臨洮棚の定語に合わせろ。」
「『秋初良夜』、表題といたします。」
公孫庭が頷き、板の端に小さく印をつけた。
「白起殿。印は私の預りで押しておきます。」
「頼む。」
梁宛と馬渓が覆いを畳みはじめる。馬渓が甕の口を布で拭い、砂を残さないよう指先で縁をなぞる。梁宛は布の紐を乾いたところにまとめ、結び目が湿らぬよう高い釘に掛けた。荀潁は筆を収め、板を束ね、清書の手順を頭の中で整えている。
白起は台の周囲を一度まわった。土塀の風抜き、灯の油、甕の置き、圭表の脚。どこにも余分な動きはない。星は薄れ始めている。夜は終わる。
台を離れる前に、白起は手短に明日の段取りを告げた。
「昼、圭表の影で照合。脚に石を一枚噛ませる。落ちは昼一番で試す。夜は今夜と同じ配り。——荀潁、二日に一度の詳記、今日分は午の前に清書。棚へ収めるように。」
「承りました。」
「梁宛、脚印を付けておくように。土は弄るな。」
「承知しました。」
「馬渓、漏刻の管を干せ。砂が回らぬよう、布をかぶせておけ。」
「ただちに。」
公孫庭が板を抱え、白起へ軽く礼をした。
「白起殿。よい初夜でした。語も手順も清い。」
「皆が助けてくれた。——これでよい。初日は欲張ると良くない。」
「はい。」公孫庭が微笑を浮かべて頷く。
台の灯を落とすと、星がひときわ強く見え、それからすぐに薄れた。東は白い。遠くで鶏の声が二つ重なった。五更が尽きる。白起は台に背を向け、丘を下りた。
城の中は、朝の支度に入っている。塩の竈は火を起こす前で、鍋に水が張られている。皮の張り場は横木が戻され、男が桶を運ぶ。馬の囲いは水を足し、番が交代する。井戸の縄がぎしりと鳴った。風は弱いまま、冷えだけが残る。
県府の裏手を回ると、書籍の部屋に小さな灯がともった。早出の書吏が棚を開けるのだろう。白起は宿舎へ向かった。廊下は冷気を溜め、壁の厚みで音を丸くする。部屋に入り、竹簡を卓に置く。荀潁が持つ板の控えを横に広げ、語を最短の句へと落とし直した。誰が見ても同じ形で拾えるようにする。それがこの土地での最上のやり方だ。
短くまとめた。
初更半 室・壁正。北紐、正。
二更尽 奎・婁・胃、順。天漢、細。
三更尽 昴、明瞭。畢、広し。色、赤、一。
四更半 参見ゆ。觜、薄く乗る。冬の徴、早し。
五更初 東、淡白。星、なお見ゆ。
通夜 風、弱。露、薄。灯、揺れず。北、澄。北落師門、色、一定。
器 落ち、二更尽で定。夜、ずれ無し。
句を読み返し、余計を削る。観測の夜が静かであるほど、語は短くできる。白起は筆を置き、帯だけ解いて寝台に背を預けた。昼の照合までに少し眠る。目を閉じる前、室・壁の四角、昴の集まり、参の三つが順に頭の中を通り、それぞれ所定の位置に収まった。
短い眠りのあと、白起は目を開けた。外はすでに昼の音だ。廊下の先で足音がし、控えの板を抱えた荀潁が戸口に現れた。
「白起様。清書の下案、仕上がりました。午の前に棚へ入れます」
「預かる。語は統一しておけ。『広し』『細』『赤』の用い方を混ぜるな。」
「はい。『広し』『色、赤』で統一します」
「よい。——昼の照合、初更で決めた基準を崩さないように。影で動いたら、脚に石を一枚。」
「承知しました。」
荀潁が下がっていく。白起は帯を固く結び直し、外衣を整えた。圭表の足を確かめ、落ちを試し、昼の影を拾う。その一連の手順を頭の中に置いたまま、戸を引いて外に出た。
昼の臨洮は、夜の記録と違い活気と雑踏で溢れていた。塩の鍋に最初の泡が立ち、皮の横木が張られ、井戸の水が満ちる。風は弱い。空は高い。夜の星の位置と器の癖を身体に入れた初日は、静かに終わり、次の手順へ移る。白起は県府の方へ歩き、照合の場へ向かった。
【5】臨洮の日常
臨洮での観測は、十日もすれば手順が体に入った。昼からは圭表の影を拾い、脚の沈みを見て印を比べる。漏刻を乾かし、管の孔を糸で締め直す。
次は帳を清書し、産と軍馬の数字を短く添える。夕刻に台へ上がり、器の点検と風の筋を確かめ、初更から拾い始める。二日に一度の“詳記”は、項の順を崩さず、語を短く揃える。
書式が決まれば、土地の癖が見えてくる。臨洮は夜に騒ぐ日もあれば、静かに透る夜もある。初日のような良夜は多くはないが、観測に支障をきたすほどの荒れも続かない。
朝の圭表は、脚の根が乾き気味の日がふえた。梁宛が脚印を見て言う。
「白起様、二日前に石を一枚噛ませましたが、まだわずかに沈みます。」
「あと一枚。今は動かすな。昼の影で照合してからだ。」
「承知しました。」
沈みの幅は微差だが、帳に残す価値がある。脚が動く土地は、昼の影を過信しない。夜の星で核を置き、昼は整える。臨洮での観測はその順で落ち着いた。
昼の官舎では、耆が湯を運び、荀潁が清書を進め、公孫庭が棚の古い束を繕う。公孫庭は目が利かなくとも、語の整えは速い。長い職務経験が活きているのだ。
「白起殿。『広し』『疎』の使い分け、部内の書板にも掲げておきまする。」
「うむ。『色、赤』の句も同じ。評価語は避け、事実の形に置くように。」
「はっ。」
韓慎は昼の県府にふらりと現れ、帳の束に目だけを走らせる。何も言わない日もある。言うときは一言だけだ。
「ふむ、いいだろう。」
それで去る。こういう距離の取り方は、むしろやりやすい。監察の目を意識して書を曲げる必要はない。曲げると記録は嫌な匂いを持つ。匂いの抜けない帳は、次の年に使いづらい。
夜の観測には変化があった。ある夜は初更の薄雲が北から流れ、室・壁の角が鈍った。二更に入る前に切れ、以後は透る。別の夜は四更に風が立ち、紐が細かく揺れた。馬渓が覆いの角度を一段下げ、紐を結び替える。落ちは乱れない。五更に入ると東の白みが遅くなり、昴が短くなる日もあった。荀潁の筆はそれを淡々と拾い、語を揃え続ける。
「白起様、『四更、北紐、微揺れ』は“注”に下げますか」
「注でよい。星の形が崩れぬなら、見取りの欄は動かさないように。」
「承りました。」
台でのやりとりは必要最小で進む。目と手の速度が合ってくると、余計な言葉はいらない。梁宛は紐と影に強く、馬渓は落ちと覆いに強い。荀潁は語の統一を崩さない。公孫庭は古い棚から“同じ夜”を探すのが早い。四人の役が揃った夜は、帳の束が軽く締まる。
夜間の通りも見慣れた。塩の竈は夜半に火を落とす日が増え、皮の横木は覆いを厚くした。「泉薄し」の年らしく、煮詰めに時間をかける。軍馬の囲いは入れ替えが少し遅れ、朝の水桶が早く空になる。数字は小さく動くだけだが、帳の端に置いておくと翌月に辻褄が合う。田陵はそういう付記を喜んだ。
「白起殿。天文の帳に産の一行があると、会計のほうが無理をしなくて済む。」
「無理は帳に残ります。残るものは少ないほうがいいと思いまして。」
「いい試みです。」
暮らしも一定した。白起は昼の食を軽くし、夜に備えて体を冷やさないようにした。眠りは短いが、眠り方は深くなった。寝起きの井戸で水に触れ、朝を確かめるのが習慣になった。
ある夜、初更に薄雲が空を渡り、二更の前に遠くで雷が一度鳴った。音は短く、光は低い。荀潁が顔を上げる。
「白起様、記しますか。」
「『遠雷、一』だけでよい。星の見えに影響はない。」
「承りました。」
四更に参・觜を拾うとき、公孫庭が小声で言った。
「白起殿。臨洮で夜を見る者は、最初の年ほど多く記し、三年目から削り、五年目で句が揃いまする。」
「揃えるには、削るものが必要である。」
「はい。切るのは、物ではなく甘えでございますな。」
白起はうなずいた。観測は、目に入ったもの全部を拾う作業ではない。必要な形を残し、要らぬ言葉を落とす。削って残る線が、その土地の筋だ。筋が出れば、次の者が活かせる。
夜と昼の間で、白起はしばしば考えた。自分の仕事は“天文の官”だが、以前の秦の職制では“軍門”の側に籍があった。観測の記は兵の動きと無関係ではない。
夜雨が続けば行軍は遅れ、乾きが続けば薪が要る。星は兵の腹には入らないが、兵の刻を動かす。天文の記を軽い飾り物にしないためには、理の線を軍用の線に接ぐ工夫が要る。
臨洮では、それが分かりやすい。要衝の町は、天候が一つ狂うと交易にすぐ響く。帳に一行添えるだけで、伝達が早く、迅速に動けるようになる。
「理に逆らうな」と馬渓に言った夜を思い出す。あれは臨洮の洪水を想定した言葉ではなく、記を運用する態度の話でもあった。理を先に置き、書はそこに添える。書を先に置くと、現場は鈍る。鈍い帳は、次の年に誰かを傷つける。臨洮の夜は、それを確かめる場だった。
韓慎は、相変わらず台の外に灯を置き、遠巻きに見る。ある晩、三更の尽き際に近づいてきて言った。
「今夜は『良夜』か。」
「そうかもしれません。」
「随分と慣れてきたようだな。」
「おかげさまで。」
「励むことだ。」
それだけだった。監察吏の言葉は、評価でも非難でもない。ただ、見たままを言う。そういう距離が続くなら、こちらも余計な力を入れずに済む。
日常の中に、季節は確かに進んだ。奎・婁・胃の立ち上がりが早くなり、昴が高く上がる時分が日々ずれる。参・觜の鮮明さも増した。北落師門の高さがひとつ分増し、色が安定した。
天漢はさらに細く、夜の暗さが均等になった。帳に置く語は変わらないが、並べる刻が自然に前へ滑る。荀潁は語の統一を保ったまま、その滑りを余白に整った字で置いた。
「白起様、『四更半』を『四更初』にずらしたほうが合う夜が続きます。」
「うむ、そうしよう。棚の『秋初』の項に小札を挟んでおいてくれ。」
「承知しました。」
昼、県府の書籍部屋で古い地誌を見に行くことが増えた。隴西の旧記には、臨洮を「通す所」として書いた短い句が並ぶ。夜雨の記、冬風の記、塩泉の記。語は少ないが、筋がまっすぐだ。書吏は棚の位置を覚え、必要な束をすぐに出すようになった。
「白起殿、昨年の『冬初』はこの束です。」
「うむ。参・觜の刻を比べてみる。」
比べてみると、今年は“冬の徴”がわずかに早い。羌の山で伐りが増えた年は、そうなる傾向があるらしい。木が減ると空気が速く冷え、夜の透りが前に出る。帳の注に短く置き、産の欄に「薪価高し」を一度だけ添えた。
白起の臨洮生活は続く。暮らしの底に、孤独は常にある。宿舎の奥の部屋は静かで、壁は厚い。夜半に帰ると、外衣の砂を払う音だけが大きく聞こえる。
食堂の椀は温かいが、会話は短い。梁宛も荀潁も、食事時は必要なことしか言わない。馬渓は場を和ませようとするが、役の話が中心だ。
公孫庭は静かに椀を持ち、食が済むと短く「今夜も頼む。」とだけ言う。そういう距離が続くと、心の中の言葉は自然に削れる。
削れた言葉の隙間に、観測の句がはまる。無駄な感想は出なくなる。白起には、その状態が仕事には向いていると思えた。
日常が続くほど、規律は緩むところと締まるところに分かれる。緩めるのは、衣と食の些事。締めるのは、語と刻と器。臨洮では、その分け方が体に馴染む。
緩めるところで無駄な力を抜けば、締めるところで詰められる。詰めすぎは避ける。余白がない帳は、翌年に息をしない。
軍門の側の仕事も、誰かの目に見えないところで動いている。田陵は兵糧の移動の刻を、観測の“詳記”と合わせるようになった。北の見張りは、夜の白みの早い日を隊の交代に当て、夏の残りが強い日を巡察に当てる。
白起が直接命じることはない。帳の短い句が、役人の手の上で静かに移動していく。そういう動き方が、秦の官のやり方としてはよいと白起は判断した。
天文が軍門に物を言うとき、語は少ないほど通る。少ない語は、責め口にも逃げ口にもならない。ただ“事実”として残る。
ある夕刻、田陵が台の下に顔を出した。
「白起殿。塩の炊き方を一日遅らせたいとの願いが出ております。夜の白みが早いので、職人が休みを取りたいと。」
「帳に『五更、淡白、早し』が三度続きました。遅らせてよいと思います。炊き過ぎると塩が薄い年は余計に弱ってしまう。」
「承知しました。軍馬の水も、朝の桶の増やしを指示します。」
「良い選択だと思います。」
短い会話で物事は進む。延々と議したり、威勢の良い言葉を並べたりする必要はない。土地の筋に合う動きなら、短い句で足りる。
夜が深まると、台の上で白起は自分の職の芯を確かめるように、同じことを考える。天文の官は“理を記す者”であり、軍門の籍にある者は“理に従い動く者”となる。理は、命令の文ではない。指図ではなく、地の癖を短く置く作業だ。地の癖に人の仕事を合わせると、無理が減る。無理が減ると、罰が減る。罰が減ると、恨みが減る。臨洮のような交易の町では、その積み重ねが安定になる。
淡い月の夜もあった。月は観測の邪魔になるが、位置が分かれば帳の側で調整できる。月の照りで昴が薄くなる夜は、別の基準点で補う。室・壁と北落師門の線で足りる夜もある。そういう夜に、荀潁が言った。
「白起様。月の夜の“詳記”は、項を一段入れ替えますか。」
「入れ替えよう。基点に室・壁を置き、月を注に下げる。月は毎年の巡りがある。星の並びのほうが、土地の違いを拾える。」
「承知しました。」
規則は固定ではない。固定なのは順序だけだ。理を先に置き、書をそのあとに置く。台に立つ者が同じ順で動けば、帳は揃う。軍事と同じ、硬軟を織り交ぜていく。
月が無い夜、四更に北西が白む筋が現れ、十分で消えた。荀潁が迷いなく記した。「北乾きの筋、一」。精確な手つきだ。若いが、臨洮で育つ筆だと思えた。梁宛の紐は揺れず、馬渓の覆いは崩れない。公孫庭は膝の上の束から、昔の同じ筋を指で示す。台の上に無駄がない。
白起は夜の終わりに息を吐き、丘を降りながら短い内省を反復した。ここでは、星は美しさのために見るのではない。美しさは、見取りの邪魔になる。美しいと思った夜の帳は、語が甘くなる。
甘い語は、誰かを楽にするが、翌年の誰かを困らせる。記は飾ってはいけない。飾りの無い記は、地味だが、動く。動く記があれば、命令を減らせる。命令が減れば、兵は怒らない。怒らない兵は、長く持つ。
臨洮での生活は、静かにそういう方向へ傾いていった。朝の井戸、昼の書板、夕の風、夜の星。季節の滑りは帳に現れ、産の数字は短い注で足りる。軍門の連絡は、観測の句と同じ速さで動く。
誰かが声を荒げる必要はない。必要なのは、夜に見えたものを、昼の動きに渡す細い橋だ。天文の官は、その橋の板を一枚ずつ並べる役だと、白起は自分に言い聞かせた。
長く降らない夜が三つ続き、次の夜に短い雨が落ちた。二更の前に通り、三更で止む。覆いの布に細かい点が残る。星の見えは四更から戻る。帳には「短雨、一」とだけ置いた。
翌朝、塩の鍋の火が遅れ、皮の横木に水滴が残った。軍馬の桶の水はすぐに濁り、番の交代が早くなった。田陵は黙って帳の注を見て、頷いた。
「白起殿。夜の一行があれば、こちらは言い訳をせずに済みます。」
「言い訳は帳に残らないですからね。」
「ふっ。」田陵が満足そうに笑う。
臨洮の日々は、そのように進んだ。夜ごとに星を置き、昼ごとに器を照合し、短い注で産を結び、軍の刻に渡す。季節は、星の位置でしか測れないほど均等に動いたわけではない。
風が止まる夜もあり、急に白む夜もある。だが観測の側に余白があれば、変化は記に吸い込める。余白は怠けではない。次の一行のための空地だ。空地がなければ、記は行き詰まる。
白起は、臨洮の夜と昼の間に、職の重さを一定に保った。天文は理を記す。軍門は理で動く。二つが噛み合うとき、言葉は少なくていい。
少ない言葉は、長く残る。長く残る言葉は、土地の筋に近い。そういう帳だけが、次の年に役に立つ。そう定めて、白起はまた夜の装いを整え、台へ向かった。初更のはじめ、室・壁の角が現れ、北の紐が張る。仕事は、同じ順で始まる。
【6】日常の経過
便りは昼前に届いた。県府の使いが宿舎まで持って来て、戸口で印を確かめ、無言で差し出した。封は上邽の県府のものと、白家の小さな印の二つ。白起は机に広げ、まず家のほうから開いた。竹簡は軽く、紐はきつくも緩くもない。凛の手でまとめたとすぐにわかった。
最初の文は凛だった。字は揃い、余白の取り方が丁寧だ。上邽は朝が冷え始め、庭の葱がよく立っていること、井戸端の石を杜が据え直したこと、蒋が学会の集まりで天文学を始めたこと。米と粟の値は先月より少し下がり、干し肉は変わらない。近所の子が咳をしているが、重くはない。門前の板を一枚取り替えた。白起の衣は一枚足してあるから、向こうでも寒さはしのげるだろう、と短く添えてある。
杜は相変わらず字が太い。畑の一角に豆を増やしたこと、薪を早めに集め始めたこと。避難させた資産で伯が商売を広げようとしていること。戻りの刻が延びても慌てない、と書いてある。
蒋は短い。三人とも体は支障ない。天文学を始めたこと。市場の規制が少し強くなったこと。青淵と遠出をしたこと。そして、白起の無事を祈る言葉で結んである。
白起は読み終え、机の上で手を組んだ。字の間に生活の気配がある。どれも小さなことだが、積んでおけば冬を越せる。臨洮の夜の句と同じだ、と白起は思った。短く、必要なことだけ。余計な慰めも、過度な心配もない。仕事に戻りやすい文だった。
返信を書いた。体は強い。夜は落ち着いている。臨洮は塩が薄い年で、皮は多い。風は弱い夜が続く。衣は足りる。戻りの刻はまだ分からない。分かればすぐ知らせる。伯の投資の件は定期的に知らせてほしいこと。臨洮の同僚は非常に優秀だということ。――文はそれだけにした。使いの台帳に名を書き、封を渡す。使いは何も言わず、深く頭を下げて去った。
午後、白起は台に上がる前に市場を一巡した。風は弱く、砂は舞わない。飯屋の鍋は半ば火を落とし、白い薄膜を土器に広げている。皮の横木には羊が数枚、日に当てすぎないよう布が掛かっている。鍛冶の槌は一定で、納品用の箱が二つ出ている。馬の囲いは静かで、桶の水が半分減っている。旅の掲には「北の道、夜静か」「南の橋、ひび」「交易の道、賊有り」の札が並ぶ。
毛皮の店の前で、白起は人に呼び止められた。
「白起殿ではないか。」
旅の衣。背は高くないが、背中に筒を一本、手には細い木箱。顔は日に焼け、目はよく動く。名乗る前に、白起は心当たりを探し、すぐに出た。
「夏侯成殿か。」
「ご無沙汰をしております。臨洮まで来たついでに、市場を見ておりました。通り過ぎるのも惜しい。白起殿に会えるとは運がよい。」
「もし時間があるなら飯を食いますか。」
「ぜひに。」
二人は市場の端の飯屋に入った。小さな竈が二つ、席は板の台が三つ。湯気は弱く、匂いは羊の出汁と葱。白起は粟の粥と薄い肉を頼み、夏侯は粟の餅と酸の効いた湯を頼んだ。
「在所は上邽のままですか。」
「はい。ですが、好奇心が抑えられず、渭水の北、羌の道の手前、谷の台をいくつか見て回りました。臨洮の空がどう違うか、確かめたかったのです。」
「どう違いましたか。」
「夜の白みが違います。上邽は冬の前に低い雲の白みが増えますが、臨洮は高いところの白みが晩秋に一度増える。十日ほど続いて、また引く。そちらの記録にもある思います。」
「『北乾きの筋、一』がこの十日で二度。夜は透るといった感じです。」
「やはり。」
夏侯は木箱を少し開け、細い竹片と小さな針金の枠を見せた。携帯用の影を見る器と、星の角度を測る簡単な枠だった。
「官の器には及ばぬが、道ではこれで足ります。昼は影の長さと形、夜は二点の角。帳は短く、場所と刻だけを残す。商の連中は、それで十分と言います。」
「うむ、足りますな。」
「白起殿の帳は、噂で聞いている。短い、と。」
「短いほうが後の者が動きやすくなります。」
「その通りです。」
粥が来た。湯気が上がり、葱の匂いが強くなる。夏侯は餅をちぎり、湯に浸して口に入れた。
「在野の人間でも臨洮の棚は見せてもらえますか。」
「公の部分だけなら問題ありません。」
「十分です。私は在野ですが、筋を見損ねるわけにはいかない。」
「在野は動きが早い。」
「仕事がそれしかないからです。」
夏侯は笑い、すぐに真顔に戻った。
「白起殿。二日に一度の詳記、あれは上邽でも続けているのですか。」
「続けています。臨洮では二日に一度にしました。夜の変化が日によって偏るので。」
「私は三日に一度にしていたが、山の向こうでは二日で拾えるものが多かった。ここも同じなら、私も二日に変えたほうが良さそうです。」
白起は干し肉を口に放り込みながら考える。夏侯成がまた問う。
「参・觜を冬の徴に置くのは、ここでも適いますか。」
「はい。参の三、觜の乗り。四更半がよいと思われます。月の夜は注に下げればよいです。」
「月の扱いは悩む。私は夜の白みを先に置いていたので。」
「それでもよいかと。基準を決め、毎年同じにしておけば。」
「了解した。」
夏侯は水を飲み、白起の粥を見て言った。
「観測に向けて、食は軽くしておられるので。」
「夜が長いので。」
「上邽から便りはありましたか。」
「今日、家から来ました。皆、健勝のようです。」
「良い。私は上邽に戻ったら、白家に挨拶しておこう。」
「ありがたいことです。」
店の外で人の声が重なる。荷が入ったのだろう。店主が戸口に立ち、注文を受けて戻る。湯は絶やさないが、火は弱い。白起は粥を静かに食べ、夏侯は餅をもう一枚頼んだ。
「白起殿。官の帳と在野の帳、どこで渡すのがよいと思いますか。」
「官の棚に在野の札を差し込むのは難しい。だが、旅の掲に短句で置くのはよいかと。」
「旅の掲、か。」
「『臨洮、夜静か、東淡白』と置けば、通る者は足を決める。官の帳は動かせない。動かせるのは、人の刻だと思っています。」
「在野は、人の刻を動かすために書く。官は、年を越すために書く。住み分けができる。」
「その通りです。」
「ならば、旅の掲に私の短句を残しておこう。臨洮に来る者のために。」
「随分と親切な在野の方だ。」白起が微笑する。
「昔からおせっかいなのですよ。」
二人は食を終え、湯を飲みきった。会計は白起が粥と湯と干し肉、夏侯が餅と肉。外に出ると、風は弱いまま、光は傾き始めていた。
「白起殿、お体に気をつけて。」
「貴殿も。」
市場の角で別れ、白起は台に向かう道に足を向けた。夏侯は逆に旅の掲へ行き、札を一枚差した。字は細く、短い。「北乾きの筋、二」。それだけだった。
宿舎へ戻ると、荀潁が清書の束を抱えて待っていた。
「白起様、本日の詳記、項を整えました。『四更半、参・觜、明瞭。冬の徴』を上に置き直しました。」
「よい。棚へ。」
「はい。それと、旅の掲に『北乾きの筋、二』の札が増えています。」
「夏侯成のだろう。」
「在野の方ですか。」
「そうだ。余計は書かない。読む者が動けばそれでいい。」
「官民共に学びになります。」
梁宛が圭表の脚印を持って現れた。
「白起様、脚、沈みわずか。日中に石を一枚噛ませ、印を打ち直しました。」
「落ちの試しは。」
「良好です。今夜は乱れは出ない見込みです。」
「覆いは低めに張れ。灯は一段下げる。風は弱い。」
「承知。」
馬渓が漏刻の管を拭きながら言う。
「白起様、今夜の油は二壺で足ります。砂は回っておりません。」
「管は替えずに行く。」
「心得ました。」
白起は短くうなずき、衣の袖を整えた。家の文は机の端に置いたままにした。読む必要はもうない。必要なことは頭に入った。臨洮の夜は、今夜も決まった手順で始まる。夏侯成との会合。在野と官の帳が、夜の空の下で同じ星を指す。筋は一本で足りる。
台へ向かう道の途中、白起は一度だけ足を止め、上邽からの便りの最後の句を思い出した。凛の字で「白様、夜は温かく」。短い句だった。白起はそれに何も返さなかったが、衣を一枚多く重ね、襟を詰めた。台の上は冷える。余計なことはしない。必要なことだけをする。臨洮での十数日のやり方は、今夜も変わらない。
【7】不穏の気配
白起が赴任してしばらくは平穏な日々が続いた。しかし、臨洮が雨季に入ったのか、雨は三日続き、四日目も止まらなかった。臨洮の秋は夜に短く降ることが多いが、このときは昼も夜も区別がなく、細い雨が切れずに落ちた。
最初の二日は静かだった。三日目の夜からは雷が加わり、四更にかけて短い雷鳴が二度、五更で一度。翌日は朝から強く、屋根に当たる音が一定で、土の匂いが廊下にまで入ってきた。
天文台では、計画を崩さずに始業したが、板に書けるものは少ない。初更のはじめ、梁宛が紐を張り、馬渓が覆いを下げる。空は一様な灰で、星は出ない。荀潁は項目を立て直し、語を短くそろえる。
「初更 雲一様、星見えず。雨、風、弱。灯、揺れなし。」
二更相当の時刻でも状況は変わらない。漏刻は湿りで落ちが重く、麻糸が膨らんで微細な調整が効かない。馬渓が口を拭い、落ちを見守る。
「白起様、落ち、重。定に寄せ切れません。注に下げます。」
「うむ。この天気だ、刻の頭だけ拾えばよい。」
四更のはじめ、雷が遠くで一度。台の屋根に雨が強く当たり、灯の覆いに水が走る。荀潁は筆を止めず、「四更 遠雷、一。降り強し」とだけ添える。五更の手前、東の白みだけがいつもどおり現れた。星は最後まで出なかった。
翌日も雨。圭表の脚は湿りを吸ってわずかに沈む。梁宛が印を見て言う。
「白起様、脚、半分の印まで沈みました。石を一枚噛ませますか。」
「今日は動かすな。影が拾えぬ。沈みを記すだけにしておけ。」
「承知しました。」
昼の県府は、雨音で常より静かだ。書籍の部屋では公孫庭が棚の「長雨」の束を開いた。十七年前の秋に五日続いた記録が一つ。さらに古いところに七日という短い走り書きがある。今回はすでに四日目で、雨脚はそれより強い。
「白起殿。記の通りに進めば、この後二日で切れるはずですが、雷の入り方が少し違います。あの年は夜半に一度、ここ数日は四更で二度、五更で一度」
「記に分けて置こう。夜の雷、刻の分布。」
「はい。」
城内も変わる。塩の竈は火を弱め、土器に広げる作業を止めた。塩の膜は作れない。皮の横木は屋内に寄せ、布で覆う。鍛冶の場は風下の扉を閉ざし、ふいごの息を短くした。
馬の囲いは泥を避けるために柵を詰め、桶の水は濁りやすく、番が短い間隔で替わる。市場は縮み、旅の掲の札だけが増える。「北の橋、一落つ」「南の浅瀬、渡し不可」「夜、雷、三」。字は細く、要件だけだ。
五日目、雨脚がいくらか増す。県府に臨時の詰所が設けられ、川筋の見張りが交代で報を入れる。田陵が白起を呼んだ。
「白起殿。羌川の見張柱、三の刻線に迫りました。昨年の最高を越えます。」
「柱の刻を写させましょう。夜の雷の時刻と重ねてみます。」
「うむ。」
見張り台から戻った兵が泥を落とし、短く報告する。北の支流に流木が多い。堤が柔らかく、踏むと沈む。雨は細かいが切れ目がない。川の音は低く、まだ氾濫はしない。数字だけが上がっていく。
田陵は唇を結び、職人の隊に砂袋を積むよう指示した。
「堤、踏み固めの時刻を昼に寄せるように。」夜は足を取られる。
天文部では、書き方の動揺が初めて顔を出した。荀潁が問う。
「白起様。夜を三度『雲一様』で埋めるのは、棚の読みが重くなります。補いの語を入れますか。」
「入れるなら短く。『雷、四更に散』など。余計な感想は入れるな。」
「承知しました。」
梁宛は紐の張りを確認し、覆いの角度を調整するばかりで、星に触れない夜が続くことに肩の力が抜ける。
「白起様、紐の点検をもう一巡しましょうか。」
「うむ。器の点検は夜でもできる。夜を無駄にしたくない。星がなくとも職務は続く。」
「はい。」
馬渓は落ちの重さを見続け、麻糸の交換頻度を上げた。
「白起様、管の口が水を吸います。砂は回っておりませんが、糸が太ります。」
「糸を一段細くする。落ちの記は刻頭だけで十分だ。」
「心得ました。」
六日目、昼過ぎに一度だけ弱くなる時間があり、城内の人々が一斉に外へ出た。井戸の列は短く、塩の場は火を入れかけてやめ、皮の横木だけ日を当てた。すぐにまた雨が戻る。市の隅の子どもが泣き、母親が背に布をかける。言葉は少ない。誰も大声を出さない。音は雨と足だけだ。
夜、四更で雷が二度続き、五更で一度。台の覆いに水が溜まり、角から落ちる。荀潁が板に手を置いたまま、筆を止めた。
「白起様。夜、記すべき星がありません。」
「『観測不能』の語は使うな。『雲一様、星見えず』で足りる。注に『雷、四更二、一』と記そう。」
「はい。」
公孫庭は古い束を開いたまま、長雨の年の欄に短い札を差した。
「白起殿。七日の記はあっても、雷がこの刻にこう続く例は少ない。『冬の徴、早し』の年と重ねると、ずれます。」
「ずれとして置いておこう。『刻のずれ』の札を作る。」
「承知。」
県府から使いが来た。韓慎の書付が添えられている。言葉は短い。
「帳はそのまま。補いは注に限る。堤の見張の刻を帳の末尾に添えること」
白起は返事を書かず、項を増やした。夜の最後に「堤の見張り、交代の刻」を一行だけ足す。天文の帳の末尾に軍門の刻が併記されるのはまれだが、必要ならそうする。
秋の臨洮の雨がさらに強くなる。廊下の土器がひとつ割れ、庭の水が抜けにくい。宿舎の耆が「屋根、二箇所」とだけ言い、脚立を運ぶ。
白起は台に出る前に県府へ寄り、見張柱の刻線を見た。古い深い刻のひとつ下まで水が来ている。柱の木目が濃くなり、苔の色が線より上に見える。田陵が脇で頷いた。
「白起殿。今夜は見張りを増やします。このまま雨が続くと氾濫は免れません。」
「増やしましょう。夜の合図は短く。騒ぎは人を動揺させます。」
「心得ました。」
夜の台は音だけが大きい。屋根を打つ雨、覆いに走る水。灯の炎は保たれているが、星は見えない。
荀潁は板に「初更 雲一様」「二更 変わらず」「三更 変わらず」「四更 雷、二」「五更 雷、一」と置き、余白に小さく「堤、交代、二更・四更・五更」と記した。
梁宛は紐と脚の確認を続け、馬渓は落ちが狂わないよう口を替える。公孫庭は言葉を足さない。夜が長く、語は短い。
九日目の朝、旅の掲に札が増えた。
「北の橋、二落つ」「南の谷、木の流れ、多」「塩、炊き止め」
字は変わらず細いが、数は多い。市の人は声を潜め、錠前を早くかける。昼の県府では、書吏の数を増やし、帳の写しを二部にして別の棚に分ける。田陵が短く言う。
「白起殿。帳を分けておきます。万一のため。」
「それがよろしいかと思います。県府の蓄えはどの程度ありますか。」
「数ヶ月は保つかと思います。しかし、雨が継続すると交通が遮断され、援助物資も届かなくなります。」
「数ヶ月の雨は聞いたことがありません。どこかで必ず止みます。県令殿は官民の慰撫をお願いいたします。私もできる限りの尽力をいたします。」
「白起殿、感謝する。」田陵は力強く頷いた。
夜、雨は止まらない。四更で雷が三つ。五更のはじめに短く止み、すぐに戻る。東の白みは見えるが、星は最後まで出ない。白起は板の末尾に「十日目の兆し」と小さく置き、語は増やさない。
翌日、昼前に一度だけ光が差した。人が一斉に空を見た。風は弱い。雨粒の間に白い空が見えた。人々は勇んで外へ繰り出し、喜びに浸った。
しかし、午後には再び強くなり、道のぬかるみが深くなる。見張柱の刻線の上に新しい細い線が刻まれた。これは今の高さだ、という印だ。
雨が当たる音にその音だけが混じる。兵が短く声を上げ、刻刀を収める。田陵が太鼓を一度鳴らし、交代の合図だけを伝える。
夜。初更から雲は一様、二更で雷が一つ、三更で二つ、四更で二つ。五更の尽き際に、遠くで長い音。時間は短くないが、近づく音ではない。
荀潁が「遠雷、長し。一」と置く。白起は台の縁で雨の線を見続ける。灯は揺れず、覆いは持つ。器は生きている。星だけが見えない。
天文の日々は続いている。書は崩していない。だが、棚に置かれる句は同じものが増え、注の数だけが並ぶ。
市の列は短く、旅の掲の札は増え、井戸の水は濁り、皮の横木は布の下で暗い。臨洮の人は騒がない。騒がないぶん、静かな不安が城の中に溜まる。
天文部の夜は、普段どおりの手順を守りながら、その不安の厚みを注の一行に少しずつ移していく。その移し方が足りないのではないか、と荀潁が一瞬だけ筆を止め、すぐにまた字を揃える。
白起は語を増やさない。増やすと記が濁る。濁った記は次の判断を曇らせる。必要な句はすでに板にある。
雲一様。雷、四更。落ち、重。堤、交代。十日目の兆し。
——これで十分だ、と白起は内で繰り返す。夜の雨は一定に落ち、灯の炎は一定に立つ。臨洮の秋が、例年と違う歩幅で進んでいる。
帳はそれをそのまま受け入れ、余白を狭めずに置いている。翌日の昼、圭表の影はまた拾えないだろう。だが脚の沈みは記せる。堤の刻は添えられる。夜の雷は刻で分けられる。
できることはまだある。そう判断して、白起は次の更の時刻に耳を合わせた。雨音は変わらず、遠雷は短く、城の中の足音は少ない。
雨は十一日目に入った。午前、県府の中庭に臨時の詰所が設けられ、見張柱の刻線が板に写される。柱は古い深い線のひとつ上に迫り、兵が刻刀で新しい印を打った。音は短く、泥の匂いが濃い。田陵は濡れ衣の袖を絞り、白起に向いた。
「白起殿、堤は三カ所、越波の兆しです。材と人は高所に寄せました。」
「弱所に畳み掛けをしましょう。柴束、筵、砂袋の順で重ね、杭で押さえ、竹籠石を水際に据えるとよろしいかと。太鼓は二打で警戒、三打は総出と、今一度、官の引き締めを行っておくべきでしょう。この雨は洗礼がありません。どのような危機が起こるか分かりませんので、万全を期しましょう。」
「白起殿がここにいてくれて安心だ。軍事の経験も活きてくる。」
睡眠時間を削り公務に当たっている白起は、天文の板を引き寄せ、末尾に項を増やした。水位・雷の刻の下に「堤・交代の刻」「材の置き場」を並べる。荀潁がすぐ筆を入れる。
「初更 見張柱、四刻線。堤、夜巡を増。材、北堤三点に前置き。」
「語は短く。夜は刻で動かす。」
「承りました。」
雨脚は昼過ぎからさらに強まった。塩の竈は火を止め、皮の横木は屋内に引かれ、鍛冶の扉は閉じられた。市場は縮み、旅の掲には「北の橋、通行止」「南の浅瀬、渡し不可」「堤、夜灯十」の札が増える。宿舎では耆が「井戸、封じます」と言い、木蓋に縄を通した。
夕刻、指揮は詰所に集約された。田陵が配りを読み上げ、白起が刻を配る。梁宛は堤の夜灯、馬渓は材の置き場と運び、荀潁は板記、公孫庭は古い「長雨」の束の抜き出し。韓慎は端に立ち、視線だけを配る。
「二更のはじめ、北堤の弱所に畳み掛け。四更に交代。夜灯は三十歩ごと、風下に置け。太鼓二打で巡、三打で総出。橋板は抜け。渡しは止めよ。」
白起の声は低く、短い。田陵が頷き、伝令が走る。走る者は少ない。足はすべて泥を踏み、声は短句だけだ。
いつの間にか白起に指揮系統が集約され始めている。かつての軍門での経験が皆を統率している。田陵もこの処置を一任しており、むしろ自分よりも白起が適任と思っている。
しかし、この行為は越権行為に当たり、韓慎が都に報告する可能性もある。そうなれば白起の処罰は免れない。しかし、それを置いても構わないくらいの緊急事態であった。
二更の半ば、北堤の越波が始まった。水が低い梢のように肩を越え、法先を叩く。夜灯が濡れ、松脂の煙が弱まる。太鼓が二打鳴り、巡視が集まった。梁宛が杭を持ち、馬渓が砂袋の列を作る。
ここに至っては天体観測どころではなく、天文部も土木作業に従事していた。公孫庭以外は皆若く、体力には自信があった。
「白起様、畳み掛けに入ります。背から押さえます。」
「うむ。柴束を最前、筵で覆い、砂袋で重ねてくれ。杭は三尺ごと、頭を揃えるように。」
「承知いたしました。」
荀潁は板の端を押さえ、太鼓の刻と堤の位置を短く記す。
「二更半 北堤、越波。畳み掛け、着手」
公孫庭が隣で古い札を開き、十七年前の「越波、畳み掛け」の語を示す。語は同じで足りる。
三更のはじめ、雨脚は変わらず、雷は遠い。北堤の畳み掛けは続き、隣の弱所へ移る。兵が肩縄で列を作り、砂袋を渡す。泥で滑る足を、杭の列が止める。太鼓は二打で巡、間に一度だけ三打が入り、総出が集まる。白起は越波の先端を見て、短く指示を出す。
「竹籠石をここへ据えろ。流れを鈍らせる。杭を先に。」
「竹籠、参ります。」
梁宛の声は途切れない。馬渓は肩で砂袋を受け、列に渡す。
「白起様、筵、まだ足ります。柴束も予置きがあります。」
「よい。覆いを低く。灯は風下で保て。」
「心得ました。」
四更に入ると、南の支流から流木が増えた。見張りの兵が短く告げる。
「白起様、南の浅瀬、木の流れ、多くなりつつあります。」
「橋板は外した。堤の前に木を止める柵を仮置きせよ。縄を二重に、杭は浅く広く。」
田陵が作事の匠を呼び、白起の短句をそのまま指示に変える。余計な言葉はない。韓慎が白起に目を向けた。
「切堤の地点は決めているのか。」
「決めてあるります。しかし、まだ使いません。遊水地に空きがあります。」
「判断は刻で変えるのだな。」
「刻で変えていきます。」
四更の半ば、北堤の越波は一時おさまった。畳み掛けが利いた。別の弱所へ人が移る。太鼓二打が続き、夜灯が増える。
荀潁は「四更半 北堤、越波、収む。別所へ移」と記し、板の余白に「夜灯、三十増」と置いた。
五更のはじめ、雨は弱まらない。東は白むが、濁ったまま。堤の上の泥は深く、足が鈍る。白起は田陵に言う。
「粥所を開けますか。夜、動いた者に熱を。塩もできる限り配っていただけるとありがたいのですが。」
「すでに炊かせています。井戸は封じ、雨樋の水を煮沸します。」
「さすが田陵殿。疫の札を掲げましょう。濡れ穀の干場を仮でよいので用意をお願いします。」
「うむ、すぐに手配しよう。」
朝、雨はなお続く。畳み掛けの列は細くなったが切れない。昼の前、見張柱の刻線に新しい印がついた。昨夜より一段高い。田陵が短く顔をしかめる。白起は板の末尾に「水位、柱、五刻」と置き、午後の配りを言う。
「昼は堤踏み固め。夜は巡視。重い施工は昼に寄せる。越波が出たら太鼓三打、総出で畳み掛け。切堤は遊水地の準備が整ってから。勝手に切るな。」
「はっ。」
次の夜も、雨は止まなかった。二更で北堤、三更で西堤、四更で南の低地。越波は点を移し、列も動く。
白起は「刻で動かす」を守り、短句だけで足を配る。荀潁の板は余白が狭くなり、注が増える。だが語は揃っている。
「越波、二更」「畳み掛け」「収む」「移」。
韓慎は板を横から見て、低く言う。
「この語なら、後で辻褄が合う。」
「辻褄のために書くのではありません。明日の工作のために書くのです。」
「わかっている。」
朝、南の支流の水が急に増した。上流の仮柵が流されたらしい。見張りが息を切らせて戻る。
「白起殿、南の谷、音が変わり申した。」
「分洪路を開けましょう。旧河道へ水を逃がします。切堤点は田陵殿の合図まで待つように伝達を。」
田陵が太鼓を鳴らし、合図を二度、間を置いて一度。旧河道の入口の土手が崩され、遊水地に水が回る。白起は歩を止めず、板の末尾に「分洪、旧河道、開」と記した。荀潁がうなずき、筆を進める。
午後、雨脚がわずかに落ち、堤の上の人の息が戻る。粥所には列ができ、塩も配られる。井戸は蓋を閉め、桶の水が煮られる。子どもが二人、囲いに避難し、老人が濡れた衣を炭火で乾かす。騒ぐ者はいない。声は短い。
夜、四更に雷が一つ。越波は点で出るが、畳み掛けが追いつく。切堤は使わずに済んだ。白起は台の端で一度だけ立ち止まり、天文の板に戻った。星は見えない。
だが板の余白に、必要なものは揃っている。
「堤、夜巡」「太鼓」「畳み掛け」「分洪」「粥所」「井戸封じ」
理は地に移され、短句で動いている。
五更の尽き際、雨脚がわずかに細くなり、東の白みがいつもより早い。白起はその差を荀潁に告げ、末尾に一行を加えた。
「五更尽、白み、早し。一」
「記しました」
田陵が肩で息をして戻り、白起に向いた。
「白起殿、今夜は持ちこたえました。昼に本復旧へ足を入れます」
「堤の増高・拡幅、河道浚い、蛇行の剪断。護岸は柴束と籠石、柳枝を差しましょう。図は午前に起こします。弱所の図はすでに板に準備しております。」
「うむ。兵は昼に踏み固め、夜は巡視に回す。」
韓慎が詰所の柱にもたれ、静かに言った。
「あなたの帳は、今夜も汚れていない。」
「簡潔明瞭な指揮はよく動きます。」
「そうだな。」
まだ雨は止んでいない。だが、不意の叫び声はなかった。太鼓は合図の数だけ鳴り、夜灯は列を保った。臨洮の城は、濡れたまま動いていた。白起は板を束ね、末尾に短く印を置いた。「良くはない。しかし、足りている。」それで十分だった。
【8】臨洮の災
雨は十四日目に入った。朝、見張柱の刻線は昨夜の印を越え、刻刀の届く位置がなくなった。兵が腰を沈め、濡れた腕で新しい線を打つ。泥が刃に貼りつき、打つたびに短い音が途切れる。
詰所の板には「水位、柱、六刻」と書き足され、墨が水を吸って滲んだ。昼までに遊水地は満ち、旧河道に逃がした水も戻り始める。田陵は袖を絞りながら言った。
「白起殿、北堤と西堤、両方に越波。材は前置きしてあるが、人が足りません。」
「北に主を当てましょう。西は見張りを倍に。太鼓を一つ南へ回す。夜灯を三十増やしておきます。」
「うむ。」
城下は朝から落ち着かなかった。市場の列は消え、旅の掲の札だけが増える。
「北の橋、通れず」「南の渡し、止む」「堤、夜灯三十」
字は細いが、書く手が震えているのがわかる。宿舎の耆は井戸に木蓋を落とし、縄を二重に結んだ。
正午前、北堤の一角で越波が続いた。畳み掛けの列が崩れずに踏ん張っていたが、三度目の波で杭が二本抜けた。水が一気に背に回り、柴束を巻き込む。
太鼓が二打、間を置いて三打。総出の合図に、堤の道を人が走った。泥が滑り、倒れる者が出る。肩縄が列を保ち、砂袋が次々手から手へ移る。梁宛が杭を抱えて駆け、馬渓が筵を抱えて叫んだ。
「背から押さえます、白起様! 杭、頭をそろえます!」
「押せ、覆いを低く。竹籠石を前へ。縄を二重に。」
「心得ました!」
決壊は一息だった。法先がもろみのように崩れ、背水側から一幅が落ちた。水が土を引き、穴が一気に広がる。
夜灯の柱が一つ倒れ、松明が水に飲まれた。兵の一人が肩縄から外れて膝をつき、隣が腕を引いた。足の下で土が動く。「退け」という声が短く重なり、列が半歩ずつ下がる。
詰所に報が入る。「北堤、決壊」。書吏の筆が止まり、板の余白に太い字でその二文字が乗った。田陵の顔が引き締まり、伝令に手刀で道を示す。白起は板の末尾に「分洪、準備」と書き、田陵に向かった。
「切堤点、合図を待っています。遊水地に空がありますか。」
「一。だが、村の畑が半分残っている。」
「人を出しましょう。先に人と穀袋を上げ、印牒と医の具を先に。」
城内の音が変わった。太鼓の二打と三打が重なり、角笛が短く鳴る。門に人が集まり、荷車がひっくり返り、子どもが泣いた。
女は背に布をかけ、老人の腕を引く。役人の声は届かず、手が届く範囲でしか人は動かない。門の外の道は泥で、足跡がすぐに消えた。
渡し守は綱を高く張り直し、舟を引いて高所へ上げる。橋板は外され、杭だけが水から出ている。旅の掲の板が外れて地に落ち、札が水に浮いた。
近郊の村から人が流れ込む。肩に穀袋、手に子の手。背に濡れた布。男は棒で荷を支え、女は鍋を抱える。粟の束は泥に濡れ、豆は袋の口から落ちる。畑の畦を越えた水が、刈り取りの束を根こそぎ運んだと言う。
牛が一本、縄を切って走り、角が門の柱に当たって鳴いた。門番が棒でいなした。列の中で怒鳴り声が上がり、すぐに沈んだ。怒鳴っても水は止まらない。
詰所では地図が濡れ、札が増え、板が重くなる。書記が竹簡の濡れを拭う。田陵は堤の配りを読み直し、白起に短く問う。
「白起殿、切るか。」
「もう一刻の猶予を。西の堤が持てば切らずに済みます。持たなければ、切りましょう。」
「合図は三打の後、二打。わかりやすく。」
「それでよいかと。」
西堤の報は悪かった。越波が連続し、畳み掛けが追いつかない。兵が息を切らして戻り、「竹籠が二つ流れた」と言った。
梁宛は北から西へ回り、馬渓は北に残った。荀潁は板の端に「西堤、越波、連」と短く置き、顔を上げない。公孫庭が古い束から「割堤」の札を引き出し、田陵の前に置く。
「田陵殿。ここです。」
「……。」
午後の半ば、村の一つが沈んだ。見張りが詰所に飛び込む。
「白起殿、南の谷の村、家の半分、水に浸りました! 収穫、流れ申した!」
「人は。」
「高台へ移動中。子と老人を先に。」
「井戸は封じたか。」
「封じました。粥所は……人が多すぎて列が……」
「粥所をもう一つ。塩を薄くして量を増やせ。医を回せ。湿った穀は干場へ。縄で棚を組め。」
田陵が「賑給」の札を取り、司倉に渡した。「倉より粥を出す」の文字が濡れて重く見える。書吏が「税の減免・徭役延期」の札を別に用意し始めた。誰もそれを口にしない。今は水の前に立つだけだ。
太鼓が乱れた。西堤から戻った若い役人が、印を飛ばして叫ぶ。
「三打を二度にしてしまいました! 人が一斉に……!」
「落ち着け。もう一度三打を一度。次に二打。合図を戻せ。」
白起の声は低いが、はっきりしている。兵がうなずき、太鼓の前に走った。音が整い、列が向きを変える。混乱の中でも、合図が揃えば足が揃う。揃わない足は人を倒す。
城の外で、牛の鳴きが増えた。囲いに上げられた牛が落ち着かない。牧の者が声をかけ、草を投げる。馬の囲いでは水が膝まで来ている。
若い者が馬の脚を上げ、別の囲いへ引いた。囲いの杭が揺れ、縄が軋む。桶の水は濁り、砂が底に沈む。番の交代は早まり、名を声に出さず、手の合図だけで交代する。声は水に吸われて届かない。
堤の上で、梁宛は杭を叩きながら、短く指示を続けた。
「荀潁、ここは『越波、四更』でなく『決壊、二更半』に直せ。刻が違う。——馬渓、筵をここへ。頭を揃える!」
「承知!」
馬渓の声は重い雨に飲まれかけながらも、近くの者には届いた。肩縄の列に位置を指で示し、砂袋の積む角を手で正す。
筵が水に貼りつき、砂袋が上から押さえる。木杭の頭は一列に見える。竹籠石が滑り、二人が足を踏ん張って止めた。流れは鈍るが、止まらない。
詰所に戻ってきた見張りが、濡れた髪を振り、息を継いだ。
「白起殿、北の村からの者が押しかけ、門で詰まっております!」
「南門は閉鎖だ。北門一本で回せ。列を作れ。印牒を失った者は印を打つ。子と老人を先に。家畜は後だ。」
「はっ。」
門の前で役人が縄を張り、列を作る。子どもが泣き、女がその頬を拭く。老人が腰を落とし、若い者が肩を貸す。
列は動く。止めない。動かない列はすぐ壊れる。列の外に怒鳴る者がいるが、二人が両側から腕を取って内に戻す。争う時間がない。
午後の尽き際、田陵が白起に小さく言った。
「白起殿。西が持ちません。切らねば、城の内側に回ります。」
「切りましょう。切堤点は第三。太鼓、五打の後、二打。案内を先に出します。切る前に人を出すべきかと。」
「うむ!」
田陵が太鼓の前に立ち、合図を打つ。五打、一息、二打。伝令が走り、切堤点の役人が杭を抜き始める。旧河道の入口に人が集まり、土が崩される準備に入った。
白起は板に「割堤、第三。分洪路、開」と書き、荀潁に渡す。
「語はそのまま。注に『人・穀、先行』」
「記しました」
切堤に向かう道で、村の男が白起に食い下がった。顔は泥だらけで、目だけが赤い。
「白起様! うちの畑は切堤の下です! 今、刈った粟が!」
「人が先だ。穀は二の次。粥を出す。塩も出す。人さえいれば次がある。」
「……はい。」
男は首を下げ、列に戻った。背中が揺れたが、声は出さなかった。
西の堤は、切るより先に一段崩れ始めた。切堤点に回す前に自然に割れたのだ。太鼓が重なり、角笛が短く鳴る。切堤の作業と、自然の崩れの両方に人が散る。混乱が起きかけた。白起は手短に配りを変える。
「切堤は予定通り。崩れの前に竹籠石を据え、流れを斜に変えろ。杭は浅く広く。」
作事の匠がうなずき、男たちが籠石を運ぶ。肩縄の列が二つに分かれ、片方が切堤、片方が崩れへ向かう。夜灯が増え、松脂の煙が風に押される。雨脚は弱まらない。空は低い。
城内の粥所は列が延び、鍋の湯気が薄い。塩は少ないが、湯は熱い。医の具は少なく、包帯は濡れる。耆が濡れた穀を干す棚を組み、子どもが小さな手で穂を並べる。井戸の蓋は重い。誰も蓋を上げようとしない。水が汚れるのはすぐだと、皆が知っている。
夕刻、詰所の地図に黒い線が三つ増えた。決壊線だ。公孫庭が札を移し、田陵が印を押し、韓慎が黙って見ている。
白起は板に「夜巡、堤三路」「灯、百」「太鼓、五打・二打」と並べ、最後に「割堤、開」とだけ書いた。
「白起殿」
田陵が呼ぶ。白起は顔を上げる。
「割りました。水は旧河道へ向かっています。遊水地は……村の端に入りますが、丘に逃げています。」
「太鼓は二打を一度。総出は解かない。——夜は四更に交代。粥も惜しまずに。」
「はい。」
門の外の道は、もう膝までの水だ。足の遅い者は肩で支えられ、荷は捨てられる。収穫は流れ、束の一部は枝に引っかかり、また外れる。
牛が一頭、流れに足を取られて鳴いた。縄が切れ、二人が飛び込もうとして止められた。舟は足りない。綱が一本、もう一本と張られ、列がそれに掴まって進む。太鼓がまた鳴り、合図が夜の入りを告げた。
初更、雨はさらに重くなった。夜灯が増え、堤の上が明るくなる。切堤の口から轟く音が続き、腹に響く。白起は板を荀潁に預け、短く言った。
「今夜は『天文』を下げ、『堤と刻』を上に置く。星は見えない。記は動くものだけ。これは稀に見る豪雨だ。後世のためにも、官民の行動を逐一、記しておくように。」
「承りました。」
白起は外衣の襟を詰め、田陵と並んで堤へ出た。水は動き、土は流れ、声は短く、夜は長い。前半はまだ終わらない。
次は、切堤の口がもつかどうかだ。太鼓が三打、二打。濡れた地が震え、列が進む。
初更の半ば、切堤の口は思ったより早く噛み、旧河道に黒い帯が走った。口の縁が刃物のように削れ、渦が二つ立つ。渦の回りは土が抜ける。白起は指で示し、短く言う。
「渦の腹へ柴束を投げろ。筵で押さえ、杭で刺せ。」
「承知!」
作事の匠が号を掛け、束が次々放り込まれる。水は束を巻き込むが、やがて速度を落とす。渦の縁が緩み、口の削れが止まる。田陵が息を吐いた。
「保つか…」
「今は。二更までに口を小さく締め直します。夜は口を広げ過ぎないように。」
「わかった。」
城内は、合図が整っても騒ぎが消えない。門の列は曲がり、泣く子の声が頻る。詰所の前に駆け込んだ男が「城が割れる」と叫び、場が一瞬ざわついた。白起は振り向かず、書吏に一言だけ落とす。
「口で言うな。板で伝えよ。」
書吏は頷き、掲示の板に大きく「城、割れず。堤、持つ。割堤、開」と書いた。伝令が板を持ち、門と粥所へ走る。声は届かないときがあるが、板は残る。人は板を見る。列の揺れが少し小さくなった。
二更のはじめ、上流の流木が切堤口に溜まり、束石に引っかかった。渦が逆に強まる。白起はすぐに指示を変える。
「口の下に籠石を一つ落とせ。流れを下げよ。——梁宛、紐を掛け、木を横へ引け。」
「承知!」
梁宛が濡れた身体で縄を回し、三人で引く。木は一度潜り、また浮く。二度、三度で外れ、音を立てて下った。
口の渦が緩む。竹籠石が位置に落ち着く。馬渓が覆いの筵を押さえ、杭が叩かれる。太鼓は二打、巡の合図を守る。
西堤の崩れは続いていた。畳み掛けの列が細り、肩縄の間隔が広がる。泥が深く、男が足を引かれ、膝をつく。隣が腕を引き、別の者が肩を貸す。隊列が切れそうになる。田陵は詰所から一段降り、声を絞った。
「三打は打つな。巡を早めろ。——兵を十、竹籠へ回せ!」
韓慎が柱の陰から歩み出て、白起に低く言った。
「夜のうちに決めることが多すぎる。」
「夜は刻で動かすしかないのです。」
「あなたは、板で動かしている。」
「板と太鼓です。」
韓慎はそれ以上言わなかった。肩にかかった雨が流れ、灯がその輪郭を一瞬だけ浮かせて消した。
二更の半ば、城内で別の破綻が起きた。避難の列に牛が紛れ、縄が切れて走る。子どもが転び、女が抱き上げる。門の前が詰まる。詰所に報が入り、荀潁が顔を上げる。
「白起様。」
「北門は一息止め。牛は西の横口から。——人は縄を張って列を二つに割れ。」
伝令が走る。縄が張られ、牛の列と人の列が分かれる。動きが戻る。粥所の鍋は常より早く減る。塩は薄いが、湯は熱い。医が小さな包みに灰を入れ、濁り水の沈殿に使う。井戸の蓋は固く縛られ、誰も手を出さない。
二更の尽き際、切堤口の周りが再び削れた。渦は二つから三つになり、縁が落ち始める。白起は短く言葉を重ねた。
「口を広げるな。縄をもう一本。上から簀を落とせ。——籠石、二。」
「簀、来い!」「籠、二つ!」
作事の匠が繰り返し、動きが揃う。簀が落ち、籠石が二度に分けて沈む。渦の縁が薄れ、口の刃が丸くなる。田陵が腕の泥を払った。
「三更まで持たせれば、朝まで行ける。」
「三更を越えろ。」
三更のはじめ、雷が近くで一度鳴った。雨脚は変わらない。堤の上の足音だけが一定に続く。西の崩れは、畳み掛けの列が戻し、いったん止まった。代わりに南の低地が危うい。浅瀬の仮柵が一部剥がれ、流木が増える。見張りが短く告げた。
「南の浅瀬、木、大」
「縄を二重に。杭は浅く広く。——柵の前で押さえるな、後ろで受けよ。」
受けの位置が変わり、木が柵を壊す前に動きが弱る。人は水際から半歩離れ、肩縄の角度を変える。
酔ったように見える動きだが、足は揃う。太鼓が二打を刻む。夜灯が一つ、二つ、雨で消え、すぐに新しい灯が置かれる。
三更の半ば、城内の粥所で揉み合いが起きた。列の脇から腕が伸び、鍋の縁に触れた。番の者が抑える。声が上がりかけ、すぐに沈む。白起は詰所の板に短く記した。
「粥所、二。守、増」
田陵が司倉に向き、穀の配りを変える。鍋は三つになり、列の間隔が広がる。医の小屋の前に濡れた布が干され、刃物が火で温められる。大声は出ない。人は口を閉じ、足を動かす。
三更の尽き際、見張柱の板に新しい札が打たれた。「水位、柱、七刻」。最深の印を越え、板の端に達した。書吏の手に震えはない。字は細く、まっすぐだ。荀潁は筆の先で余白を計り、白起に問う。
「白起様、書き入れる位置が尽きます。」
「下へずらせ。刻の字を小さく。——『七刻、尽』の印を付けろ。」
「承りました。」
四更のはじめ、切堤口の流れがわずかに鈍った。雨脚がほんの少し細くなったのか、渦の肩が低くなる。白起は動きを急がせない。田陵も急がせない。
急がせると列が乱れるからだ。梁宛は杭を叩く手を緩めず、馬渓は筵の端を抑え続ける。荀潁は「四更、雨、細し、一」と小さく注した。
四更の半ば、北の村へ回した舟が一艘戻らないという報が入った。綱が切れたのだろう。詰所の空気が一瞬重くなる。誰も声に出さない。田陵が静かに言う。
「西の舟を一つ回せ。綱を二本に。——呼吸を合わせて漕げ。」
伝令が走る。白起は板の端に「舟、一、戻らず」と細く記し、それ以上は足さない。記は、足のためにだけ残す。
四更の尽き際、切堤の口は保ち、旧河道の水筋が太く安定した。南の浅瀬は柵が持ち、北堤は越波が散発に変わる。西の崩れは止まっている。白起は初めて短く言った。
「保ったか。」
田陵が頷き、角笛を一度だけ鳴らせた。総出の合図ではない。交代の合図だ。肩縄の列が一歩ずれ、別の肩が縄を受ける。粥所に置いた鍋の湯気が再び濃くなる。医の小屋の前で火が一つ増える。
五更のはじめ、東がかすかに白い。雨は続くが、音はわずかに軽い。太鼓の合図が刻を示し、人の歩が朝に向かう。白起は荀潁に言う。
「『五更初、白み、薄し』。——『口、保つ』を上に。」
「記しました。」
門の外では、泥の道に足が深く入り、列の足跡がすぐに水で消える。子どもを抱いた女の顔には泥の筋だけが残り、老人は背を伸ばしたまま歩く。誰も振り返らない。後ろは水だ。前に高処がある。役人は縄を持ち、列の間を走る。怒鳴らない。手の合図だけで割り、繋ぎ、戻す。
五更の半ば、田陵が白起に近づいた。顔の泥を袖で雑に拭き、目だけで笑う。
「白起殿。切った口が保ちました。遊水地は際まで。丘に逃げた者は無事です。」
「はい。夜のうちにできることはしました。」
「次は昼の重い仕事だ。」
「踏み固め、増高・拡幅、浚い、剪断。護岸、柴と籠、柳枝。——図は今、作ります。」
「うむ。」
公孫庭が古い束を胸に抱え、詰所の卓に運ぶ。札をずらし、余白に新しい札を挟む。「越波」「決壊」「割堤」「分洪」。同じ語が並ぶが、刻が違う。違いだけが、翌日の足になる。韓慎はその並びを見て、短く言った。
「夜の帳が、軍の帳になった。」
「理は同じです。」
「あなたの語は短い。」
「短いほうが動きやすいのです。」
五更の尽き際、雨がさらに細くなった。切堤口の轟きは続くが、腹に響く重さが一歩下がる。見張柱の板に、新しい線は増えない。荀潁が筆を置き、白起を見た。白起は頷き、板の末尾に今夜の“核”を三行で置いた。
「越波、決壊、割堤、四路。刻、守。
分洪、旧河道、口、保つ。
賑給・井戸封・舟救、継ぐ」
それから、もう一行だけ足す。「死傷、未詳。行方、不明、若干」。字は小さい。荀潁は何も言わない。字を揃え、板を束ねる。
朝の合図が鳴った。太鼓が一度、角笛が短く続く。粥所の列は長いが、動いている。井戸の蓋は閉じたまま。医の小屋の火は消えず、干し棚の縄は濡れ穂で重い。
堤の上では、夜灯が消され、杭の頭が並んでいる。切堤の口に新しい束が追加され、籠石の上を薄い水が走る。水はまだ高い。だが、夜の乱れは少し退いた。
詰所では、昼の配りが読み上げられた。田陵が声を張る。
「堤は北・西・南の三路に分け、踏み固めを第一。増高は午後。——河道の浚いは西の崩れ前から。蛇行の剪断は匠が印を付ける。護岸は柴束と籠石、柳枝を差す。橋は架け直しの前に杭を打ち直す。——賑給は粥所を三、塩を薄く保て。医は疫を先に見ろ。井戸は封じ続ける。——記は刻ごとに出す。太鼓は乱すな。夜は巡視に戻す。」
白起はそれを板に短句に落とし、荀潁に渡す。梁宛は脚印を携え、圭表の足を見に走った。馬渓は漏刻の管を拭きながら、昼の落ちを試す準備をする。
公孫庭は札を束ね、棚の「長雨」の束と今夜の札を並べて括る。韓慎は柱に寄り、外の光を一度見てから、何も言わずに詰所の外へ出た。
城門の前で、白起は一度立ち止まり、北の空を見た。雲はまだ低い。だが、白さがある。星はない。必要もない。今は地の仕事が続く。夜に聴いた轟きは、昼の土と竹と縄で受け止める。白起は軽く息を吐き、堤へ向けて歩を進めた。
堤の脚はぬかるみ、靴が深く沈む。肩縄の跡が縦に並び、杭の列が一定に続く。夜灯の消え残りが煙を細く上げ、松脂の匂いが薄い。
肩を並べる男たちは、もう多くは言わない。短い合図だけで足と手が動く。女は濡れた布で子どもの背を拭き、老人は座る場所を譲る。
誰も泣き叫ばない。声は、太鼓と板に集められる。天は怒らない。人は騒がない。水は動く。理は地で働く。
白起は堤の上で、杭の頭を一つ撫で、束の結び目を一つ締めた。それから田陵に近づき、昼の順をもう一度だけ短く言い直した。
「踏み、描き。据える。——刻で動けるように準備しましょう。」
田陵は肩で息をしながら「承知。」と言い、合図を出した。昼の太鼓が鳴り、夜の列が昼の列に変わる。上邽で受け取った家の便りの最後の句が、遠いところで短く浮かんで消えた。白起は襟を詰め直し、濡れた土のうえを、次の杭の位置へ歩いた。
【9】白起の統率
昼の太鼓が三度、一定の間で打たれた。詰所の板に「昼配り」と太い字が立ち、白起は短い句で項を埋めた。
「堤は北・西・南、三路。踏み固めを先。増高は午後。河道は西前から浚う。蛇行は匠の印で切る。護岸は柴・籠・柳。橋は杭から。賑給は粥三か所。井戸封じ続行。医は防疫。記は刻ごと」
田陵が読み上げ、伝令が板の写しを抱えて走る。白起はすぐ次の板を起こした。官と民の作業を混ぜる配りだ。
「持場:堤・材・舟・炊・医・記。什伍で組め。肩縄を揃え。列は崩すな。」
堤の上では、夜の肩縄の跡が泥に残っている。白起は北路の頭に立ち、半歩ずつ隊を動かした。踏み固めは声で揃えない。
足裏の重みで揃える。杭の列を目安に、三歩で一拍、拍で一列。田陵が一段下から「間を切るな」と低く言い、匠が法先の角を手で示す。笛は吹かない。太鼓だけが刻む。
「杭の頭、揃え。砂袋、角を落とすな。筵、重ね二。籠石、先に据える。柳は後で差す。」
白起は列の脇に立ち、指で角度を示した。濡れた筵が水を吸い、砂袋の角が沈む。若い者が勢いで押しすぎると、白起は手のひらを下にして動きを抑えた。動きは細かく途切れず続く。大声は一度も出さない。
西路では、河道の浚いが始まった。匠が棒で底を探り、浅瀬の筋を見つけると、白起は板に「刈り取り」と一語だけ書いた。鍬の先が砂を掬い、竹籠に砂礫が落ちる。竹籠は二人で運び、堤の背に積む。
蛇行を切る位置に匠が印を付け、作事の組が杭を打つ。流れが鈍り過ぎないよう、白起は籠石の置き方を変えた。斜に一つ、直に二つ。水が肩を変える。太鼓は一度だけ鳴り、隊の向きが半身ずれる。
南路では、柵の補強と舟の回しが重なっていた。縄は二重、杭は浅く広く。舟の先に細い簀を吊り、流木を受けてから横に逃がす。白起は「受け、逃がせ」と短く言い、舟頭と目を合わせる。
舟が戻るたびに、漕ぎ手の肩が大きく上下した。息は荒いが、声は出さない。韓慎が柵の陰で動きを見、何も言わずに詰所に戻る。
粥所は五つに増えた。塩は薄い。列は長いが、太鼓の小さな合図で間が詰まる。司倉が穀袋の口を結び直し、耆が柄杓の受けを増やした。
医の小屋では、灰を溶いた水が桶に用意され、濁り水の沈殿に使われた。包帯が火のそばで温められ、刃は拭かれて布に包まれる。白起は板の隅に「粥五、守増、医二」と置き、荀潁に渡した。
「掲示の言葉、長くするな。三語で足りる。」
「承知しました。」
午後に入ると、雨脚がほんの少し細くなった。堤の上の泥が若干軽くなり、踏む音の間が整う。白起は増高の指示を短く変えた。
「踏み終えた列から、砂袋を上段に。法先の角に三、背に二。頭は一直線。杭は頭が見えるまで。」
梁宛が頷き、打つ音が続く。馬渓は砂袋の列を二筋に割り、角に“角取り役”を置いた。角が崩れると列が一気に乱れるからだ。
崩れそうな角には筵を一枚足す。筵が足りなくなる前に、白起は「材、南から回せ」と板に書いた。伝令が足で走り、材の組が道をすり抜ける。声の代わりに手が挙がり、指が向きを示す。
西路の浚いは、浅いところが片付くと、蛇行の剪断に移った。匠が印を付けた位置に杭を並べ、板で仮の水路を狭める。白起は「締めるな。絞れ」とだけ言った。
締めると上で溢れる。絞れば下で流れる。絞った口に籠石を置き、上から筵を落とす。流れの肩が変わり、旧い筋が息を吹き返す。田陵がそこへ人を配し、踏み固めの組と交互に働かせた。疲れた肩を交代させるためだ。
南路では、柵の裏に濁りが溜まり始めた。船頭が手で示し、白起は一つだけ指示を足した。
「柵の上を越す前に、裏を掃け。簀で払い、籠で掬う。前を守って後ろで受ける。」
舟が簀を引き、濁りを押し流す。籠が砂を掬い、背の土に落ちる。単純な動きが、刻の中で反復される。
詰所の板は、刻のたびに項が増え、余白が詰まる。荀潁は字を小さくし過ぎない範囲で詰め、同じ語は同じ位置に置いた。
「越波」「収む」「移」「踏む」「据える」「描く」
公孫庭は古い束の脇に今の札を挟み、並びの違いだけに朱を打つ。韓慎は横から見て、「語が揃っている」と一言だけ言った。
午後の尽き際、北路の増高が一段落したところで、堤の背に人が集まり過ぎた。砂袋の山が偏り、列が詰まる。誰かが焦って押し、袋の角が二つ崩れた。
男が足を取られて倒れ、後ろの者がのしかかった。声が上がりかけた瞬間、白起は太鼓へ目で合図を送る。短い二打が一度。列が一呼吸止まり、前だけが半歩進む。崩れが止まる。
白起は手で“半歩戻れ”と示し、倒れた者の腕を二人が引いた。声は出ない。動きが戻る。荀潁は板に小さく「偏、止」と記した。
「焦るな。角を整えろ。袋の口を上に向けろ。」
白起の声は低い。近い者だけが聞く。遠い者には太鼓が届く。太鼓は乱れない。
増高が続く間に、白起は賑給の板をもう一枚起こした。
「粥五、列、縄。塩、薄。乾場、棚、縄二段。井戸封じ、続。疫、便所の溝切り」
耆が縄を張り直し、粥の列が二筋に割れる。濡れ穀の棚は横木が増し、縄が二段に張られる。便所の溝が切られ、灰が撒かれる。医は「濫飲、禁」の札を粥所の脇に立てた。
日が落ちる。雨は弱くなったが、川は高い。白起は夜の配りに移った。
「夜巡、堤三路。灯、百。太鼓は二打で巡、三打は総出。刻は初更から。見張柱の札は二刻ごと。舟は南一、西一。粥は夜も一つ開きましょう。」
田陵が頷き、夜の板を掲げさせる。昼の列が夜の列にかわる。肩が入れ替わり、灯が増え、太鼓の間が夜の長さに合わせてわずかに伸びる。
初更、北路の上で灯が二つ消えた。雨ではない。油が足りない。馬渓が油壺を抱えて走り、覆いの角度を下げ、炎を守る。
梁宛は照準紐のように灯の間隔を見て、「三十歩」と短く確認する。白起は頷き、板の端に「灯、補」を小さく置いた。
二更、見張柱の札が「七刻の下」を保ち、上がらない。荀潁は「水位、留」と書く。詰所の空気は硬いまま緩まない。緩めると崩れるからだ。韓慎が白起に近づいた。
「人の顔が変わってきた。怒りが引いて、空のほうを見ている。」
「油断はできません。」
夜半、南路で流木が一本、柵を破って内に入った。舟が寄る前に杭が一本傾く。田陵が「三打」をためらい、白起が首を振る。
「二打、二度。巡を寄せましょう。総出にせずに。——舟は横からです。」
太鼓が二度、短く鳴る。巡の列が半身ずれて集まり、舟が横から入る。簀が木の腹に当たり、力を逃がし、縄が木を引く。杭の頭が戻る。白起は板に「木、受、逃」と三語だけ置いた。
三更、粥所の鍋が尽き、列の先に子が二人眠ってしまった。耆が布を掛け、医が湯を足し、小さな椀で分ける。荀潁が板に「粥、夜一、増」と書き、司倉が穀袋を一つ追加する。白起は「塩、薄」とだけ指で示した。
四更、北路の堤の背に小さな沈みが出た。昼の踏みが足りなかった場所だ。白起は灯の下で泥の表を指で押し、沈みの輪を見た。
「砂袋を一段、背へ。角は崩すな。筵、薄くかけろ。——踏むな。置け。」
踏むと沈む。置けば締まる。列が音もなく動き、背に一段が加わる。沈みの輪が薄くなり、灯の影が揺れない。荀潁は「沈、小、置で収」と記した。
五更、東が白む。雨は細い。白起は夜の“核”を板の末尾に置いた。
「堤、踏・増、高、二路終。西浚・剪、進。柵、持。粥、夜一、増。水位、留」
田陵が小さく息を吐く。緊急は続いている。だが、秩序は続いている。白起は帯を締め直し、片手で額の泥を拭うと、再び昼の配りの板を起こした。
「本復旧へ移るが、巡は薄めるな。——堤は増高の仕上げ、護岸の据え直し。河道は浚いを進め、剪断の口を少し広げる。橋の杭は二本ずつ打ち替え。賑給は粥三を保ち、井戸封じ、続行。医は疫を先」
韓慎が柱の陰から出てきた。
「あなたは星を見ずに、刻を見ている」
「天は今、板の上にある」
「それで臨洮は保つか」
「保つかどうかは明日決まる。今夜は刻で動いた」
白起は詰所を出て北路の堤に戻り、杭の頭を指でなぞった。並びは揃い、角は立っている。踏みの跡が細かく重なり、砂袋の口がすべて上を向いていた。
背の沈みには薄い筵がかかり、灯は一定の間を保つ。水はまだ高い。轟きは続く。緊急は終わっていない。白起は田陵に向き直り、最後の配りを短く言った。
「昼、踏め。描け。据えろ。夜、巡れ。刻で動け。——太鼓を乱すな。板を汚すな。」
合図が出る。太鼓が一度、角笛が短く続く。列が動く。濡れた土が沈み、杭が立つ。粥の湯気が上がる。医の火が小さく揺れる。誰も空を見ない。板と足だけが前へ進む。緊迫は薄れない。だが、秩序は前を向いたままだ。
夜明け前、轟きが一段下がった。切堤の口はまだ唸っているが、雨脚が薄い。灯に当たる粒が見えなくなり、覆いの布が濡れを保ったまま、揺れをやめた。
見張柱の板に付けた札は「水位、留」のまま動かない。白起は太鼓の間をわずかに延ばし、巡の足を緩めた。
「二更尽、雨、細。太鼓、間を広げる。」
荀潁が記し、公孫庭が頷く。田陵は肩で息をしながら、北路の先に合図を送った。肩縄の列が一呼吸だけ長くなり、また同じ間で進む。誰も声を上げない。息の音だけが堤に残る。
四更のはじめ、切堤の口に立つ渦の肩が低くなった。籠石の上を走る水の筋が細り、筵の端が持ち上がる。梁宛が杭の頭を叩きながら、白起に目で問うた。
白起は小さくうなずくだけで、合図を出さない。早めると崩れる。田陵も動かない。太鼓は同じ間を守る。
四更の半ば、灯の炎に小さな光が映った。雨ではない。濡れた布から落ちた最後の滴だった。音はなかった。荀潁が板に「四更半、雨、止」と小さく置く。書き終えた手が一瞬だけ止まったが、すぐに次の刻の余白を整えた。
五更のはじめ、東の白みが昨日より明らかに早い。空はまだ低いが、雲に白が混じる。堤の上で誰かが深く息を吐き、隣がそれに気づいて肩で応じた。
粥所の鍋に湯気が立ち、柄杓が二度続けて打ち鳴らされる。列の前の子が目を開け、母が背から降ろして椀を持たせる。医の火は消さない。井戸の蓋は縛ったまま。
五更の半ば。切堤の口は持ち、旧河道の太い筋は濁りを強くしたまま安定した。西の浚いは夜のあいだに絞った口が働き、蛇行の肩が切れた。
南の柵は綱二本で持ちこたえている。太鼓が一度だけ間を空け、巡の列が交代した。白起は板の末尾に夜の“核”を置く。
「雨、四更半、止。口、持つ。水位、留。巡、継ぐ」
田陵が合図を二つ送った。総出を解く合図ではない。夜から朝への移りを告げる合図だ。肩縄の列は歩みを続け、粥所には新しい鍋が一つ増える。
詰所の板に「雨、止む」の大きな字が立った。書吏は墨を濃くせず、いつもと同じ色で書いた。
城門の前には、まだ人の列があった。背に布を掛けた女が空を見上げ、目を閉じた。声は出さない。老人は腰を伸ばし、杖の先を一度だけ地についた。
牛の囲いから低い鳴きがひとつ。縄は切れていない。舟は綱に沿ってゆっくり戻る。渡し守は綱を点検し、結び目を両手で掴んで締め直した。
雨が止んだと、誰かが言った。言葉は列の中で短い返事に分かれ、すぐに消えた。嬉々とした声はない。泣き声もない。
安堵は、椀を持つ手が震えないこと、太鼓の間が乱れないこと、灯の油が減りにくくなったことに現れた。白起は詰所の柱に手を当て、泥の付いた掌を一度だけ拭った。
「巡は減らさず、踏み固めは昼に回します。粥は五のまま、土木は午後まで延ばしましょう。」
「うむ。」
田陵は短く答え、伝令を二人だけ走らせた。韓慎は板の「雨止」の字を見て、白起に近づく。
「やっと止んだか。」
「まだ水位は高いです。二次の災の可能性があります。」
「慎重なことだ。」
韓慎はそれ以上、何も言わなかった。背の泥が乾き始めたところから落ちた。詰所の地図は濡れたままで、黒い線が三つ増えている。決壊線だ。白起はその上に薄い紙を敷き、今日の配りの印を書き込んだ。
朝の合図が鳴った。太鼓が一度、角笛が短い。肩縄の列は歩みを崩さず、目だけが一瞬空を見た。雲の白が広がり、風が変わる。
濁った匂いに乾いた土の匂いが混じる。城壁の上には濡れた布が並び、煙は細くまっすぐ上がった。雨は止んだ。
誰も叫ばなかった。誰も踊らなかった。安堵は、静かに、隊列の間に落ちた。
白起は板に最後の一語を加えた。「雨、止」。その下に、いつもの語を並べる。「巡、継」「踏、昼」「粥、五」。秩序を動かす語だけだ。手を止める理由にはならない。
堤の上に立つと、切堤の口から吹く風が湿っていた。耳の奥の轟きは残る。だが、空から落ちてくるものはなかった。白起は襟を詰め直し、田陵に向いた。
「昼の配りを押し通します。」
「承知。」
田陵の返事は短い。短さが、終わりと始まりの両方を意味した。安堵は列に行き渡り、緊急はまだ続いている。雨が止んでも、城は止まらない。
白起は堤の杭の頭を指で押し、角の固さを確かめてから、詰所へ戻った。板は濡れて重い。重さは、今は働くための重さだ。
午の直前、雲の白は少し強くなった。陽は出ない。だが、光はある。粥所の湯気は細くまっすぐ立ち、医の刃は乾いた布で拭われる。井戸の蓋は縛ったまま。賑給の札は動かない。
城の中はゆっくりと息を取り戻した。誰も笑わない。笑う時ではない。安堵は、背の力が少し抜けたことにだけ現れた。
午後、白起は板の隅にもう一行だけ置いた。「声、控」。それで十分だった。
雨が止んだ日の夕刻、切堤の口はなお唸り、旧河道の筋は太い。翌朝には水位が一段下がり、二日目の朝にもう一段下がった。見張柱の板は「七刻の下」から「六刻へ」「五刻へ」と戻り、札の色は同じでも、手の震えは消えた。
轟きは鈍り、代わりに匂いが強くなる。腐った草と濁りの匂いだ。静かさは戻らない。別の音が立つ。崩れた土が乾いて割れる音、折れた木の枝を切る音、鍬が硬い砂礫を掬って滑る音。
臨洮は変わっていた。城下の通りは泥で塗られ、家の壁は下から黒い帯を残した。畦は形を失い、田は砂礫と流木で覆われた。
刈り取り前の穀物は消え、束は河原の石の間に引っかかっている。皮の横木は歪み、塩の竈は灰で固まっていた。橋は杭だけが残り、板は流された。
井戸は封じられたまま、蓋の縄に泥が乾いてこびりつく。舟は傷だらけで、漕ぎ手の掌の皮は剥けた。
避難した人の列は小屋に収まったが、夜は眠りが浅い。子はすぐ目を覚まし、母は背をさする。老人は天井を見ている。粥所は三つから二つになったが、列は短くならない。
塩は薄いまま。鍋の底に焦げはない。医の小屋には古い布が重ねられ、刃は錆びないよう油が塗られる。疫に備えて便所の溝が深く切られ、灰が降り注ぐ。
死者の名は板に書かれない。行方不明とだけ書かれる。数字は出ない。出せない。誰も強く問わない。問えば、板が重くなる。
村は半分が場所を失った。丘に立つ家だけが残り、低い家は壁の痕を残して崩れた。牛は数が減り、馬は痩せた。畑に埋まった石を掘り出す音が町に広がる。
子は石を運び、大人は石を積む。積んだ先に何が戻るのか、誰も口にしない。戻るかどうかを問う声はない。粥を食べ、石を運び、夜に横になる。それだけだ。
田陵は「租税の減免・徭役の延期」の札を出した。札は濡れずに掲げられ、人々はそれを見る。誰も歓声を上げない。札はただそこにある。白起は棚の「長雨」の束に今年の札を挟み、朱は打たない。
語は揃っている。「越波」「決壊」「割堤」「分洪」「賑給」「井戸封じ」。揃っていることが、今は何の慰めにもならない。
夜、白起は天に戻った。初更、室・壁が現れ、二更、奎・婁・胃が続き、三更、昴・畢が上がる。星は見える。見えるが、台の上の空気は乾かない。
筆は動く。語は短い。「星、鋭」「北紐、正」。板は軽い。軽さは、足の重さに釣り合わない。白起は初めて、帳の末尾に一行だけ加えた。
「良くはない。足りない。」
翌朝、堤の上で子どもが小石を拾って投げた。水はもう轟かない。濁りがゆっくり流れるだけだ。子どもの手は細い。白起はそれを見て何も言わず、杭の頭を撫で、角の固さを確かめた。町は静かだ。静かさは安堵ではない。空は高い。誰も見上げない。
雨の線が消えてから、臨洮は音を失った。濁った水だけが旧河道を太く走り、堤の杭がぬめった光を返す。城門の外は、畑も道も同じ褐色の面になっていた。
橋の板は失われ、杭だけが水面から覗いていた。渡るには縄を二本張り、足を絡めて手で進む。子どもは抱かれ、老人は両側から支えられる。渡る前に名を問う者がいて、書吏が濡れた板に細い字で写す。名を失った者は「印」と記された。未詳、と書かれる札も少なくない。
旅の掲は新しく作り直された。古い板は流れ、札は消えた。新しい板に、必要な語だけが並ぶ。「北の橋、無し」「南の浅瀬、不可」「堤、巡」「井戸封じ」「粥四」「疫、禁」。
長い言い回しはない。人はそれだけを見て足の向きを決める。慰めや訓戒の文は掲げられない。掲げても役に立たない。
死傷の札は詰所の脇に別の板で掛けられた。「死」「不見」「負傷」。名のある札、名の書けない札、地名だけの札。札は濡れ、乾き、また濡れた。札に触れる指は灰色で、紐を締める手が慎重だ。
死は多くないとは言えない。数えるのは板であり、口ではない。組ごとに丘の北側に浅い穴が掘られ、土をかぶせ、目印の杭が一本立つ。
香は焚かない。濡れた火が消えやすいからだ。名のわかる者には薄い木札が打たれ、未詳には「未」とだけ刻まれる。誰も泣き叫ばない。声は粥所と堤の上に集められている。
堤は昼も夜も巡が続く。増高の仕上げが遅れ、法面に筵を貼る手が足りない。柳枝を差して泥を締める仕事だけは先に進められた。
西の浚いは淀みを掬い、剪断した口を少し広げ、流れが曲がらぬよう籠石を据え直した。橋は杭から打ち直し、小舟が一本、綱で上げられたまま仮の渡しに使われる。
舟を漕ぐ者は日ごとに変わり、肩が落ちても座り込まない。座り込む場所がない。
市場は開かれない。値札は消え、秤は塵をかぶる。名人の手癖で作られた品が箱の中で黙っている。代わりに役所の板の前に人が立ち、今日の配りの短い文を読む。
堤、午の巡入替。粥、四。井戸、封。橋、杭。疫、便所の溝切り。読めない者には子が読み上げる。読み上げる声は低い。笑いの癖が抜けない子も、今は笑わない。
家々では、片付けの順番が板と同じように短く決まる。湿った衣を外に出し、折れた箪笥をばらし、燃えるものと燃えないものを分ける。
使える木は干し場の横木に加え、使えない木は火の下へ。火は小さく、長く。濡れた泥床を板で掻き、扉の前に溝を切る。夜に眠る場所を決めるための仕事が先だ。祭具は布で包まれ、土間の隅に寄せられる。祈る言葉は外に出ない。出さないのではなく、出している暇がない。
郊外の村には、まだ戻らぬ者がいる。堤の上の札に「北二里・未帰」と細く記され、翌日も消えない。見張柱は「七刻の下」を保ったまま、墨が薄くなっていく。
水は引かないが、上がりもせず、音だけが日に日に軽くなる。軽くなっても、泥は固まらない。足を抜くたびに力が要る。力のある者は堤へ、力のない者は粥所へ。順番はそれだけだ。
疫の札は目に入る場所に増やされた。便所の溝を深くし、灰を撒き、濡れた衣を煮る。医の小屋では刃が火の側で温められ、小瓶の薬が一本ずつ減る。
咳き込む子が増え、老人の足が滞る。死者が出ると、穴は丘の北へ延びる。穴は深くないが、目印の杭はまっすぐ立ち、数だけが増える。数を声にしない約束は、誰とも交わしていないのに守られる。
白起は堤と城内を歩き、板の端に短い句を足す。「堤、巡。灯、減らすな」「井戸、封」「粥、四」「死傷、札」「賑貸、札」。
文字は細く、余白に無理をしない。夜になれば台に上がる。星はまだ見えないことも多い。見えなければ「雲一様」と書き、「風、弱」「白み、早し」を注に置く。
天文の板の末尾に「堤の巡」と「粥の刻」がしばしば並ぶ。不自然ではない。夜に決めた刻が、翌日の足を動かす。理はこの土地では地に降りたまま働く。
臨洮の人々は空を見上げない。空に向ける時間は地に使われる。掻き、運び、括り、煮て、締める。声は太鼓と板に集められ、他所へ散らない。安堵は過ぎた。惜しむ暇はない。これからの長さが、目の前の短い動作に押し込まれる。
誰かが「冬」と小さく言い、同じ声が二度と続かない。冬に入る刻を測るのは白起の職だが、白起が測らずとも、この町は冬を自分の体で知るだろうと思えた。
夕刻、切堤の口の轟きが一段細くなった。籠石の上を流れる水の色が薄まり、堤の背の泥が少し締まる。灯が一本、二本と落とされる。
油は残さねばならない。太鼓の合図が夜の刻に切り替わり、巡が始まる。白起は板をまとめ、末尾に一行だけ置いた。「明日、堤・橋・井戸」。語は短い。短い語しか残らない。短い語だけが、まだ動く。
【10】復旧
臨洮は復旧の配りに入った。詰所の卓に「復旧」と太く書かれた板が立ち、白起は短句で項を埋める。
「堤は北・西・南の三路。踏み固めの仕上げ、増高・拡幅。護岸は柴束・竹籠石・柳枝。河道は浚いと剪断。橋は杭から。井戸は洗い直し。粥は三、賑貸、続行。疫は便所の溝、深く。」
田陵が読み上げ、伝令が板の写しを抱えて走る。白起はつづけて、人の編成を一息に書いた。
「持場:堤・材・舟・橋・井戸・炊・医・記。什伍で組み、肩縄を揃え、列は崩すな。」
堤の上では夜の巡が昼の踏みに変わった。泥は重いが、足取りの間が戻る。白起は北路の頭に立ち、角のそろいを指で示した。
「砂袋、角を落とすな。筵は薄く、ずらせ。籠石は斜に一つ、直に二つ。杭は頭一列。」
梁宛が「承知。」とだけ言い、杭を叩く。馬渓は角取り役を置き、砂袋の口が上を向くよう列を整える。
荀潁は板を抱え、刻ごとの作業名と人数を短く記す。「午前 北路・踏・二伍。午後 西路・拡・一伍」。公孫庭は古い「洪水後」の札の束を持ち、似た順序の年を指で示す。
「白起殿、剪断の口は、昨年の記ではもう少し下流に。」
「今年は上で曲がるはず。印を付け替えてくだされ。」
「は。」
午前は堤、午後は河道が主になる。川筋の掃きは匠が棒で底を探り、浅瀬に籠石を沈め、仮の側壁を板で立てる。
白起は「締めるな、絞れ。」とだけ言った。締めれば上で溢れ、絞れば下で流れる。夕方には口の肩が変わり、旧い筋が戻る。
橋は杭からやり直す。板はまだ遠い。杭を二本ずつ打ち替え、縄を二重に張り、仮渡しを一本、午後のうちに通す。渡る前に名を問う吏が立ち、濡れ板に細い字で写す。
名のない者には印を打つ。老人と子は先。牛馬は後だ。舟は南と西に一艘ずつ回し、皮舟を借りて補う。舟頭には「受け、逃がせ」の短句だけが落とされる。
井戸は封を解かず、洗い直しの準備に回す。まず周りの溝を深く切り、濁り水を遠ざける。次に桶で汲み、煮沸し、灰を落として沈める。蓋はそのまま。札に「井戸、洗、準」と書かれ、耆が縄をいじる手を止めた。
粥所は三つを保った。湯は薄いが、炊き手は増えた。司倉が穀袋の口を結び直し、「賑貸」の板は濡れない棚に移された。田陵は租の札を裏返したまま戻さず、「延」「減」が表に出たままにしてある。拍手はない。板だけが動く。動く板に、人がついていく。
疫の札は見やすい場所に移され、「濁水、煮」「便所、溝」「濡衣、煮」と三語で足りる文が並ぶ。医の小屋は火を絶やさず、包帯を干し、刃を温めた。老人の咳は増えたが、粥の列は崩れない。
白起は天文の段取りも取り戻した。夜は台に上がり、風の筋と白みの刻を拾う。星が透る夜は少しずつ増え、昴と畢の形が戻る。
帳の末尾に「復旧の刻」を併記し、「午の踏」「申の剪」「戌の粥」と置いた。理は地に降りたまま働く。天文の句は、翌日の配りを整える目安にもなる。
数日で、堤の背が太り、法先が落ち着いた。北路は踏みの仕上げに入り、西路は拡幅に移る。南路は柵を抜いて護岸に交代する。
白起は板に「堤 本仕」「護 据」「河 浚・剪」を並べ、刻の配置をずらした。梁宛の杭の音は一定で、馬渓の声は官の調子を取り戻した。
「白起様、角取り二人、交代を入れました。砂袋の口、上に揃えました。」
「よい。頭を直線に保て。筵を節約しろ。」
荀潁は「復旧の詳記」を作り、項の順を固定した。
「堤・路」「河」「橋」「井戸」「粥・医」「旅掲」。
各項の末尾に氏名と人数、刻が小さく入る。公孫庭は古い束を繕い、今年の札を括った。韓慎は遠くから見て、板の余白の使い方にだけ一言落とす。
「余白がまだある。」
「あります。急ぐほど、余白は要ります。」
十日も経つと、橋の一本が仮に渡れるようになった。板は薄く、杭はまだ濡れている。渡る者は足元を見て、何も言わない。
旅の掲には「北の橋、仮」と札が出た。「井戸、洗、入」の札も一つ。湯の列の脇に「濫飲、禁」の札が立ち、灰の匂いが強くなる。
塩の竈は遅い。土台を組み直すのに時間がかかる。白起は「塩、火、遅」の札を板の脇に足し、軍馬の囲いに水の割り当ての刻をずらした。
桶を洗う番を増やし、朝と夕を厚くする。馬は痩せるが、立つ。立てば働ける。働けば橋が進み、堤が持つ。
日が進み、風が冷え、空が高くなった。早朝に薄い霜が出る日もあり、乾場の穀の重みが減る。灰を払う音が軽い。粥の鍋の湯気が白く立ち、子どもの頬が色を取り戻す。
笑い声は出ないが、泣き声は減る。白起は「粥、三、保」「干、一段下げ」と板に置き、夜の帳には「四更 白み、早」と小さく注を足した。
郊外の村の片付けは、丘の側から始めた。土壁の落ちた下を板で支え、戸を仮に直し、土間を掻き、溝を切る。祭器は布で包んで上に上げる。そこまでやって初めて屋根に触る。順を乱すと崩れる。白起は村の頭に向けて短く言う。
「足をまず乾かせ。家は次だ。」
男はうなずき、その通りに動いた。女は濡れた衣を煮て、布を絞り、寝る場所を作った。老人は座り木を整え、子どもは細い柴を集めて束にした。ことばは少ない。板と太鼓の合図だけで暮らしが前へ動く。
日ごとに、白起は朝と夕の二度、堤と橋と井戸を回り、田陵と一言ずつの確認をした。
「堤、本仕、北・西、明日。南、明後日」
「橋、杭、二歩。板、三日で一筋」
「井戸、洗、一。明朝、二」
「粥、三、保。賑貸、札、二増」
韓慎はその会話をただ記憶するように聞き、何も挟まない。挟まれる言葉は今は要らない。
晩秋に入ると、復旧の項目のうち「急」の札が減り、「常」の札が増えた。「堤、巡」が「堤、巡(薄)」になり、「井戸、封」が「井戸、開(制)」に変わる。
橋は一本が本架に近づき、仮の縄がほどかれる。河道の剪断は口が安定し、籠石の上に薄い草が引っかかる。天文の帳には、冬の徴がはっきりと出た。
四更半、参・觜、明瞭。荀潁の筆は迷いなく「冬の徴」と置き、末尾に「復旧、常に移る」と小さく添えた。
復旧の手の中で散らばりかけたものを、白起はひとつに戻した。旅の掲は古い形式を取り戻し、在野の札も混じる。「北の橋、狭」「南の浅瀬、緩」「堤、巡(薄)」「井戸、開(制)」。
無駄な言葉はない。商の秤に埃が薄く積もり、鍛冶のふいごが乾き、塩の竈に小さな火が戻る。皮の横木に一枚、薄い皮が吊るされる。薄いが、ある。
田陵はひとつ、板を掲げ替えた。「徭、延」から「徭、段」に。完全ではないが、区切りができたという印だ。白起は何も言わない。
板が動いた、それで足りる。賑貸の棚は高いところに置かれたまま、札が少し減る。返すという語は口にされないが、手が受け取る量がわずかに少なくなった。
ある朝、白起は天文台の脇で梁宛に言った。
「今夜から、台の語を元に戻す。復旧の刻は注に下げる。空が動く。」
「承知しました。北紐、張り直しました。落ちは定です。」
「よい。」
夜、台に上がると、風は弱く、昴はまとまり、畢に赤が少し乗っている。参が横に並び、觜が薄く乗る。白起は語を整え、荀潁がそれを板に写す。
公孫庭は古い束に指を入れ、「今年は一歩早い」と短く言う。馬渓は油を足し、覆いの角度を一段低くする。韓慎は外の影に立ち、何も言わない。
復旧の配りは、それからも続いた。橋は二筋目にかかり、井戸は三つが「開(制)」に移る。堤の巡は薄いが切れない。粥所は二に減ったが、夕刻に一つだけ湯を継ぐ日がある。
疫の札は減らないが、位置が一段下へ下がった。死傷の板は動かず、札の紐が締め直される。穴の杭は増えたが、まっすぐ立ち続ける。
晩秋の風が鋭くなり、朝の土が固い。踏めば音が違う。白起は堤の上で、足裏にその固さを受けた。季節の刻は戻った。戻っていないのは人の数と穀の量だ。そこは板が担う。板は残る。残った板が、来年の足になる。
田陵は白起に向かい、短く頭を下げた。
「白起殿。臨洮は、冬に入れます。」
「なんとかここまできました。」
「賑貸は年内、続けます。」
「はい。井戸の水にお気をつけください。橋は凍る前に二筋目の杭を。」
「承知した。貴殿のおかげで難を逃れた。」
白起は詰所の卓に、最後の「復旧・晩秋」の板を置いた。語は少ない。
「堤、巡(薄)。橋、杭。井戸、開(制)。粥、二。疫、注。旅掲、常。夜、天文、本へ」
荀潁が清書し、公孫庭が印を押す。梁宛は脚印を持ち、圭表の足を確かめに走る。馬渓は漏刻の管を布で包み、砂の回りを指でなぞる。韓慎は柱から離れ、板に目を落とし、ほんのわずか頷いた。
暮れに近い一日、白起は堤の上で、切堤の口を見た。丸く抑えられ、籠石は沈んでいる。柳枝が芽を持たず、ただ土を押さえている。
旧河道は細くなり、音は軽い。冬が来る。臨洮は冬を受ける。白起は帯を締め直し、田陵に一言だけ残した。
「災害は去りました。しかし、厳しい冬になります。」
田陵は厳しい顔で頷き、板を掲げ直した。白起は台へ向かった。夜は短く、冷える。星は透る。帳は本に戻った。復旧は続く。語は短い。短い語だけが、次の者に渡る。
【11】帰還命令
復旧の配りが日課になったころ、臨洮はようやく「急」の札を外し始めた。堤の巡は薄く、橋は一本が本架に近づき、井戸は「開(制)」の札が三つに増えた。旅の掲は常の語に戻り、在野の札も混じる。
「北の橋、狭」「堤、巡(薄)」「井戸、開(制)」。人の足取りはまだ重いが、列は乱れない。夕刻、粥所の湯気がまっすぐ上がり、炊煙が細く伸びる日が増えた。
そうした日の一つ、堤の上で人の列が自然に割れ、白起の前に出た老人が両手で深く頭を下げた。顔は日に焼け、腕に縄の痕が残る。
「白起様。うちの村は半分が流れましたが、丘に人は残りました。堤が保ったからです。」
「堤は皆で守ったのだ。」
「それでも、あの配りがなければ、わしらは走るばかりでした。」
老人の言葉に、周囲の者は何も足さない。頭を一つ下げ、次の砂袋を肩に移した。白起は「うむ。」とだけ答え、杭の頭を一つ撫でた。
県府では、田陵が朝夕の配りの合間に呼び込みを重ね、復旧の功をどう書くかを考えていた。帳に短く項を立て、名前の順を整える。
天文部の働きを「刻で動かす」と書き、堤の現場には「畳み掛け・割堤・分洪、刻守」と置く。賑給は司倉の責、舟は渡し守の責、指示は県令と天文官の連名、と整理した。
「白起殿、郡へ上げる文に、あなたの名をはっきり掲げたい。」
「いえ、名は田陵殿のみにしていただきたい。」
「承知。……だが、臨洮はあなたに礼をしたい。」
「臨洮の民が活気を取り戻す。それだけが私の望みです。」
「そこまで言われるのなら。」
田陵は笑わず、筆を進めた。公孫庭が古い束を示し、「十七年前の長雨の年、県令と正天文官に小さな褒があった」と短く添える。荀潁は帳の語を揃え、「形を足すな」と自分に言い聞かせる調子で清書した。
馬渓は油を運ぶ手を止めず、「白起様のおかげで、太鼓が乱れなかった。」と、役人らしい言葉でひとことだけ言った。梁宛は杭を叩きながら、頷く代わりにもう一度打った。
市場の端で、旅の掲の前に細い札が一つ増えた。「白起様に礼の札を」。誰の手かは知られない。札の横に粟の袋がひとつ置かれ、すぐに耆がそれを粥所へ運んだ。誰も笑わず、誰も止めない。札は夕刻には外され、翌朝には無かった。
数日を置いて、郡から使いが来た。郡守の回覧とともに、
「臨洮復旧の功、上申の件、承知。」という短い返文が添えられていた。
田陵は安堵した。白起は表情を変えない。韓慎は使いの顔を見、竹簡の縁を撫でるように見て、それから柱の陰に戻った。
その夜、県府の奥で小さな席が設けられた。酒は薄く、言葉も少ない。田陵が盃を置き、白起に向いた。
「白起殿。臨洮はこの冬を越せます。橋は凍る前にもう一本。井戸は三つ、開けられます。あなたに官の礼を。」
「礼は必要ありません。」
その席の終わりに、韓慎が唐突に口を開いた。声は低い。
「短い語は、読む側に余白を与える。余白があると、読み手は何かを入れる。」
田陵が視線を向ける。「監察官殿、その“何か”は何を指しておられる。」
「事実だ。たとえば、白起殿の帳に“堤の夜巡・太鼓の刻・賑給・井戸封じ”が併記されている。天文の帳に軍門と倉の語が入っている。——それは便利だが、法の上では別の帳に落とすべき事柄だ。つまりは越権行為だな。」
白起は盃を置いた。
「刻で動かすために、末尾に並べました。」
「理由はわかる。だが、咸陽で理由を問うのは別の筋だ。」
席はそこで終わった。誰も声を荒らげない。田陵は盃を伏せ、「文は文、現場は現場。」と短く言った。韓慎は頷かず、否とも言わず、そのまま出て行った。
翌日、監察の帳場が県府の一室に設けられた。韓慎は書吏を二人連れ、台帳と札束の写しを求めた。
天文の帳、堤の板、賑給の帳、井戸の封印札。書吏は淡々と出し、梁宛と荀潁が必要な説明だけを添える。白起は呼ばれたときだけ短く答え、余計な言を増やさない。
「この『割堤・分洪』は、誰の決にて。」
「私と田陵殿。」
「郡守の許可の印は。」
「刻が先でした。印は後に添えました。」
「官倉の穀の賑給、帳面に『白起指示』とある。」
「粥所の刻を定めるためです。実務の責は司倉に一任しました。」
「井戸の封印と洗い直し、開閉の刻は。」
「封印は私の指示。開閉は田陵殿の印です。」
「旅の掲の札に『井戸封じ』『粥四』とある。官印は無い。」
「刻を知らせるために短く置きました。」
韓慎はすべてに頷かず、否も言わず、筆で「記」とだけ書いた。書吏が細い字で併注する。「便宜、刻のため」「緊急、印後付」「掲示、太鼓と併用」。意味がどう取られるかは、遠い場所が決める。
数日を置かず、監察の帳場の前に、県の者や郊外の頭がひっそりと集まるようになった。誰も声を上げない。行列の先に出た男が、韓慎に向かってうやうやしく言った。
「監察官殿。白起様は夜に太鼓を乱さず、堤で死者を減らされました。」
「承知している。帳にも書かれている。」
「白起様は、子どもを先に粥所に通されました。」
「承知している。賑給の帳にある。」
「白起様は——」
「列を崩すな。仕事に戻れ。」
韓慎は声を荒げない。列は自然に薄れ、男は頭を下げて去った。田陵はその光景を遠くから見て、歯を食いしばった。近づいて声をかける。
「監察官殿。民は今、声でしか礼ができませぬ。」
「礼は不要だ。事実の記録があればよい。」
「帳が何を言うかは、遠いところが決める。つまりは咸陽。」
「それは…。」
臨洮の内部でも、文言の調整が細かくなった。田陵は上申の文から「白起殿の独断」という語を消し、「臨時の決」に改めた。
「割堤」を「非常の分洪」にし、「賑給」を「賑貸」に置き換える。白起は文の端を見ただけで頷き、「短く」とだけ言った。荀潁は清書し、公孫庭は束に紐を通し、郡への使いが馬を出した。
その夜、韓慎が白起の宿舎に現れた。戸口で足を止め、部屋に入らない。
「白起殿。明日、もう一度帳を見せてほしい。」
「かしこまりました。」
「あなたの語は短い。余白が多いですからな。」
「短いほうが組織は早く動きます。」
「その権利があればの話だがな。」
白起は何も答えない。韓慎はそのまま踵を返した。
翌日から、監察の質問は鋭くなった。堤の夜灯の数と間隔、太鼓の合図の種別と回数、割堤の時刻の書きぶり、掲示の札の有無、民の動員の刻の決め方。すべて「越権か否か」の境に置かれる。田陵は一つ一つに、落ち着いた声で答えた。
「太鼓は二打が巡、三打が総出と定め、県内に通達しました。印は翌朝に押しました。」
「夜灯は三十歩。危険箇所は十歩。板に記し、翌日に承認を得ています。」
「割堤は“合図の後に開”とし、旧河道と遊水地に逃がしました。刻は板に残っています。」
「民の動員は什伍で組み、肩縄を揃え、徭の枠内で扱っています。」
韓慎はうなずかない。筆を運び、併注を増やす。「承認遅れ」「掲示印無し」「便宜」「臨時」。白起は呼ばれたときだけ短く添える。
「刻で動かしました。書は後に記しました。」
「その順が、法に合うかどうかを問われる。」
「お望みのままにどうぞ。」
臨洮の空気は、堤の泥が乾くのに似て重くなった。民は白起に声をかけたいが、役所の前では口を閉じる。市場の端で、旅の掲の前に立ち止まり、札だけを見る。
札は短い。「堤、巡(薄)」「橋、板一列」「井戸、開(制)」。そこに「白起」の字は無い。無くてよい。無いほうが動く。
田陵は書机の前で、上申の文をもう一度だけ読み、印を押した。机の脇に小さな箱がある。褒の札と、米一石の札。誰に渡すかは明らかだ。
だが箱は閉じられたまま、机の端に置かれた。韓慎はその箱を見、何も言わない。言わなくても、箱の意味は誰にもわかる。
夕刻、白起は堤から戻り、宿舎の水で手の泥を落とした。指の節に砂の細かい感触が残る。戸口で耆が言った。
「白起様。市場の者が、粥の米を一袋、粥所に置いていかれました。」
「受け取れ。札は立てるな。」
「承知いたしました。」
夜、台に上がると、昴がわずかに濃く、参・觜が冬の形になりかけている。風は弱く、灯は揺れない。荀潁が筆を整え、「四更半、参・觜、明瞭。冬の徴」と置いた。白起は末尾に小さく「復旧、常」と添えた。韓慎は外でそれを見て、暗い中で小さく息を吐いた。
数日が過ぎ、監察の帳場に新しい束が届いた。咸陽からの問い合わせの写しだという噂が、声にならずに廊下を走る。田陵はそれを見て口を結び、白起は目を落とすだけだった。韓慎はその束を静かに机に置き、筆をとった。
「“越権の疑いあり”——言葉は軽くない。」
彼はそう言ってから黙り、灯の芯を短く切った。灯は小さくなったが、消えなかった。臨洮の夜は静かだった。静かな分だけ、重かった。
命は朝のうちに届いた。郡の使いではない。咸陽の封が押され、紐は固く、竹簡は厚い。県府の広間に人が集められ、田陵が封を改めたのち、韓慎が一歩前に出て文を開く。声は平らだった。
「上邽天文官・白起、臨時任務は既に完了と見做す。即刻、上邽へ帰還せよ。——臨洮在任中の便宜措置のうち、越権の疑いあるもの多し。今後、任地においては各司に従い、帳と印を正すべし。褒は与えない。俸も減のまま。以上」
広間の空気が少しだけ沈んだ。誰も声を出さない。板の上に置かれた文の墨が、湿りで重く見えた。田陵は唇を固く結び、すぐに「承知。」とだけ答えて頭を下げた。
白起は一歩前へ進み、膝をつく。額は地に届かない。手だけが床に触れる。韓慎は文を巻き、封を閉じ直し、姿勢を崩さない。
広間を出たとき、廊下にいた書吏たちは目を伏せた。誰かが軽く咳をした。誰も言葉を足さない。庭の端にいた耆は、持っていた桶を置き、白起に向かって深く頭を下げた。白起は短く会釈しただけで通り過ぎた。
田陵は詰所に白起を呼び、扉を閉めた。机の上には「復旧・晩秋」の板が残っている。
「白起殿。……道理が立たない。臨洮はあなたで保った。褒が無く、減給、そして訓告だと。」
「文は文です。官吏であるのなら咸陽は絶対です。」
「上申は続けます。褒の札は用意している。」
「私への褒賞は粥所へ回してください。あなたは臨洮を守らなければならない。」
田陵は目を細め、短く頷いた。「承知。」それから声を下げる。
「民が集まるでしょう。心を持っている。だが、表に出せない。法が先にある。」
「列を乱させないでください。堤の巡もあります。余計な騒ぎは咸陽の疑いを増してしまう。」
「わかっています。」
その日の午後、旅の掲の前に人が立ち止まった。札は増えない。「堤、巡(薄)」「橋、杭」「井戸、開(制)」。端に小さな紙が貼られた。誰かが書いた細い字。
「白起様、帰還の刻」。耆が無言でそれを外し、紙は粥所の焚き火の脇に置かれた。誰も咎めない。火は小さく、その紙は燃えないまま湿って沈んだ。
夜、台では語を変えなかった。風は弱く、昴がまとまり、参・觜が冬の形をはっきりと示す。荀潁が筆を整え、「四更半、参・觜、明瞭。冬の徴」と置く。
白起は末尾に「堤、巡(薄)・橋、杭」と注を添えた。韓慎は外の影からそれを見て、何も言わずに背を向けた。
翌朝、引継ぎの板が起こされた。白起は天文小屋に四人を集め、机の上に器の札と棚の札を並べる。
「紐はここで張り替える。落ちは細い糸に。油は夜半で一壺。——荀潁、詳記の順は固定する。『初更・二更・三更・四更・五更』、末尾に『堤・橋・井戸・粥』の刻を小さく併記。」
「承知しました、白起様。」
「梁宛。杭の頭は直線。角は崩すな。籠石は斜に一つ、直に二つ。夜灯は三十歩、危所は十。」
「承知。」
「馬渓。材の前置きは西から。砂袋の口は上を向ける。角取り役を一人置け。油は節約するが、灯は落とすな。」
「心得ました、白起様。皆に申し伝えます。」
「公孫庭殿。棚の『長雨』『洪水後』の束は上段へ。今季の札は朱を打って括る。冬の徴は一番上に。」
「承知致した。台の語は本へ戻し、注は現地の者に任せます。」
四人はそれぞれ頷き、短く返事をした。誰も長い言葉を選ばない。言えば崩れる。崩せば残らない。白起は机の端に置いた木の尺を一度撫で、戸口まで歩いて振り返る。
「刻で動く。」
それだけを残して出た。
県府では、田陵が各司を回り、白起の返還すべき品と渡すべき札を整えた。圭表の脚印、落ちの管、観測の板の写し、堤と橋の図。白起は私物の包みを小さくまとめ、衣を二枚重ね、帯に細い紐を一本足した。宿舎の耆が戸口で言う。
「白起様、あなたの功績は皆が知っております。」
「耆よ、それだけで十分だ。」
昼過ぎ、県の役人たちが詰所の前に並んだ。言葉はない。田陵だけが一歩出て、白起に向き直る。
「白起殿。臨洮は礼を言います。」
「この先も配りを崩さないでください。」
「肝に銘じます。」
田陵はそこで少しだけ声を落とした。
「復旧の際には礼の品を届けます。」
その場の端に韓慎が立っていた。肩に雨の痕が残る衣をそのままに、白起と目を合わせる。しかし、両者に言葉はなかった。
その夕刻、城の外に人の列ができた。堤の巡の道ではない。門の脇の細い道だ。誰も声を上げない。子が母の衣の端を握り、老人が杖を突く。列の先頭で若い農夫が、白起に低く言った。
「白起様。うちの村は北の二里。切った口の下です。粥はまだ薄いですが、子は立っています。」
「立てば冬を越せる。」
「越します、必ず。」
農夫は深く頭を下げ、列はそのまま散った。名も礼も言わない。言えば捕まるわけではないが、言葉は秩序を乱す。秩序を乱せば、明日の刻が乱れる。皆がそれを知っている。
夜、最後の観測に上がった。風は冷え、星は透る。昴の粒は固く、畢の列はきれいに並ぶ。参は横に張り、觜が薄く乗る。
荀潁が筆で「四更半、参・觜、明瞭。冬の徴」と置き、末尾に小さく「白起様、帰還」とだけ書いた。白起はその字を見て首を振った。
「その行は消せ。」
「……承知しました。」
荀潁は静かにその行を拭い、墨痕が薄く残った。公孫庭が巻物をまとめ、梁宛が油を仕舞い、馬渓が覆いを畳む。
「星は遠い。遠いものほど、手の届かないところで動く。」
「地は近い。近いものほど、手で持つ。」
「そうだ。」
それ以上は話さなかった。
翌朝、門の前に馬が一頭だけ用意された。荷は少ない。書吏が道の札を手渡し、耆が水の袋を渡す。田陵は最後に一歩近づき、目を見て言う。
「刻で動き続けます。」
「動かしてください。」
白起は鞍に上がり、手綱を一度だけ引いた。門の外で列が自然に割れ、誰も声を出さない。太鼓は鳴らない。鳴らすべきときではないからだ。白起は頷き、馬を歩ませた。風は冷たく、空は高い。——帰還の刻だった。
【12】帰還道中
臨洮を出た朝は、風が乾いていた。堤の上の杭の頭に霜が白く残り、切堤の口は細い筋にまで痩せていた。白起はひとつ頷き、馬の腹を軽く蹴った。荷は少ない。観測の板の写しと、筆と、衣が二枚。水の袋は耆が新しく縛ってくれた。田陵は何も言わず、遠くで手を挙げただけだった。
道は南へ折れ、丘陵の肩を伝い、やがて渭水の支流へ降りる。秋が尽きかけ、冬が匂いを見せる時季だ。畑は刈り株だけが残り、土の面は風に削られて薄く波打っている。
乾いた草に薄い霜がつき、午前の陽に遅れて光る。川面には薄氷が寄り、日が高くなると静かに割れる。鳥は少ない。遠くで烏の群れが一度だけ低く輪を描き、すぐに散った。
白起はほとんど口を開かない。馬の歩みに合わせ、頭の中で距離を割り、丘の肩の角度で方角を修正する。地図は要らない。風が北から下りる形と、谷の口の広さで、おおよその刻が出る。
時折、背後で冬の風が長く鳴り、乾いた枝が擦れる。土の匂いは薄く、皮の帯の擦れる音だけが一定に続く。
昼までは、村の影を見ない。畑の端に折れた杭が三本立ち、縄の切れ端が風に揺れる。あの向こうに家々があったはずだと、白起は思うだけに止めた。
馬を止めない。止めると、体から熱が抜ける。衣の下で汗が冷えると、夜の疲れが残る。歩いていれば、考えは沈み過ぎない。
正午を過ぎる頃、崖の縁に小さな祠の残骸が現れた。土の台が半分崩れ、板は流され、柱だけが一本残る。
柱の根元に、誰かが乾いた草を束ねて置いたらしい。白起は馬から降りず、通り過ぎた。祠に言うべき言葉は持たない。言えば崩れる。崩せば、次の刻が濁る。
午後の風は冷たい。雲が低く流れ、陽が斜めに差す。影が長い。道の端に凍りかけた水たまりがあり、馬が蹄で割る。薄い音がする。
白起は、臨洮の堤の頭に指を置いたときの感触を思い出す。砂袋の口が上を向き、筵の糸が濡れて固かった。太鼓の間が一定で、人の足が揃っていた。あの夜、書は短く、板は動いた。——それでも、文は動かない。文は遠くで、濡れないところで止まる。
咸陽の封の文字は重かった。越権の疑い。褒無し。帳を正せ。白起は句を反芻し、余計な語を剝がすように一つずつ内で捨てた。「疑い」は誰の手にも置ける。「褒無し」は誰の口にも置ける。
置かれたものに、足は使いようがない。使えるのは、刻だけだ。刻は地に落ちる。夜に聞いた太鼓の間、四更の雷の回数、見張柱の刻線。あれは遠くの文では汚れない。
日が傾き、風がさらに冷える。白起は小さな駄賃宿の跡に寄り、軒のない壁の影で少しだけ馬に水を与えた。井戸は封じ札が残され、蓋は外され、底は濁っている。水は使わない。
腰の袋の水で足りるだけにして、手を濡らさずに口へ運んだ。指先が悴む。帯を締め直すと、皮が固く鳴る。宿の裏手に回ると、干し場の横木が二本、斜めに残っていた。ここでも、薄い冬が焼け残りのように漂っている。
その夜は、谷の口の上にある古宿に滞在した。空は乾き、雲は薄い。風は止んだり、細く鳴いたりする。火は小さく、煙はまっすぐ上がった。息を吐くと、白い。夜の音は少ない。遠くで小さな水の音がし、さらに遠くに狼の声のようなものが一度だけ響いて、すぐに途切れた。
初更が過ぎ、二更に入る頃、東の稜線の上に白い輪が昇った。月だ。薄く欠け、冷たい。白起は身を起こし、しばらく黙って見た。月の光は地を選ばない。
刈り株も、崩れた祠も、折れた杭も、同じ色で洗う。臨洮の堤も、監察の帳場も、咸陽の文も、この光で等しく白くなる。白起は、それを見ながら口をひらいた。誰に聞かせるでもない、細い声だった。
「月。——あなたは遠い。遠いものほど、よく見えるが、触れられない。」
韓慎の言葉が自然に戻ってきた。白起は目を細め、火の棒を持ち直した。
「地は近い。近いものほど、手で持つ。」
それだけ言い、言葉を止めた。言葉を増やすと、火が小さくなる。夜は長い。火は短い。火を守るのに、語は要らない。白起は火の上に手をかざし、指の感覚を確かめた。筆を持つ感覚はまだ戻る。戻るなら、上邽で書ける。
うとうとと短い眠りが続き、三更が過ぎ、四更に入る。風が一度だけ強く吹き、枯れ草が擦れた。月は高く、冷たい。空は透き、星の粒が少しだけ見える。昴が薄くまとまり、参が横に伸びる。
臨洮の台にいた夜の手順が、体のどこかでそのまま動いた。板はない。だが、語は内で整う。「四更半、参、薄。白み、遅」。字を書く代わりに息で唱え、すぐに消す。
冬の手前は、音が途切れやすい。臨洮の夜もそうだった。越波が収まり、切堤の口が持つと、音は一段軽くなる。軽い音に油断が混じりやすい。混じれば崩れる。崩れないように、太鼓は間を変えなかった。
板は語を増やさなかった。——白起は火の前で目を閉じ、その原則をもう一度だけ内でなぞった。文は遠くで止まり、監察は遠くで詮議し、范雎の目はどこにでも置かれる。置かれても、刻は地にある。地にあるものだけが、明日の足になる。動かせるのは、そこだけだ。
夜が割れ、東が白くなる。息がさらに白く、土は堅く、霜が踏むたびに細く鳴る。白起は馬に水を与え、帯を締め直す。
二日目の道は、前日より人影があった。川の浅瀬の上に仮の縄が渡され、二人が向こう岸へ荷を移している。白起は距離を保ち、馬を少し止め、縄の張り具合と足元の流れを見ただけで通り過ぎた。声はかけない。声をかけると、目が集まる。目が集まると、噂になる。噂は板を濁らせる。
午後、低い日が丘の肩を赤くして、影がさらに長くなった。草の穂に薄い氷が残り、日向でだけ融ける。水たまりの縁の氷は夕方まで消えず、馬の吐く息が白く筋になる。
白起は衣の襟を詰め、胸の前で掌を擦った。掌の皮は硬い。堤の杭の頭を数え、砂袋の角を整え、覆いの角度を直した夜の痕が残っている。あの痕は、文では消えない。誰が何と書いても、手に残る。
夕暮れ、丘の影の下に小さな集落の跡があり、土壁に焼け跡はないが、扉が外され、屋根の片側が落ちていた。窓の枠から風が出入りし、屋内の空気が冷えている。白起は馬を木に繋ぎ、壁の外の風の当たらない場所に身を寄せた。
火は起こさない。夜の月は昨夜よりも薄く欠け、冷たさは変わらない。手は袖の中で温め、足は膝の上で重ねる。二更、三更と数え、四更に遠い犬の声を聞き、やがて眠りに落ちる。夢は見ない。見ても記さない。
三日目の道中、上邽への道の石標を見る。欠けているが、刻は読めた。距離は、内の計算と大きく違わない。白起は小さく息を吐いた。空気は乾き、遠くがよく見えた。
丘の肩を一つ越え、斜面を上がり、尾根に出る。風が正面から当たり、目が痛む。白起は手の甲で一度だけ目尻を拭い、足を揃えて尾根に立った。
正面、冬の空が平らに広がり、その下に淡い色の帯が長く横たわっている。帯の中に、黒い線が二つ三つ、揃って並んでいる。もっと先、霞の向こうに、低い城の輪郭と、数条の細い煙。陽は低い。煙はまっすぐ上がり、途中で折れない。——上邽だ。
白起は立ったまま、帯を確かめるように視た。距離はまだある。だが、道はここから単純になる。標木は多く、畑の区ははっきりし、渡るべき川は浅い。
太鼓の合図は聞こえないが、動きの癖が視える。戻る場所の癖だ。白起は帯の結び目を確かめるように帯を握り直し、馬の首筋を軽く叩いた。馬は鼻を鳴らし、足を前に出す。
風は冷たい。空は高い。土は硬い。——それでよい。硬い土の上でこそ、細い文字はまっすぐ引ける。白起は尾根を下りながら、内の帳に一行を足した。
「帰府の刻、近し。」
言葉は短い。短いほど、足は揃う。冬は長い。だが、刻は分かれる。分かれれば、動ける。動けるうちは、負けではない。白起は息を静かに吐き、斜面を下った。前方、上邽の手前の畑が、冬の色で待っていた。
【第3章 完結】