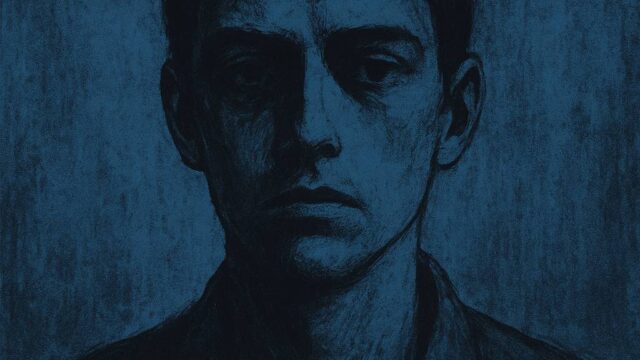序章 咸陽宮への召喚
【1】
咸陽の空は、春のはじめだというのにどこか冷たかった。王城の回廊を渡る風は、雪解けの匂いを含み、石畳の上で細く鳴っている。
白起はゆるやかにその音を聞きながら、宮門へと歩を進めた。甲冑を脱ぎ、粗衣をまとってからすでに十余日。軍の喧騒を離れても、耳の奥ではなお、戦鼓の低い響きが残っている。
衛士が槍を立てて道をあけた。白起の姿を見ると、どの兵も背筋を伸ばした。恐れではない。ただ、彼の名がこの国において「戦そのもの」を意味していた。
宮門の内は静まり返っていた。左右に並ぶ柱の影に、官人たちの視線がある。羨望と怯えが同居した眼差し。白起はそれを見ぬふりをして、石段を上がった。
謁見の間には、薄く香が焚かれていた。壇上の玉座には昭襄王が座し、その右手に宰相の范雎が控えている。王は老いを隠さず、白い鬚が胸に垂れていた。その眼はなお鋭く、まなざしだけで人を射抜く。
「白起、よく参った。」
王の声は低く、遠雷のようであった。
「恐れながら、陛下のご召により参上いたしました。」
白起は膝をつき、額を床にすりつけた。長年の戦で傷んだ膝がわずかに震える。
「顔を上げよ。」
王が言う。白起はゆっくりと顔を上げ、王の目を見た。かつて幾度もこの眼と戦略を語り合った。いま、その眼には疲れと、かすかな猜疑の色が混じっていた。
「白起。」
「はっ。」
「汝の功、天に届いておる。」
「恐悦至極に存じます。」
「ゆえにこそ、休め。」
一瞬、白起は耳を疑った。王は淡々と続ける。
「長平よりこのかた、汝の手により戦は勝ち続けた。だが戦が続けば、国は疲れる。人は血の味に慣れ、善を忘れる。余は、そなたに休息を命ずる。」
「……休息、にございますか。」
「そうだ。」
「戦が続くときにこそ、剣は錆びさせるなと、王様自ら仰せでした。」
「錆びぬ剣ほど危ういものはない。」
そのやり取りのあと、王は目を細めた。
「白起。余は汝を疑っておるわけではない。だが、天下は変わりつつある。
戦は終わらぬが、戦を動かす理は変わる。」
范雎が、王の隣でわずかに微笑を浮かべた。
「王様のお言葉は、深き思し召しにございます。将軍、功は山よりも高く、時に山を崩すこともございますゆえ。」
白起は、静かにその男の顔を見た。奸智、理を語ることを好む相貌。だがその理の底には、冷たく濁った欲の影があった。
「宰相様、山を崩すのは、功ではなく、風ではありませぬか。」
その言葉に、范雎の眉がわずかに動く。反論を想定していなかった驚きと白起への侮蔑が混じっている。王が片手を上げて、やり取りを止めた。
「よい。二人とも退け。」
王は天を仰ぐように小さく息を吐いた。
「白起、余は命ずる。戦を離れ、隴西にて天を見よ。」
白起は深く頭を垂れた。その声は低く、掠れていた。
「隴西……恐れながら、臣に何ゆえ天を仰げと。」
「地を見尽くした者は、天を見るほかあるまい。」
「はっ。」
その言葉を最後に、王は目を閉じた。范雎が進み出て、「下がれ」と冷ややかに告げる。
白起は立ち上がり、玉座に深く一礼した。この一礼で将軍白起は滅する。広間を出る背に、誰も声をかけない。ただ、石床に響く足音だけが、長い廊下に残った。
宮門を出ると、風が頬を撫でた。春の風でありながら、その冷たさは鉄のようだった。
白起はしばらく空を仰いだ。灰色の雲の向こうに、ひとすじの光が見えた。それは太陽ではなく、星のかけらのように小さな光だった。
「天を見よ、か……。地の将を退き、天の官を志す。血を墨に換え、遅れて届く光を量る…か。」
白起は小さく呟き、歩を進めた。その背を、遠くから范雎が見送っていた。范雎は扇を閉じ、唇にわずかな笑みを浮かべる。
「天を仰ぐ者は、やがて地を失う。それが、世の理というものだ。」
咸陽の鐘が、重く鳴った。その音は、勝者の耳にも敗者の耳にも、同じ重さで響いた。
【2】
白起が広間を辞したのち、謁見の間はしばし静まった。玉座の側で香が細く立ちのぼり、火は見えぬのに煙だけが在る。昭襄王は片手で扇をあおぎ、目を閉じた。范雎が一歩進み出て、低く辞した。
「王様、先ほどの御断は、天下のためにもよろしゅうございました。」
「范雎よ。」王は瞼を開けずに言う。
「白起は余の柱であった。柱を抜けば屋は軋む。おぬしは、その軋みをどう収める。」
「ははっ。柱をそのまま天に向けて立て替えまする。『観象』の柱として。」
王がわずかに目を開いた。范雎の声は冷たく澄み、理に油を差す者の調子があった。
「地の柱を、天の柱に、か。」
「左様にございます。将軍の名声は地を動かしすぎます。ゆえに地から離して、空へ上げるのが、もっとも穏やかにございましょう。」
范雎は扇を閉じ、玉座の段下から控える廷臣らへ視線を走らせた。郎中令が前に進み出る。
「宰相殿、白起将軍の旧軍の扱いは、いかが取り計らいましょう。」
「三に分けよ。」范雎は即答した。
「一は辺境守備へ、二は都の禁軍へ、三は解散して農籍に復せしめよ。集えば力、散らせば息である。」
「ははっ。」
廷尉が続いて伺う。「将軍の邸宅に出入りする者ども、取り調べの沙汰は。」
「吏を遣わすな。」范雎は首を横に振った。
「吏は騒ぐ。騒げば噂が立つ。噂は神を作る。神を作らせるな。静かに糧道を替え、筆を増やし、墨を与えよ。」
廷臣らが一斉に頭を垂れた。范雎はさらに言葉を継ぐ。
「白起は剣を置いた。置いた剣は、拾わせぬことだ。――天文台の修復を命ぜよ。器具を充ち、紙を満たせ。書けば書くほど、人は剣から遠のく。」
剣を封じ、筆を増やす。
速さを収め、遅を働かす。
王が扇を止めた。「白起は余の友でもある。」
「存じ上げております。」范雎は深く頭を垂れた。
「ゆえにこそ、友をして国に害ならしめぬ道を取るのでございます。」
王はしばし沈黙した。香の糸は相変わらず細く、途切れぬ。やがて王は小さく頷いた。
「よい。任せる。」
「ははっ。」
范雎が退こうとすると、王が呼び止めた。
「范雎。」
「はっ。」
「おぬしの理は鋭い。鋭き刃は、いつか鞘を裂く。おのれの鞘を、大事にせい。」
范雎は微笑した。
「鞘を裂く刃は、折れる運命にございます。折れる前に、研ぎ直しましょう。」
王はそれ以上、何も言わなかった。
謁見の間を出ると、回廊に春の光が斜めに落ちていた。范雎は扇を手の中で回しながら、側に控える書記官に命じた。
「観象台修繕の件、工部に走れ。費用は戸部の余剰から引け。あわせて旧星図と曇損した器具の目録を調えよ。」
「ははっ。」
「また、学士の中より言葉巧みなる者を選び、白起の傍に置け。筆談の相手となり、記録の友となれ。争うな、諫めるな、ただ書かせよ。」
「心得ましてございます。」
范雎は回廊の端に立ち、都の屋根を見下ろした。瓦が光り、遠くまで続く。人の世は川のように流れ、そのうえに理と名が浮き沈みする。彼は小さく、誰にも聞こえぬ声で呟いた。
功は山のごとく重し、影は身を離れず。
影を薄くする法は、光を散らすのみ。
足音が近づき、若い侍史が恐る恐る口を開いた。
「宰相様。世間にては……白起将軍を、神と申す者もございます。」
「神など要らぬ。」范雎は扇を開き、風を作った。
「国に要るは秩序である。秩序は、静かに運ばれる。」
「左様でございますか。」
「静けさは、よい刀だ。」范雎は目を細めた。「音がせぬぶん、深く斬れる。」
侍史は言葉を失い、ただ頭を垂れた。
そこへ、戸部の役人が小走りに現れた。「宰相様、先般の戦後処置に関し、白起将軍の恩給につき……」
「削るな。」范雎の返答は早かった。「恩給は削らず、口を削れ。」
「口……にございますか。」
「うわさ話の口を、だ。」范雎は軽く笑った。
「金は人を黙らせ、理は人を騒がす。今は金を使え。理は、あとで使う。」
役人は慌てて頭を下げ、「ははっ」と去った。
范雎は再び廊に一人となった。遠く、城外の土色の山並みが霞む。そこに、かつて白起が築いた陣の形を、彼はふと重ねた。名将の功は国を高くする。しかし、高さは風を呼び、風は屋根を鳴らす。屋を守る者は、鳴りを嫌う。
天は無言、地は多言。
無言を借りよ。多言は、やがて剣となる。
ややあって、内侍が小声で近づいた。
「宰相殿。王はお疲れでございます。今日の政は、これまでに。」
「承知した。」范雎は扇をたたみ、歩き始めた。
「書記官に伝えよ。――白起の邸に、竹簡と墨を多く送れ。良い竹だ。乾きの早いもの。」
「はっ。」
「それから、天文台の灯用に油を。夜を明るくせよ。明るい夜は、人を眠らせる。」
回廊の端まで来たとき、范雎はふと立ち止まった。宮門の外の空が、薄く青んでいる。白起は、邸宅に着いた頃であろう。彼は扇の要を軽く弾き、独りごちた。
「天を見よ――王はそう言われた。よろしい。天を見てもらおう。地は、われらが見る。」
扇の骨がかすかに鳴り、音は春の風に紛れた。
【3】
咸陽の城下を離れてゆくほどに、土塀は低く、家並みは疎らとなった。白起の邸は、都の西に寄った丘の肩にある。かつては兵馬の出入りが絶えず、朝な夕なに埃が立ち上ったが、いま門前の道は静かである。門の両脇に据えられた石獅子は苔むし、冬の名残りを思わせる風が、まだ庭の竹を細く鳴らしていた。
扉を押し開けると、軋む音が広庭に吸い込まれた。土間は掃かれてこそいるが、几帳面な掃除の手の跡ではない。人が減り、手が足りていないと知れた。敷石を淡く濡らす露の光を横目に、母屋の縁へと歩を運ぶ。
奥から歩み寄る影があり、膝をついて深く頭を垂れた。老いたが、背骨はまだ真っ直ぐである。白起家の家宰である杜であった。
「将軍……いえ、恐れながら、いまだ将軍とお呼びしてよろしいものでございましょうか。」
「杜よ。」白起は口許をわずかに和らげた。
「名は風のようなものだ。強く吹く時もあれば無風の時もある。」
「ははっ。」老臣は顔を上げぬまま、絞るような声で応じる。
「宮中からのお戻り、お顔色を拝しまして……」
「王は静けさを望まれた。」
白起は縁に腰を下ろし、脇息に手を置いた。
「范雎は理を添えた。理は油のようなものだ。火に近ければよく燃える。」
杜は一瞬目を閉じ、顔の皺の奥に苦い笑みをしまい込んだ。
「ご沙汰は……」
「剣を置き、天を見よ、と。隴西の上邽にて。まもなく将軍ではなくなるだろう。」
「はっ。」
老臣の背がさらに深く沈む。杜は白起が将校となった時に家宰に就いた。思い返せば途方もない付き合いだ。それ以来、白起家の内を守護してきた。
「それでは、軍の処置は……」
「大方は、おぬしの予見どおりであろう。」
白起は庭に視線を移した。梅の古木が一本、白い苔に足首を浸しながら、枝先に緑をためている。これから冬に入る白起とは対照的な情景だった。
「兵は散らされ、噂は抑えられ、竹簡は増えよう。」
「竹簡、にございますか。」
「竹簡は静かに人を遠ざける。——太鼓の代わりに、筆を鳴らすのだ。干戈の音もない。ひたすらに沈黙の夜空だ。」
杜は唇を噛み、やがて「相済みませぬ。」と低く言った。
「戦は、もはや……
「戦は終わらぬ。」
白起は遮った。声は穏やかであるのに、言葉の端は硬かった。心の中で一区切りしたような声色だった。
「ただ、場が変わる。場が変わろうとも私は。」
剣は速し、星は遅し。
速きを捨て、遅きを学ぶ。
そのとき、柱の蔭から若い影が現れた。小走りに近寄り、膝をつく。
「書生の蒋にございます。将軍、お戻りをお待ち申し上げておりました。」
「蒋。」白起は名を繰り返した。「歳はいくつだ。」
「二十と一、にございます。」
「若い。」白起は目を細める。蒋は市場で杜が勧誘した学徒であった。元々、法家の門を潜ったが、科学や天文の方に興味が湧き、独学の道を歩んでいた。しかし、苦学の中で持ち金がそこをつき日雇の仕事で糊口を凌いでいた。飯屋で席を一緒にした杜が蒋の好奇心に惹かれ、白起家に使えさせたようだ。しかし、どうにも時期が悪かった。彼の意気揚々と比べ、白起家はこれから没落となるかも知れなかったからである。
「若さはよい。理に傷がない。……杜、湯はあるか。」
「すぐに。」老臣は立ち上がり、台所へ声を飛ばした。
温い湯で手を清めると、白起は奥の書院に移った。壁には遠征のたびに描き足された地図が並ぶ。川の筋、山の脈、街道の線。墨の濃淡は季節を、朱の印は血を思わせた。白起はひとつ、ひとつ、と小刀を用いて壁の留めを外す。地図はため息のように落ち、地に伏した。
蒋が息を呑んだ。「将軍、それは……」
「地を畳む。」白起は淡々と言う。
「地図は道を示す。だが生き残った者だけにだ。——もうよい。私に地は必要ない。区切りをつけねばなるまいよ。」
巻いた地図を杜に手渡す。
「火にくべるな。湿った土の匂いが残る場所へ預けよ。」
「はっ。」
壁が白く露わになる。そこに古い穴がいくつも並び、針で刺したような星座をなした。白起は思わず近づき、指先でそっと数えた。
「……斗、昴、心。」
長く忘れていた名前が舌の奥から浮かぶ。
「将軍、いま何と……」
「星の名だ。」
白起は微かに笑い、書机の引き出しを探った。底のほうに、押し花のように薄くなった紙束があり、取り出すと、そこには古い筆跡で星宿の表が記されていた。誰の手によるか、記憶がすぐには結び戻らない。若い日、誰かが語った。「星は天の軍、将は地の星」と。行軍に使えるかもしれないと思い、一時期、天文学の書籍を読んでいた。若き日の思い出が白起の脳裏をかすめた。
杜が戻り、膳の準備ができたことを告げる。
「粗末にございますが。」
「粗末はよい。」
白起は箸を取り、口に運ぶ。固い飯の甘さ、薄い汁の塩の気配。咀嚼の合間に、しずかに思いはほどけた。このようなゆったりした食事の時間も久しぶりだった。陣営では空腹よりも勝利に飢えていた。食を終えると、蒋が遠慮がちに口を開いた。
「恐れながら……宮中の沙汰、世間の耳目に入りましょう。門前に、すでに何人かが。おそらく噂を聞きつけた人間の影かと。」
「ほう。」
白起は湯呑みを置いた。
「どのような目だ。」
「信仰と、詮索と、恐れ。三つにございます。」
白起はこの若者の知恵に触れた。短い時間で白起の来歴を分析し、的確に述べる優秀さを。
「信仰は盲を呼び、詮索は毒を呼び、恐れは嘘を呼ぶ。」
白起は立ち上がり、庭へ出た。
「三つとも、風で払うがよい。」
「風、にございますか。」
「門を開け、しばらく閉めずにおけ。人は開け放たれた門を恐れる。秘密は、隠すより晒しておいたほうがよい。」
杜が「心得まして。」と答える。白起は庭石に腰を下ろし、日向を掌で確かめた。春である。だが春はまだ固く、掌の温もりのほうが勝る。これから冬に入る自分には暖かすぎた。
名は軽く、眠りは重し。
今宵、何を抱かん。
何刻経ったのか、夕餉の支度の匂いが台所から立ちのぼり、湯気が視界を薄く曇らせる。白起は自室に戻り、軍装の棚を開いた。胸甲、籠手、脛当——鉄は黙っている。布で油を含ませ、ひとつずつ拭った。手が覚えている順序で、無言の儀式のように。
蒋が恐る恐る近寄る。
「お手伝いを。」
「見ておれ。」
白起は短く言った。
「剣は、布を恐れる。」
「剣が……布を。」
「刃は血を知る。だが布は、血の熱を奪う。私の熱も勅命という名の布に奪われてしまった。」
拭い終えた剣を鞘に納め、白布で包み、紐で十字に結ぶ。床の間にそれを横たえ、白起は長く息を吐いた。
剣を置く。掌の熱、なお去らず。
杜が盆を捧げ持って来た。
「王都より早馬が参り、油と竹簡の手配につき伺いが。」
「油は灯に、竹簡は沈黙に。」
白起は答えた。
「灯は明る過ぎぬほうがよい。竹簡は、乾きの早いものを。」
「ははっ。宰相の差配に相違なき由、工部より報せが。」
「理は油の匂いがする、とさきほど申しただろう。」
白起はわずかに笑った。
「よい。油も竹簡も、天文に使おう。これからは俸給も減る。貰えるものはしっかりと受け取っておこうではないか。」
この男には珍しく破顔した。杜も蒋も顔を見合わせた。夜が降りると、庭の石灯籠が淡い光を宿した。蒋が筆硯を持って来る。
「将軍、何かお書きに。」
「書は戦に似る。」
白起は筆を取り、硯の面に水を落としてゆく。
「はじめに勝つべからず。まずは竹簡を観る。」
筆先に墨が滲み、白起は白簡を前にしばらく黙した。やがて、ゆっくりと一行だけ記した。
——天は高く、地は広し。人は其の間にありて、理を知らず。
蒋が息を飲み、頭を垂れた。白起の境遇を鑑みると、迂闊なことは何も言えなかった。
「……よろしき句でございます。」
「句ではない。」白起は首を振った。
「傷のかさぶたに過ぎぬ。」
「傷……」
「戦は肉を裂き、理は心を裂く。私の最大の敵は味方であったようだ。後ろから来る矢には反応が遅れる。」
白起は筆を置いた。
「裂け目から、星が見える。天が我に道を示しているようだ。」
庭では風が竹の葉をすすり、遠くで犬が二度ほど吠えた。杜が火の番をしながら、低く問う。
「将軍。明日より、いずこへ。」
「山に登る。」白起は即座に答えた。
「咸陽の観象台の修繕が始まる前に、骨組みを見たい。古い柱は使えるか、器は息をしているか、竹簡と布はどこへ置くのがよいか。隴西での観象台の参考にしたい。」
「お供を。」
「杜、おぬしは邸を守れ。門を開き、風を通し、人を怖れさせぬことだ。蒋、お前は——」
「はっ。」
「古い星表を整理せよ。詩経の注と、書庫の天文学を拾い、書を積み直せ。占いの語は端に寄せ、測量の語を手前に置け。」
「御意。」
「忘れるな。最後の咸陽になるかも知れぬ。各々、会うべき人に会っておくが良い。」
「ありがたきご配慮。」
二人が同時に答えた。白起は指で机を軽く叩いた。
「占は人の心を温め、測は人の心を冷ます。どちらも要る。だが冷めた椀に温い汁は似合わぬ。椀を温め、汁を冷まし過ぎるな。」
蒋は深く頭を垂れた。
「肝に銘じます。」
杜が薪をくべ、火が小さく爆ぜた。部屋の隅に置いた剣の白布が、わずかに灯の色を含む。白起は目を細め、火の背で揺れる影を見た。影は剣より長く、壁を伝って天井にまで伸びていた。
山は動かず、影のみ移る。
名もまた然り。
更けるほどに、邸の静けさは密になってゆく。人の声が少ない家は、音の代わりに匂いで満ちる。油の匂い、竹の匂い、古い革の匂い、湿った土の匂い。白起はそれらを一息に吸い込んだ。かつて兵の陣中で嗅いだ血と鉄の匂いはない。匂いの欠落が、かえって胸を重くした。
「杜。」
「はっ。」
「明朝、馬は一頭でよい。軽い鞍で、余計な鐶は外せ。荷は巻物と竹尺、それに水。」
「ははっ。」
「蒋。」
「はい。」
「竹簡を五十、紐を五。筆は太と細を半々。油は——」
白起は宙に視線をやり、指で数えた。
「二瓶で足りる。」
「承りました。」
彼らが散り、広間にひとり残ると、白起は座したまま目を閉じた。額の内側に、咸陽宮の玉座が浮かぶ。王の白い鬚、范雎の冷たい微笑。言葉は短く、意味は長い。
勅は一言、理は万里。
歩むは一歩のみ。
やがて白起は立ち上がり、床の間の剣に一礼した。長く共にあった刃である。彼は白布の上から両手でそっと撫で、布の織り目が指腹にかすかに引っかかるのを確かめた。
「行って来る。」
独り言のように呟き、灯を落とす。暗闇は、すぐそこにいた友のように、音もなく広がった。
翌けの空はうす青く、東の端がわずかに白んでいた。白起が門を出ると、露の冷たさが足首に触れた。杜が控え、蒋が巻物の包みを抱える。門は外へ開かれている。白起は一歩、石畳に足を置いた。土の匂いが立ちのぼる。
「将軍。」
杜が呼んだ。
「ご武運を、と申し上げたいところにございますが……」
「武運は要らぬ。」
白起は微笑んだ。
「天運があればよい。咸陽をぶらつくだけだ。何も気にすることはない。」
蒋がほんの少し笑い、すぐに顔を引き締める。
「お気をつけて。」
「心を軽くせよ。」
白起は二人に目を配り、馬の手綱を取った。
「重い心は、理を曲げる。」
丘を下る道は、朝露でしっとりとしている。遠くの畑では、早起きの農夫が鍬を肩に、空を見上げていた。白起もつられて仰ぐ。淡い光の粒が、まだ消えずに残っている。
勝は既往、赦は未至。
われ中道に佇つ。
その粒は、やがて日の気配に溶け、見えなくなった。見えなくなったものほど、心を支えることがある。白起は胸の内で、その見えぬものに礼を言い、手綱を軽く引いた。馬が静かに歩み出す。邸の門は開かれたまま、春の風を受けていた。
風は、噂を運ぶ。だが風はまた、沈黙も運ぶ。白起はその沈黙に耳を澄まし、丘を下っていった。天は高く、地は広い。人はその間を、ただ歩くのみである。理は遠く、しかし道は足元にある。その二つの距離が、これからの彼の務めであった。
【4】
二人に見送られる当日は、夜の寒気はまだ骨の芯に残っていたが、庭の水鉢には氷の皮が薄く張るだけで、指先を乗せれば、たやすく割れた。割れた破片は陽の気配の中でかすかに鳴り、雲間の光を受けて、魚の鱗のようにきらりと光った。白起はそれを一つ手に取り、耳にあててみる。軋む音が、遠い戦のきしみに似ていた。
梅の老木は、まだ硬い蕾を握りしめたままだ。だが、枝先の色は冬の黒から、ほんのわずかに浅緑へ寄っている。竹の葉はまだ乾かず、風にすれて低く音を立てる。白起は白布で包んだ剣に一礼し、戸口で履を履いた。邸の門は、外へ向けて開いたままにしてある。風が入る。風は噂も運ぶが、沈黙も運ぶ。彼はそのどちらにも傾きすぎぬよう、背をまっすぐにして外へ出た。
冬は音を固くし、春は匂いをほどく。
邸を下る小道は、夜露の名残でややしっとりしている。土の色は淡く、踏めば素直に形を残す。丘をおりると、咸陽の町はすでに朝の支度に入っていた。東門に向かう道には、都へ入る荷車が連なり、牛の鼻輪が時々金具を鳴らす。野菜を積んだ籠からは、まだ冷たい土の匂いがした。遠くの畑で、小さな火が二つ三つ見え、藁を焚いた煙が地を這うように流れてくる。
門前の番所で、番の男が木札を持って立っている。白起は懐から簡(かん)を出し、頭を下げた。
「おや、将軍。外へ出られるのではなく、内へお入りで?」
「観象台へ。少し見ておきたい。」
「観象台……」男は目を細め、白起の顔をまじまじと見た。見覚えがあるのだろう。名を呼ぶことはしなかったが、声の底にわずかな緊張が混じった。
「このところ、星のことで都も騒がしゅうございます。日数がずれるとか、暦がどうだとか……。農作にとって暦は重要でありますから、お上にはなんとかして頂きたいところではありますね。」
「暦が揺れれば、人の心が揺れる。」白起は静かに言った。
「揺れる心を座らせるために、台がある。その台が農民にとっては暦であり、収穫である、か。」
「へえ。」男はうなずき、道をあけた。
「将軍の足下、お気をつけなされ。橋の板、霜でまだ滑りませい。」
市の中へ入ると、冬と春が一つの布に織り込まれたような景色が現れた。川沿いの柳は枝だけを空へ伸ばし、その足元で女たちが洗い物をしている。水は冷たいはずだが、彼女らの手つきは容赦なく、布を石に打ちつける音が、凍りかけた空気に乾いた拍を刻む。川の縁には薄氷がまだ残り、打たれる布のしぶきが当たると、鈴のように微かに鳴った。
市場はすでに活気づいていた。麻の反物を並べる者、縄を捩(よ)る者、鍋の塗り直しを受ける錠前師。手焼きの薄い餅を売る屋台からは、白い湯気がゆるく立ちのぼり、山椒と葱の匂いが混ざっていた。白起が足を止めると、屋台の主人が声を張った。
「将軍さま、朝の腹に一つどうで? 寒い夜の名残を追い出しますぜ。」
「一つ。」白起は銭を置いた。主人はひょいと餅を返し、葱塩をのせて差し出した。噛めば、熱が舌に広がる。塩の粒が柔らかく崩れ、夜の冷えがゆっくりと退いていく。
「観象台へ?」主人が目を細める。
「このところ、空の話は商いの種でしてね。『今年は雨が遅い』『いや、星は笑っている』なんて。笑う星なんぞ見たことぁないが。」
「笑うのは人だ。星は笑わない。さらにその詩人は笑われるだろう。」
白起は餅をもう一口かじった。「ただ、遅れて届く。それが星の煌めきだな。」
「遅れて、ねえ。」主人は首をかしげ、「ま、遅れても飯は食わにゃならん。空腹に勝る学問はないですぜ、旦那。」と笑って、次の客に声をかけた。
星は遅れて届き、人は先に騒ぐ。
通りの角で、竹簡と筆を売る商人が積み荷を広げていた。白起は目をやった。中原の竹だろうか。あまり見ない品種である。墨は油の香りが強い上物だ。商人はすぐに手を擦り合わせた。
「将軍、よい竹簡と墨が入っております。冬の間に仕入れたもので、春の風でよく乾いておりますゆえ、滲まず、乾きも早い。」
「今日は観測台に行くのでな。」
白起は指で縁を押し、水気を確かめた。まだ季節の湿りが宿っている。
「墨は柔らかいか。」
「この墨は南の方から。香がよく、煤が細こうございます。」
商人は得意げに箱を開け、一本を出した。
「筆は、早い字より、遅い字に向いております。腰は強く、穂先はよく吸う。」
「遅い字に向くとは、よいことを言う。」白起はわずかに笑った。
「遅い字は、残る。これまで敵を早く撃滅することしか考えてこなかった者には痛烈だな。」
銭を置くと、商人が身を乗り出して小声になった。
「あの……将軍さま。噂を聞きまして。隴西へ行かれるとか。」
商人は白起の顔色を伺いながら、おずおずと問いかけた。白起は一瞬だけ目を伏せ、ただ「風向き次第だ」とだけ答えた。商人は気まずさにうつむき、すぐに調子を戻して「ご武運を――いや、違いました。ご天運を。」と言い直した。言葉は滑る。白起は笑みでそれを受け取った。
大通りの中ほど、鍛冶場の前を通る。槌の音が一定の拍を保ち、火の粉が寒い空気に散ってはすぐ消える。若い職人が汗を拭い、白起に気づくと、慌てて槌を置いて頭を下げた。
「将軍、失礼をば。今日の打ちは鋤でございます。畝を割る刃は、剣よりも性が素直で。」
「剣は人を割り、鋤は土を割る。」
白起は火床の上の鉄を見た。
「土は、怒らない。どれほど打擲されようともな。」
「怒るのは人で。」若者は照れたように笑った。
「春の支度で忙しくなります。農民からの注文が増えておりましてね。空の具合、どうでしょう。」
「空は、人の都合を知らない。」白起は槌を持ち直した若者の手を見た。
「だから人が、空の都合を聞きに行く。天に近い観象台でな。」
「なるほど。」若者は槌を上げた。
「であるなら、わたしは土の都合を聞かにゃなりませぬな。」白起に同調するような声色で若者答える。
同拍は安んじ、異拍は醒ます。
土の拍は、火の拍より長い。
市を抜けると、官の建物が連なる通りに出る。壁は白く塗られ、軒は長く、石畳は人の足で磨かれて鈍い光を放っている。史局の使いが行き交い、竹簡の束を抱えた書記が足早に角を曲がる。白起が近づくと、書記の一人が立ち止まり、礼をした。
「白起殿……ではございませんか。」
「名を口にするな。」白起は穏やかに手を上げた。
「風が名前を運ぶ。うろうろしている噂が立つと迷惑がかかる。」
「はは……失礼を。観象台へ?」
「都の台を、一度見ておきたい。」
「今日の高には厳殿が入っておられます。」書記は声を潜めた。
「“凶”の字を軽々しく使うな、と朝から繰り返し通達が。都は春へ向かうのに、言葉はまだ冬でございます。」
「言は冬でよい。冬がなければ、春は急ぎすぎて口の災いを招く。」
白起は短く返し、歩みを進めた。書記は深く頭を下げ、その場にとどまった。白起の後ろ姿を見つめているような気配がいつまでも続いた。
官の区画を抜けると、通りの先に観象台が見えてきた。土台の上に木と石で組まれた高所、四角に切り取られた天窓。外壁には、古い刻みで二十八宿の名が残り、ところどころ薄れているが、筆勢はいまだ生きている。門前には衛士が二人。白起が近づくと、槍を立てなおした。
「どなたにござる。」
「この先、隴西の観象役を預かる者。」白起は深く頭を下げ、腰の符を示した。
「名は問うてくれるな。今日だけ、天を見せてほしい。」
衛士は符を改め、互いに目を交わし、すぐに道をあけた。
「どうぞ。足場、凍りが残っております。お気をつけなさりませ。」
内に入ると、香の匂いはなく、木と墨と冷えた石の匂いだけがあった。階を上がり、上段に出る。天窓から、淡い冬の光が舞い込んでいる。壁際には圭表の柱、滴りを計る漏刻の甕、巻物を納めた長い箱。どれも手入れが行き届いている。白起は指先で柱を叩き、骨の音を確かめた。都の台は、山の台よりも落ち着いている。柱は太く、梁はよく鳴り、風はよく通う。
背後で衣擦れの音がした。振り向くと、青い衣の若い官吏が立っている。顔はまだ丸く、目の中に理屈の光が宿っていた。まだまだ駆け出しのようだが、心に秘める野心が垣間見える。
「来客と承っております。」若者は礼をし、「どちらから。」
「丘の上から。」白起は曖昧に答えた。「観るだけだ。」
「観る者は、こちらへ。」若者は天窓の下へ案内し、指さした。
「この窓から、北はここ、南はここ。昨日は風が強く、今日は風が弱い。風は弱ると竹簡を乾かすが、心を乾かすかどうかは、わかりません。」
「心は、乾かすより、湿らせるほうが難しい。」白起は窓の縁に手を置き、空を見た。
「名は。」
「鄭(てい)と申します。」若者は胸に手を当てた。「観測部の下、書き役で。」
「書くのか。書く者は、良い。」白起は頷いた。
「書く者は、剣を知らずとも、剣の重さを知る。」
「剣の重さを……」鄭は首を傾げ、「わたしは剣を持ったことがございません。」
「持たぬがよい。」白起は短く笑った。「持てば、置くのが難しい。各々行く道は違ってくる。」
「将軍は剣の道を?」
「ああ、これまではな。」
号令は響きて散る、記録は沈みて残る。
怪訝な顔を白起に向けた鄭は、何やら問いたげだったが、階の下から、ゆっくりとした足音が近づいてきた。厳である。朝に聞いた書記の言葉どおり、彼は台の上に入り、白起を見ると一瞬だけ目を細め、すぐ公の顔に戻した。
「珍しい客だ。」
「都の台を、一度見ておきたくてな。」白起は礼をした。「隴西に行く前に。」
「噂は早い。」厳は肩をすくめた。
「風は名前と噂を運ぶ。――ここは、あなたの名を置く場所ではないが、目は置ける。見てゆかれよ。」
鄭が驚いたように白起を見た。厳はそれに気づいて、静かに言葉を足した。
「名は風で、理は骨だ。骨は見えぬが、立つ。――鄭、滴りを見るがよい。」
「はっ。」鄭が甕に近づき、滴る水音を数え始める。白起は天窓から空を仰いだ。薄い雲が大路のように伸び、風の向きは東へ寄っている。街の屋根が、ところどころ、薄い霜を残して光っていた。路地では子供が凧を上げようとして糸をもつれさせ、母親に叱られている。凧は上がらず、地上で揺れた。上がらぬ凧の影が、走る犬に踏まれてほどける。冬はまだ、地を放さない。
「白起殿。」厳が脇に立った。声は低く、刃のような冷たさはない。
「あなたは、なぜ都の台を見に来られた。」
「山の台を見る前に、都の台の骨がどのように立っているのか、知りたくなった。」
白起は窓から目を離さずに答えた。
「山は遠く、都は近い。近い骨は、遠い骨よりも、折れやすい。」
「折れぬように支えるのが、我らの役目で。」厳は短く笑った。
「“凶”の字を軽々しく使うな、という通達に、書き手たちは顔をしかめている。だが、凶が出れば、民は凍える。春が遅れる。そして実りも危うくなる。」
「春は遅れる。」白起は言った。「遅れるから春だ。」
厳は黙ってうなずいた。沈黙のうちに、彼は白起の横顔を一度だけ見た。目に冬の名残と、春の匂いと、長い夜の疲れが並んでいる。鄭が滴りの数を読み上げる声が、低く続いていた。しばしの後、厳が話題を変えた。
「隴西では、風が違う。星の冴えは深いが、言葉は届きにくい。」
「届かぬ言葉は、丁度よい。」白起は小さく笑った。「届きすぎる言は、刃になる。」
「天文部としては、あなたの“見”を要する。」厳は声を落とした。
「“解”は、我らが引き受ける。“見と解を分けよ”。――これは、あなたのためでもある。」
「見は私、解は公。」白起は静かに繰り返した。「ただし、余白は私に残せ。」
「余白は、責任の器ですからな。」厳は口角をわずかに上げた。「あなたは器を作るのが上手い。剣の時代から。」
遠くで、鍛冶の槌の音が微かに聞こえた。市で耳にした拍と、ここで数える滴の拍が、奇妙に重なった。同じ拍が重なると、人は安心する。異なる拍が重なると、人は目を開く。白起は窓の縁に触れ、木の温もりを指に確かめた。
同拍は安んじ、異拍は醒ます。
眠りに似た秩序、醒めに似た自由。
そのとき、階の下から急ぎ足の気配。年配の役人が上がってきて、厳に耳打ちした
「……村の祠より、心宿犯月につき、至急の照会が。」
厳は目を細め、白起に視線を流した。「星は、すぐに政治になる。」
「政治は、すぐに祈りになる。」白起は答えた。
「祈りを否めば、血が湧く。祈りに寄りかかれば、数が死ぬ。」
「では、どうする。」
「見を渡す。」白起は短く言った。「解は渡さぬ。」
厳は深く息を吐いた。
「――鄭、記せ。“昨夜、風弱く、薄雲あり。心宿の傍に月近づくも、赤を侵さず”。それだけだ。」
「はっ。」鄭が筆を走らせる。筆の音は、剣の音よりも長く残る。
厳は白起に向き直った。
「あなたは、都を離れる前に、なにか望むことがあるか。」
「都の台の柱に、耳を当てることを許せ。」白起は意外なことを言った。「柱は、鳴る。」
「鳴らぬ柱は、折れる。」厳はわずかに笑った。「お好きなだけどうぞ。」
白起は柱に近づき、掌をそっと当て、ゆっくり耳を寄せた。木は、冬の間に固くなっている。だが、内にわずかな水の音が残っている。遠い山の水が、春の用意をしているような音だった。耳を離し、掌を退けると、木の肌が冷たく、乾いていた。
木も、人も、冬ののちに水を待つ。
台を降りるとき、鄭がそっと近寄った。
「あの、白――失礼を、将軍。わたしは、あなたの書く“余白”が好きです。」
「余白は、呼吸だ。」白起は答えた。「息が止まると、字は死ぬ。余白を大事にせよ。人生においてもな。」
「字は死ぬ……」鄭は頷き、ふと口を滑らせた。
「わたし、実は剣を見たことはあります。戦の帰り、橋の下で。錆びていて、重そうで。……ああいうものを、持たれていたのですね。」
「持っていた。」白起は短く言い、足を止めずに階を降りた。「そして、置いた。」
「置けるものなのですか。」
「置く場所があれば、置ける。そして、我が意に反して置かなければならぬ時もある。」
「置く場所……」
「台の窓の下。竹簡の端。人の沈黙。国家の足元。」
鄭は深く頭を下げた。厳が遠くからそれを見て、何も言わずに階の上へ戻っていった。
外に出ると、陽は先ほどより強くなっていた。屋根の霜はほとんど溶け、瓦の端から水がぽたり、ぽたりと落ちる。通りには、朝より多くの人が溢れ、声は暖かさを取り戻している。白起は観象台を一度振り返った。都の台は、よく立っている。骨の鳴りは静かで、息は高い。彼は軽く頭を垂れ、歩き出した。
帰り道、川沿いの柳の下で、屋台の主人がまた餅を焼いていた。白起が通ると、主人が片手を上げた。
「将軍、さっきの話。星は遅れて届くって。」
「そうだ。」
「人は先に腹が減る。」主人は笑って、焼け具合を確かめた。
「だから、今日の腹は今日のうちに埋めておく。――あなたは、今日、何を埋める。」
「余白。」
「余白?」
「天文部の人事名簿を埋めるのさ。」
主人は目を丸くしたあと、しわの間に笑いを沈めた。
「妙な客だ。だが、妙な客は、妙に腹に落ちる。腹持ちも良いものだ。」
少し先、鍛冶場の前を通ると、若い職人がさっきよりも軽い拍で槌を打っていた。白起は立ち止まらず、彼の背にひとことだけ残した。
「土は、怒らない。」
若者は槌を止め、振り返って深く頭を下げた。言葉の意味を、彼はまだすぐには受け止めきれぬだろう。だが、言葉は遅れて届く。星のように。
市を出て、門へ向かう。番の男が寒風から身を守るために襟を立て、白起に気づくと道をあけながら尋ねた。
「将軍、観象台は……どうでした。」
「柱が鳴っていた。」
「柱が……」
「春を呼ぶ音がした。」
「そうですか。」男は頬を緩め、
「じゃあ、うちの婆さまの骨も鳴ってるはずで」と笑った。
「春になると昔痛めた膝が疼くと申しますんで。」
「骨は、春をよく知っている。」白起は頷いた。「婆さまを大事に。」
「ありがたきお言葉。」
門を出ると、風の匂いが変わった。土の湿りと、どこか青い匂いが混じる。邸に戻る道は、朝と同じでありながら、違っていた。足跡は増え、露は乾き、鳥の声がひと筋増えている。庭へ入ると、梅の蕾が朝よりもわずかに膨らんで見えた。白起は剣の包みに一礼し、机に手を置いた。布を広げ、筆をとり、短く記した。
——見は私、解は公。余白は、息。
筆を置くと、指先に墨の冷たさが残った。白起は掌を合わせ、掌の中に残った冷えと、街の温かさと、台の骨の鳴りを、ひとつの呼吸にまとめるようにして、ゆっくりと息を吐いた。窓の外では、竹の葉が乾き、冬の音から春の音へとわずかに調子を変えていた。
春は急がず、遅れて来る。
遅れて届くものだけが、長く残る。
午後の光が庭石に斜めに落ちるころ、杜が戻ってきて、門前の様子を報告した。
「噂の口、三つほど。詮索が二つ、信仰が一つ。いずれも風で払っておきました。」
「よい。」白起は窓の外を見た。「風は、今日よく働いた。」
「観象台は、いかがで。」
「骨が鳴っていた。」
「骨が鳴る台は、倒れませぬ。」杜は満足げにうなずき、温い湯を置いた。
「隴西へ行く前に、都の空を一度見られて、ようございました。」
蒋が控えめに言った。
「都の空と、山の空は、どちらがよろしゅうございますか。」
「どちらも、天だ。」白起は笑った。「違うのは、人の背の数。」
「背の数……」
「都は背が多い。山は背が少ない。背が多ければ、言は早く、息は浅い。背が少なければ、言は遅く、息は深い。」
「わたくしは、どちらの息が似合いましょう。」
蒋は少し考え、「遅いほうが好きかもしれません。」
「ならば、遅いほうに居よ。」
白起は机に手を置き、布の端にもう一句だけ添えた。
——剣を置き筆を執る。血は墨となり、地は天となる。
墨は、朝よりも早く乾いた。春が近いということだ。白起は筆を洗い、布で拭き、机の端に置いた。門の向こうの空に、薄い雲が一筋のびている。その形は、都の観象台の窓から見上げた雲と、同じ形をしていた。空はひとつで、名だけが変わる。彼はそのことを確かめるように、もう一度深く息をした。
名は衣、理は骨。
衣は替えられ、骨は替えられぬ。
夕刻、邸の前を通る農夫が鍬を担ぎ、空を見上げて足を止めた。「殿、明日は、土が笑いますな。」
「土は、怒らない。」白起は答えた。「だから、よく笑う。」
農夫は笑い、背を向けて歩き出した。彼の背は、冬よりわずかに軽かった。白起はその背を見送り、門を閉めなかった。風が入ってくる。風は噂も運ぶが、沈黙も運ぶ。彼はその沈黙に椅子を寄せ、夜の気配が降りてくるのを待った。都の観象台で聞いた骨の鳴りが、耳の奥で細く続いている。遅い音だ。長く残る音だ。やがて、その音は、いつもの夜の沈黙に溶けていった。翌日からの旅の支度は、もう心の内で整っている。
隴西は遠い。だが、遠いから、言が遅れて届く。遅れて届くものだけが、長く残る。白起は灯をともさず、薄闇の中でしばらく座り、やがて立ち上がって庭に出た。梅の蕾は、ほんの少しだけ、朝よりも膨らんでいるように見えた。冬はまだ地に残り、春はまだ空にある。人はその間にいて、息をしている。
天は無言、地は多言。
われ其の間にして、ただ息す。
【5】
白起は都の観象台をあとにして邸へ戻った。瓦の縁を伝って落ちていた水が、もう土に吸い込まれていた。門前の砂利は朝より柔らかく、踏めばこくりと沈む。冬の冷えが背を離れ、代わりに春の匂いが薄く袖にからむ。門は外へ向けて開け放したまま、蝶番がひとつ、風に合わせて小さく鳴った。
翌朝、広間に出ると、家人たちが動いていた。畳の上には巻物の包み、槍掛けには布で包まれた剣が横たわり、奥では箱が縄で締められている。土間からは湯の音、遠く台所では包丁がまな板を叩く一定の拍。冬の家は音が少ないが、春は音が増える。
杜が朝の挨拶と共に近づいてくる。
「荷の目録、半ばまで。運ぶもの、売るもの、割り振りはおおかた済みました。」
杜は手にした板札を捧げる。
「竹簡、十巻ずつ三包。油は胡麻四、菜二。麻縄十把。工具、槌、楔、鋸、鉋。漏刻の甕は重うございますゆえ、藁で囲って別に載せます。圭表の柱は、長さゆえ馬に抱かせ、先に出しまする。」
「よい。」白起は板札に目を通し、短く頷いた。「火の用心は。」
「油と竹簡、木簡の箱は別所に。火縄は湿らせておきます。」
「余白も忘れるな。」白起は板札の端に指を置いた。
「箱にも、人にも、余白を作れ。詰めすぎると、途中で息が切れる。もっともこれまで余白なく戦争を指揮した人間が言うことではないがな。」
家を畳むは、心を畳むこと。
余白は、息。
襖の陰から、若い書生の蒋が束ねた書物を抱えて現れた。目の下に少し夜の疲れを宿しながらも、頬は春の光のように明るい。
「白起さま、古い星表の整えができました。甘徳と石申の名のあるものを上に、占に偏ったものは後ろへ。注記に朱で“見(観測)”と“解(解釈)”の印を付けておきました。」
「よい。」白起は受け取り、書の呼吸を確かめるように一枚めくった。「布はまだ湿を含む。長い道で乾きが進むだろう。――蒋、圭表の基礎に用いる盤の寸法、もう一度確認しておけ。隴西は風が違う。影の伸びが変わる。」
「承りました。」蒋はうなずき、ふと顔を上げた。
「白起さま。都の観象台は、やはり……」
「よく立っている。」白起は短く答えた。
「だが、名は置かぬ場所だ。目だけ置いてきた。」
「目だけ……」蒋はその言葉を反芻して笑い、「では、心はこれから隴西へ。」
「心は、ここを通って向こうへ行く。」白起は庭の方へ顎をしゃくった。
「まず、家を通す。」
その時、台所へ続く戸口から年配の女中が顔を出し、慌てて手拭で手を拭きながら駆け寄った。
「白起さま、お帰りでございますか。お腹は……朝の餅だけじゃ持ちますまい。薄い粥と卵を。」
「気が利く。」白起は微笑んだ。「卵は星を見る者に効くそうだ。」
「ええ、婆さまの言い伝えでございますよ。」女中は笑って戻っていった。戻り際に、廊下の角で若い下働きに指を立てさせ、「油の箱は日の当たらんところに」と小声で指示を飛ばす。家の中の声が、冬より少し高い。
白起は広間の中央に座し、周囲を見渡した。地図を外した壁は白く、釘穴が星座のように点在している。その白さに、これまでの来歴がうっすらと写る。若き日の初陣、川の水位を測って渡河の刻限を決めた朝。敵の糧道を断ち、三日の渇きに耐え抜いた夜。長平の谷に立ち込めた埃と叫び。凱旋の道に並んだ子供らの瞳。勝で得たものと、失ったもの。名は山より重いと言う者がいるが、実際に重いのは山ではなく、影だ。勝つほど影は伸び、影は身を離れぬ。
功は山のごとく重し、影は身を離れず。
影を薄くする法は、光を散らすのみ。
その影を散らす光が、冬の終わりにようやく薄く巡って来た。白起は胸の内で短く息をつき、杜に目配せした。
「鎧はどうした。」
「白布で包み、油を含ませてございます。」杜は奥を指した。「あなた様のお手で封じられたそのままに。」
「見せよ。」
杜が白布包みを運び、白起の前にそっと置いた。白起は布の結び目を解かず、上から両手で一度撫でるだけにとどめた。布越しに伝わる鉄の冷たさは、もう彼の手の熱を必要としない。包みの角に、朱で小さく印を付ける。
「“留”だ。」白起は言った。
「隴西へは連れぬ。ここに留める。――杜、床の間の隅に、湿りの少ない場所を見つけて、低い台を置け。布の下に薄板を敷く。地の冷えを避ける。」
「ははっ。」杜の声は低く、どこか晴れやかだった。
「置く場所があるものは、置けまするな。」
「置く場所がなければ、人は抱えて倒れる。」
白起は布を軽く押さえたまま、短く目を閉じた。
「置くことを恥とするな。置いて、息を作れ。」
粥が運ばれ、白起は蒋と杜とともに膳を囲んだ。薄い塩の味、卵の柔らかい甘み。湯気が顔に当たると、目の奥の冬が少し溶ける。蒋が匙を置き、遠慮がちに口を開いた。
「白起さま。――もし、お差し支えなければ。あの日のことを、お聞かせいただけませんか。長平の……」
杜が肩をわずかに強張らせ、女中が廊下の角で足を止めた。白起は匙を置き、蒋を見た。若い目はまっすぐで、愚かではない。しかし、若さの無謀もまた真実だ。
「見たものは、見たまま語れぬ。」白起はゆっくり言った。
「音のないところで起きた音を、音のある言で語ることは難しい。」
「難しいから、知りたいのです。」蒋は小さく身を傾けた。
「わたしたちがこれから書く“見”は、人を静めるための“見”です。知ろうとする心まで静めてしまっては、書く手が鈍ります。」
「……よく言った。」杜がぽつりと漏らした。白起は膳に戻り、粥をひと口含んだ。温かいものは、人に言葉を与える。彼は匙を置き、掌を膝に置いて、短く語り出した。
「谷に入る前、空気に鉄の匂いがあった。土が乾きすぎて、靴の底が鳴った。夜、敵の焚き火の数を数えながら、水の音を探した。見えぬ水の音が、こちらの心を割いた。翌朝、霜が解ける音がした。敵もこちらも、同じ音を聞いた。――そのあとに起きたことは、ただの理だ。糧は足りず、人は疲れ、声は途切れ、影は伸びた。影は、身を離れぬ。」
蒋は息を呑み、杜は静かに目を閉じた。女中は音を立てぬようにして、そっと盃を片付けた。白起は続けた。
「だから、私は観る。剣で割ったものは、筆では繋がらぬ。だが、割れてしまったものの上に、静かな影をかけることはできる。影は涼しい。人は落ちつく。落ちついた心で、鍬を握れる。」
勝は既往、赦は未至。
われ、中道に佇つ。
粥を終えると、家の拍がふたたび早まった。中庭では、駄馬の背に巻物の箱が載せられ、革の帯が締められる。若い下働きが肩で息をして、縄を両手で引き締めると、杜が脇から手を添えて結び目を整えた。
「締めるとこは締める。遊ばせるところは遊ばせる。」杜が言う。
「道は揺れる。揺れで壊れるのは、締めすぎか、ゆるみすぎだ。」
「人の心も同じ。」白起は荷駄の横で、軽く頷いた。
「――蒋、圭表の柱は?」
「ここに。」蒋が長い丸太を示す。
「長さは身の丈三つ半。西の鞍に斜めに載せ、先を布で巻いて傷を避けます。」
「風に鳴く。」白起は丸太の端を軽く叩いた。「鳴かぬ柱は折れる。鳴く柱は立つ。」
裏庭の片隅では、女たちが布を畳み、糸の束を仕分けていた。年長の女中が若い者の手元を見て「角は合わせるが、息は詰めるんじゃないよ。」と笑い、鼻歌をうっすらと乗せた。冬の間は止まっていた歌が、春になると自然に出る。歌は息だ。息は家を立てる。
荷の割り振りが進むにつれ、「残す」「持つ」が家の中で明確になっていった。書架の下段に積まれた兵法書は、白起が指で背をなぞりながら、「留」と朱で印を付けた。誰のためでもない。自分のためだ。剣と同じく、ここに置くことで、心の場所が一つ確かになる。蒋がその印のありようを見つめ、静かに頭を下げる。
「置くことを、恥としない。」蒋がつぶやいた。
「うむ。」白起の声は短いが、温かった。「置く場所を作るのが、家人の務めだ。」
「杜よ、我が家の借財、債権はどうなっておる。」
「はっ、借財はきれいに清算しております。この都に借りはありません。債権の方は年間を裕に暮らしていけるだけの利子が入ってくるようになっております。」
「ふむ、戦場での生涯も無駄ではなかったか。」
「はい、資産があることは心に余裕をもたらします。」
「隴西に到着後も家の財務はそちに任せる。」
「かしこまりました。家宰の名に恥じぬ働きをご覧にいれます。」
やりとりを聞いていた蒋に向かって白気が語りかける。
「蒋よ、学問も良いが財務管理についても杜に学んでおくが良い。財は時に汝を助ける。」
「肝に銘じておきます。」
日が中天に差しかかるころ、門の外からぽんと手を打つ音がした。見れば、雑貨の商人が包みを抱えて立っている。朝、都で会った男だ。
「将軍さま、約束の上物をもう少し。道が長いと聞きまして、手前勝手で持ってまいりました。」
白起は思わず笑い、門の陰にいた杜が感心したように商人の荷を受け取った。
「都は耳が早いな。」
「耳を早くして食うのが、商売人でして。」商人はおどけて頭を掻いた。「
お代は、隴西に着かれてからで結構。布は先に走らせるに限ります。」
「上布は、心を先に走らせる。」白起は包みを撫でた。「礼は、隴西に落ち着いてから。」
「お待ちしております。時には咸陽にもお立ち寄りください。」
商人は深く礼をして、足早に去っていった。風が彼の衣の裾を持ち上げ、土の匂いと混じって消えた。
道は先に荷を送らず、まず心を送れ。
心が着けば、荷は迷わぬ。
午後、白起は机に向かい、旅の経路を簡単に記した。渭水をさかのぼり、西へ西へ。谷の口で風が変わる。山の影が長くなる。隴西の空は乾き、星は剣よりもよく光る。竹簡の上の線は少なく、余白は広い。杜が背中越しにそれを眺め、「道は短く書いても長いもの。」と呟いた。
「長い道ほど、余白がいる。」白起は筆を置いた。
「余白に息を置く。息が切れたら、そこへ戻れる。しかし、咸陽には。」
その時、門の外で小さな騒ぎ。覗けば、近くの子供が二人、ぎこちなさの残る凧を持って上目遣いで覗いている。朝、都で見た凧とよく似ている。蒋が気づき、笑って手招きした。
「どうした。」
「おじさま、これ、飛ぶ?」上の子が凧を差し出す。「風があるのに、地べたを這う。」
「糸がからんでおる。」蒋がしゃがんで糸を解く。
「風に任せすぎても、手に引きすぎても、だめだ。」
「どれくらい?」
「風の息に合わせて、指二本ぶんだけ。」
蒋が白起を見上げると、白起は微笑んでうなずいた。
「風を読むには、まず自分の息を読む。」白起は子にやさしく言った。
「息を短くしすぎるな。長くしすぎるな。胸の真ん中に風を入れろ。」
子は真剣にうなずき、凧を持って走り出した。少しよろけながらも、凧は土から離れ、空へ上がっていく。二人の笑い声が門の外に広がり、冬の名残を押していった。
春は急がず、遅れて来る。
遅れて届くものだけが、長く残る。
日が傾き始めると、荷駄の点検が最後の段に入った。油の徳利は藁に寝かせ、竹簡の包みには布を掛け、紐の結び目に朱で小さく印を付ける。蒋が漏刻の刻線を布で巻き、杜が楔を数えた。女たちは手拭を肩にかけ、残る布を畳み続ける。白起は床の間の剣の前に進み、静かに膝をついた。布の上から両の掌を当て、低く一言だけ。
「留む。」
それきり、剣に背を向けた。背を向けるには、背の力がいる。彼は立ち上がり、広間の中央に戻って、家人たちを見渡した。顔は煤で黒く、眉は汗で濡れ、手は縄で紅い。ひとりひとりが家の骨であり、息だった。
「皆、聞け。」
白起の声は大きくはなかったが、よく通った。作業の音がすっと細り、家の中に静けさが降りた。
「明朝、荷の先発を出す。杜は二名を連れて荷に付け。蒋は私と遅れて出る。――道は長い。詰めすぎるな。遊ばせすぎるな。声は短く、手は長く。争わず、譲り合え。助けを求める者があれば、先に水をやれ。言よりも先に水だ。」
家人たちの背がまっすぐになり、膝が深く沈んだ。白起は続けた。
「都で名を呼ばれても、名で返すな。道の端でうわさを投げられても、拾うな。拾ってしまえば、荷が重くなる。荷を軽くせよ。心を軽くせよ。――隴西に着いたら、我らは“見”を司る。解を欲する声に、解で返さぬ。数で返す。沈黙で返す。人が落ちつく言葉を選べ。凶の字は、みだりに使うな。」
「承りました。」杜の声は低く、しかし晴れやかだった。蒋は大きく呼吸し、若い下働きたちは互いに顔を見合わせてから、力強くうなずいた。
号令は道を塞ぎ、記録は道を作る。
塞ぐは勝ち、作るは生。
夕餉は、いつもより少し賑やかだった。左遷される人物の家とは思えない雰囲気だった。豆の煮物と蒸した穀、浅い味噌の汁。女中が「旅立ちは腹から。」と笑い、杜が「腹が立てば、台が立つ。」と応じ、笑いが広間の梁にたまった。白起は多くは語らず、杯を少しだけ傾けた。酒は薄く、香は短い。冬の酒は骨に染みるが、春の酒は息に溶ける。
夜、家の音が一段落すると、白起は庭に出た。空は薄い紺で、梅の蕾は昼よりもすこし硬く見えた。土の上には昼の気配が残り、足裏に柔らかい温が伝わる。遠くの路地で犬が二度吠え、止んだ。彼は空を仰ぎ、指で四角を作る。都の観象台の窓と同じ四角。そこに星は少なく、音はない。だが、音のないところでこそ、息は長い。
背後で戸がすべり、蒋が現れた。手に小さな包み。
「白起さま、旅の間に書きつけるための小布を作りました。折って胸に入るように。」
「よく気が回る。」白起は受け取り、掌で重みを確かめた。「重くない。――蒋。」
「はい。」
「これからお前は、言いたい時に言えぬことが増える。それでも、言わぬほうが正しい場面がある。言わずに済む用意を、先にせよ。」
「言わずに済む用意……」
「数だ。」白起は微笑んだ。「数と、余白だ。」
蒋は深く頭を垂れた。白起は庭石に腰を下ろし、短く目を閉じた。胸の内に、これまでの道が折り畳まれて入っているのがわかる。若い日の疾駆、名を呼ばれる快さ、名に呼ばれる危うさ。戦の音。凱旋の喧噪。沈黙。――そして、遅れて届いた一条の光。
剣を置き筆を執る。
血は墨となり、地は天となる。
やがて彼は立ち上がり、広間に戻った。床の間の剣の白布は、夜の灯をうっすらと含んでいる。彼はそれに背を向け、机に向かった。布を一枚、静かに開く。筆の穂先を水に湿らせ、墨に含ませる。墨はすでに春の湿りを含み、冬よりも柔らかい。彼は書いた。誰にも見せぬ短い誓いを、余白の多い紙の端に。
見を司り、解を制す。
数は人を落ちつかせ、余白は死者の居場所となる。
凶の字、みだりに用うべからず。
言は短く、息は長く。
功は語らず、罪は隠さず。
天は無言、地は多言。われ其の間にして、ただ息す。
筆を置くと、墨の匂いが静かに立ちのぼった。彼は布を折り、胸の内側へそっとしまった。胸に冷たさが少し残る。自制は冷たい。だが、冷たさの奥に、春の温かさは忍んでいる。外では、竹の葉が乾いた音で触れ合い、梅の蕾の中で目に見えぬ何かがほどけていく。
灯を落とす前に、彼は家の中を一巡した。土間の火は消え、甕の水は縁まで澄んでいる。荷の紐はすべて朱で印が付き、油の徳利は藁に寝ている。女たちはもう寝所に入り、家の拍は低く、長い。杜は戸口の陰で横になりながらも目は半ば開いており、蒋は机に伏して小布を抱いたまま眠っている。白起は彼らの肩に布をそっと掛け、門の蝶番をもう一度確かめた。風が夜の匂いを運び入れ、家の中の冬と春をひとつの呼吸に混ぜる。
最後に、床の間の前に立った。剣の白布は静かだった。彼は小さく頷き、声にはせずに言った。
――留む。
灯を落とすと、闇はすぐに友のように寄ってきた。闇は何も問わず、ただ息の長さを確かめてくる。白起は目を閉じ、心の中で再び誓いの句をなぞった。明朝、門は朝の風を受け、荷は道へ出る。道は長い。だが、長い道ほど、余白がいる。余白があれば、息は切れぬ。息が続けば、星は見える。星が見えれば、人は落ちつく。
天は無言、地は多言。
われ其の間にして、ただ息す。
【序章 完結】
【第1章】
↓↓↓↓