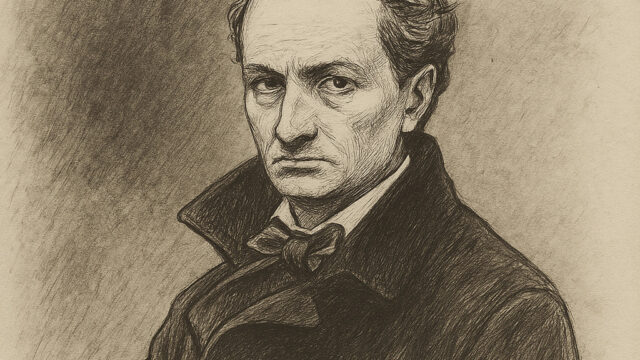麁服の朝—忌部の祭祀
夜は薄く、川は名乗らず、麻は息をひそめる。吉野の水はまだ冷たく、眉山の影はまだ名を持たぬ。名を与える前、すべては静物である。静物に触れる掌だけが、わずかに温かい。私は掌を洗い、麻を撫でる。撫でた麻は、朝の気配を吸い、細く、強く、言葉を孕む。
斎(いつき)の家に火が落ちる。太鼓は鳴らず、ただ灰が息をする。息は細く、息は長い。息の長さで、ひとの徳は量られる。忌部の古き家は、徳を誇らない。誇らぬ徳は、梁にとどまり、梁の影をひとの額に置く。額に影を受け、今日も働く。働くとは、神へ近づくのではなく、神から遠ざかりすぎない配慮である。
水は走りて麻を洗い、風は止みて刀を磨く。刀は布を裂くためのものではなく、布を布たらしめるための境界である。境界を作る者は、境界に住む。境界に住む者は、しばしば名を失う。名を失うことを怖れぬとき、仕事は仕事のまま気高くなる。麁服(あらたえ)。粗にして精、荒にして潔。言葉は少なく、手つきは一定。一定は退屈に似て、退屈は祈りに似る。
私は糸を撚る。撚りは左へ、撚りは右へ。左右が均されると、心は端座する。端座した心は、やや重く、やや軽い。軽い心で重い日に入る。重い日は、軽い言葉を嫌う。だから私は黙る。黙ることは、沈黙を増やすことではなく、音の居場所を空けることだ。
朝の川、石の背が白む。白む石は、いにしえの膝である。膝は折られず、ただ曲げられる。曲げられた膝の弾力で、ひとは未来を受ける。古代の祭祀は、未来の受け皿だった。受け皿は陳列されず、ただ使われ、洗われ、欠け、また使われた。欠けを恥じるな、器の由緒は欠け目に宿る。
忌部の若者は、麻の中から一本を選り出す。選りは厳にして柔。柔らかい厳は、母の掌、川の瀬。選られた一本は、群れを羨まず、群れの誇りをその身で代表する。一本が束になり、束が布になる。布が祭りに化する。化した布は、言葉のない聖典である。聖典は読まれず、着られる。着られた言葉は、汗で濃くなり、雨で薄くなり、火で乾く。
火の前に、年長が立つ。語らぬ師、指を二度だけ動かす。動きは小さく、意味は大きい。小さい大きさは、徳の形である。徳は軽い。器は静かだ。静かな器は、音を遠くへ運ぶ。遠くへ運ばれた音は、朝の鳥に紛れ、やがて町の屋根に降りる。屋根の上で、現代の洗濯物が揺れる。Tシャツ、作業着、校章のついたシャツ。どの布にも、麻の祖が眠る。
私は思う。歴史は歩いてくるのではない。歴史は佇む。佇むものに、私たちが歩み寄る。寄る歩みの歩幅が、地域の拍子になる。阿波の拍子は、盆の「やっとさ」にだけあるのではない。台所の湯気、漁港の汽笛、登校の自転車の鈴、加工場のベルトコンベヤ。これらの拍が重なり、町は呼吸を覚える。呼吸を忘れた町は、まず祭りを忘れる。祭りを忘れぬために、布は編まれ、編まれた布に、季節が縫いとめられる。
午前、私は工場の灯を点す。点灯は小さな祭礼である。スイッチは賽の目のように四角く、指は一瞬だけ祈りの形をつくる。モーターがうなり、ステンレスの台が光る。魚の身は白く、皮は青い。青白のあわいに、古い蔵の煤がよぎる。藍の町は、藍ばかりで生きたのではない。藍に似た規律で生きたのだ。規律は嫌味ではない。規律は労働を軽くする器具である。
見上げれば、眉山は今日も背を押す。背を押されて、私は軽く前のめりになる。前のめりの姿勢は、過ちの前兆ではなく、学びの姿勢である。師は山であり、川であり、古い布である。布は語らないが、折り目が語る。折り目は畳まれ、畳まれた角に埃が溜まる。埃は時間の粉だ。粉を払うたびに、私はいつかの誰かに触れている。
昼の前、斎場に女たちが集う。沈黙の輪は、言葉の輪より強い。糸巻きが回るたび、歴史は少しだけほどけ、また巻き直される。巻き直す手つきは、怒りを忘れた者の手つきである。忘れられぬ怒りは正義かもしれないが、忘れうる怒りは慈悲に近い。慈悲は布の裏側に縫い込まれて、表からは見えない。
午後、私は出荷伝票に数字を刻む。数字は直線だ。直線は川に似ない。川は曲がる。曲がることを恥じぬものは、遠くに至る。数字は曲がらない代わりに、重なる。重なった数字は、秤の皿の上で、今日という一日を言い当てる。言い当てられた日は、静かに終わる。
終業の笛が鳴る。笛はか細く、しかし確かだ。確かな細さは、古代からの贈り物だ。厳しくて脆い。脆いから尊い。尊いから、無駄を許さない。無駄を許さぬ者は、遊びを忘れがちである。だから私は回り道をする。川沿いの小径へ、橋脚の影を踏むために。影は軽く、心は軽く、靴底だけが重い。重い靴底は、今日の地面を刻む。
夕刻、私は忌部神社の鳥居をくぐる。祭りのない日、境内は用件を持たない。用件のない場所は、ひとの品位を試す。品位は背骨であり、背骨は見えない。見えないものに礼をする練習を、私はここで続けている。拝は深くない。深くない礼には、深い気配がある。鈴の音が風に挟まれ、風が松の間を通って、まだ乾かぬ布に触れる。
私は賽銭を惜しまない。惜しまぬ金は、使えば忘れられる。忘れられる金は、善い金だ。忘れがたい金は、しばしば悪い。悪は額に刻まれる前に、指の節に現れる。節が固くなる前に、私は手を湯で温める。温めた手で、鳥居の木目を撫でる。撫でれば、木は言う。「持ち越すな」。
帰路、商店街のシャッターの前に、阿波おどりの古いポスターが貼られている。笑い方の古い顔。踊りの姿勢は、いまも古い。古いことは、浅いことではない。古いとは、深いことである。深いものは、すぐには役に立たないが、すぐには壊れない。壊れにくいものを選ぶのは、倹約ではなく、勇気だ。
夜、台所に火を点す。点火は祈りに似る。鍋の底に小さな宇宙が生まれ、塩が星のように散る。米が泡立ち、蓋が鳴る。鳴る音は、遠い渦潮に似ている。鍋の渦は、すぐに鎮まる。海の渦は、すぐには鎮まらない。鎮まらぬものに、ひとは教えられる。鎮める技ではなく、待つ徳を。
食後、私は机に向かい、今日の折り目を数える。布の折り目、言葉の折り目、心の折り目。折り目が多い日は、簡単に広がらない。広がらぬ日も、悪くはない。狭いまま温かい夜が、ひとつぐらいあってよい。
窓を開ける。夜風は藍の匂いを運ばないが、藍に似た規律の匂いを運ぶ。規律の匂いは、清潔と違う。清潔は洗い立ての白であり、規律は干し上がった影だ。影が揺れ、月が薄く、川が名を持つ。ようやく、私は言う。「吉野川」。
名を与えた瞬間、ものは過去を帯びる。過去を帯びた川は、古代からの贈答品となる。贈られた私は、礼を返さねばならぬ。礼は大きくなくていい。明朝、布を干し、靴を磨き、挨拶を先に言う。その程度で十分だ。十分が続くのが、豊かである。
床につく前、私は掌を合わせる。合わせた掌に、麻のささくれが触れる。触れた痛みは、微細で、覚えやすい。覚えやすい痛みは、忘れやすい悦びより信頼できる。信頼できる感覚が、私の祈りを支える。祈りは大袈裟でなくてよい。小さく、長く、同じ場所に置けばいい。
消灯。闇は粗い。粗い闇は、かえって目を休ませる。休んだ目で、私は明日の糸を視る。視えた糸は、まだ名を持たない。名のない糸を、私は指で撚る。撚りながら、ひそかに唱える。
—粗にして精。荒にして潔。徳は軽く、器は静か。
その唱えは、古い家の梁から降りてきて、私の枕元で止まる。止まった言葉は、やがて眠りに解け、眠りの底で、また布になる。布は朝に乾き、朝はまた、川の名を忘れる。忘れた川を、私はまた、名付ける。日々の麁服。
稲の梵鐘――東大寺阿波庄開拓記
夜は浅く、湿りは深い。
吉野の水はまだ名乗らず、葦は肩を寄せて眠っている。
僧は灯を囲み、木簡を伏せ、地図のない地図を指でなぞる。
—ここに溝を引け。—ここで堤を折れ。
言葉より先に、指が祈る。祈りは測量の初手である。
水は導きて田に満ち、
風は止みて稈を乾かす。
対を成すものは争わず、
ただ互いに相手を成り立たせる。
開拓とは、その礼譲に名を与える作法だ。
東大寺領・阿波某郷。
不輸の墨はまだ乾き切らず、
それでも鍬の先は朝の土に確かを求める。
土は黙り、しばらくのあとでうなずく。
うなずきは、最初の年貢より尊い。
僧形の監(げん)と在地の手が、同じ縄を引く。
縄は真っすぐを望み、川は曲がることを欲する。
真っすぐを曲げず、曲線を怒らせず、
人は間を選んで土地を得る。
間合いこそ、徳である。徳は軽く、器は静か。
杭は打たれ、杭の影が昼に伸びる。
影の長さが一日の教本だ。
刈敷が蒼く腐り、田面は甘い匂いで息をする。
牛が踏み、鋤が返し、
返された土の熱で、僧の読経も少しだけ早くなる。
藍瓶はまだない。
けれど水はあらゆる青を予感し、
麻はまだ衣となる日を知らないのに、
指の節はすでに麁服のしなやかさを覚え始めている。
作る前から、作られる形が手を教える。
昼下がり、堤の肩に柵が組まれ、
用水は新田へと分かれる。
分かれた水は恨まず、
ただ光の道を増やすだけだ。
増えた光に驚くのは、いつも人の方である。
庄官は帳に印を押し、
公文は重さを量る。
米は白い直線、麦は淡い曲線、粟は点の群れ。
点と線と曲線が、秋の一章を描く。
章の余白に、名もなき手の笑い皺が刻まれる。
—ここを掘れ。—ここで止めよ。
合図は短く、動きは長い。
短い言葉は重く、長い労は静かだ。
静かなものが、遠くへ届く。
梵鐘の音が山を渡るように。
夕刻、吉野川は眉のように低く稜を描き、
町はまだ輪郭に過ぎない。
しかし、輪郭は中身を呼ぶ。
草庵の煙、苗代の水皺、
鶴嘴の鉄が石を裂く明るい音。
声は少なく、仕事は多い。
多さを誇らず、ただ明日を軽くするために。
夜、僧は灯を絞り、
経を閉じて、掌で土の匂いを確かめる。
土は無数の生を記す史書で、
読めない字ばかりだが、指は文法を知っている。
触れて、置いて、待つ。
待つことが、もっとも難しい技だ。
雨期は試す。
水位は句読点を失い、
堤は一瞬だけ、ためらいの顔を見せる。
その顔に、在地の衆は肩でうなずく。
「ここで逸らせ」「ここで抱け」
命令ではない、古い相談だ。
相談の古さが、流域の倫理である。
やがて秋。
稲は傾き、米は軽く重い。
軽い重さを背負って、舟が出る。
撫養へ、小松島へ、
海口は口をすぼめ、また笑う。
笑いに似た白波を越え、
米は寺へ、灯へ、声へと変わっていく。
年貢は寺を太らせたか。
いや、声を太らせた。
太い声は権を呼ぶか。
いや、遠くを慰めた。
慰めは、国を治めはしない。
けれど、働く者の背骨をまっすぐにする。
幾歳月。
荘は移り、印は薄れ、
条里の線は草に飲まれ、
鍬だけが、空気の中で光る。
光の細さに、私は今日も目を細める。
細いものほど、歩みを続ける。
現代。
重機が入り、法面は美しく均され、
堤の内側に公園の芝が伸びる。
子が走り、犬が吠え、
ベンチの裏で、しずかな水が動く。
遠い木簡の行は読めない。
しかし、溝の角度はまだ残っている。
残るべきは、たいてい角度だ。
角度が暮らしの姿勢を決める。
私は堤の上で弁当を開く。
米は白く、海苔は黒い。
白黒のあわいに、僧の影が薄く立つ。
影は説教をせず、
ただ私の箸の速度を少しだけ遅くする。
遅さが礼で、礼が腹を温める。
夕映え、橋脚が長く水面を渡る。
水は古く、町は若い。
古いものは急がず、若いものは待ちきれない。
その間に暮らしはある。
東大寺の名は遠く、
しかし、耕された地の癖は近い。
癖のやさしさに、私は頭を下げる。
夜更け。
風が稲の夢を撫で、電灯が小さく瞬く。
私は胸の中で短く唱える。
—守って流し、流して守る。
—粗にして精、荒にして潔。
唱えは誰のものでもない。
僧のものでも、在地のものでも。
ただ川の呼吸が借りてきた、作法の骨子である。
やがて闇は粗く、
粗い闇が目を休ませ、耳を澄ませる。
耳の底で、遠い梵鐘が鳴る。
鐘は金ではなく、稲でできている。
稲の梵鐘は、明日の腹で鳴る。
腹の音が、国の静けさになる。
静けさの上に、橋がかかる。
橋の上で、私は小さく会釈する。
—この地を耕した手へ。
—この水を受けた堤へ。
—この音を今に運んだ、無名の角度へ。
豊野真人篠原伝――阿波国司記(評伝散文詩)
天平勝宝の空は薄藍、任命の文は黒々と。
詔の端はまだ乾かず、官人たちの声は乾いていた。
—阿波守、豊野真人篠原。
名を呼ぶ声が一度だけ強く、あとは静かであった。
静けさは、遠さの別名である。京から瀬戸へ、瀬戸から眉の山へ。
舟は潮を量り、馬は風を辿り、国司は地図のない地図を胸に折り畳む。
赴任の日、彼は掌を洗った。
「徳は軽く、器は静か」
その一句を、父より受けた。
軽い徳は声を上げず、静かな器は遠く届く。
届くべき先は、未知の川原、未詳の条里、まだ名を持たぬ田の呼吸。
一 着任
国庁は、まだ仮の姿だった。
柱は若く、屋根は風に驚き、机は墨の重さを知らない。
「戸籍の名は正しく、租は等しく、労は軽く」
彼は三つだけ紙の上に記し、筆を置いた。
記すことは容易い。難しいのは、名を持たぬ顔に名を与え、
税の数字に体温を与え、労の一歩に道を与えることだ。
郡家の古老は語らない。
語らぬ代わりに、苔むした洪水碑を示す。
—ここまで来た年があった。だが、ここで止まった。
止まった理由を、人は功績に取りたがる。
彼は頷き、功を数えず、角度を測る。
堤の肩はわずかに寝て、用水の口は僅かに閉じる。
僅かさが、暮らしの胆力である。
二 政務
春、彼は調を軽くした。
遠い浜の貝は免じ、山の薪に小さな印を押す。
「遠きを軽く、近きを等しく」
等しさはときに不公平に見える。
だが、不満の声と同じ数だけ、胸の奥で礼が灯る。
礼の灯りは報告書に記されない。
記されぬものが、国を支える。
戸籍の改竄を告げる訴えがあった。
名は長費か、長直か。
証拠は薄く、感情は濃い。
彼は紙をめくるのをやめ、当人の手を見た。
節の角度、爪の傷、握るときの力の順。
「名は器に従え」
紙の字は戻され、手は仕事に戻った。
――この判断を、後年、人は軽いと言い、重いと言った。
軽さは慈悲に似て、重さは威に似る。
彼はどちらにも与しない。与せぬことが、最も重い。
三 開拓
夏の前、条里を引く。
縄はまっすぐを望み、川は曲がることを欲する。
真っすぐを曲げず、曲線を怒らせず、
人は間を選んで土地を得る。
間合いこそ徳。徳は軽く、器は静か。
杭が打たれ、杭の影が昼に伸びる。
影の長さが、一日の教本だ。
石樋が据えられる。
水は音を立てずに膝を折り、
新田へ入るときだけ、わずかに笑う。
笑いは泡の輪で、輪はすぐ消える。
消える印が好い。
残りすぎる仕事は、誰かを縛る。
彼は痕跡を薄くし、効能を深くしたいと願う。
深さは報われにくい。だが、長く持つ。
四 祭祀
やがて疫が走った。
家々の灯は青く、井戸の縁は白い。
彼は剣を持たず、火を持った。
日峰の山に登り、古き式に倣い、火焚の座を組む。
火は祈りの最短距離で、祈りは労の最長距離だ。
薪は湿り、始まりは遅い。
遅さが礼で、礼が人をつなぐ。
—風よ止め、火よ上れ、
—祖の名、ここに在れ。
夜半、火は柱となり、
翌朝、病の足は僅かに鈍った。
鈍りは救いで、救いは誰のものでもない。
ただ山の空気が、ひと晩だけ古代に戻った。
五 幸
秋、稲は傾き、船は出る。
撫養へ、小松島へ。
年貢は白く、笑いは薄く、息は深い。
深い息が町の背骨を伸ばし、
伸びた背骨が次の畝をまっすぐにする。
郡家の子は文字を覚え、
漁師の妻は針目を細かくし、
職人は刃を新しく研いだ。
—国司殿の功にあらず。
彼はそう書き付け、印を押さなかった。
功を名乗らぬことが、功の形である。
六 不幸
冬、訴えは増える。
等しさは誰かにとって損で、
軽さは誰かにとって怠惰だ。
彼は夜更け、灯をひとつ減らす。
減らした暗がりで、耳だけを働かせる。
嫉妬の音、恐れの音、子の咳の音。
音の秩序を取り戻した時、
紙の秩序は自然に整う。
だが、すべては間に合わない。
間に合わぬことで人は老い、
老いは判断を鋭くも鈍くもする。
ある夜、遠い都から書状が届く。
功も罪も記されず、ただ短く、
—留意せよ。
留意は讃美でも叱責でもない。
留意とは、孤独の別名である。
旱の年、彼は雨乞を許し、
洪水の年、彼は堤に立った。
乾く罪と、溢れる罪。
どちらも国司の罪で、どちらも国司の力を超える。
彼は罪の名を借りて、自らの慢心を砕いた。
砕かれた器は、なお水を湛える。
破片の隙間に、礼が宿る。
七 家
京に残した妻より、短い文。
—子、無事。
無事の二字が、最も重い。
重さは肩で受け、彼は返事を書かず、
翌朝、戸籍台帳の埃を払った。
払う所作が祈りで、
祈りは長く、書状は短い。
短さは愛の器だ。
八 余白
任期の終、彼は川原に降りた。
石は丸く、風は新しく、眉の山は低く笑う。
彼は手を川に入れ、名を呼んだ。
—阿波。
名は遠く、しかし確かに振り向いた。
振り向いた気配が、彼の胸を少しだけ軽くした。
軽さは別れの礼である。
送別の宴で、彼は語らない。
語らぬ代わりに、盃の影を見つめる。
影は黒く、黒は軽い。
軽い黒は、音を遠くへ運ぶ。
遠くで子の笑い、近くで湯の音。
どちらが国か。どちらも国だ。
国は紙の上に在り、また台所にも在る。
彼はその両方に印を押す術を、
任期の終わりにようやく知った。
九 帰京
帰路、海は穏やかで、
穏やかさは不安の別名でもあった。
都は評議を重ね、讒も賞も等距離に置く。
彼は呼ばれ、あるいは遠ざけられ、
やがて別の官に就いたと記録は言う。
記録が語らぬのは、胸の中の角度である。
角度が暮らしの姿勢を決める。
阿波で覚えた角度は、
彼の背を小さく前へ押し続けた。
十 跡
国庁の庭に植えた楠は、
今も風の文法で葉を鳴らす。
条里の線は草に隠れ、
用水の口は石の色に溶け、
洪水碑の苔は、年ごとに緑を増した。
増えた緑は、誰の功でもない。
功の名は消えても、
角度だけが残る。
残るべきは、いつも角度だ。
角度が人をまっすぐにし、
まっすぐさが、やがて誰かの秋を軽くする。
——
豊野真人篠原。
その名は歴史の欄外に細く、
しかし、暮らしの中に太い。
太さは声ではなく、作法の骨子である。
守って流し、流して守る。
粗にして精、荒にして潔。
彼が阿波で学び、阿波に残したのは、
その二行、ただそれだけ。
それで足りる。
足りるものは、長く持つ。
行基—阿波の水脈(散文詩)
夜は浅く、湿りは深い。吉野の水は名を名乗らず、眉の山は眉のまま、まだ言葉を持たない。行基は杖の先で砂利を撫で、川の呼吸を測る。測りは祈りに似て、祈りは測量に似る。
—ここで折れ、ここで抱け。
水は反駁せず、ただ音を低くする。
水は導きて田に満ち、風は止みて稈を乾かす。
対を成すものは争わず、ただ互いに相手を成り立たせる。
開くことを開拓と呼び、結ぶことを橋と呼ぶ。
橋と田、その間に人がある。人の間に法がある。法の間に情がある。
阿波の野はまだ若い。忌部の古き家は黙り、藍はまだ瓶の底で眠る。
行基は名を刻まず、角度を残す。用水の口は僅かに閉じ、堤の肩は僅かに寝る。
僅かさが暮らしの胆力である。大工は頷き、農は汗を拭き、子は石を積む。
「徳は軽く、器は静か」
彼は誰にも向けずに言う。軽い徳は遠く届き、静かな器は長く持つ。
朝。
霊山寺の前身に火が点り、極楽寺の地はまだ草の香を手放さない。
行基は梁を見、土を捏ね、尺の影で季節を読む。
読まれるのを土は嫌わぬ。読まれぬままでは人が困る。
田は人を招き、橋は人を渡し、寺は人を坐らせる。
坐らせるために、彼はまず歩く。
昼。
堤に杭が打たれ、石樋が据えられる。
水は膝を折り、田に入る時だけわずかに笑う。
笑いは泡の輪で、輪はすぐ消える。
消える印が好い。残りすぎる仕事は誰かを縛る。
彼は痕跡を薄くし、効能を深くしたいと願う。
深さは報われにくい。だが、長く持つ。
午後。
説法は短く、手順は長い。
「功徳はここに」(胸を指す)「利益はそこに」(田を指す)
人々は頷き、鍬を取り、溝に影を落とす。
影の長さが一日の教本だ。
藍商の先祖は目を細め、漁師は潮目を思い、巡礼の笠は静かにうなずく。
道はまだ八十八へと弧を描かないが、弧の気配は草の擦れに宿る。
夕。
橋脚の足元で、行基は子に問われる。
「僧はなにを食べて歩くのです」
「明日の礼だ」
彼は笑い、米を分け合い、器の欠けを指で撫でる。
欠け目に由緒が宿ることを、器のみが知る。
器は説教しない。光を受けて、ただ静かに在る。
夜。
眉山の黒が低く、町の灯は少なく、川音だけが律を持つ。
行基は帳に印を押さない。印を欲すれば名が重く、名が重ければ川が鈍る。
彼は名を川に預け、ただ角度を残す。
角度が暮らしの姿勢を決める。
阿波は角度で立ち、角度で眠る。
年が巡る。
旱の年は火を讃え、洪の年は土を讃える。
人はどちらの年にも僧を讃えたが、行基はどちらの年にも川を讃えた。
「守って流し、流して守れ」
彼の句は短く、手順は長い。
長い手順は退屈に似て、退屈は祈りに似る。
祈りは火ではなく、灰の働きだ。灰は声を上げず、遠くまで届く。
やがて都より勅。
大仏の鋳型が国々へと影を落とす。
阿波の米も、木も、人の背骨も、遠い銅の光に向かって少しずつ傾く。
行基は頷く。
「寺は遠く、田は近い。遠きを照らす灯は、近きを曇らせるな」
彼は供出の手順を軽くし、残る飯を子に回す。
残るべきは、いつも温度だ。熱の礼が、翌日の労を軽くする。
伝説は増える。
池を掘れば「行基の池」、橋を架ければ「行基の橋」。
彼は笑い、「名は器に従え」とだけ言う。
器が静かなら、名も静かになる。
静かな名は、長く持つ。
ある朝、霧。
吉野の水面は紙の白で、舟の影が墨の一点。
行基は杖を立て、耳で川を視る。
音の等間隔が乱れる場所、そこに手を入れよ。
乱れを鎮めるのではない。乱れに居場所を与えるのだ。
水の倫理は、町の倫理に変換される。
叱るより、位置を与える。止めるより、道を逸らす。
別れは唐突だったとも、ゆっくりだったとも伝える。
彼は多くを言わず、多くを置いて立った。
置かれたものの名は、角度、影、拍、そして礼。
礼は形式ではなく、速度である。
急ぐべき時にゆっくりし、ゆっくりすべき時に急がない。
その遅速が、阿波の水脈になった。
現代。
撫養の風は塩を運び、小松島の岸では犬が吠え、
眉山の影は相変わらず低く、人々の歩幅は相変わらず一定だ。
一定は退屈に似て、退屈は祈りに似る。
台所の蛇口から落ちる直線が、鍋の底で円になる。
直線から円、円から湯気、湯気から明日。
その簡素な変換の上を、行基の名のない橋が、いまも人を渡している。
——
稲の梵鐘は金ではなく、腹で鳴る。
その音を聞き分ける耳を、誰が阿波に置いたか。
行基という名を呼べば、彼は否むだろう。
「名は川へ、功は土へ。私は間を歩いただけだ」
間を歩いた者の足跡は浅い。
浅いから、長く残る。
浅いから、誰の足でも重ねやすい。
その歩幅で、きょうも堤の草が揺れ、
藍の瓶は静かに呼吸し、
子は石を積む。
阿波は角度で立ち、角度で眠る。
行基の仕事は、ただその一行—
守って流し、流して守る—
を、水脈に書き込んだ。