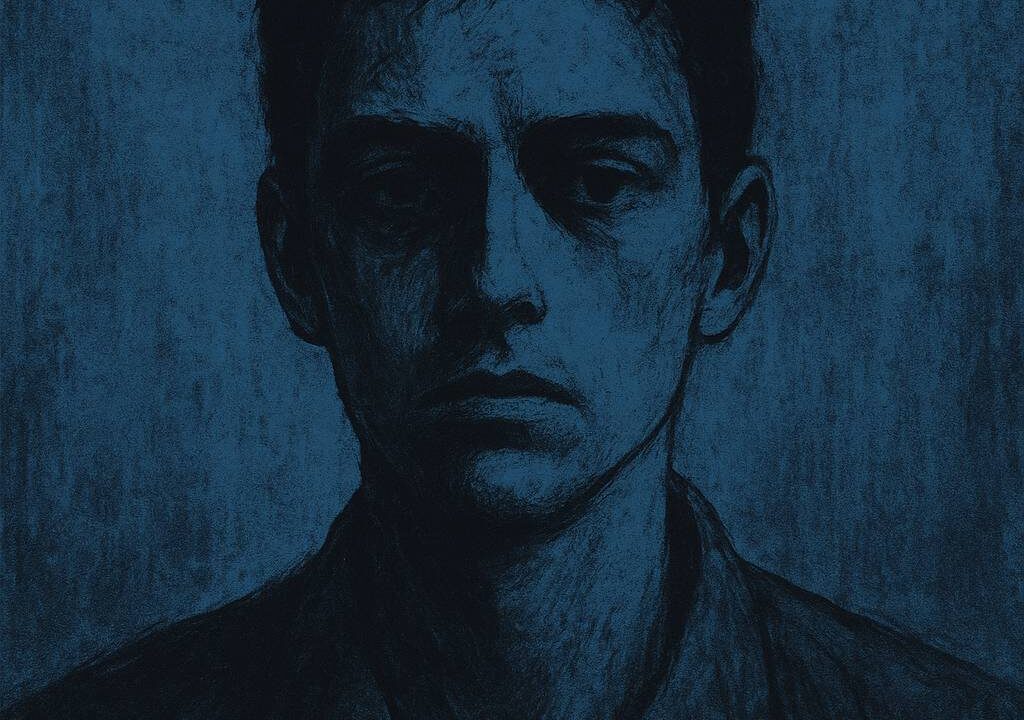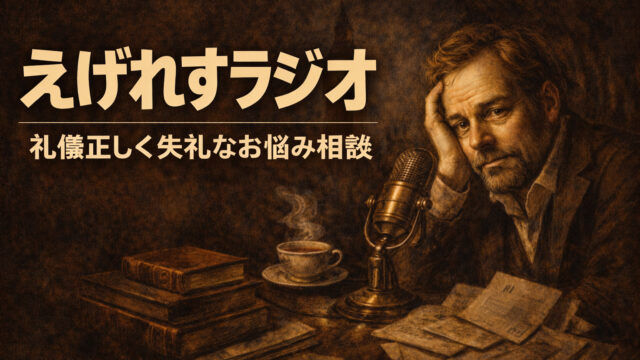【現地到着から採用面接、観光、帰国まで】
半隠遁者のベトナム出張 上巻 発売中!
【1】機内への侵入
ハノイ行きの飛行機は、定刻通り出発予定とのアナウンスが流れた。空港の雑踏に埋もれた機械的な声が、まるで巨大な工場で流れる昼休み終了のサイレンのように聞こえる。これから数時間、私たちは「労働」と「余暇」のあいだに宙吊りにされる。
今回のフライトでは、座席は互いに離れた配置になっていた。これは同行のトンさんの気遣いによるものだろう。数日間、四六時中顔を突き合わせる旅程を考えれば、機内でまで同じ相手と呼吸を合わせる必要はない。むしろ、孤独の時間こそ人間にとっての救済だ。誰とも話さない時間が私を深海へと誘って行く。今後の人生についての思索を深めていく。
私は心底ありがたく思った。さすがは百戦錬磨のトンさんだ。管理団体の理事長という肩書きに恥じず、人の心理の隙間に水のように入り込み、適度な距離を確保してくれる。水のように千変万化し、どのような環境でも適応していく生存本能。これができるからこそ、彼は「やり手」なのだろう。私なら、こうした配慮をする前に根を上げてしまっているに違いない。戦場から逃走する逃亡兵となるだろう。そして、軍法会議にかけられ処刑されていく。
搭乗アナウンスに従って、私たちは順々に鋼鉄の筒へと吸い込まれていく。ベトナム航空のエコノミークラス。庶民の檻。機内の座席は工場の作業台と同じだ。割り当てられた区画に腰を落とし、四時間という生産工程に耐える。成果物はハノイへの到達、それだけだ。各自の作業内容は一任される。今回のフライトではどのような工程を組んでいこうか。飛行機の中でさえサラリーマン根性が抜けない自身に少しだけ苦笑いした。
昼食を挟むとはいえ、四時間は長い。窓の外には蒼穹、眼下には雲海。だが、それらは私を解放しない。むしろ「空を飛んでいる」という非日常のはずが、座席に縛られた瞬間に「地上の労働」となんら変わらぬ日常に転化してしまう。航空機とは奇妙な存在だ。自由の象徴であるはずなのに、乗客に強制されるのは窮屈な姿勢と不自由な移動だ。
リリエンタール以降、人類は空を飛ぶことに躍起になってきた。ライト兄弟もそうだ。今では空を飛ぶことに何の感動も疑問もない。平気で宇宙に行く時代だ。飛行に憧れた人類が到達したのは、長時間にわたって鋼鉄の箱に収容される禁固刑だ。
ふと、私はこのフライトに小さな社会の縮図を見た。ファーストクラス、ビジネスクラス、そしてエコノミー。座席がそのまま階級を表している。そこには努力や人柄の余地など一切ない。単純に金銭が支配する。資本主義の真髄がここに凝縮されている。
フランス国民はこの現状をどう思うだろうか。大革命を経て王権を断頭台に送り、平等を掲げた民衆が、いまだ鉄の檻の中で分断されている。頭上には「自由・平等・友愛」という標語が霞のように浮かんでいるのに、足元ではビジネスクラスとエコノミークラスの差が歴然と存在する。雲海のように掴み取れない虚像になってしまっている。
血と硝煙で築き上げた共和制は、結局のところ、座席の広さとワイングラスの厚みで再編成されてしまったのか。マラーやロベスピエールが、この機内を見たら何を言うだろう。「人民の勝利だ」と讃えるのか、それとも「ブルジョワの衣替えにすぎぬ」と断罪するのか。
鉄と血の時代を再び呼び戻す必要はないのかもしれない。革命の理念は飛行機の座席表にまで浸透していない。だが、逆に言えば金銭で座席を買い替えることができるという現状は、身分の固定化よりも幾分ましな光景かもしれない。血統や特権ではなく、クレジットカードの限度額で身分が入れ替わる世界。現代人はそれを「平等」と呼ぶのだろう。
私はエコノミーの狭い座席に腰を沈めながら、ルソーが「人間は自由なものとして生まれた」と言ったことを思い出す。なるほど、自由ではある。自由に選んだ結果、この窮屈な座席で4時間を過ごす羽目になっているのだから。もはや私はタブラ・ラサではない。神の手から俗界へと舞い降りたのだ。選択の自由という名の鎖。そういえばサルトルもフランス人ではなかったか。自由の刑。そう考えると、隣の座席の肘掛けの取り合いもまた、近代自由主義の縮図に見えてくる。
私は当然ながら労働者階級、すなわちエコノミーに身を置く。王侯貴族のような席には座れない。だが、資本主義は残酷であると同時に滑稽でもある。努力と偶然の積み重ねで、明日はビジネスクラスに座れる可能性もある。いや、もしかすると一生座れないかもしれない。
それでも人々は「のし上がれる」と信じ、働き続ける。まるでベルトコンベアに乗せられた工員のように、今日も機内で規律正しくシートベルトを締める。だが、あくまでもそれは資本主義という舞台の上だけの条例。舞台が変わると戦術も変化を生む。自分がどの舞台にいるか、どのように生きていきたいかを熟考する必要がある。
思えば歴史上の多くの思想──社会主義、共産主義、独裁主義──は、この資本主義の滑稽さを是正しようとして生まれては消えていった。だが結局のところ、私は日本という自由資本主義の国に生まれ、今日もこの機内で「等級に従って座る」ことを受け入れている。それを滑稽と呼ぶべきか、自然の摂理と呼ぶべきか。答えは曖昧なままだ。この等級と囚人番号の違いはなんだろうか。
ハノイまでの四時間。鋼鉄の箱に押し込められ、海を越え、山を越え、国境を越えていく。その道中で私が得るものは、せいぜい味気ない機内食と、哲学的な虚無感くらいだろう。それでも、虚無に価値を見出そうとするのが人間なのだ。ムルソーのように「太陽が眩しかったから」と言い訳しながら、私もまた、この不条理なフライトを受け入れていくのだ。
【2】初老の紳士風ベトナム人
乗務員の挨拶に迎えられながら自身の席を目指す。自分の席に腰を下ろし、シートベルトを締める。窓の外では滑走路が陽光を浴びて白く光り、まるで巨大な工場のベルトコンベアのように、飛行機という鋼鉄の製品が定刻通りに流れ出していく。
航空会社のスケジュールもまた、巨大な製造ラインの一部に過ぎない。サラリーマンの朝の出勤と同じく、遅延は許されない。だが同時に、そこには人間的な自由も創造性もない。私はいま、巨大な歯車の中で回されるボルトの一つに過ぎないのだ。
飛行機は定刻通りに離陸した。快晴。雲一つない青空を突き抜け、しばらくして揺れもおさまり、安定飛行に入った。つまり、ここからが空中の昼休み。機内サービスという名の慰労会が始まる。CAたちは笑顔を浮かべたまま、工場の検品係のように通路を行き来し、ドリンクという報酬を労働者たる我々の前に差し出す。
私は無難にアップルジュースを選んだ。濃厚でも薄くもない、なんとも中庸な味が、かえってこの不条理な時間を際立たせる。ひと口飲むと、喉の奥にひやりとした爽快感が広がった。気がつけば、それだけで一つの仕事をやり遂げたような錯覚に襲われる。まるで工場の持ち場でボタンを一つ押し、今日も無事に製品を流したぞと胸をなでおろす瞬間のようだ。
ぼんやりと窓の外を眺めていると、不意に低い声が横から投げかけられた。隣の席に座る初老の男が、私に向かって何事か話しかけていたのだ。しわの刻まれた顔に濃い眉毛、小柄ではあるが多くの経験を積んできたことを匂わせるような風貌だった。深い皺は、ハノイの湿度よりも長い時間を刻んできた証拠だろう。皮膚に染み込んだ煙草と魚醤の匂いが微かに漂い、妙に安心させられる。瞬時に気づく──これはベトナム語だ。久しぶりの実戦に思わず冷や汗が出る。大学時代、第二外国語として学んだ記憶を必死に掘り起こしながら、私はつっかえつっかえ返答する。
「……ベトナムは、初めての訪問です。」
すると、初老の男はにやりと笑い、会話を続けた。どうやら彼は送り出し機関に実習生を紹介する、いわばブローカーのような存在らしい。技能実習制度を骨の髄まで知り尽くした語り口は、どこか胡散臭さを漂わせながらも、同時に知性とユーモアを忍ばせていた。
「日本の工場は、規律が厳しい。だが、我々の若者は、そこに希望を見出すのです。」
「それは立派なことですね。ただ……規律は時に檻のように息苦しいですよ。」
「そうですな。しかし、檻の中でも成長する獣は強くなる。自由すぎる獣は、すぐに飢えて死ぬ。どちらの獣になるかは各々の自由。」
会話の端々に、不穏さと哲学的な響きが交錯する。彼の手首には分厚い金時計が光っていた。随分と羽振りがいいようだ。制度の闇を食い物にしながらも、どこかで合理と不条理を弁えているのだろう。私は再びアップルジュースを口に含みながら思った。──この男と私の違いは何だろうか。私は労働者を送る側に加担するただの歯車、彼は歯車同士を繋ぐ潤滑油。どちらも同じ機械の中で擦り減っていくだけの存在ではないか。
「あなた、日本人にしてはベトナム語が上手い。どこでベトナム語を?」
「恐縮です。大学の第二言語で学習していました。ただ、ブローカーと会話する訓練は受けていませんから。」
「ははは、訓練のない会話が一番面白いものです。こういう仕事をしていると杓子定規な会話に飽き飽きしてしまいますからな。特に日本人は堅い挨拶がお好きだ。」
初老の笑い声が、機内のエンジン音に溶けていった。日本人への少しばかりの皮肉を聞きながら、ベトナムという国の影を、まだ到着前から垣間見た気がした。この制度には私の知らない闇がまだまだある。現地ではその闇を垣間見ることは難しいかもしれない。いつだって真実は隠されて行くものだ。
「初めてのハノイですか?」
「ええ、そうです。」
私は素直に頷いた。
「そうですか。ハノイは美しい街ですよ。ただし、あなたが“美しい”と呼ぶ基準にもよりますが。」
言葉の端に毒があった。まるで美しさという概念そのものを疑っているようだ。
「基準は曖昧ですからね。日本でも、工場の煙を“経済の美”と呼んで喜んでいた時代がありました。今では排煙規制のおかげで、煙が少なくなるほどに不安を覚える工場経営者もいるでしょう。」
彼は私の皮肉を聞いて、皺の奥に埋め込まれた眼を細めた。
「なるほど。あなたは哲学者ですか?」
「いいえ、ただの労働者です。魚を捌いて、味をつけて、パックに詰める。知的生産とは程遠い仕事です。」
「それでも哲学は可能ですよ。プラトンは市場を歩きながら、マルクスは工場を見学しながら考えました。労働は哲学の母です。」
私は頷いた。確かに、うちの工場でも労働者はよく哲学している。なぜ給料は上がらないのか、なぜ上司は太るのか、なぜ人は働くのか──。実に形而上学的な議論だ。
「あなたの国は不思議です。」
と初老の男は続ける。
「戦争では負けたのに、いまや我々に工場を持ち込み、人を送り込み、教育まで施している。勝ったのか、負けたのか、分からなくなる。」
「勝った者も負けた者も、結局は労働者になりますよ。勝者は労働者を安く使いたい。敗者は働き口を求めて安く働く。どちらにせよ汗を流すのは同じ人間です。いずれにせよ資本主義という舞台の上で踊る舞子のような存在です。」
「ふふ、そういう考え方はベトナム的ですね。いや、ベトナムだけではないか。資本主義人的思索といったところか。」
一人で自問自答している自分が可笑しくなったのか、彼は笑いながら、機内サービスの温い水を一口すすった。
「あなたは、人生に勝ちたいですか?」
「勝ち負けに興味はありません。ただ、無駄に苦しまずに、無駄に楽しめれば十分です。」
「ショーペンハウアーのようなお人だ。人生を何度も周回したような台詞回しだ。確かに無駄こそ人生ですからね。」
その言葉には、奇妙な説得力と知性とユーモアがあった。これまで積み重ねてきた教養の産物だろうか。
「そういえば、フランス人はこの現状をどう思うでしょうね。」
私は少し考えて口に出した。
「革命を成し遂げた国なのに、座席ひとつで階級差が復活している。『人間は平等である』と高らかに宣言した割に、今もエコノミーとビジネスとファーストの格差に揺れている。結局、階級は形を変えて温存されているのかもしれません。」
「ええ。だから彼らはワインを飲んで忘れるのです。ベトナム人はビールで忘れます。日本人は何で忘れるのです?」
「焼酎ですかね。あるいはテレビのワイドショーで他人の不幸を眺めるとか。」
二人で乾いた笑いを漏らした。
「日本はまだまだ人手不足ですか?」
と彼が問う。
「ええ、慢性的に。求人を出しても応募者すら来ません。」
「ベトナムも似たようなものです。ただ、こちらは若者が多い分、仕事を求めて外へ出るのです。ベトナムの外貨稼ぎは海外の出稼ぎ労働者が大きく貢献しています。昔からそのような伝統があるので、若者も海外に行くことを躊躇しません。仕送りのお金で内需が拡大し、経済が発展していく。いずれは出稼ぎの規模は縮小するでしょうが根絶はしないでしょう。」
彼の分析は鋭利な刃物のようだった。現状を正確に射抜いているかと思いきや、時折混ぜ込んでくる皮肉とユーモアで笑いを取る。日本人やドイツ人に教えてもらいたいほどの話術だ。おそらく英語も流暢に話すのだろう。世界を股にかけるビジネスマンの掟だからだ。
ブローカーはさらに続けた。
「結局、社会はどこでも階級ですよ。カネを持つ者、持たぬ者。東京もハノイも同じ。共産主義?社会主義?看板が違うだけで、人はやっぱり上と下に分かれるのです。」
まるで革命の亡霊が横で囁いているような言葉だった。私は窓の外を見やった。雲海の上を進む鋼鉄の箱。ここにも階級はある。ビジネスクラスの椅子は、あたかも玉座のように前方に並んでいる。私はもちろんエコノミー。労働者階級の群衆に紛れ、膝をすり合わせながら過ごす。社会学の教科書の縮図がここにある。
フランス人がこの光景を見たらどう思うだろうか。バスティーユを襲撃したあの群衆も、結局は今のように「シート幅」という新しいヒエラルキーに従っている。革命は成ったのに、階級は座席の等級として蘇る。捲土重来とはこのことか。いや、むしろ「カネで座席を買い替えられるのだから自由の勝利だ」と喝采を送るかもしれない。
そう考えると、現代日本のサラリーマンの姿が重なった。週5日間、朝8時から夜遅くまで労働に押し込められ、昇進の座席はいつまでも空かない。上司はビジネスクラスに座り、下っ端はエコノミーに縛り付けられる。たまに奮起して「努力すれば昇格できる」と言われても、実際にはマイレージ不足で格上げされることは滅多にない。
ブローカーはにやりと笑ってこう締めくくった。
「人は自由に見えて、結局は座席指定ですよ。」
その言葉は妙に腹に落ちた。私は目を閉じ、機内の振動に身を任せた。考えても仕方がない。むしろ、チャイティーのようにスパイスが効いた不条理を楽しむしかない。甘さと苦さの入り混じる液体を啜るように、人生の矛盾を飲み込む。
その瞬間、私は奇妙に落ち着いていた。これから待ち受けるベトナムの現実も、きっと同じだ。甘さと苦さ、光と闇。結局、全部まとめて飲み干すしかないのだ。
【3】機内食と工場労働
その後しばらく沈黙が続いた。機体は安定飛行を続け、窓の外では雲がただ白いだけの存在として広がっていた。私は思った。この雲の上では、勝者も敗者も、王も奴隷も存在しない。あるのはシートに押し込まれた人間の群れだけだ。天空の牢獄だ。
しかし、着陸すれば再び階級と労働が支配する現実に戻る。みな資本主義というベットタウンに帰っていく。99の労働と1の安らぎ。そう考えると、今ここで交わした会話も、やがてどこかに消え去るのだろう。吹けば飛ぶ埃のように。無駄で、しかし必要な言葉として。
そうこうしているうちに機内食が配られた。白いトレイに整然と並ぶ料理は、どうにも大量生産された工場製品のようで、温かみと冷たさが同居している。メインは鶏肉のトマト煮込み。機内特有の加圧式オーブンで蒸し焼きにされたせいか、妙に水っぽく、それでいて塩味だけは過剰に主張している。付け合わせには白飯が控えている。日本米ではないらしく、粒が立たずにベタリと張りつく。それでも、腹を満たすためにはありがたい存在だ。
天空の檻の中で食べる囚人飯。といっても腹はしっかりと満たされ、少しも貧相な感じはしない。生まれつきの貧乏舌のせいか何でも美味しくいただける。知人の中には機内食など食えた物ではない、と言う者もいる。肥えた舌には味気ないのだろう。
どちらが幸せなのだろうか。肥えた舌と貧乏舌。無論、お金がかかるのは肥え舌だ。しかし、世界の珍味を知っているというのも悪くない。経験の積み重ねが人生なのだから。食の経験も多いに越したことはない。
かく言う私はメリハリをつけている。日常生活は自炊を中心とした粗食に勤しんでいる。外食はしない。友人、恋人との旅行、会食などでは多いにお金を使う。久しぶりの外食は何とも美味いのだ。
パンが一つ添えられている。小さな丸パンで、やや乾いていて表皮がパリッと硬い。中身は不思議と空洞が多く、口に入れると水分を奪われる。バターの小袋を塗りたくると、少しは人心地がついた。
デザートはチョコレートムース。どこか人工的な甘みで、口内にいつまでも残り続ける。まるで「甘美な後悔」のように。失われた青春の帰還。飲み物は赤ワインか、コーラか、あるいはオレンジジュースか。私は迷わずオレンジジュースを選んだ。少量だが、旅の始まりにふさわしい儀式のように思えた。酒盃は現地までお預けにしておこうと思う。
思えば、機内食とは縮図だ。国際線の狭い座席に押し込められた乗客たちに、均一化された「幸福」が配布される。これは小さな資本主義社会。長時間のフライトという労働を課された労働者である我々は同じ定食を口にする。飲食で束の間の安らぎを得る。ランチタイムのサラリーマンのように。そして粛々と労働に戻っていく。
ビジネスクラスやファーストクラスでは、きっともう少しマシな食事が供されるのだろう。そこでもまた階級差が口に運ばれる。革命後のフランス人が見たら嘆くだろうか、それとも笑い飛ばすだろうか。結局のところ、人類は胃袋の中にまで階級を輸出してしまったのだ。だが、不思議と嫉妬や憎悪はない。この労働者然とした待遇が気持ち良く感じられる。自身の隠されたマゾヒズムに浸りながらハノイへのフライトは続く。
パンを噛み締めながら、私はふと思う。ベトナムに着けば、これとは正反対の食文化が待ち受けているのだろう。路上に並ぶ屋台のフォー、油にまみれたバインミー、独特の香草の匂いが鼻をつくブンチャー。鶏の内臓、カエルの唐揚げ、ドリアン。
いずれも現地人にとっては日常の糧であり、我々には冒険の対象だ。日本の労働者が昼休みにコンビニ弁当を頬張るのと同じように、彼らはプラスチック椅子に腰を下ろし、汗を流しながら食べる。その違いは、文化の厚みか、気候の熱気か。全てが奇異に感じるが、同時に日常でもある。海を越えるだけで世界が一変する。文明も未開もない。人間の営みがそこにあるだけだ。
私は硬いパンをもう一口かじる。味気ないが、これもまた旅の序章だ。ベトナムの街角で本物の香辛料に舌を痺れさせるその瞬間を想像すれば、この工業製品のパンですら有難い前菜のように思えてくる。オレンジジュースの酸味が喉を焼き、私は小さく笑った。不条理で不格好な食事でさえ、旅への欲望を否応なく煽ってくれるのだから。
機内食を平らげると、私は素知らぬ顔でトレイを片付け、背もたれを少し倒して本を開いた。タイトルは『イギリス紳士のユーモア』。よりによってベトナム行きの機内で読むには不釣り合いな一冊だ。植民地帝国だったイギリス。ベトナムはフランス統治だったが、憎き帝国主義国家には違いない。だが、私はわざとこの選択をした。周囲がハノイ到着後の予定に浮き立つ中、私の頭の中だけロンドンの霧に包まれていた。
ページをめくるごとに、紳士の教養や趣味、服装や振る舞いが並んでいる。朝は新聞と紅茶、昼はランチとジョークを交えた会話、夜は暖炉の前で読書。規律ある退屈の美学だ。私は不意に思う――工場でゴム長靴を履き、魚をさばいて塩水に浸す私のような人間にも、この「紳士の嗜み」なるものは移植可能なのだろうか。
イギリス人はよくパブに出かけていく。日本のコンビニ並みにパブが存在する。そこで一杯ひっかけ寛ぐ。悠々自適の紳士生活。現代の紳士はフォーマルな時間にはパリッと決め、日常生活ではラフな服装を好む。一見、これが紳士なのかと疑う容姿。しかし、中身の教養は本物。
ナイフとフォークの扱い方や、スリーピースの着こなしはさておき、ユーモアの精神は万人に開かれているはずだ。労働者が汗をかきながら発する一言が、時にサロンの機知を凌駕することもある。だが現実はどうだろう。ライン作業での冗談は「早く手を動かせ」という上司の一喝にかき消される。遊び心もあったものではない。知性やユーモアは心の余裕あっての営みなのだ。
上司の一喝の後には、魚の目玉より冷たい笑いしか残らない。冷たくなった魚のようにユーモアも冷えていく。知性がこの世を去って行く。これを紳士的と呼べるかは怪しい。知性もユーモアも工場労働という騒音に抹殺されていく。だが、知性とユーモアを兼ね備えた工場労働者。何とも異端で歪な響きだろうか。
それでも、私は思う。紳士の伝統は格式張ったステッキやシルクハットにあるのではなく、日常の矛盾を笑い飛ばす精神にこそ宿るのではないか。イギリス人が紅茶の渋みに人生の苦味を重ねるように、私は塩辛い作業着の匂いの中に世界の理不尽を嗅ぎ取る。そして、それを笑いへと変換できれば、工場労働者も立派な紳士だ。
一方で、現代の流行にも触れてみる。本書が描く「古き良き紳士」とは対照的に、スマートフォンに振り回される現代人は、もはや常時通知に反応する「召使い」ではないか。アプリから命令が飛び、我々は忠実に従う。労働者であれ、サラリーマンであれ、紳士であれ、結局は機械仕掛けの奴隷だ。私は窓外の雲海を眺めながら、思わずくすりと笑った。
「工場労働者でも紳士の嗜みは可能か」――これはただの問いかけに見えるかもしれない。しかし、労働と余暇、伝統と流行の狭間で揺れ動く我々にとって、切実なテーマでもある。ベトナムでこれから会う実習生たちもまた、労働に押し込められながら、自分なりの「紳士のユーモア」を育てるのだろうか。もしそうだとしたら、労働の現場こそ最も新鮮な笑いの源泉なのかもしれない。
ページの端を指で折りながら、私は半ば退屈、半ば満足の入り混じった気分に浸った。伝統と現代、ユーモアと虚無感。そのすべてを抱え込みながら、鋼鉄の箱は東南アジアの空へと進んでいく。
【4】到着へのカウントダウン
機内は静かに時間を刻んでいた。トレイが片付けられ、残り香だけが漂う。コーヒーの苦味、ビーフシチューの残滓、どこかで誰かが落としたパン屑の乾いた匂い。それらが混ざり合い、密閉された機内という小さな宇宙を構成している。私は椅子に深く沈み込み、窓の外を眺めた。
機体はすでに高度を保ち、眼下には海と雲が交互に広がっている。窓際に座った私は、ただその白と青の模様を眺めていた。時間の流れが遅く感じられる。異国に到着する前の緊張感と、どこか冷えた空虚感が、奇妙に同居していた。胸の内にざわつきはあるのに、頭の中は妙に冷静なのだ。
眼下には雲が、海原のように果てしなく広がっている。ときおり切れ間から見える大地は、幾何学的な模様のように切り分けられ、田畑とも工場地帯とも判別がつかない。人間の営みなど、上空一万メートルから見れば線と点に過ぎないのだ。私はその事実に、どうしようもない空虚さと、同時に言いようのない安堵を覚える。
思えば、工場での日々も同じことだった。魚を切り、味を付け、パックに詰める。流れ作業の一部品として回転する毎日。だが、今私が座っているこのシートも同じだ。座席番号、搭乗券、与えられた機内食。まるで巨大な工場のラインに組み込まれているようだ。資本主義の歯車であることを自覚しながら、それでも人は空を飛び続ける。愚かで愛おしい習性だ。
シートベルトの金具に触れると、冷たい感触が指先に残った。束縛と安全は紙一重。ベルトを外せば自由だが、突如乱気流が襲えば即死の可能性もある。人間の自由とは、たかがこの程度のものなのだろう。条件付きの自由。選択肢を与えられた自由。いや、選ばされた自由。フーコーやサルトルなら、きっと鼻で笑うに違いない。
機体が少し揺れる。機長の声がアナウンスで響く。少し雲の中を進むので機体が揺れる、と。旅の始まりは、いつもこの揺れと共にある。日本という安全圏を離れ、別の世界へ投げ込まれる瞬間だ。異邦人のムルソーが地中海の太陽を浴びながら自らの運命を呑み込んだように、私もまたハノイの空気を吸うことになるのだろう。
「人生とは、結局は空港の入国審査みたいなものかもしれないな。」ふとそんな比喩が浮かんだ。スタンプを押されれば通過、拒まれれば帰国。理由は誰も教えてくれない。ただ、そこに座る無名の係員が生殺与奪を握っている。
機体はすでにベトナムの空域に入ったのだろうか。窓の外には雲の切れ間から光が斜めに射し、金属の翼に鈍い輝きを落としている。機内はざわついているようで、しかし本質的には静寂だった。人間の声というものは、いくら集まろうとも結局は断片でしかない。
「早く着かないかなぁ、足がもう痺れちゃってさ」
と隣の列の中年男性が愚痴をこぼす。隣席の妻らしき人物は
「だからスリッパにすれば良かったのに」
と平然と返す。どうやら足の痺れは結婚生活の縮図のように、互いに気にされもせず、淡々と流される運命らしい。
前方の席では若い男女がガイドブックを広げ、声を潜めては笑っている。
「ホアンキエム湖に行こうよ。インスタに映えるんだって」
「いや、アオザイを着て写真撮らないと意味ないでしょ」
彼らにとってハノイは“背景”でしかないらしい。恋愛の舞台装置、SNSの燃料、未来の思い出のスクラップ。だが、そのどれもが現地の人間の暮らしとは無関係だ。
後方では壮年のビジネスマン風の男がPCを開き、書類を打ち込んでいる。
「この時間を有効に使わなきゃな」
独り言が聞こえてくる。資本主義の亡霊に憑かれた兵士は、空の上でも戦場を離れられない。もしかすると彼の人生の着陸地は、空港ではなく書類の山かもしれない。
一方で、私の斜め後ろでは初老の男が口を開けて熟睡している。規則的な鼾が揺れるたび、人生を生き抜いてきた証が重力のように響く。夢の中では、きっと戦争か、青春か、あるいは何も見ていないかもしれない。いずれにせよ、この鼾こそ最も誠実な声なのかもしれない。
私は座席に深く沈み込みながら、これらの断片を拾い集める。眠る者、愚痴る者、未来に浮かれる者、そして労働に追われる者。人は皆、到着前の機内で人生の縮図を演じているのだろう。滑稽な縮図劇場。ここに「自由」はあるのだろうか? いや、自由とは、椅子に括り付けられたシートベルトのことを指すのかもしれない。
間もなく窓の外に、大河が蜿蜒と流れるのが見えてきた。紅河か。それとも別の支流か。いずれにせよ、その褐色の流れは歴史の奔流を思わせた。インドシナ戦争、社会主義の独裁、資本主義との折衝。すべてを飲み込み、濁った水となって今も流れ続けている。
エンジンの唸りが低くなり、車輪が大地を求める音が聞こえてくる。いよいよだ。ハノイ、ノイバイ国際空港。そこには何が待っているのか。笑顔か、混沌か、それとも沈黙か。私はただ、窓の外に広がる青灰色の大地を見つめ続けていた。
ハノイに到着すれば、新しい光景が待ち受けているだろう。だが今は、その直前の「宙吊りの時間」だ。到着と未到着のあいだ。意味と無意味の狭間。緊張があり、同時に空虚でもある。私はシートに身を沈めながら、思わず薄ら笑いを浮かべた。空虚すらも、こうして一つの娯楽になるのかもしれない。
【5】ノイバイ国際空港
日本を出発して四時間あまり、機体は予定通りにハノイのノイバイ国際空港へ向けて降下を始めていた。飛行は安定していて、乱気流に大きく揺さぶられることもなく、乗客たちは機内食を食べ、映画を眺め、うたた寝を繰り返すうちに、いつのまにか異国の上空に差しかかっていた。座席に身を預けながら、私の意識もどこか曖昧で、日常から切り離された浮遊感を味わっていた。
着陸間近になると、窓の外に見える景色が急速に解像度を増していった。最初はただの濃い緑と茶色のまだら模様だったものが、目を凝らすにつれて山並み、耕地、そして蛇行する河川へと姿を変える。
日本の川は、雨上がりを除けば青や銀色に近い澄んだ色をしている。だがここでは、太く濁った茶色の帯が大地を分断し、うねりながら海へ向かっている。水そのものが大地の一部を抱え込んでいるかのようだ。その濁流を目にした瞬間、日本の自然の繊細さと脆さが、逆に鮮烈に浮かび上がった。地質、気候、風土の違いが、これほどまでに川の色を変えるのか。
眼下に広がるのは、どこか単調でありながら力強い街並みだった。高層ビル群は少なく、赤茶色の屋根がぎっしりと敷き詰められている。均一に区画された住宅地の灰色が、大地に群がる蟻塚のように見えた。
屋根のオレンジ色は夕暮れの残光のようで、そこに暮らす人々の営みを想像させる。窓の外の景色をカメラに収めるべきかと一瞬迷ったが、結局レンズを向けることはやめた。記憶に焼き付ける方が、写真よりも長く心に残るように思えたからだ。
機内に「まもなく着陸態勢に入ります」というアナウンスが響く。乗客の誰もがそれを聞き慣れているはずなのに、途端に空気が張り詰めたように感じられる。着陸は技術的には日常の一部であり、失敗などまずあり得ないことだと誰もが分かっている。
それでも人間は、無意識のうちに最悪の事態を想定してしまう生き物らしい。墜落する映像を脳裏に浮かべてはすぐに打ち消し、ベルトを締め直す。その緊張感は言葉にはならず、ただ座席の揺れと心拍数の高まりとなって伝わってくる。
やがて機体は地上に吸い寄せられるように滑り込み、車輪がアスファルトを強く叩いた。機体全体に小さな震えが走り、それと同時に機内には目に見えぬ安堵の吐息が一斉に広がった。歓声は上がらない。ただ静かに、確実に、ほとんど全員の胸から緊張が解けていく。心臓の鼓動も、さっきまでの警報のようなリズムから、日常の拍に戻っていった。
飛行機は速度を落とし、誘導路を進んでいく。外の景色は、遠い雲の上ではなく、地面に密着したものへと変わっていた。駐機場には、白と青の機体が並び、各国からやってきた人々を吐き出しては飲み込み続けている。ベトナムの空港は、日本のそれよりも幾分か素朴で、しかし、生き物のように脈打っていた。
完全に停止した瞬間、私は大きなプロジェクトを完了した後のような感覚に包まれた。達成感というより、むしろ拘束から解き放たれたような解放感だ。四時間の空白が閉じられ、私はいま確かに異国の土に足を踏み入れようとしている。
機内アナウンスが再び流れ、乗客たちは一斉に立ち上がった。頭上の棚からキャリーケースやバックパックが引き出され、通路は人の流れで詰まる。私もその一部となりながら、ふと窓の外を見た。太陽が中天を過ぎ、夕刻に向けて走り出した空の下、滑走路の一部が窓口から垣間見える。数え切れないくらいの飛行機を受け入れてきたものがそこにいた。
飛行機のドアが開くと同時に、私たちはまるで工場の労働者のように列を成して進み始めた。行き先はただ一つ、空港内の検査ライン。前のめりで押し合う群衆は、まるでベルトコンベアに乗せられた魚のパックそのものだった。行列に並んだ瞬間から、私という「個」は剥ぎ取られ、番号札のついた製品に変わる。収監された囚人に割り振られる番号のように。
最初に待ち構えていたのは検温と書類チェック。白衣を着た係員が淡々と体温検査機を額に突きつけ、目だけを動かして紙と照合する。あの目は、工場で初期検査を行う検査員の目と同じだ。もしここで規格外と判断されれば即リジェクト。ラインから外され、再利用もされず、廃棄か倉庫行きだ。日本の工場なら「不適合報告書」という名の回覧がオフィスを舞うのだろうが、ここでは眉がわずかに上下するだけだ。人間が人間を弾く瞬間が、これほど無味乾燥であることに、私は改めて感心する。
そしてパスポートチェック。無表情の審査官が、私の顔と写真を交互に見比べる。その目は人事部の採用担当の目にそっくりだった。履歴書上は「有能」に見えるが、実物は果たしてどうか? そんな無言の審査。こちらは必死に「私は規格内の人間です」とアピールするが、表情筋の一挙手一投足が測定されている気がする。落ちれば即帰国、履歴書が破り捨てられるように。ガシャ、というパスポートに印が押される音で無罪が宣告される。面接は無事に合格したようだ。
次は荷物検査。ベルトの上を私物が晒されていく。鞄の中身がひとつ残らず露わになる様は、家庭の冷蔵庫を隣人に覗かれるような屈辱感を呼び起こす。普段は机の奥に隠しているカップラーメンや、若気の至りで購入したアニメDVDを突然同僚に見られてしまう、そんな恥に似ている。サラリーマンなら残業机の上に放置したコンビニ弁当やら内緒の漫画雑誌やらを、翌朝上司に発見されるのと同義だろう。埃にまみれた書類とともに、魂の隅々までスキャンされてしまう。この恥を超えた先に入国という目的地があるのだ。だが、現代人は海外旅行に慣れすぎたため、いちいちこのような恥は感じない。むしろ相手国側の権利とまで思っている。
無事に一連の検査をクリアし、ハノイという陳列棚に並ぶことを許された。これからは商品として、ハノイの市場に流通していく。旅先でドンをどんどん落としていく観光客の一員だ。そう思った時、自分が出張できていることを思い出す。そうだ、これは仕事なのだと。いつの間にかハノイの異国情緒に当てられていたらしい。先が思いやられる。
思えばこの一連の流れ、日本のサラリーマンが朝オフィスに辿り着く儀式に酷似している。満員電車という輸送ラインを経て、改札というゲートで社員証をピッと通す。エレベーターという立体ベルトに揺られ、オフィスの席という「最終検品場」に配置される。違いといえば、押されるのがスタンプかハンコかくらいのものだろう。
私は列を進みながら考える。なぜここまで人間を物として扱う工程が徹底しているのか。安全のためか、秩序のためか、国家の威信のためか。理由はいくつも掲げられるが、最終的には魚のパックと同じ「異物混入を防ぐため」に収束する。つまり私は異物であってはならない。にこやかに、何事もなく通過し、無傷の製品として次の国に収められねばならない。私は無害であり、貴国に利益をもたらすといことをアピールする必要がある。
そして結論に至る。人間とは、どこまでいっても誰かに検査され、承認印を押されてやっと存在を許される商品ではないのか。工場労働者であれ、サラリーマンであれ、旅客であれ。私たちはただ流され、検査され、規格内の烙印を押され続ける。ここは空港であり、同時にこの世の縮図でもある。
一連の検査を終え、無事にキャリーケースを回収する。ベルトコンベヤーを巡回する黒い箱は、所有者に捕獲される順番を待つだけの獲物に見えた。流れに従い、やがて誰かに取られていくか、取り残されるか。社会はだいたい、これと同じ仕組みで動いている。
私はその一つを手に取り、合流場所へ向かう。約束どおりなら、ここでトンさんたちと落ち合う。通路を進むと、すでに三人が待っていた。発光看板の白々しい光の中で、誰もが旅人ではなく、旅の役者のように見える。
「おや、蒲生さん。お待ちしていました。長旅、本当にお疲れ様でした。体調のほうは大丈夫ですか?」
トンさんはいつもの柔らかい調子だ。声の奥に、時刻表とタスクの連鎖が静かに回転している音がする。
「お待たせしました。ええ、大丈夫です。特に問題もなく、ここまで来られました。」
私は必要最小限だけ言う。余計な情報は、余計な選択肢を生む。
「無事で何よりです。お二人とも既に合流されています。まもなく、送り出し機関のスタッフが車で迎えに来るはずです。」
送り出し機関──日本では耳馴染みのない言葉だ。だがこの国では、若者を海外に送り出すこと自体が一つの産業で、語学訓練、健康診断、身元保証、手数料、そして融資が、見事に一つのパッケージに組み上がっている。夢の包装は丁寧だが、糸を解けば借金が先に出てくる。
「おお、蒲生君。お疲れさま。顔色を見る限り、元気そうだね。」
大伴社長は安堵したように目尻を下げた。部下が無事に到着することは、プロジェクトの最初の成果に計上される。
「いやぁ、疲れましたなぁ。ホテルに入ったら、何よりも先にベッドに潜り込みたいですわ。」
小野社長は率直だ。率直さは美徳だが、たいてい誰かの段取りを少しだけ重くする。
「すみません、お待たせしました。荷物検査の列が思った以上に進まず……。」
私の弁解は、空港という施設が大量生産するテンプレートの一つに過ぎない。
「今日はいつもより人が多い気がしますね。日曜日ですから、帰国が重なっているんでしょう。──では、出口に向かいましょう。送り出し機関の車が待っているはずです。」
【6】現地スタッフとの邂逅
トンさんを先頭に、私たちは出口へ向かう。磨かれた床をキャスターが鳴き、広告の笑顔がこちらを見ている。両替所の前では、紙幣を数える人たちの指先が忙しい。SIMカードの売り場では、接続の不安が一時金に変換されていく。
自動ドアが開くと、空気が変わった。湿度が皮膚に触れて、旅が外気に認証された気がする。日本の秋の乾いた空気とは正反対の、ねっとりとした温度だ。肺の奥に入り込むたび、身体の境界線が曖昧になるように思えた。私は、ついにベトナムに到着したのだ。昼下がりの微睡、道路の熱、あちこちで鳴るクラクション。空港の外は、いつでも街のイントロダクションだ。
特に車のクラクションの音には驚かされる。狭いロータリーの中に鮨詰めにされた車両。進まない列にイライラしたのか、力任せに鳴らすクラクション。混雑言うよりカオスだ。湿度と気温の高さから、みな憤怒を曝け出している。慣れるまでに幾許か時間がかかりそうだ。
「お待たせしました、皆さん。こちらです。」
若いスタッフがボードを掲げて近づいてくる。印刷された社名のフォントが、少しだけ古い。古いフォントは、だいたい古い体質と仲がいいが、古い体質が必ずしも悪いとも限らない。長く続ける技術を持っているという点では、しばしば新しい会社を凌駕する。
「Xin chào.(シンチャオ) よろしくお願いします。」
と言うのはベトナムの現地スタッフ。流暢な発音で日本語を添える。さすがは日本人相手のビジネスをしてきた者たちだ。外国人が日本語を操るだけで旅の安心感が違う。こちらの意図を明確に汲み取り、現地の情報にも精通している。最強の軍師が味方になった気分だ。まさに張良を得た劉邦の如きだ。
「こちらこそ、お世話になります。」と日本勢がお辞儀挨拶を交わし、名刺交換を行う。柔らかい笑顔は、国境を越えるための万能通貨に近い。だが、異国の地でも大和魂は失われていなかったようだ。むしろ、自分たちのアイデンティティを確認するかのように一連の動作を行う。
「ホテルまで、どれくらいですか?」と小野社長。どうやら酒池肉林への欲望が抑えられないようだ。
「今日は日曜で、道路はやや混雑しています。四十分くらいでしょうか。」とスタッフ。彼は私のスーツケースを軽々と持ち上げ、バンの後部に積む。労働の矢印が自然に彼のほうへ向いていく。私たちは見ている側に回る。ここでは私たちは顧客なのだ。突然、労働を奪われると手持ち無沙汰だ。労働魂もここに極まれり、だ。
続々とバンに乗り込む。大型のバンで10人は乗れるだろう。後部座席は前後参列で、前から小野、大伴、私と言う順に座った。
「シートベルト、お願いします。ハノイへようこそ。よろしくお願いします。」
運転手が振り返って簡潔に言う。簡潔は善だ。命令が短いと、従うことに余計な意味が生まれない。車が滑り出す。窓の外で、街の看板がひらがなのように流れていく。理解できなくても、読めない文字は美しい。意味が遅れて追いかけてくるので、景色のほうが先に届く。
「ところで、明日のスケジュールですが……」とトンさん。
「午前は送り出し機関で教育施設の見学、その後、候補者の面談です。」
「健康状態の確認、履歴書の整合性、通訳付きの面接、簡単な作業テストといった感じで採用者を決めていただきます。」
チェックリストが一つずつ宙に現れ、走行風で後方に飛んでいくイメージが浮かぶ。実際には、どれも現実に重い。技能実習制度の利点は、紙に書くと簡単だ。人手不足の業界に労働力が供給され、若者は技能と賃金を得る。
国と国との関係も、ニュースの見出し程度には温かくなる。欠点も、紙に書くと簡単だ。言葉の壁、賃金の格差、借金、ミスマッチ、そして誰のための「技能」なのかという問い。紙の上では両者が拮抗し、現場では日々の都合が勝つ。
「ホテルはどんなところですか?」
と小野社長。声に、夕食とシャワーの希望が混じっている。
「清潔で、朝食がおいしいと評判です。ベトナムの中では高級ホテルの部類に入ります。」
とスタッフ。どの国でも、ホテルの説明はだいたいこの二点に収束する。清潔さと食事。つまり、人は眠れて食べられれば、あとは自分で何とかする。異邦人でも飛び込んでしまえば、知らないうちに順応する。
「小野社長、お身体は大丈夫ですか。」とトンさん。
「うん、問題ないよ。」
小野社長は窓の外を見ながら短く答える。リーダーはたいてい、感想を短く言う訓練を受けている。長い感想は、会議の敵だからだ。
赤信号で車が止まり、ベトナムの風情が覗き込む。空港は郊外にあるため、しばらくは広大な田畑が続く。温度のある生活が道路の脇で淡々と進行している。私たちはその生活の横を通り過ぎて、温度のない会議室へ向かう予定だ。
20、30分も走ると窓の外には、ハノイ特有の雑然とした秩序が現れる。道路は複数の生き物が共存する川のようだ。バイクが群れを成して走り、荷台には果物籠、ガスボンベ、家族四人が無理やり収まっている。バイクのテールランプが赤い小魚の群れのように光を放ち、交差点に差しかかるたびに渦を巻く。クラクションは合図であり、怒声ではない。誰もが譲り合い、誰もが突っ込み、結果として流れは止まらない。
「これがベトナムの交通です。」
とトンさんが小声でつぶやく。説明は不要だった。すでに窓の外が、何百の証言を同時に語っている。証明は終了している。道路脇では、鉄製の簡易テーブルがずらりと並び、客たちがプラスチック椅子に腰を下ろし、熱いフォーを啜っている。
湯気はバイクの排気と混じり合い、立ち上るたびに太陽に照らされて一瞬だけ金色に光る。その光景は、どんな高級レストランの演出よりも雄弁に、この街が「生きている」ことを示していた。私にとっては非日常、彼らにとっては日常なのだ。
やがて車は市街地の幹線道路に入り、両脇には巨大な看板が林立する。韓国コスメの広告、中国資本の不動産、そして英語で書かれた「New Life」「Future City」。未来を売る文字が、過去の建物の壁に無理やり貼り付けられている。そのアンバランスさが、逆にこの国の現実感を強めていた。だが、ベトナムの未来は明るい。若者の破竹のような勢いが国力を増加させるだろう。
川を渡ると、橋の上から点在する家々がぽつんぽつんと浮かび、まるで虫籠の中で灯る蛍の群れのようだ。街の低いざわめき、川面を渡る湿った風。眠りにつく都市と、これから働きに出る都市が、同じ時間に同じ場所に重なっていた。
バンはさらに進み、葉の影が車窓に細かな模様を刻んでいく。街は古さと新しさが縫い合わされたパッチワークのようだ。フランス植民地時代の建物が肩を寄せ合い、その隣にガラス張りの高層ビルが突き立っている。どちらも完成しているようで、どちらも未完成のまま放置されているようにも見える。歩道の所々は荒れており、発展国特有の粗雑さを見せている。
「ホテルまでは、あと十分ほどです。」
とスタッフが告げる。声は事務的だが、その響きには都市のリズムが混じっている。前方に、大きな鉄の塊が見えてくる。フォーチュナホテルだ。光沢のある外壁が浮かび上がり、通りの混沌に一つの句読点を打つように輝いている。近づくにつれて、ロビーに出入りする人影がはっきりし、スーツケースを押す客、制服のベルボーイ、タクシーの呼び込みが交錯しているのが見える。
車がホテルのロータリーに滑り込み、乗客を吐き出していく。送り出し機関のスタッフが素早く下車し、荷物を運び込んでいく。日本人も舌をまく気遣いの良さだ。一心不乱に労働に従事する姿が眩しく映る。
ベルボーイが素早くドアを開け、フォーチュナへと誘う。湿気と排気ガスの匂いは、ドアの開閉一つで外に押し戻され、代わりに冷房の冷気と花の香りが流れ込んでくる。異国の雑踏から切り離された瞬間だった。先程までの、機械の合唱が嘘のように静まり返る。
「チェックインをまとめて済ませますので、パスポートをお預かりします。」
トンさんは慣れた手つきで私たちのパスポートを集め、送り出し機関のスタッフとともにフロントへ向かった。その背中を見送りながら、私はふと思った。人間の尊厳を最も手軽に預けられるのは、いまや銀行口座ではなくパスポートだ。数枚の紙が、国境を越える私の存在を保証している。逆に言えば、それを失った瞬間、人は一気に「誰でもない者」に転落する。
入れ替わりにホテルの従業員が現れ、流暢な日本語で声をかけてきた。
「チェックインまで少々お時間をいただきます。こちらにお掛けになってお待ちください。すぐにお飲み物をお持ちいたします。」
わずかに訛りはあるが、耳に心地よい日本語だった。トンさんの説明によれば、このホテルは日本人御用達で、出張や観光客で常に賑わっているらしい。近くにあるハノイホテルも同じだという。スタッフが日本語を身につけるのは、生存戦略の一つなのだろう。初めて異国を訪れる日本人にとっては安心材料だが、同時に「我々はもはや市場として翻訳される存在なのだ」と考えると、笑えない気分にもなる。
社長二人とロビーのソファに腰を下ろすと、冷房の効いた空気が体を包み込んだ。しばらくして、飲み物が運ばれてくる。
「どうぞお召し上がりください。」
無駄のない所作で差し出されたグラスの中には、氷と茶色の液体。一見ウーロン茶だが、口に含むとほんのりと甘い。汗で荒れた喉を潤すには十分だった。日本であれば「お茶は苦くて渋いもの」という常識があるが、ここでは甘さが標準装備らしい。思えば日本でも、戦後の闇市では砂糖は通貨のように扱われていた。豊かさの尺度は時代と地域でいとも簡単に変わる。
「ようやく一息つけましたなあ。まだ夕方の五時、ベトナムの夜はこれからですな。」
小野社長はコップを一息に空け、手を挙げてスタッフに追加を注文した。
「ごめん、ドリンクもう一杯!」
合図の素早さは、部下への指示と変わらない。即断即決が美徳なのは仕事の場だけでいい気がするのだが、こういう癖は異国のロビーでも発揮されるらしい。すぐにおかわりが届き、小野社長は再び喉を潤した。よほど乾いていたのか、それともこれから始まる宴への助走なのか。
「秋口だというのに、まだまだ暑いね。バイクや車が密集しているせいで、余計に熱気がこもる。」
黙っていた大伴社長が感想を漏らした。彼は常に大局を語りたがる。
「ええ、日本の暑さとはまた違いますね。」私は相槌を打つ。
「そうそう。湿気は日本ほどじゃないが、あのクラクションの多さが不快感を増す。だが、いずれは自動車に置き換わるのだろう。」
「かもしれません。日本もそうでしたから。」
「今のベトナムは、昔の日本の高度経済成長を見ているのかもしれない。」
私は思わず口を挟んだ。
「なるほど……確かに街全体が拡張工事中のように見えます。ですが日本の高度経済成長の終わりがどうなったかを思うと、ベトナムも注意が必要でしょうね。」
「大伴社長が子どもの頃はどうでした?」と私は話題を向けた。
「私か?そうだな。ここまでバイクだらけじゃなかったが、それでも普及率は高かった。何より安価だったし、自動車は高すぎた。家や車を持つのは親の夢だったよ。今では当たり前のように家を建て、車を複数所有する家庭も珍しくない。『失われた何十年』なんて言うけれど、生活水準は確実に豊かになっている。」
私は頷きながら心の中で思った。確かに物質的には豊かになった。しかし日本のサラリーマンは、毎日満員電車で魂をすり減らし、残業で家族の顔もろくに見られない。給料が増えても、自由は減っている。最近ではその給料も停滞している。幸福度という言葉を持ち出せば、数字はおそらくベトナムに逆転される日も近いのではないか。
「では、幸福度はどうでしょうか?」私はついに口に出した。
二人の社長は一瞬黙り込み、それから互いに顔を見合わせて笑った。
「君は急に難しいことを言うね。」
「サラリーマンにとって幸福度なんて、年のボーナスと上司の機嫌で決まるものさ。」
笑い話のように聞こえるが、どこか刺さる言葉だった。幸福とは結局、数字よりも「目の前の小さな余裕」のことなのだろう。冷房の効いたロビーで飲む甘いお茶も、その一つだ。
大伴社長も笑いながら加勢する。
「そうだ。あとは定年まで持ちこたえられるかどうか。それ以上を望んでも、だいたいは無駄だ。」
冗談めいた口調だったが、その実感のこもり方が、むしろ胸に突き刺さる。私は黙ってグラスの氷を揺らした。カランと乾いた音が、ロビーの冷気の中で妙に響いた。
幸福とは何だろう。彼らのように「仕事を全うし、家庭を維持し、老後に年金を受け取る」ことを幸福と呼ぶなら、日本の多くのサラリーマンは十分に幸福の条件を満たしているはずだ。しかし、数字や制度の上で保証される幸福は、なぜか肌に馴染まない。
私はふと、自分の目指す半隠遁生活を思い出した。社会との縁を完全に切るのではなく、必要最低限のつながりを保ちながら、余計なものを持たずに暮らすこと。大きな家や複数台の車よりも、一冊の本と静かな時間に価値を置くこと。
幸福を「所有」ではなく「不要の削減」で測るとしたら、どうだろう。財布に厚みがなくても、時間に余白があれば心は膨らむ。肩書きがなくても、自分の思索に耽る余地があれば、それは十分に幸福ではないか。
社長たちの言葉を聞きながら、私は心の中で小さく反論していた。幸福度ランキングがどうであれ、幸福の定義はいつも個人の内部にしかない。サラリーマン的尺度では、幸福は「外部から与えられる報酬」に依存してしまう。だが半隠遁を志す私にとって、幸福とはむしろ「外部から切り離しても残るもの」なのだ。
グラスの甘いお茶を口に含みながら、私は考える。ベトナムの人々が夜の屋台で笑いながらフォーを啜っている姿は、日本の幸福論より説得力がある。収入や制度の比較を超えて、日々の呼吸の中にある「今この瞬間の余裕」こそが幸福の核心なのだろう。
そのとき、フロントからトンさんの声が響いた。
「皆さん、チェックインが完了しました。お部屋のカードキーをお持ちしました。夕食は19時からになります。その時間にロビー集合で、それまでは自由時間とします。よろしくお願いします。」
思索は唐突に切り上げられた。幸福とは何か、という問いはグラスの底に沈んだ氷のように残ったまま。私は小さな溜息をつき、立ち上がった。パスポートと引き換えに渡されたカードキーは、異国のホテルの部屋への扉を開く。だが、果たして幸福への扉も同じようにカード一枚で開くものだろうか。
私は足を踏み出す。ここから始まるのは、労働と交渉と、そして小さな観察の積み重ねだ。旅情の幕は閉じ、別の劇場の幕が上がる。
半隠遁を志すには、静けさが必要だとよく言われる。だが静けさは、静かな場所にしかないわけではない。騒音の中にも静けさはある。自分に向かう矢印を弱め、世界のほうを少し強くするだけで、静けさは勝手に見つかる。
今日の拘束は、ようやく形を変えるだろう。ベッド、シャワー、無線LAN。拘束の質は悪くない。私は窓に指先を当て、ガラスの微かな冷たさで、今ここにいることを確認した。旅は、しばしば確認の連続だ。自分がまだここにいるという、単純で厄介な事実の確認である。
【7】ハノイ散歩
トンさんが差し出したカードキーを受け取り、私たちはそれぞれの部屋へと向かった。エレベーターに乗り込むと、鏡張りの壁に映る自分の顔が、わずかに疲れを帯びているのに気づいた。飛行機の長旅というより、先ほどの幸福論の応酬に精神を使ったのかもしれない。サラリーマンは議論でさえ出張の一部だ。
部屋に入ると、冷房の冷気がまとわりついてきた。ベッドは二つもあるが、使うのは一つで十分だ。余った一つは、まるで「豪華さの証明書」として置かれているにすぎない。スーツケースを開け、シャツを掛け、書類を机に置く。わずか数分の荷解きなのに、旅の「外様」だった自分がこの部屋の「住人」に格上げされる感覚がある。ホテルの部屋は、簡易的な住居であり、同時に仮設の人生だ。
椅子に腰を下ろし、ふと天井を見上げる。思考は再び幸福へ戻る。日本のオフィスで「生産性」「効率化」と唱えられるたびに、人間の幸福度は下がっていく気がする。効率化された先に残るのは、余白のない一日と、過労死ラインのグラフ。幸福はGDPに換算できない、と口では言いながら、誰もそれをやめようとはしない。
半隠遁生活を目指す私にとって、幸福は「余白の奪還」に他ならない。高級なソファや豪勢な夕食よりも、誰にも邪魔されない読書の一時間が欲しい。だが、現実にはまだ私は社長たちの随行員であり、夜の接待という儀式が待っている。幸福への道は、チェックインよりも複雑な手続きを要するらしい。と言っても、今回は私も接待をされる側だ。
時計を見ると、まだ夜の始まりだ。ベッドに倒れ込むには早すぎる。私は軽く顔を洗い、身支度をした。窓の外にはバイクのテールランプが赤い川のように流れている。あの流れの中に一歩踏み出せば、また別の幸福の断片に出会えるかもしれない。
私はカードキーをポケットにしまい、再び廊下へ出た。ホテルの部屋は私を一時的に守るが、旅の記憶を与えてくれるのは、やはり外の喧騒だ。異国の夜は、幸福を測り直すための実験場である。
せっかく異国に来たのだ、少し街を歩いてみよう。ホテルの外に出ると、熱気が再び身体にまとわりつく。さっきまで冷気に守られていた分、肌に貼り付く湿度はより濃密に感じられる。だが、この不快さこそが「本物」だ。旅人はたいてい快適さを求めるが、記憶に残るのは不便の方である。夕食まで2時間ほどある。
通りに出ると、ハノイの夕刻はすでに賑わっていた。道路の端には、プラスチック椅子に腰かける人々が、湯気の立つフォーの椀を前に談笑している。青いタンクトップの若者、制服姿の学生、仕事帰りの労働者。彼らの表情は、日本の居酒屋で生ビールを傾けるサラリーマンと大差ない。ただ、テーブルの上に置かれたのは唐揚げではなく、香草の束とライムである。
通りの両側には、無数の屋台が連なっている。金属鍋を叩く音、油の弾ける音、香草と肉が焼ける匂いが風に乗ってくる。日本で「ベトナム料理」として紹介されるとき、それは健康的で洒落たイメージを帯びる。しかし現場に来てみれば、油煙と排気ガスと香辛料が一緒くたになり、鼻を直撃する。だがその混沌が、この街の味を豊かにしているのだ。
道路は常にバイクで埋め尽くされている。赤いテールランプの群れが、川の流れのように絶え間なく続いていく。ヘルメットの上から電話をする者もいれば、荷台に信じられないほどの荷物を積む者もいる。暑さとクラクションで頭がいっぱいになる。日本なら即座に交通違反だろうが、ここではそれが秩序になっている。法律よりも習慣が強い国は、しばしば人間らしく見える。
「横断歩道を渡るときは、決して立ち止まらず、ゆっくり歩け」──かつて読んだ旅行記事の助言を思い出す。実際に渡ってみると、なるほど、バイクの群れは私をよけて流れていく。彼らにとって歩行者は障害物ではなく、動く信号機のようなものらしい。私は不思議な自信を覚えながら道路を渡り切った。命の値段はどこでも同じだが、その計算式は国によって違うのだ。
路地の角に小さなカフェがあった。裸電球が揺れ、木製の椅子とテーブルが歩道に置かれている。壁には色あせたポスターと古びた時計。ガラス戸越しに見える店主は、慣れた手つきで銀色のフィルターに湯を注いでいた。店員はチラリと私の方を見て頷いてみせた。
私は迷わず席に腰を下ろし、アイスコーヒーを注文する。数分後、運ばれてきたのは、練乳が底に沈んだ深煎りのコーヒーだった。黒々とした液体の中で氷が音を立て、グラスの表面に夕刻の湿気が滴る。ストローでかき混ぜると、甘さと苦さが渦を巻いて混ざり合う。ひと口飲むと、その濃厚さに舌が痺れた。日本で飲むコーヒーが「目覚めの一杯」なら、これは「人生への挑戦状」だ。
向かいの椅子に、いつのまにか一人の男性が腰を下ろしていた。年の頃は三十代半ば。痩せ型で、シャツの袖を無造作にまくり上げている。店内の席が埋まっているせいか、あるいはただの好奇心か、彼は軽く会釈して相席を求めてきた。私は笑ってうなずく。日本式の挨拶を知っているのだろうか。
「Xin chào.(シンチャオ)」
彼が先に口を開いた。
「Xin chào.」
私もぎこちなく返す。自分の発音が正しいのか不安だが、彼は気にした様子もなく微笑んだ。どうやら通じているみたいだ。入国前の突貫工事練習が効いたようだ。
「日本人ですか?」
ベトナム語が続く。
「はい、徳島から来ました。」
「トクシマ?」
彼は少し首をかしげ、すぐに
「Tokyo?」と聞き直した。
「いえ、Tokyo ではなく、四国の小さな地方都市です。」
「オー、シコク!有名じゃない。でも面白そうですね。」
彼はテーブルに置いた自分のグラスを指で弾きながら、
「ベトナムへは仕事ですか?それとも旅行?」と尋ねた。
「仕事です。技能実習生の面接で。」
「Ah… 実習生。」彼の表情が少し曇る。
「私のいとこも日本で働いています。工場。夜勤ばかりで大変そう。でも、日本で学べることもある、とメールに書いていました。」
彼の声には、誇りと不安が同居していた。私はどう返すべきか一瞬迷う。正直なところ、日本の工場で外国人がどのように扱われているかを私は知っている。それを肯定するのは偽善だが、全面的に否定するのも不誠実に思えた。
「日本での生活は決して楽ではありません。ですが、経験や技術を持ち帰る人も多い。きっと、彼の未来に役立つはずです。」
私の言葉に、彼は少し安心したように頷いた。
「でも、日本は厳しい国ですよね?」
「ええ、規則は多いですし、時間にも正確さを求めます。」
「ベトナム人には難しいかも。でも、あなたたちは忍耐強い。」
「忍耐強いというより、諦めるのが上手いのかもしれません。」
そう冗談めかして言うと、彼は吹き出した。
「それ、哲学ですね。諦める才能。ベトナム人も持っていますよ。」
「それなら、我々は親戚のようなものですね。」
二人で笑った。会話は拙くも、奇妙な連帯感が芽生えた。やがて彼はポケットからスマートフォンを取り出し、写真を見せてくれた。バイクにまたがる家族の写真、テト(旧正月)の飾り付け、田んぼの風景。私はそこに、自分の故郷の田園を重ねて見た。どこの国でも、人の生活は似ている。違うのは屋根の色と、川の色と、コーヒーの甘さくらいだ。
グラスの底で氷が小さく砕け、会話が一段落する。私は勘定を済ませ、立ち上がった。彼も笑顔で手を振る。
「また会いましょう。Enjoy Hanoi!」
「ありがとう。またどこかで。」
会計を終えると6時を少し過ぎていた。夕刻の湿気が再びまとわりついた。カフェの裸電球は遠ざかり、バイクの洪水が通りを埋め尽くしていた。私はその中に歩を進める。異国は、見知らぬ誰かとの一杯のコーヒーで、確かに自分の中に根を下ろすのだ。
カフェを出て通りをゆく。バイクのエンジン音、笑い声、犬の鳴き声、そして遠くで聞こえるクラクション。街全体が一つの大きな交響曲を奏でているようだった。ふと、自分がこの音楽の観客であると同時に、微かな演奏者でもあるように思えた。異国の空気を吸い込み、目に映るものすべてが「私の物語」に組み込まれていく。
ハノイの街は、観光地として美しく整えられる前に、すでに人々の生活そのもので満ちていた。その素朴さが、旅人の心を掴んで離さない。
数分も歩かないうちに、角の薄闇がふわりと明るくなる。裸電球が一つ、風に揺れている。小さなワゴンの上には、細長いフランスパンが斜面に積み上げられ、黄金色の皮が月光の代わりを務めていた。鉄板では豚肉がじゅうじゅうと油を跳ねさせ、刻んだ香草が熱でわずかに身をよじる。金属のヘラが鉄板を擦る音は、路上のオーケストラにとってのシンバルだ。屋台の背後では、若い女性がパンに切れ目を入れ、迷いのない手つきで具材を押し込んでいく。ためらいのない料理は、たいてい正しい。
「バインミー?」と彼女が目だけで微笑む。
「はい、一つください。」
その二語で取引は成立する。政治制度が違っても、胃袋の民主主義は世界共通だ。間も無く夕食だが、この香りと店主の実直さに負けた。フランスパンひとつくらいどうと言うことはない。ハノイの夕暮れと共に押し込んでしまう。
フランスの植民地時代の置き土産が、二十一世紀のベトナムで最も庶民的な軽食として生き延びている。歴史はしばしば皮肉を好む。帝国は滅びても、パンは残る。国旗が降ろされても、朝食は廃止されない。制度よりも、日々の空腹のほうが政権交代に強いのだ。
焼き立てのバゲットに、焼き豚、きゅうり、キャベツ、香草、そしてチリソース。彼女の手は、順序を迷わない。職人芸というより、生活のリズムがそのまま指先になっている感じだ。漢詩を諳んじるようにバインミーを仕上げていく。
「卵を追加できるよ?」
「今日はなしで。」
「ハーブを入れても?」
「もちろん。」
「香辛料追加は?」
「少しだけ。」
「少しだけ?」
彼女は「ふむ、少しか」と言いながら、ベトナム基準の「ちょっと」を容赦なく絞り出した。世界には信じてはいけない単語がいくつかあるが、「少し」は上位に入る。
「日本人?」
「ええ。」
「何となく分かるよ。」
彼女はニタリと笑い、バインミーを差し出す。おそらく私の所作が日本人の典型なのだろう。彼女は目ざとくそれを見つけた。接客業、そして、ベトナムの名物バインミーの店だ。多国籍の客が来るだろう。国籍の特徴を暗記していてもおかしくない。
受け取ったバインミーを両手で包むと、想像以上の重さが掌に落ちた。パンの皮は薄く硬く、内側は湯気を孕んでいる。ひと口目で殻が気持ちよく砕け、熱と香りが同時に膨らんだ。焼き豚の脂は低く甘く、野菜群が軽快な音を鳴らし、レモンの酸が全体をきゅっと締める。香草は鼻に通り抜けて、体内の換気扇を回す。そこへチリが遅れて警察のサイレンのように鳴り込んでくる。練乳コーヒーで甘やかされた口腔に、緊急通達。「避難訓練を開始してください。」
「うまい。」
独り言のはずが声になって漏れた。屋台の女性が聞き取ったかどうかは分からないが、彼女の手つきはさらに軽くなった気がした。料理人の給料には、客の一言も含まれている。その一言が明日の活力になる。同時に傷を作る時もある。
隣のプラスチック椅子に、いつの間にか中年の男が腰を下ろしていた。シャツの胸ポケットにボールペンを三本。仕事帰りの匂いがする。彼はパンにかぶりつきながら、視線だけこちらに滑らせた。
「どうだい、バインミーは?」口いっぱいになりながら男が問うてくる。
「さすが食の大国ベトナムだ。」私は親指を立てる。
「ふっ、分かってるねぇ。」
彼は笑い、再びパンへ戻る。言葉はそれだけで十分だった。パンの中には、言葉以上のものが詰まっている。男は母国への自負心と誇りを胸に、私は異国での遊興を噛み締めながらバインミーを貪る。
二口、三口と進むたび、構造が見えてくる。表面の破片は鋭く、内部は柔らかく、油分は重力を理解していて、ソースは統治を嫌う。食べ物には物理法則が正直に宿る。だから、食べ方には性格が露見する。私は慎重に進めるつもりが、いつの間にか頬にソースをつけ、指先に油をつけ、紙ナプキンをもう一枚要求した。半隠遁を志す者は、食卓での痕跡を減らしたいものだが、屋台のバインミーはその誓いを軽々と破らせる。
「辛いかい?」
と屋台の奥から女性店主が茶化すように笑う。
「ええ、少しね… ベトナムの少しは、ちょっと強いですね。」
「ははは! ベトナムの少しはこれさ!」
彼女は胸を張って、唐辛子の瓶を得意げに掲げた。辛さに誇りを持つ文化はだいたい勤勉だ。チリソースが異邦人を打ちのめす。観光客にも容赦しないのがベトナムだ。こちらも腹を括って勝負に出るしかない。
支払いのとき、私は小さく折りたたんだ紙幣を取り出した。薄くて軽い。その軽さが、今夜の満足に比べて滑稽に思える。価格を尋ねると、彼女は指を折って簡単に示した。数字よりも指の動きのほうが、納得しやすい値段だ。私は少し多めに渡し、お釣りを受け取りながら礼を言う。謝意は通貨に似ている。流通させるほど世の中が円滑になる。
食べ終えるころ、口の中は辛さと香草の清涼感で、ほぼ新規格に更新されていた。味覚のOSアップデートだ。星付きレストランの長いコースより、路上の一本のバインミーが説得力を持つ瞬間がある。政治演説より、屋台の一口のほうが人を動かすこともある。人間を動かすのは理念ではなく、たいていは温度と匂いだ。
屋台の女性が手を振る。私は会釈を返し、パン屑を払う。指先に残る油膜は、夜風でゆっくり薄まっていく。歩き出すと、バイクの赤い尾灯が川の稚魚の群れのように流れ、看板のネオンは発音の分からない単語を夜空に書き続ける。どこの街にも方言があるが、ハノイの方言は光だ。光は訛る。
路面の割れ目に雨の名残がわずかに残り、そこへ電球の光が落ちて、紙片や蟻を金色にしていた。道端の小さな祭壇には線香が立ち、細い煙が真っ直ぐ上っている。私は立ち止まりそうになって、やめた。敬意は足を止めなくても払える。視線の静かさで充分だ。
ふと思う。半隠遁とは、世間から距離をとることではなく、世間を過剰に所有しない技術のことだ、と。今、私の所有は満腹感とわずかな小銭、そして指先の油だけだ。これ以上は持たないほうが身軽でいられる。満たされすぎた荷物は、旅をにぶらせる。
背後で屋台のヘラが再び鉄板を叩く。次の誰かのための音だ。私は歩を進める。口の中に残る香草の余韻が、夕刻の湿気と混じり合い、街全体がゆっくりと呼吸しているのが分かる。パン屑一つとて、たしかに私の旅だった。文明の真価は宮殿ではなく、こうして路上で分かち合われる温度にあるのだろう。ハノイの夜はそれを、くどいほど明快に教えてくれる。
ホテルまでの帰り道、私は思った。異国を旅する理由は、美しい景色を写真に収めるためでも、高級な食事を味わうためでもない。日常の枠から少し外れて、他人の生活を一瞬だけ借りるためだ。ハノイの夜風は、私にそのことを思い出させてくれる。
【8】ベトナム夕食会
一通りのハノイ散歩を終えると、腕時計の針はすでに19時に迫っていた。ロビーでの集合時間もちょうど19時。そろそろホテルに戻らなければならない。夜風に混ざる排気ガスの匂いを最後に吸い込み、私は足を速めた。
ホテルの玄関に戻ると、すでに二人の社長がロビーに腰を下ろしていた。小野社長は新しいシャツに着替えており、すでにビールの一杯でも引っかけてきたような顔色をしている。大伴社長は腕時計を見ながら、軽く足を組んで待っていた。几帳面な男は集合時間前に揃うのを当然と考える。
「お帰りなさい。」
ロビーの一角で立っていたのは、今夜の接待を担当する現地スタッフだった。三十代半ばほどの男性で、細身のスーツを着こなし、名刺を差し出す仕草も板についている。
「私はヴァンと申します。本日は皆さまをご案内いたします。どうぞよろしくお願いいたします。」
流暢な日本語での挨拶に、社長二人の表情がほころぶ。異国で母語が通じるというのは、それだけで三割増しの安心感を与える。地獄に仏とはよく言ったものだ。
やがて全員が揃い、ヴァンさんの先導でホテルを出た。駐車場には黒塗りのワゴンが待っており、乗り込むとエンジンが低く唸りを上げて動き出す。窓の外に広がるのは、昼間よりも一層鮮やかに輝く街の灯り。バイクの群れは昼の雑然を超え、赤と白の光の帯となって夜を駆け抜けていく。街のネオンは煌々と輝き、これからのベトナムの未来を象徴していた。
「今夜は少し特別なレストランを用意しました。」
運転席の横からヴァンさんの声が響く。
「お食事とお酒、それから…音楽とダンスも一緒に楽しめます。」
社長二人は顔を見合わせ、同時に笑った。日本で言えば、キャバクラにレストランとクラブを足したような場所だろう。出張に付きものの「異文化体験」は、だいたいこうした夜の店に集約される。特に小野社長のような野獣派には。
店に到着すると、ネオンサインが夜の空気を切り裂くように輝いていた。入口のドアマンは黒いシャツに蝶ネクタイ、笑顔の奥に職業的な無表情を宿している。
「さあ、到着しました。席は予約しておりますので、店のスタッフの案内がしてくれます。」
手際の良さを見せつけ、日本人の不安を振り払うようにヴァンさんが伝える。
「いやぁ、さすがベトナム。夜の街も活気付いているなぁ。」
小野社長が舌なめずりするような声で呟いた。
「夜の店がその国家の景気を表していると俗人は言いますね。」
すかさず分析官のような大伴社長が続ける。彼にとっては、これも海外視察の一環なのだろう。どのような行為にも意味を持たせ、哲学的意味を導こうとする。
中へ入ると、まずはレストランのロビー。受付係が近づいて来て予約を確認する。どうやら予約者限定の店のようだ。
ヴァンさんの一言で合点がいったのか、にこやかな顔で案内を続ける。スタッフの視線の先には地下に続く階段が見えた。地下一階全てをレストランに改築しているそうだ。
地下レストランは、四角のテーブルを中心にしたコの字型のボックス席がいくつもあり、そのボックス席も大中小と規模が違う。照明は暖色で薄暗いが、落ち着いた雰囲気を醸し出している。中央にはダンスステージと思しきスペースがあり、食事を盛り上げる一役を担いそうだ。部屋の隅には音楽を操作するオペレイトスペースがある。若い男二人が機器を操っている。高級レストランまでとはいかないが、一定の規律を持った中級のレストランのようだ。
しかし、奥からは軽快な音楽が流れており、ナイトクラブの様相も帯びている。格式と大衆感が織り混ざった会場。既に数組の客が笑い声を上げ、ベトナムの夜を満喫していた。
「こちらのお席になります。後ほど何人か追加されますので。」
このスタッフも流暢な日本語を使う。どうやら行く先々の店は日本人御用達ばかりのようだ。それにしてもこのスタッフは意味深長なことを言った。人が追加。どういうことだろうか。
「ほお、これは日本のキャバクラとレストランを足したような感じですな。音楽もうるさ過ぎない。美味い飯にもありつけそうだ。」
小野社長が店を見渡しながら評価を下す。いかにも遊び慣れていそうな台詞回しだ。
大きめのコの字型ボックスに入り着席する。小野社長、ヴァンさん、大伴社長、トンさん、私という順に座った。座って気がついたが、コの字の直角部分は人が出入りできる戸板がついており、いつでも席を外せるようになっている。直角部分に座席がなく、少しばかりの空白がある感じだ。
円卓の中央に置かれた花が、ほのかに萎れかけていた。照明は暖色で、まるで時間そのものが黄ばんで見える。空調の音がやけに大きく聞こえるのは、誰もまだ何を話すか決めかねているからだろう。
ヴァンさんがドリンクメニューを配り、注文を手配する。ベトナムということで全員ベトナムビールに決まった。
「ハノイの夜に乾杯だ」
小野社長の声が響いた。グラスが触れ合う音が一斉に鳴り、泡立ったビールがこぼれ落ちた。トンさんがにこやかに笑い、英語混じりの祝辞を述べる。小野社長は肩を軽く揺らしながら「いやあ、本場の空気はいいですね」と言い、まるで自分が発見した文明の匂いを吸い込むように箸を構えた。
私は少し遅れてグラスを持ち上げ、口を湿らせる。乾杯は儀式のようなものだ。ここでは言葉より先に、互いの沈黙の角度を合わせることのほうが重要らしい。
料理は思っていた以上に繊細だった。魚の甘みと香草の苦味、そのあわいに漂うのは、異国の調和というよりも、むしろ文化の衝突が一度発酵して落ち着いたような味だ。前菜は生春巻き、メインは香ばしく焼かれた牛肉。味は申し分ない。だが、食事だけを目的にここへ来る人間はほとんどいないだろう。
私はふと考える。――料理とは、国家が最も穏やかに表現される形なのかもしれない。
暴力や支配ではなく、香辛料の配合で相手を説得する芸術。
ヴァンさんはそんな私の思索をよそに、せっせと皿を取り替え、笑顔で次の料理をすすめてくる。その笑顔は、本当に楽しげなのか、それとも仕事の一部なのか。彼の笑顔を見ながら、私はふと日本の接客業を思い出す。
笑顔を貼り付けることが、ひとつの倫理になった国。笑うことが「労働」であるという倒錯に、私たちは慣れすぎてしまったのかもしれない。
「ガモウさん、これ、好きですか?」
ヴァンさんが尋ねる。
「ええ、とても。香りがいいですね」
私はそう答えた。本当は、彼が皿を差し出す仕草の方が、どんな料理よりも洗練されていると思った。食とは、結局、人間そのものを味わう行為なのだ。
小野社長は酔いが回ったのか、唐突に「人材育成がいかに大事か」と語り始めた。彼の語彙はビールの泡のように軽く、弾けるたびにどこかへ消えていった。トンさんは笑顔で頷きながら、タイミングよく合いの手を入れる。通訳とは、言葉だけでなく、空気まで翻訳する仕事なのだろう。
大伴社長が箸を置き、静かに言った。
「こうして異国の人たちと一緒に食べると、人生の意味を考えますね」
私には、その言葉が本気なのか、儀礼なのか判別できなかった。だが――確かに、人生の意味とはこういう瞬間に紛れ込むものかもしれない。食卓に並んだ料理のように、熱が冷め、やがて皿の縁に残る少しの油のように。
私はグラスの底を覗き込みながら、思った。この円卓もまた、ひとつの宇宙だ。それぞれの人間が自分の軌道を描きながら、互いの引力でなんとか崩壊を防いでいる。ビールの泡が消えるまでのあいだだけ、私たちはその宇宙に属している。
料理が一巡したころ、店内の照明がわずかに落とされた。ヴァンさんが笑顔で何かをベトナム語で告げると、奥のカーテンが静かに開く。そこから現れたのは、三人の若い女性だった。ドレスの色がそれぞれ、赤、白、黒。国旗の色のようで、私は少し苦笑した。彼女たちは慣れた動きで円卓に加わり、何事もないように私たちのグラスに酒を注いでいった。
ヴァンさんが先頭に立ち、流れるように紹介する。
「こちら、今夜のホステスさんたちです。少しでもリラックスしてもらえたら、と。」
その口調は事務的で、それが逆に不思議な色気を帯びていた。まるで、愛想すらも業務の一部であることを自覚しているようだった。
大伴社長が早速ジョークを飛ばし、小野社長がそれに乗る。ふたりの笑い声が響き、店内の空気が急に軽くなる。音楽は少しだけボリュームを上げ、スモークのように甘い香りが漂った。
私はビールを一口飲みながら、ゆるやかに場を観察する。日本人特有の、仕事と遊びの境界が曖昧になる瞬間。彼らは今、立派に演技している。「異国の夜を楽しむ男たち」という役を、与えられた台本どおりに。
ヴァンさんは、私の隣に座る女性に何かを耳打ちした。彼女は微笑を浮かべ、私のグラスにそっとワインを注ぐ。その仕草には、明確な意図があった。たぶん彼女は、私を楽しませるために雇われている。だが、ヴァンさんは私の反応を観察していた。まるで、どこまで人間は誘われるかを試すように。
――これが「女籠絡」というものか。ふと、そんな言葉が頭をよぎる。だがそれは、彼が私を誘惑しているというより、社会そのものが人間を誘惑する構造に似ていた。欲望とは、制度の言語であり、国家の柔らかな支配の手段でもある。
私は笑顔を作りながら、もう一度ワインを口にした。苦味と甘みの間に、奇妙な静寂がある。その沈黙の味を確かめるように、私はグラスを傾けた。
赤いランプシェードの下で、グラスの縁が鈍く光った。彼女は黒のドレス。髪は後ろで無造作にまとめ、耳元に小さな翡翠のピアスが揺れている。にじむような笑顔が、職業の一部であることを私は知りながら、それでも人の気配の端にある「私的なひずみ」に目がいく。
「お名前は?」
「蒲生です。ガモウ」
「ガ・モウ」
ランはゆっくり反芻して、舌の上で小さく転がすように発音した。
「私はランです。花の『蘭』。でも、ベトナム語では『蘭』はそこまで高貴なイメージじゃないですよ。庭の隅に強く咲く花、みたいな感じです。」
「強い花は、香りが長いですね」
「香りは、長いと困ることもあります。忘れられないから。」
妙にねっとりとした言い回しの後、彼女は私のグラスにワインを少し足し、泡の細さを見てから慎重に瓶を戻した。指の動きは水のようだ。
向こうのテーブルでは小野社長の笑い声が上がり、トンさんがちょうどいいタイミングで相槌を打つ。場はよく整っている。整った音楽の上で、私たちは少しだけ拍をずらして話し始める。
「日本から?」
「ええ。東京ほどの華やかさは持ち合わせていませんが。」
ランは笑った。目尻の皺は、気の抜けた幸福の皺に似ている。
「お仕事は?」
「魚を調味加工して、箱に入れて、出荷します。」
「箱は安心ですね。」
「なぜ?」
「境目がはっきりするからです。ベトナムは、境目が曖昧です。道と店の境目、仕事と休みの境目、恋と家族の境目。」
「曖昧さを嫌いませんか。」
「好きですよ。曖昧は、息がしやすいから。程よく住みやすい環境が一番です。」
彼女はテーブルの端に置かれた紙ナプキンを四角く折り、角を小さく合わせた。完璧ではないが、きれいだった。なんとなく会話の空白を埋める仕草だった。
皿が一つ取り替えられる。揚げた白身魚に甘酸っぱいタレ。香草の影が皿の上に揺れた。私はひと口だけ食み、骨の近くの柔らかさにわずかに目を細める。
「美味しいですか?」
「骨のそばは、静かに美味しいですね」
「静かな美味しさは、お金持ちは見逃す。」
「どうして?」
「派手な音の方が、今は高いから。」
「音の大きさで値段が決まるのは、世界どこでも同じです。」
「あなたは、静かなものが好き。」
「ええ、おそらく。」
トンさんが席を立ち、歌のリクエストをしている。音楽はベトナム語のポップスに変わり、
歌詞の意味は分からないが、声の震え方だけで人間の切実さが伝わってくる。「愛」とはどこの国でも同じ語彙を持ちながら、発音だけが違う。それは神のいたずらだろうか。世界の多様性とは、結局、愛の訛りの集合なのかもしれない。
また音楽が変わり、ベトナム語の古い歌が流れ始める。誰かがチン・コン・ソンの曲を頼んだのだろう。ランは耳を傾ける仕草をし、少しだけ真顔になった。
「この歌、母が好きでした。若いころの戦争の話を、歌でしかできなかったと言ってました。」
「歌は、訊かれない告白かもしれませんね。」
「あなたは、訊かれない告白を持っていますか?」
「少しだけなら。」
「例えば?」
「今夜、あなたのピアスが翡翠じゃなかったら、私はもっと安心していた。」
「なぜ?」
「翡翠は永い石だから。長いものを身につけている人に、短い嘘は似合わない。」
彼女は笑い、指でピアスを軽く触れた。
「じゃあ、私は長い嘘にします。」
「長い嘘は、小説になりますね。」
「あなたは書く人?」
「書こうとしている人、ですかね。」
「書こうとしている人は、書く人です。」
遠くでグラスが立て続けに触れ合い、乾杯の言葉が油のように音の隙間を満たす。ランが身を少し寄せ、声を落とした。
「日本の人は、乾杯で『何に』乾杯するか、いつも迷います。彼らを支配する対象はなんでしょうか。」
「たしかに。私たちは何かと理由をつけたがる。」
「ベトナムの人は、『今』に乾杯します。過去は難しすぎるから。」
「では、未来は?」
「未来は、コーヒーが冷めないうちに来ます。」
「いい速度ですね。」
「いい速度は、人により違う。」
「あなたの速度は?」
「踊る速度。」
「それは早い。」
「でも、曲が終わるまでの早さ。終わったら、遅く歩く。」
彼女の視線が一瞬だけ、向こうの席のヴァンさんに流れ、すぐに戻ってきた。
「ヴァンは、あなたを面白いと言ってました。飲み方がゆっくりで、頭が早い。」
「観光客の悪癖です。」
「悪癖は憎い時もあるけど、愛らしい。」
「褒められた気がします。」
「半分だけ。もう半分は、注意。」
「注意?」
「観るばかりだと、映らない。」
彼女の言葉はやわらかいが、芯があった。
「歴史の話をしても?」
「ええ、してください。」
「私たちは長い間、他国の言葉で自分を説明してきました。フランス語、中国語、英語。自分の言葉で自分を説明できるのは、贅沢です。今はベトナム語が当たり前になっていますが、当時はそれすら許されなかった。」
「日本も、戦後はしばらく他人の言葉を借りました。政治、経済、文化。多くの慣習が闇に葬られました。」
「今は?」
「今は、借りていることを忘れています。知らず知らずのうちに定着しています。魂に刷り込まれているイメージです。」
「忘れるのは、才能ですね。忘れていることで救われることもあります。」
「しかし、覚えているのも才能です。先祖の功罪を含めて。」
「あなたは、どちらですか。忘却?記憶?」
「夜は忘れ、朝は思い出す人間です。」
「便利な記憶装置をお持ちだこと。」
彼女はこれまでにないくらいに声をあげて笑った。
「便利は、倫理と逆走します。便利になる過程で失われていく倫理はどうなるのでしょうか。」
彼女は小さく首を傾げる。
「じゃあ、あなたの倫理は?」私は一歩踏み込んでみる。
「なるべく静かに、誰にも見えないところで整える。陰でこそ輝く人間もいるのです。
「隠れキリシタンのような祈りですね。」
「少しだけ。ベトナムにキリシタンは少ない。今は弾圧されることもなくなりました。フランスの植民地時代の影響ですね。」
料理がまた変わり、青いパパイヤのサラダが運ばれる。ナッツ、唐辛子、ライム。ランがフォークで少しずつ、私と自分の皿に分けた。
「少し話題を変えて、恋の話をしましょうか。」
「あなたの?」
「いいえ、『恋』という制度について。お互いの国で恋というものはどのように扱われているのか。」
「いいですね。」
「恋はベトナム語で二種類あります。『tình yêu(愛)』と『tình cảm(情)』。前者は強く、後者は広い。日本でいうところの人情に近いのかも知れません。困っている人を見過ごせない感じ。」
「日本語も似ています。『愛』と『情』。そして『縁』。最後は人間の不可思議なつながりという感じですね。」
「『縁』は好き。目に見えない道。知らないうちに繋がっていく関係は奥深いものです。」
「見えない道は、地図になりません。現代の人間には不安の元ですね。」
「でも、人はついていく。社会的な生き物ですから。」
「ついて行って、たまに迷子になる。グループの中にいても不安は完全になくならない。」
「迷子は、好きな状態です。自分を見つけるためにもがいている感じ。」
「なぜ?」
「探すから。探す人は、優しくなる。冒険は誰でも好きなのではないですか?」
彼女はわずかに遠い目をして、再び近くに戻ってきた。戻ってきた時にはイタズラ少女のようにニコニコしていた。
「あなたは迷子になったことがありますか?」
「よくあります。徳島でも、ハノイでも、そして仕事でも。迷子が私に気付きを与えてくれます。」
「仕事で迷子?」
「選ぶことは、いつも迷子です。正解が遅れてやってくるから。同僚、上司、顧客の間で。」
「恋も同じですね。」
「正解は来ますかね?」
「来ます。たいてい別の名前で。しかし、時間もかかりますし、不正解と出会うこともある。」
私たちの間に、短い沈黙が落ちた。沈黙は、会話の中心に置かれた透明な器だ。何を注ぐかで、味が変わる。このベトナムでは香辛料のようにピリッとした味に仕上がりそうだ。
「あなたはいつか、ここを離れますか?」
私の問いに、ランは一瞬だけ眉を動かし、すぐ微笑んだ。
「離れると言うと、残るものが多くなります。残ると言うと、離れるものが多くなる。不思議ですね。私はこのハノイを愛しています。しばらくは根を下ろしているでしょう。」
「言葉の重力ですね。」
「私はたぶん、ここにいます。家族も、友だちも、歌も、ここにありますから。言葉、文化、習慣、魂の重力。」
「そこにあるもので、十分なら滞在は自由です。しかし、ベトナムは共産主義国家でしたね。」
「十分であることは安寧。しかし、挑戦する意志も忘れてはいけませんね。」
「野心は?」
「野心はあります。けれど、私の野心は人を踏みつけない靴底です。じわりじわりと踏み出していきたいものです。」
「良い靴だ。」
「高くないはですよ。しかし、自尊心はとてつもなく強い。」
「値段の話ではなく、覚悟の問題。」
ランは笑い、グラスの縁を指ではじいた。
「あなたは、価格の話をしない人ですね。日本人はビジネス好きと聞いていますが。」
「フォーは値がつきますが、覚悟にはつかない。」
「詩人を副業にしていますね。」
「と言っても労働者に変わりはない。身を削り、文字を生み出す。」
「詩人で労働者は、よい組み合わせ。」
遠くで流れる歌が、サビへ向かってふくらむ。二人の会話の高低を表しているかのようだった。
「あなたは、何を恐れますか?」
彼女の問いは、砂に立つ針のように静かに刺さる。
「私ですか?」
「はい、日本のビジネスマンの恐怖の根源。」
「効率の良い絶望ですかね。」
「その詩人の言葉はどういう意味になりますか?」
「何もかも合理的に諦められること。諦めに説明がつく世界です。人間は言い訳を作る天才です。いや、人間というよりも私ですかね。」
「それは、少し怖い。合理的もいきすぎると害悪ということですね。」
「あなたは?」
「愛の速度を間違えることです。遅すぎても、早すぎてもダメ。相手との速度を合わせることが大事。」
「早すぎるか、遅すぎるか。」
「はい。音楽はタイミングで美しくなる。人間も同じようなものです。」
「愛も?」
「ええ。森羅万象の全て。」
彼女は目を伏せて、パパイヤをひと口たべた。辛さに遅れて甘さが来て、また遅れて酸味が追い越す。タイミングの練習みたいな味だ。
「一つ、頼んでもいいですか?」
「どうぞ。」
「私のことを、誰かの代わりにしないで。」
彼女はまっすぐに言った。声はやわらかいが、逃げ場はない。
「ええ、しません。肝に銘じておきましょう。」
「ありがとう。あなたのことも、誰かの代わりにしません。」
心臓が、半歩ずれた場所で打った気がした。
「今夜、ここで交わす言葉は、明日には薄くなる。それでも、少しだけ残るでしょう。残ったところに、水をやってください。いつかは思い出の花が咲くでしょう。」
「水は、どこから?」
「朝ごはんのコーヒーから始めてください。」
「随分と甘くて濃い水ですね。」
「愛の速度には、ちょうどいい。ゆったりとしていて、じんわりと沁みていく。」
向こうのテーブルから、酔いの回った小野社長のカラオケに行こうという声が上がる。トンさんがこちらに視線で合図し、会計の手配が始まる。ランが小さく肩をすくめた。
「第二幕の始まりですね。」
「脚本は?」
「即興です。あなたは役柄はなんでしょうか?」
「沈黙の役。」
「似合う。日本のサラリーマンらしい言葉ですね。でも、ひとつだけ歌って。」
「何を?」
「知らない歌。知らない歌を、上手に歌えたら、少しだけ信じます。」
「信じる?」
「演技じゃないところを。」
彼女はそう言って、指でグラスの水滴をすっと拭った。透明が、指の腹で形を変える。
「あなたの役柄は?」
「私は——笑います。つまりは観衆。上手に笑えたら、少しだけ信じて。」
「ええ、信じます。」
「ありがとう。」
席を立つ前、ランがそっと囁いた。
「ガモウさん。ベトナム語で『また』は『lại(ライ)』って言います。『もう一度』の『また』」
「lại」
「そう、いい発音です。」
「また、ですね。」
「約束じゃなくて、選択の言葉。約束は重いけれど、選択は軽い。今度はプライベートでいらしてください。」
「軽いものは、遠くへ飛ぶ。風船のように。」
「それでいい。夜は短いから、楽しみは早く食べないと。」
ほんのわずかに肩が触れた。演者としての彼女と、観客としての私。舞台の境目は、皿より薄い。それでも、今の私たちには十分だった。赤いランプの下で、翡翠は緑をやめず、ワインは黒に近い赤を続けている。音楽が次の曲へ移る。第二幕のために、私たちはゆっくり歩き出した。
音楽のリズムがフロアを揺らす。ステージ上では、ダンサーたちが光を受けて艶やかに動いていた。煌びやかな衣装が照明に反射し、観客席にきらめきを投げかける。ワインレッドのカーテンが背景を包み込み、どこか場末感と贅沢が同居している。
ステージから降りてきた一人のダンサーが、我々のテーブルに近づいた。きらめく衣装の裾を揺らしながら、軽く腰を落として挨拶をする。
「こんばんは。楽しんでますか?」
とベトナム語で尋ねてきた。すかさずヴァンさんが皆に通訳する。
「Yes, very much.」
と小野社長は答える。彼女は軽く笑い、流れるように他のテーブルへ移動した。ほんの数秒の接触だが、それだけで観客は「自分もこの舞台の一部になった」と錯覚する。舞台と観客の境界を曖昧にするのもまた、この店の演出の一つなのだ。
「なあ蒲生君。」小野社長がウキウキした顔で尋ねてくる。
「こういう場所は日本のキャバクラとは違うだろう?」
「ええ。日本なら接客とお酒で終わることが多いですが、ここは演出のスケールが違いますね。」
「そうだ、演劇だよ演劇!」小野社長は声を張る。
「俺たちも今夜だけは役者なんだ。」
その言葉を聞きながら、私は心の中で皮肉を抱いた。人は夜になると必ず演技をする生き物だ。昼間の会社では「有能な部下」を演じ、家庭では「良き父親」を演じる。そして夜の街に出れば「自由な男」を演じる。人生は三交代制の舞台なのだ。違うのは、観客と演者が同じ人間だという点だけ。
ワインが回ってきたのか、小野社長の頬は赤く染まり、言葉も熱を帯びていく。
「いいか、ベトナムはこれから伸びるぞ。工場もインフラも、どんどん整備される。俺たちが若い頃の日本を思い出すね。」
「確かにそうですね。高度経済成長のような。」と私は答えつつ、彼の握るグラスの揺れ具合に意識が向いた。未来を語る手ほど危ういものはない。
やがて大伴社長も口を開いた。
「日本はどうだろう? GDPだの少子高齢化だの、暗い話ばかり聞こえてくる。だが、結局は生き方の問題なんじゃないかと思う。」
「おっしゃる通りです。」
私は頷きながら、心の中で半隠遁生活を重ね合わせた。国の成長や衰退は、個人の幸福に直結するとは限らない。むしろ余計な数字や競争から一歩引いたときに、人は初めて自由に呼吸できるのではないか。
「蒲生君、君はどう思う?」
不意に問われ、私はグラスを置いた。
「そうですね……日本のサラリーマンにとって幸福は、たいてい他人の物差しで測られています。ボーナスや昇進、持ち家や車。ですが、本当に必要なのは“自分にとって不要なものをどれだけ切り捨てられるか”だと思います。」
二人は一瞬黙り込み、それから声をあげて笑った。
「ははは!なんだ、哲学者みたいなことを言うじゃないか。」
「半分は酔っているんですよ。」私は肩をすくめた。
だが、心の中では確信していた。幸福は所有ではなく、削減によって立ち上がる。夜のきらびやかなステージを前にしながらも、私が本当に欲しているのは静かな部屋での一冊の本と、誰にも邪魔されない時間だった。
ショーは佳境に入り、照明はさらに強く、音楽は重低音を増した。社長たちは手拍子に夢中で、ホステスは慌ただしくグラスを満たしていく。周囲の客たちは笑い声を上げ、ステージのダンサーは笑顔を崩さない。ここでは誰もが「幸福」を演じていた。
私はワインを一口飲み、心の中で小さく呟いた。
──幸福とは、演技が終わったあとの静寂のことかもしれない。
小野社長はすっかり舞台に没頭し、両手を叩きながら声を張り上げた。まるで応援団長のようだ。大伴社長は相変わらず姿勢を崩さず、しかし目尻には楽しさを隠しきれない笑みが浮かんでいる。彼らの対照的な姿を眺めながら、私は思った。──人は「年齢」や「役職」ではなく、酒と音楽によって正体を露呈するものなのだ。
テーブルには食べかけの料理と、空になったグラスがいくつも並んでいた。ウェイトレスが絶えず動き回り、笑顔を絶やさない。彼女たちにとって、これは労働であり舞台であり、生活そのものだ。客が非日常を演じている間、彼女たちは日常としての演技を強いられている。どちらが滑稽で、どちらが真実なのか。
最後の演目が終わると、照明がふっと和らぎ、拍手が嵐のように響いた。社長二人も立ち上がって惜しみない拍手を送る。私はゆっくりと手を合わせながら、その音の中に一抹の虚しさを覚えた。舞台は終わったが、外の現実は何も変わらない。いや、むしろ「現実から逃げていた時間」が積み重なっているだけだ。
ヴァンさんが近づき、軽く頭を下げた。
「そろそろホテルに戻りましょう。明日も朝から予定がありますので。」
彼の穏やかな声が、宴の幕引きを告げる鐘のように響いた。
「今夜の約束、楽しみにしていますね。」
ランが去り際に伝えてきた。契約の履行を催促するかのような言伝だった。いずれはハノイに舞い戻るのだろうか。
外に出ると、湿った夜風が頬を撫でた。店内の騒がしさとは対照的に、通りには再びバイクの群れが走り抜け、クラクションの音が連なっていた。あの喧噪が、逆に落ち着きを与える。人間の作る人工的な騒ぎより、街そのものの混沌のほうが誠実に感じられた。
車に揺られてホテルに戻ると、ロビーは昼間と同じ整然とした静けさを保っていた。豪奢なシャンデリアが薄く光を落とし、フロントのスタッフは変わらぬ笑顔で客を迎えている。宴を終えた私たちが通り過ぎると、その笑顔の裏にわずかな安堵が見えた気がした。──これ以上酔客を増やさずに済む、という安堵だ。
部屋に戻り、スーツを椅子に掛ける。靴を脱いでベッドに腰を下ろすと、静寂が一気に押し寄せてきた。さきほどまでの照明と音楽が夢のように遠ざかる。グラスの氷の音も、ランの笑顔も、すべてが舞台装置のようだった。
私は目を閉じ、心の中で小さく呟いた。──人は夜になると必ず演技をする。だが演技を終えた静けさの中でこそ、本当の自分が顔を出す。異国のホテルの部屋で一人きり。これ以上の「半隠遁」はないのかもしれない。
ようやく世界が音を失った。ベッドの白いシーツが、昼間の会議室のホワイトボードのように空白を差し出してくる。私は靴を脱ぎ、椅子に腰を落とし、ぼんやりとテーブルに残ったミネラルウォーターのペットボトルを眺めた。
──幸福とは何か。先ほどの社長たちの浮かれぶりを思い返す。彼らにとって幸福は、酒と音楽と賑やかな声の中にあるらしい。だが私にとっての幸福は、こうして静かに考える時間の中に潜んでいる。サラリーマン生活が強いる「演技の連続」から解放された、わずかな隙間。
グラスに残っていた水を一口飲むと、体の奥にようやく「自分の声」が戻ってきた気がした。宴会では、誰もが他人の声に同調しなければならない。だが今は違う。壁に遮られ、冷房に包まれたこの空間でだけ、私は「演じない自分」を確認できる。
しかし、静けさは長くは持たない。ホテルの窓から見下ろす街の灯りが、私を呼んでいた。赤や黄色のネオンが夜の湿気に滲み、バイクの尾灯が川の流れのように途切れなく続く。そのざわめきの中に、どうしても歩みを進めたくなる衝動が芽生える。
深夜の散歩は、危険であることは承知していた。見知らぬ街の夜は、日中の観光ガイドブックには決して載らない顔を見せる。観光客のいない裏通り、街灯の切れた影、屋台の片付けを終えた男たちの無言の背中。すべてが、日常と非日常の境界を曖昧にする。
私はジャケットを羽織り、カードキーをポケットに押し込み、廊下に出た。エレベーターの鏡に映る自分は、ただの出張者ではなく、探検に向かう一人の旅人の顔をしていた。
ロビーを抜け、ホテルのドアが背後で静かに閉じる。湿った空気が再び体にまとわりつく。遠くで犬の鳴き声が響き、近くでは遅い時間まで営業する屋台が最後の客を相手にしている。
「危ないかもしれない」と理性が囁く一方で、「この瞬間を歩かなければ後悔する」と心が答える。半隠遁を目指す人間にとって、夜の街を歩くことは矛盾しているように見える。しかし、孤独を抱えながら雑踏に足を踏み入れることこそ、矛盾と共存する現代の隠遁なのだろう。私は歩き出した。バイクの光が背中を追い越し、異国の深夜がゆっくりと私を呑み込んでいく。
【9】ハノイ深夜散歩
ホテルのドアが背後で静かに閉まると、夜は音を取り戻した。バイクの尾灯が赤い魚影のように通りを滑り、遠くで犬が二度だけ鳴いて沈黙する。空気は湿り気を宿し、どこか甘い。昼の熱気がまだ街の壁に貼りついているのだろう。私は歩き出した。危険についての理性は、カードキーと同じポケットにしまいこむ。出張者には、時に理性の居場所を変える権利がある。
最初の角を曲がると、小さな屋台がまだ灯っていた。銀色の鍋から湯気が立ちのぼり、裸電球がその湯気に輪を描く。店主は痩せた中年の男で、シャツの袖を肘まで捲り上げ、無駄のない動作で麺を泳がせている。木の低い椅子がいくつか並び、客はまばら。遅い時間の屋台は、誰もが少し疲れ、少し親切だ。
「An đêm không?(夜食いるかい?)」
「はい。小さいのを。」
日本語で言うと、彼は目尻だけで笑い、指で輪をつくって「小」を示した。言語は要るが、炭水化物はだいたい不要だ。日本語が伝わっているのかは分からない。
運ばれてきたのは、丼というより深い皿に近い器だった。スープは透明に近く、鶏の骨から出た穏やかな香りが鼻をくすぐる。麺は白く、上に薄い鶏肉と刻んだ香草、ライムのくし。レンゲで一口含むと、塩気が過去の疲労を伴奏に変える。私は笑ってしまう。──人間は、温かい塩水を飲むだけで他人に優しくなれる。
隣に座った若い男が、スマートフォンから目を上げた。
「日本?」
「日本。」
「仕事?」
「面接、工場の。」
「いとこ、日本行った。静岡。寒い、でもお金、OK。」
彼は短い日本語で、必要な情報だけを並べる。日本のサラリーマンが会議で使う資料より、よほど効率がいい。
「静岡はお茶が有名です。」と私は言う。
「茶。知ってる。インスタで見た。」
彼は笑い、器を傾けてスープを飲み干した。画面の光が彼の顔を青く照らす。世界はかつて海で繋がっていたが、今は親指で繋がっている。
屋台の主人がこちらに顔を向ける。皺がきれいに刻まれている。
「日本、むかし来た。」
「いつ頃ですか。」
「むかし、トヨタ。短い。帰った。」
彼はそれ以上多くを語らない。だが、鍋をかき混ぜる音に、彼の日本での季節が混ざっている気がした。異国で働く時間は、だいたい鍋の中で静かに沸騰している。
会計を済ませて立ち上がると、店主は親指を立て、チョコレートをひと欠片おまけしてくれた。
「お腹、元気。」
「心も、元気。」
と私は言った。屋台の礼は、いつも身体より先に心に届く。
通りを離れ、裏路地に入る。照明はまばらで、ところどころ電球が切れ、闇が階段の段差のように足元へ現れる。洗濯物が夜風に揺れ、青白い壁に影を落とす。開け放たれた家の奥でテレビが笑い、床に座った子どもが眠そうに画面を見ている。ベトナムの夜は、扉の隙間から生活を覗かせる。日本の夜は、カーテンの内側にすべてを隠す。どちらが礼儀かは時と場合による。
薄暗い角を曲がると、古い家屋の軒先に小さな祠があった。赤い蝋燭が一本、短く燃えている。供え物の皿には、ちぎったバナナとビスケット。線香の煙が真っ直ぐ昇り、頭上でほどける。私は立ち止まり、黙って手を合わせるまではしないが、視線の角度だけで敬意を払う。宗教は言語に似ている。下手に真似るより、静かに聞く方が礼儀正しい。
路地の端で、年配の男がプラスチック椅子に座り、タバコをふかしていた。彼は顎で道の先を指し、
「Đêm khuya, cẩn thận.(深夜、気をつけな。)」とだけ言う。
「Cảm ơn.(ありがとう)」
私の発音は怪しかったが、彼は満足そうに頷いた。注意喚起は、最高の地域通貨だ。少し開けた場所に出た。廃れかけた市場の屋根が黒い塊になって並び、その脇に、屋台というより小さなバーのような店が一軒だけ光っている。高めのスツール、色の褪せたポスター、安いスピーカーから流れる古いベトナムポップ。私はドアを押した。
カウンターの内側で、短髪の女性がグラスを磨いていた。歳の見当がつかない。笑うと年若く、黙ると年季が出るタイプだ。
「遅い時間の訪問ですね。」
「お酒のせいで眠れなくて。」
「旅の人は、時差より心配ごとの方が眠りを妨げます。今回はお仕事での訪問ですか?」
彼女は氷を落とし、透明な液体を注ぐ。
「ええ、ベトナムの実習生の採用面接できました。」
「何が心配です?」
「明日の面接と、明後日の帰国と、来月の会議と、来年の給料。最後に実習生の教育ですかね。」
「随分と悩み多い旅人ですね。」
「日本人は悩みを分割払いにするのが得意です。」
「こちらは一括払いです。払えないときは寝る。寝ると何か解決策が降りてきそうな気がするのです。」
彼女は肩をすくめ、笑った。合理的だ。たぶん世界で一番強い睡眠薬は貧困ではなく、価値観の割り切りだ。
「ところで」と彼女が続ける。「日本は今、幸せ?」
「質問が詩的ですね。」
「ベトナムは“これから”とみんな言う。でも“いま”が好きな人も多い。」
私は答えに窮し、グラスの氷を見た。日本のありのままを話すと、ベトナム人の理想を破壊しかねない。
「日本は“むかし”が好きな人が多いです。だから“いま”を好きになる練習中です。」
「練習?」
「はい。たぶん反復練習が必要で。慣れ親しんだ習慣を手放すのは名残惜しいのでしょう。」
「練習の後はご褒美が要りますよ。日本人にとってのご褒美とはなんでしょうか?」
「ご褒美、ですか。」
「ここでは夜風と、少しの音楽、そして、グラス一杯の美酒。」
彼女はスピーカーの音量を一段だけ上げた。古い曲のサビが、店の木の壁を震わせる。私は頷き、グラスを傾けた。ご褒美は、思ったより安くて、思ったより効く。
店を出ると、角の向こうからバイクタクシーの男が声をかけてきた。
「Xe ôm?ホテル?」
「歩きます。」
「日本人、歩く。強い。」
「日本人、考えすぎ。弱い。」
互いに笑った。国籍ジョークは、うまくいくとちょっとだけ世界を縮める。私は再び歩く。歩道の割れ目から、昼の熱がまだ抜け切っていない。足裏に伝わる温度は、街が生き物である証拠だ。ふと、頭に寓話が浮かぶ。
――昔々、二つの川があった。一つは日本の川で、石を撫でるほど清く速い。もう一つはこの国の川で、大地の粉を抱えて太くゆっくり流れる。二つは互いの色を羨んだ。清い川は「重たさが欲しい」と言い、濁った川は「澄みたい」と願った。ある日、風が二つの川に壺を渡し、それぞれ相手の水をひと掬い分け合った。清い川はひととき重みを得て、濁った川は瞬間だけ透き通った。だが翌朝、両方とも元に戻っていた。川は知った。自分の流れしか歩けないこと。そして、ほんの一杯の他者を抱くことで、相手の気持ちだけは分かるということを。
寓話は勝手に終わり、私は笑った。半隠遁の訓練は、他人をたくさん持たないことだが、ひと掬いなら心に置いておける。
ホテルが近づくほど、街は居眠りを始める。屋台の火が一本ずつ消え、プラスチックの椅子が音を立てて重ねられる。路上の猫が私を一瞥し、政治家のように何も約束せず去っていく。ビルのガラスに、自分の小さな影が浮かぶ。昼間は会社の歯車として正体不明だが、深夜になると影だけが本名を名乗る。
ふと、もう一つの出来事。ホテルの手前で、制服姿の学生二人が数学の教科書を広げて歩道に座っている。夜風の中、問題を指差して議論している。
「Xin lỗi(すみません)」と声をかけ、英語で「試験?」と尋ねる。
「Tomorrow. Big test.」
「どのくらい勉強するの?」
「Until sleep.」
彼らは笑い、肩をすくめた。私は親指を立て、頭を下げた。未来に投機しながら、今夜だけは現金主義――賢い。
ホテルの明かりが、帰巣本能を思い出させる。ドアマンが小さく会釈し、ドアが静かに開く。冷気が頬に触れる。さっきまでの夜風が、ページの向こうへ閉じられていく。
エレベーターの鏡の中で、自分の顔にうっすら汗が光っていた。危険はなかった。いや、なかったことにする。旅の価値は時々、統計の外側に生まれる。私は肩の力を抜き、最後の考えを手帳に走り書きした。
──幸福は、昼に役目を忘れ、夜に自分を思い出す技術。
──半隠遁は、世界を所有せずに、ひと掬いずつ借りる作法。
部屋の鍵がかすかな音で開き、白いシーツがまた空白を差し出した。私は靴を脱ぎ、気配をすべて床に置いて、ベッドに倒れ込む。天井のどこかで、エアコンの静かな呼吸だけが続いている。目を閉じる直前、ライムの香りが指先に残っていることに気づいた。今夜の収穫は、それで十分だった。
【10】早朝のハノイ散歩
目覚ましより早く目が覚めた。カーテンの隙間に薄いミルク色の光がたまっている。昨夜の喧噪は、どこか別の都市へ運び去られたらしい。かわりに、空調機の低い唸りと、どこか遠くの箒の音が、海底のような静けさに小さな傷をつけている。
シャワーを短く浴び、支度を済ませる。ドアを開くと、廊下は涼しい。清掃用ワゴンの隅に、折りたたまれたタオルがレンガのように積まれている。どこかの部屋から、早起きの人間のテレビ音声が漏れてきて、「世界は既に始まっている」と告げる。私は昨夜の酒の名残りを舌の奥に見つけ、口をゆすぐように無言でエレベーターに乗った。
ロビーは明るい。夜の客人たちの物語を飲み込んだソファは、今朝はただの家具にもどっていた。ドアマンが軽く会釈する。外に出ると、湿気が顔に触れた。ハノイの朝は、思ったよりも柔らかい。空は白に近い灰色で、雲が薄い布のように重なっている。街は、まだ完全には目を覚ましていない。しかし、その欠伸の合間から、生活の歯車がすでに回り始めているのが見える。
歩道の石は一部はがれ、雨水がつくった小さな池をいくつか抱えている。タイルの模様は場所ごとに違い、昨日の都市計画と一昨日の思いつきが同じ地面で同居している。電線はあらゆる方向へ伸び、鳥の巣のように絡まっている。美しさというのは整然さのことではない、と私は思う。多すぎる線が、逆説的に一本の線を思い出させるからだ。
バインミーの屋台が、道端に背の低い椅子をならべていた。氷の塊が小さく鳴き、包丁がパンの腹を開く。女性の手は迷いがない。パンの表面に浅い斜線が刻まれているのは、夜のうちに受けた熱の記憶だろう。彼女の親指の付け根に硬い茹で卵のようなタコがある。立ち仕事の年月。ホームズなら、そこに日々の売上まで読み取るだろう。私はせいぜい、彼女が雨季と乾季のどちらを好むか、想像に努めるくらいだ。
バイクが通り過ぎる。ヘルメットのステッカーは色褪せ、背中のリュックは汗で暗く染まっている。ナンバープレートの泥の乾きかたから、昨夜、郊外で小雨に遭ったと推測できる。帰路のカフェで雨宿りをして、結局長居したのだ。そういう濡れ方をしている。推理というより、羨望の投影かもしれない。
湖の方へ歩く。ホアンキエムの水面は、うっすらと乳白色をまとっている。縁の欄干に寄りかかり、朝の太極拳に合わせて腕を振る人たちを見る。動作はゆっくりで、時間だけが濃い。彼らの靴底は均一に擦り減っていない。左右で磨耗の仕方が違う。膝の悪い人、腰の固い人、それぞれの身体に、それぞれの歴史がある。群舞のように見えて、実はひとりずつ別の人生を踊っている。社会とはたぶんそういうものだ。足音の合唱に聞こえるが、誰も同じ靴ではない。
湖畔のベンチに、制服の少年が座ってパンを食べている。パンの端を折り、小さく丸めてから口に入れる。几帳面な癖だ。試験前かもしれない。パンの袋が、教科書の角で小さく裂けている。彼は裂け目を上に向けることを覚えている。小さな失敗を繰り返して身につけた知恵だろう。私は自分の鞄のポケットを触り、昨夜もらった名刺の角がゆるく曲がっているのに気づく。大人の知恵は、案外に雑だ。
道路の向こうでは、屋台の火が上がり、フォーの湯気が白い旗のように立っている。私はプラスチックの椅子に腰を下ろし、指で机の端をなぞる。表面には無数の傷。勘定の計算にも使われた歴史。店の青年がカップを置く。早朝のベトナムコーヒーだ。
青年は、私のカップの持ち方を一度だけ観察してから、すぐに他の客の方へ目をやった。彼の瞳には、職業的な焦点距離がある。客の動きと動きの間に、さっと身体を差し入れて秩序を保つ。秩序とは、目に見えない忙しさの別名だ。私はカップの底を見、白い器に残る薄茶の輪を眺める。人間の一日は、こうした輪をいくつ積み重ねるかで測れる。輪は薄く、しかし消えない。
席を立つ。勘定を渡すと、青年は片手でお釣りを数え、もう片方の手で鍋の蓋を押さえる。彼の手の甲の毛は薄く、指は長い。ピアノには向かないが、器の蓋には向いている。人間には、それぞれ蓋を押さえるために生まれてきたような瞬間がある。海を支える石のように小さく、しかし必要な役目。
通りは、だんだんと音を増していく。古い拡声器から、朝の連絡事項のようなベトナム語が流れる。意味はわからないが、声の温度で、注意と励ましが混ざっているのが分かる。音は街路樹の葉に当たり、緑色の反響をつくる。葉裏には、早起きの蜥蜴が潜んでいるに違いない。見えないものを信じるには、朝がいちばんいい。
市場の入口に来る。果物の山が築かれ、マンゴーの皮に包丁の呼吸が残っている。秤の皿は傷だらけだが、真ん中だけが柔らかく光る。重さは、日々ここで公平に測られている。公平は傷を恐れない。魚屋の前を通り過ぎると、氷が溶けかけ、銀色の鱗が夜の名残りを反射している。匂いは生きているが、嫌ではない。海の古い挨拶のような匂いだ。
歩道に積まれたレンガを横目に見る。新しい舗装の工事だろう。レンガの角はまだ鋭く、職人の指先を警戒している。束の結束バンドが一本だけ切れていて、そこから小さな解放の気配が漏れていた。秩序はいつでも、解放に少し似ている。均されることは、時に楽で、時に息苦しい。
雨樋の下で、ぽたぽたと水が落ちている。見上げると、エアコンの室外機が規則的に震えている。ベトナムの都市は、室外機の呼吸で朝になる。ホテルの壁面に沿って伸びる配管は、地下鉄の路線図みたいに曲がりくねっている。目的地を知っているのは水だけだ。人間はしばしば行き先を知らずに歩き、しかし足は賢い。足は頭より先に帰り道を知っている。
十字路に出る。信号の切り替わりは日本より少し長く、横断歩道の白が薄い。白は使い込まれるほど、優しくなる。二人乗りのバイクが止まり、子どもが眠たげに父の背中に顔を押しつける。父の肩越しに、子は世界を半分だけ見る。世界を半分だけ見るのは、実は正しい練習かもしれない。全部見ようとすると、肝心なものを見逃すからだ。
寺の前で線香が上がる。煙は、朝の湿気にためらいがちに混ざり、すぐにほどける。祈りとは、ほどけることを受け入れる力だ。境内の石灯籠に、昨夜の雨が残した水滴が連なり、斜めに光っていた。水はいつも、角を丸める。人の言葉も、角を丸めてゆくなら、もう少し楽に生きられるだろう。私は昨夜の宴会で言い過ぎた言葉がないか、頭の棚を指でなぞる。埃は少し舞ったが、致命的な欠品は見当たらない。よかった、と独りごちる。
通りの端で、修理屋がシャッターを半分だけ開けている。半開きは、慎重とやる気の折衷案だ。店内で男が古い扇風機の羽根を外している。羽根の根元に綿埃が固まり、海鳥の腹綿のように見えた。そこに溜まった夏と冬の時間を、男は無言で指先からほどいていく。道具を直す人は、時間の整備士でもある。
角を曲がると、コーヒーの匂いが狭い路地を満たしていた。おかわりの欲求が私をせき立てる。金属のフィンが、ゆっくりと黒い雫を落としている。私は小さな卓に座り、氷の入ったグラスと、練乳の白さを眺める。甘さは、いつだって物事の重力をゆるめる。最初の一口で、舌に小さな祝祭が灯る。祝祭は短いほうが、記憶が長い。
隣の卓の男が新聞を広げる。言葉は分からないが、紙の触れあう音は世界共通だ。彼の指先のインク汚れは新しい。印刷所の朝と、彼の朝が重なった証拠だ。見出しの端に、昨夜のサッカーのスコアが載っているらしい。男は眉をひそめ、すぐに笑って肩をすくめた。敗北の受けとりかたが、良い。人間は、負け方に教養が出る。
通りの向こうから、荷台に氷を積んだ三輪車がやってくる。氷は反射で半分だけ空を抱き、半分だけ地面を抱く。運転手の首筋に四角い日焼けがあり、首から下げた小さな御守りが胸で跳ねる。彼の目は先だけを見る。過去は氷の上で溶け、未来は日差しの中で蒸発する。その間だけが、たしかに彼のものだ。
私は勘定を払い、路地を抜ける。歩道の継ぎ目に小さな蟻の列ができていて、パン屑を運んでいる。彼らは、運ぶことに意味を必要としない。意味を捨てると、世界は案外軽い。人間は意味を拾いすぎるのだ。私はポケットの中のレシートを一枚捨てる。軽くなった気がしたが、気のせいだろう。気のせいでも、朝には効く。
ホテルが見える通りに戻る。ガラスの外壁が、白い空と電線の複雑な譜面を映している。私はふと立ち止まり、映った自分の姿を見る。旅人というより、ただの歩行者だ。歩行者でいることには、自由と責任が同居する。目的地を曖昧に保てる自由と、どこにもたどり着かない可能性という責任。私は靴紐を一度きゅっと締め直す。靴は答えないが、地面はわずかに頷いた気がした。
ロビーに戻ると、冷気が肩に落ちる。フロントの花が活け直され、昨日よりも背が低くなっている。水替えの音が小さく響く。誰かが見えないところで、一日を整えている。整える仕事は目立たない。目立たない仕事が世界を支える。私は昨夜の円卓を思い出す。演者の影で、皿を替え、笑顔を保った人たち。彼らの手つきは、祈りに一番近かった。
エレベーターの鏡に、少しだけ赤味を帯びた自分の目が映る。眠気と覚醒の中間にある顔。部屋のドアを開けると、外の白さがすこしだけ付きまとってきた。窓際に立つ。街はもう本格的に動き出し、クラクションが短い会話を始めている。私は深呼吸をする。肺の奥に、香草とガソリンと湿った紙の匂いが混じって沈む。異国の朝は、いつも調香師の作品のようだ。調香師の名は、誰も知らない。
私は机にノートを開く。ペン先が紙に触れた瞬間、軽い抵抗があり、すぐに滑り出す。言葉は足あとだ。湿った歩道に残して、乾けば消える。けれど消えたからといって、歩かなかったことにはならない。旅とは、消える足あとを量る秤だ。
書きながら、私は思う。人はなぜ旅に出るのか。答えはいつも貸し借り勘定のように合わせづらいが、今朝の私はこう書く。「世界の細部を、自分の細部で受けとるため」。ハノイの電線の絡まりを、私の神経の絡まりで受けとる。フォーの湯気の曲がりを、私の呼気の曲がりで受けとる。そうして、少しだけ身軽になる。身軽とは、軽薄のことではない。重さの持ち方を知る、ということだ。
カーテンの向こうで、また朝が一段階明るくなる。私はノートを閉じ、昨夜の名刺を束ね直す。角は、朝のあいだに少しだけまっすぐになっていた。紙は生き物だ。人間も、たぶんそうだ。水と光があれば、少しはまっすぐになる。
もう一度、窓の外を見下ろす。通りの角で、誰かが笑っている。笑い声は言葉を持たないが、意味を持つ。意味のない意味。そんなものが、朝にはいちばんよく効く。私は口の端をわずかに上げ、ドアに手をかけた。二日目が始まる。世界は準備がいい。私も、とりあえず靴紐だけは、ほどけていない。
【11】朝食の時間
エレベーターがロビー階に着く前、香辛料の匂いが先に乗り込んできた。扉が開くと、バイキング会場の入口でスタッフの女性がカードを確認し、可動式の笑顔で「グッドモーニング」と言った。笑顔に疲れはない。昨夜の宴会のホステスたちの微笑と違って、こちらは朝の制度に属している。どちらが本物かは問うだけ無粋で、朝の笑顔は、歯の裏側まで涼しい。
会場は大きな水槽みたいに明るく、窓の向こうで曇天がほの白い。保温器の蓋が半分だけ開けられ、湯気が音のない会話を続けている。カチカチとトングの触れる高い音、陶器の皿が重なる低い音、果物のナイフが皮を滑るときの小さな鳴き声。朝食の楽団が、すでに通し稽古を終えて本番に入っている。
私は空席の多い端のテーブルを選び、荷物を置いてから、皿を取りに向かった。最初の皿は清掃の一種だ、というのが個人的な信条だ。胃袋の床掃除。白いご飯を小さく、蒸し野菜を少し、そしてベトナム式のオムレツを薄く。オムレツ・ステーションの青年が片手で卵を割り、もう片方の手でフライパンの柄を軽やかに回す。動作は無駄がなく、音符みたいに整っている。彼の袖口に小さな焦げ跡があった。昨日の混雑で、油が跳ねたのだろう。袖口の歴史は、メニューの歴史より信用できる。
フォーの鍋の前に立つと、香りが鼻の奥の引き出しを開けた。骨の影、スターアニスの輪郭、葉の青味。厨房の男が、湯の中から麺をさっと持ち上げ、私の丼に落とす。葱と香草、ライムの薄切り。ヌックマムの瓶がさりげなく置かれ、辛味の皿には赤い斜線が幾重にも刻まれている。私はライムだけを絞った。酸味は、昨夜の会話の余韻を洗うのにちょうどよい。
席に戻る途中、私は客たちの皿を観察する。黄色い卵で皿を埋め尽くす欧米の男性。パンを左右対称に並べ、バターを几帳面に塗る日本人の中年。ドラゴンフルーツの白と黒を長く眺めてから、やっと一口食べる韓国の若い女性。子ども用の椅子に座ったベトナムの少年は、パンの中央だけを先に食べ、端を残している。端は世界の余白みたいに固い。父親はその残された余白を、自然な所作で自分の皿へ移した。家庭の秩序は、余白の引き取りで保たれている。
テーブルに戻る。まずはスープ。表面の油が薄く広がり、私の顔を歪めて映す。昨夜の私が、そこに微かに混じる。演技の薄皮。口に含むと、塩味は控えめで、出汁の記憶が長い。骨の時間が、舌の上でゆっくりと座る。朝のフォーは、夜の会話と違って言い訳を必要としない。湯は言い訳を嫌う。
オムレツに箸を入れると、端が静かにほどけた。青年は具を少なめにしてくれたらしい。私が具材の前で一瞬だけ迷ったのを見て。観察は、もてなしの最小単位だ。昨夜、ヴァンさんは、私のグラスの減りをよく見ていた。減り方で人は分かれる。勢いよく減らす者、慎重に減らす者、減っていないふりをする者。私は昨夜、減っていないふりをして、たしかに減らした。演技の稽古は社会が提供する。上達は速いが、褒められはしない。
隣のテーブルでは、二人のビジネスマンが英語で予定を擦り合わせている。片方はネクタイの結び目が浅く、もう片方は靴の甲に浅い傷。浅さにも種類がある。結び目の浅さは睡眠不足、甲の浅い傷は昨日の雨。彼らの皿は茶色が多く、緑は少ない。会議は長引くのだろう。長引く日には、茶色を選びがちだ。茶色は心の防波堤になる。私の皿は白と緑が多い。今日の私は、まだ波を見る余裕がある。
窓際の家族連れが、果物コーナーに向かった。子どもがパイナップルを指さし、母親が躊躇なく大きく切る。父親は少し離れたところで写真を撮る。父の画角はいつでも、少しだけ余計なものを入れる。未来の懐かしさのために。写真はいつも、忘れられるもののために撮られる。
フォーを食べ終えると、皿を取り替える。二枚目は作業の皿。バインミーを半分、ヌクチャムで和えた野菜、ソーセージの薄切り、チャーゾーを一本。パンの皮に指を当てると、夜の熱がまだ遠くで鳴っている。かじると、外は短く砕け、内側は静かに吸い込まれる。ヌクチャムは甘味の後ろから透明な刃を出し、喉に小さく刻印を残す。食べ物は、国の名刺だ。昨夜の名刺束の中で、ベトナムの名刺だけが香りを持っていたことを思い出す。
チャーゾーの端を齧りながら、私は一口の中に昨夜を見つける。赤・白・黒のドレス、グラスを満たす指の角度、笑いの高低差。ヴァンさんは、組子のように会話を組み立て、誰もが一度は自分の中心に来たように錯覚するよう、椅子の向きまで微調整した。あれは「籠絡」という言葉の粗さに入らない精密さで、むしろ場を人間に返す技術だった。返すためには、まず奪わなければならない。奪って返す。もてなしの逆説。今朝の笑顔は奪わない笑顔だ。だから、私の警戒は下がる。人間は思った以上に単純で、単純であることをなかなか認めない。
コーヒーマシンの前に小さな行列ができている。欧米風の全自動機と、ベトナム式のフィンが並んで置かれていた。どちらの列に並ぶかで、人の時間の使い方が見える。速さを選ぶ者、待つことを選ぶ者、迷った末にジュースでごまかす者。私はフィンの列に立った。待つことに意味がある朝が、旅には必要だ。順番が来ると、スタッフが金属のフィンを前に、粉を入れ、蓋をして、上から少しだけ湯を落とす。粉が膨らむのを待ち、また湯を少し、そしてもう少し。滴が黒い約束のように落ちる。この国のコーヒーは、口に入る前から味を持っている。
席に戻る前に、果物を少し。ドラゴンフルーツの白と、ジャックフルーツの黄、パパイヤのオレンジ。色は簡単に幸福を装うが、悪意はない。ナイフの刃に果汁が光り、私は指先に残る粘りを舌でほどいた。甘さはいつも記憶を早口にする。昨夜の断片が少し騒がしくなった。私はコーヒーの滴を見つめ、静かに落ち着くのを待つ。黒は、色の終着駅だ。
皿をもう一度だけ取りに行く。最後の皿は予言の皿だ。今日の自分に必要なものを選ぶ。私は小さなヨーグルトを一つ、ピーナッツを少し、そして米粉の蒸し菓子を一切れ。面接の日は、口の中に静かなものを置いておきたい。静かなものは、緊張の波を穏やかにする。波は防げない。サーフボードが要るだけだ。私はヨーグルトに蜂蜜を数滴落とし、スプーンで円を描いた。小さな天気図。
会場の一角で、中国語が弾む。団体客のリーダー格の女性が、配膳の効率を矢継ぎ早に指示し、若い添乗員が頷きながら皿を集めている。彼女の動線は完璧で、ゴミ箱に向かうときだけ歩幅が少し小さくなる。靴が新品だからだ。新品は、遠慮がちに世界を踏む。私は自分の靴底を視線で確かめる。昨夜の路地で拾った砂粒が、片足の溝に居残っていた。旅の証拠は、いつも意外なところに隠れている。
新聞を読む老紳士が窓際にいて、紙面の端で指を軽く叩く癖がある。叩くリズムは規則的で、記事の内容よりも指の記憶に忠実だ。彼の皿にはバナナが一本、皮のまま置かれている。食べずにおく果物は、思考の重石になる。思考はときに、軽くなりすぎる。重石が一つあると、飛ばない。私は頭の中で、今日の面接の名簿を並べる。名前は、故郷の地図だ。発音の抑揚で、河の流れや丘陵の起伏が見えてくる。ゲアン、ナムディン、ハイズオン。音の中に、家の匂いが立つ。彼らが持ってくる匂いと、私が持ってきた匂いが、今日、同じ部屋で混ざる。
コーヒーが落ちきった。フィンを外し、蓋の裏に残った滴を軽くカップに振り入れる。黒は完全になった。まずは砂糖なしで一口。舌の上に、土と煙とカカオの古い記憶が並ぶ。次に練乳を少し足し、スプーンで底からゆっくり持ち上げる。白と黒が合流し、川になる。最初の甘さは躊躇なく、後味はきっぱり。ベトナムコーヒーは、短い人生論だ。人生は先に甘くても、最後は苦くてもいい。順序が分かっているなら、腹はくくられる。
窓の外、ホテル前の車寄せで、ベルボーイが荷物を積み込み、運転手と短く冗談を交わす。冗談は世界の潤滑油だ。昨夜、私たちは潤滑油で夜を滑り抜けた。今朝は、機械そのものの点検に向かう。面接という機械。そこで問われるのは、油ではなく、部品の相性と、摩耗への耐性だ。志望動機は正直である必要はないが、構造が必要だ。構造のない動機は、湯気みたいに消える。私はカップを持ちながら、自分の質問票の余白を思い浮かべる。訊くことは決めている。けれど、その「答え方」を見る準備もしておこう。人間は、答えよりも、答え方に住んでいる。
会場の奥で、小さな女の子がマンゴーをひと切れ落とした。母親がすぐに拾い、紙ナプキンで拭いてから、娘の手にもうひと切れを渡す。落とした分は、見なかったことにするのが、今朝の正しさだ。社会には、見ないことでうまく動く場所がある。昨夜の円卓でも、誰かの沈黙を見ないことで、あの場は保たれていた。面接の部屋では、逆に見なければならない沈黙がある。言葉の合間の呼吸、視線の落ちる位置、指先の所在なさ。沈黙は履歴書の余白に書かれている。
私はコーヒーを半分残し、もう一度果物の皿の前に立つ。ドラゴンフルーツの種の密度を指で数えるように眺める。種は小さく、均一に散っている。可能性の見本。面接の可能性は、こんなふうに均一ではない。誰かの家の借金、兄弟の数、祖父の健康。種は偏在する。公平は、偏在を認める勇気から始まる。私は小さな房をひとつだけ皿にのせ、席に戻る。
再びコーヒー。今度は冷たい氷の上に落とす。音が小さく跳ね、黒が透明をゆっくり侵食する。氷は、熱の過去形だ。過去形と現在形が混ざると、未来形は案外まともに現れる。採用面接の部屋で、私は未来形を見たい。言い換えれば、動詞の活用を見たい。過去に何をし、今どうし、これからどうするか。語尾が整っていれば、物語は歩き出す。語尾が曖昧でも、歩ける人もいる。靴が良ければ。私は視線だけで靴を見てしまう癖を思い出し、苦笑した。靴は、遠慮なく本音を語る。底のすり減り方、踵の斜め、紐の捻れ。人の生き方は、靴の文法に刻まれる。
スタッフが私のテーブルに近づき、「エブリシング、オーケー?」と柔らかく尋ねた。私は親指を立て、ついでにフィンをもう一台頼む。彼女は笑って頷き、去り際にテーブルクロスの皺をひと撫でする。朝の整理は、儀式であり、祈りだ。整える手は、つねに世界の背後にいる。昨夜も今朝も、その手が舞台を支えている。支える手がある限り、演者は間違えてもやり直せる。面接もそうでありたい。間違いを罰するより、やり直せる場を示したい。私の役目は、選ぶことだけではない。選び方を、彼らに残すことでもある。
最後の一口のコーヒーは、少しだけ冷えて、甘さが厚くなった。厚みは安心を連れてくるが、油断も連れてくる。私はカップを置き、背筋を伸ばす。窓の外の曇りは、まだ本降りにはならない構えで空に居座っている。今日の天気は、決めきらない大人のようだ。決めきらない日に面接をするのは、悪くない。人間もまた、決めきらない生き物だからだ。
会場を出る前、私は一度だけ振り返る。空いた皿、拭かれたテーブル、控えめに咲く花。朝食は戦いではなく、整形だった。歪んだ夜の顔を、朝の手がやさしく撫で直した。鏡の中の私は、たしかに昨夜より穏やかだ。穏やかさは、弱さの反意語ではない。準備の同義語だ。
ロビーを抜け、エレベーターに乗る。上昇のわずかな重力が胃の底に触れ、そこに黒い湖の静けさが返ってくる。部屋の扉を開けると、外光が薄く床を這っている。机に名簿と質問票を広げ、ペンを置く。私は深く、ゆっくり息を吸って、吐く。肺の奥に残っていた夜の金属音が、朝の香草に置き換わる。さて、始めよう。世界は準備がいい。私も、コーヒーの分だけは。
【第2部 完】